抗生物質とコミュニケーションについて
国立研究開発法人
国立国際医療研究センター病院
AMR臨床リファレンスセンター
藤友 結実子
【分からないことを聞いていますか?】
「抗菌薬・抗生物質についてわからないことがあるとき、医師や薬剤師に質問していますか?」
私たちが以前行った【抗菌薬に関するアンケート調査】では、この問いに対し、
●「質問する」人は3割
●「聞かれれば質問する」人が3割
●「質問しない」と答えた人が4割
でした。処方された藥について疑問があっても聞かない(聞けない?)まま、終わってしまう人が4割います。
たしかに、子どもが熱を出したとき、
「たぶんかぜだと思うけど、本当に大丈夫か」、
「抗生物質が必要な状況なのか、そうでないのか」、
「お医者さんにどう質問したらよいのか、よくわからない」
…というのはよくあることです。
例えば、こんなこと、みなさんもご経験があるのではないでしょうか?
●具合が悪くて機嫌の悪い子どもの面倒を見るのに精いっぱいで、診察室で、何か聞きたいけれど、気の利いた質問なんて出てくるわけもなく、モヤモヤしているうちに薬が出て、家に帰ってきてしまう。
●嫌がる子どもに、なんとか処方された抗菌薬を飲ませ、子どものうんちがゆるくなって、その処理にまたあたふたし、そうこうしているうちになんだか元気になっていた、ということを繰り返す。
診察室のお医者さんも忙しそうですが、親も忙しい・・・
【抗生物質(抗菌薬)の正しい知識を】
そもそも抗生物質とは、どういう薬なのでしょう?
前述の調査では、抗菌薬(※抗生物質と抗菌薬は同じものを指します。)のことを「知っている」と答えた人でも、抗菌薬ではない薬を抗菌薬だと思い込んでいたり、「かぜに抗菌薬が効くので、かぜの時には抗菌薬を処方してほしい」と思っているなど、勘違いをしている人が多いことが判明しました。
また、抗菌薬を処方されても、最初から飲まない人もいるようです。
(※詳しくはこちらをご覧ください。http://amr.ncgm.go.jp/infographics/008.html)
抗生物質(=抗菌薬)は、「細菌」による感染症を治療する薬です。
一方、ほとんどのかぜやインフルエンザは「ウイルス」が原因となる感染症です。
「ウイルス」と「細菌」は、とても小さな生物という共通点はありますが、全く異なる生き物です。「細菌」は自分の体のパーツを色々持っていて、自分で栄養を作り、増えることができますが、「ウイルス」は自分だけでは何も作り出せず、自己複製するために必要な、最低限の遺伝子くらいしか持ちません。
抗菌薬は細菌の体のパーツをターゲットにした薬なので、ウイルスには全く効果がありません。かぜをひいたときに抗菌薬を飲んでも、早くよくなるわけではないばかりか、皮疹や下痢といった副作用が出る可能性があります。
【抗菌薬の不適切な使用で、薬剤耐性菌が増える】
さらに、抗菌薬を不要なのに飲んだり、いい加減に服用したりすると、細菌が、抗菌薬が効かないように変化する(薬剤耐性)きっかけになります。「薬剤耐性対策」は、今、日本だけでなく、世界的な課題となっています。
薬剤耐性菌が増えると、これまでなら効いたはずの抗菌薬が効かなくなり、様々な病気の治療や予防が難しくなります。新薬の開発にも時間がかかるため、今ある抗菌薬を大切に使うことが、とても大切なのです。
ではどうすればいいのでしょう?それは、抗菌薬は必要な時はしっかり飲むが、不要な時は飲まない、ということです。
【医師とコミュニケーションを】
かぜだと思って受診したのに、処方薬に抗菌薬が入っていて「あれ?」と思ったら
「かぜかなと思っていたのですが、抗菌薬はやっぱり飲んだ方がよいのでしょうか?」と聞いてみて下さい。
医師も、患者さんの診察をしながら色々なことを考えています。
「この患者さんは何も言わないけど、実は抗菌薬がほしいと思って受診したのではないだろうか。」とか、熱が出始めて1-2日で受診した患者さんを診ている時は、「おそらくかぜだろうけど、もしかしたら他の病気かもしれない」と心配したりもしています。
もしも、患者さんから質問されれば、「たぶんかぜだと思うので、今日のところは抗菌薬を処方しませんが、熱が5日以上続いたり、ごはんが食べられなかったり、息苦しかったりするときは受診してください」とか、「経過によっては、ひどい中耳炎になってしまうことがあるから、1週間後に治っていなければ抗菌薬を処方しましょう」などと説明できるのです。
質問されて答える機会がなければ、「念のため抗菌薬を処方しておこう」と、不要な抗菌薬処方につながってしまう可能性があります。
私自身は患者さんに「風邪には抗菌薬は効かないから、必要ないですよ」と言ったときに、「え、そうなんですか?」ととても怪訝そうな顔をされたのに、それ以上何も聞かれず、どのくらい分かってもらえたのか、不安になったことがあります。
分からないことがあれば、是非、質問してください。質問から会話が始まります。
「あれ?昔、風邪の時に別のお医者さんで抗菌薬をもらったような気がするんですけど。」と質問されて、気を悪くしたり、怒る医師は少数です。
質問される医師は、説明する機会を与えられます。
何事においてもそうですが、自分にとって当たり前のことでも、他人には当たり前ではないのです。
これは、会話をしてみないと分かりません。
「こんなことを聞いたら、ばかにされるんじゃないか」と心配になったり、ご自分にはとんちんかんな質問に思えても、それはお互いに前提としているところが違うだけです。
最近小児科では、診療報酬の制度で、かぜや胃腸炎のときに、「抗菌薬は効かないので、必要ない」と説明することに、点数がつくようになりました。医師は説明をすることが求められているのです。
【質問をするために…】
本当は聞きたいけど、どう聞いたらいいのかわからず、なんとなく診察が終わって帰宅してしまうという人は、あらかじめ聞きたいことや、自分が心配していることを、メモしておくのがよいと思います。
家で机に向かってじっくり考えて紙にメモしなくても、診察を待っている間に思いついたことを、スマホにメモしておくだけでも、いいのです。
気の利いた質問でなくてよいのです。医師とのコミュニケーションに、ちょっとだけ勇気をもって、一歩踏み込んで頂ければ、きっと、不安な気持ちの解消にもつながることと思います。
さらに、患者さん自身が、医療に関心を持つのも、大切なことです。
医師にとっても、医療の知識がある患者さんと話すことで、より効果的な治療が実現できます。
最初は難しいかもしれませんが、小さな質問の積み重ねが、一人一人が受ける医療の質の向上につながります。
そしてそれは、薬剤耐性対策にも大きな意味を持つものなのです。
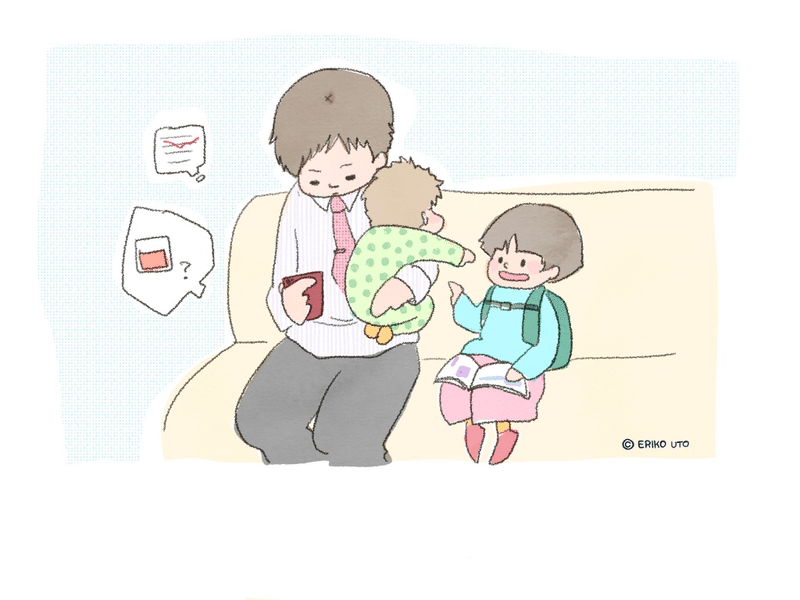
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
