
フジロック2023(Tohji)を振り返って
7/28-30にかけて、今年もフジロックフェスティバルが開催された。
私自身、今年のフジロックが野外フェス初参戦だったのもあって、全く十分な準備をできていないままに日程が訪れた。
フジロック参戦前
もちろん、いち音楽好きとして、フジロックの存在は知っていた。しかし、私の好きなアーティストたちの出演は、過去にあるはずもなく、"ロックフェス"という冠が強いだけあって、少々食わず嫌い気味になっていた。
その固定観念を壊すかのように、私の大好きなアーティストの一人であり、ここ5年、私のSpotifyのランキング上位に入り続けているTohjiの出演が決定した。
さらには、Tohji出演の同日夜にGanban Squareにて、E.O.U含むPalsoundsの面々の出演までもが決定された。
私にとっては、それだけであの高いチケット料金を無視させる理由になった。
(フジロックの高すぎる料金については、また別のポストで触れたいと思う)
Canteen Radioのフジロック回の冒頭のように、「フジ」ロックなのになぜ苗場で行うのだろう?という疑問も抱えつつ、参戦した。
フジロックに参戦するにあたり、車と宿の確保は、先決事項だった。
車は、免許を1月ほど前に取得したばかりで、嬉々として運転を楽しんでいた僕が担当し、
宿に関しては、ありがたいことに友人の別荘をお借りすることになったので、大きな問題には至らなかった。
苗場の様子
しかしながら、他の自分も同年代のフジロック参戦者は、どのように過ごしていたのか非常に疑問に思った。苗場は正直言って、フジロックの規模感に合わせて作られている都市(街)ではない。
周辺の宿も少なく(苗プリはあるが...)、コンビニもほぼない。
最寄りのスーパーも車で30分ほどかかる場所にあるため、数日を費やす観光・レジャー・エンターテインメント目的としては非常に心許ない立地で、生活インフラとしても、普段東京で過ごしている僕らにとっては、不十分と感じられるほどだった。
確かに、1日を通して屋台は営業し続けているし、食べ物や飲み物で困ることはないが、留意したいのはその価格設定。
このフジロック全体の料金設定、立地条件からは、音楽(特にロック)というものが、貴族の娯楽のようになってしまっているのか?
はたまた、カルチャーを形成していく上では無視してはならないユースの力を軽視しているのか?と思うほどだった。
Tohjiのパフォーマンス
到着から5時間ほどの間で、あの広大な会場を一周して、昼食をとった。
ロック好きの私の友人3名にTohjiの良さをなるべく最大限伝えたかったのもあって、最前列を取るため、Tohjiのひとつ前のStutsの出番からWhite stageで待機した。
いよいよ18時、Tohjiの持ち時間が訪れた。
冒頭1,2分ほど、最近来日していたBloodzboiとの楽曲、『Across the sea my dreams are born in silence』にのせて、Tohjiの今までの活動を振り返るようなビデオが正面の特大ディスプレイに映し出された。
特に、2020年(コロナ禍、緊急事態宣言下)、またTohjiが活動自粛を余儀なくされた前後を思い出させるようなシーンでは、MallboyzおよびCanteenの皆さんの心情を思うと、涙が出てきた。
楽曲が進みTohjiのパートになると、聴き馴染みのある声が聞こえてきた。しかしながら、その当人の姿は、前方にはなかった。もしやこれは?と思った私は、即座に振り返った。一番ステージの反対側をみると、そこには黒いローブを羽織ったTohjiの姿があった。

その瞬間、私と私の友人は顔を見合わせた。到着して5時間の間いくつかのアーティストを流し見た後(その後の2日間にも無いようなものでした)の私たちは、他のどのアーティストとも違った(Alternativeな)表現を、登場の段階から感じることとなった。「学校の休み時間でついつい語りたくなるようなアーティスト性」を、友達もその段階ですでに如実に感じていたのだった。
2曲目の『Oh boy』とともに、観客を分断してステージに登る動線を歩んでいくTohjiの姿は、ローブを被り後ろから登場したことも相まって、さながら「神」のように見えた(アーティストが神格化されていくことには、コミュニティ発達の観点からして批判的な立場ではあるが、ここでは、1観客として私が感じたままのニュアンスで表現したい)。また、YeことKanye Westにも似たものを、その時改めて感ぜられた。
これまたCanteen Radioで遠山さんが触れていた内容ではあるが、その動線に向かう最中に撮られた、小さな男の子がTohjiを見つめている写真は、Tohjiというアーティスト性を表現する上でも、そしてその楽曲にがっちりマッチした表現としても、非常にアイコニックな、さながら宗教画のような複数の意味を持つこれ以上ない良い写真だと感じた。
そして3曲目、私の一番好きな楽曲である『Oreo』が演奏された。Tohji自身も思い入れが深いと明言していた同楽曲は、その後観客を踊らせていくためにギアを上げていくためのものとしても、うまく作用していたと感じる。
4曲目では『SugAA』で、古くからのファン=前列の観客盛り上がりを誘いつつ、"ゲイ レズ バイ なんでもこい囚われない 括りとかFxxk 関係ない"というリリックで、6,70年台のロックのムーブメントとの共通点も感じさせ、
5曲目の『Twilight Zone』でBladee、すなわち欧州とのコネクトを感じさせ、
6曲目でついに『Ultra Rare』が演奏された。
普段のMCとは少し違い、敬語混じりでレア度を説明し、「ウルレア」という単語を観客に言わせるのではなく自身で言ったところも、後方のオーディエンスが冷めない仕掛けとして感心させられた。
その後の『Goku vibes』、Mallboyz (Gummyboy, Yaona Sui)を迎え入れての『My life』、Jerseyに合わせた踊りレクチャーを踏まえての『Mango Run』、『Do u remember me』で、後方から前方までの全てのオーディエンスの熱を極限まで高めた。
次曲の『Slomo』で、Muramasa、またまた欧州とのコネクトを感じさせ、未発表曲『Aglio e Olio』を演奏した(Tohjiの作るガーリックパスタが世界で一番美味い。とE.O.Uからタレコミを踏まえた上だったので、個人的にすごくアガッた)。
そして、2022年夏以降のTohjiを代表する楽曲である『Super Ocean Man』で、初日ヘッドライナーのStrokesにも勝るほどの大盛り上がりを見せた。
『ねるねるねるね』で、コロナ禍のリアルな音楽を表現し、『M78』で今はなきFDと、Tohji自身の幼少期に思いを馳せ、最後、『I'm a Godzilla duh』、自身のデビュー作で締めるというショーだった。
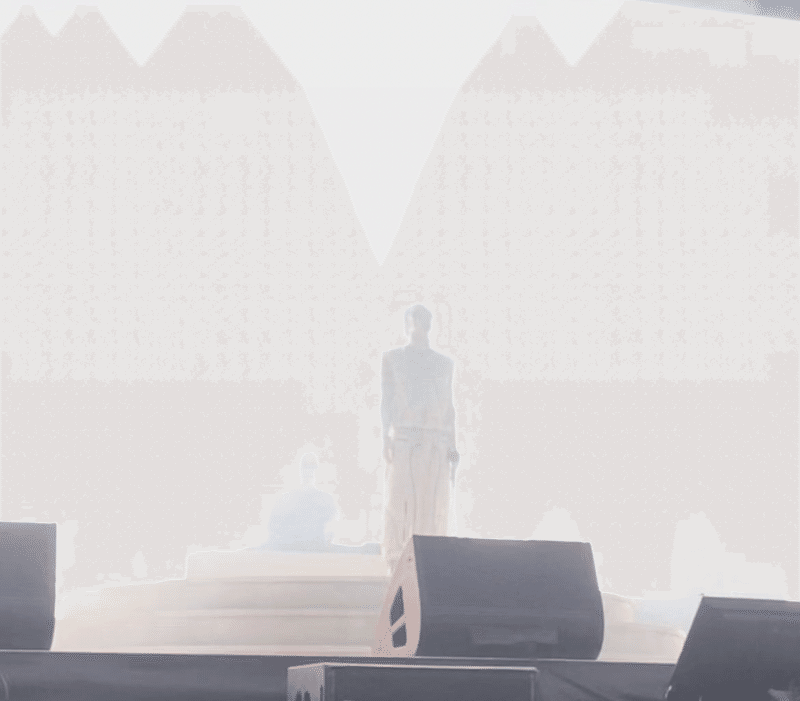
特に最後、『I'm a Godzilla duh』では、(あのキャパに対しての音響設備の上で最前列にいたからこそなるものだったのか)すぐそこに本当にゴジラがいるかのように、(普段のライブ会場にいる時のように腹に響くサウンドではなく)肌の表面が、音でピリピリしたのを感じた。その演奏の最中、はたまた涙を流してしまった。
しかし、その涙の理由が、「色々あったけど、ここまできた」ということだけではなかったのは、その後の『Mango run』、『Super Ocean Man』などの"踊ってしまう音楽"を踏まえた上でのこの『I'm a Godzilla duh』だからなのだと理解した。
自分のように深くTohji周辺の情報を知っている人間と、そうではなくただフジロックを楽しみにきた人、あるいは私の友人のように、好きなアーティストをおすすめされて聴きにきた人、たださらに奥のステージに向かうためにWhite Stageを経由しただけの人。多種多様な人々が一つのステージに集められて音楽を聴いて踊っているこの状況こそが、大規模フェスあるいは音楽、カルチャーそのものの楽しさなのではないかと感じたからだった。
カルチャーの本来性に近しいものを感じつつ終えたTohjiのショーケースは、ロックフェスという一見アウェーな場所でのパフォーマンスだったことを感じさせないもので、Mallboyz、およびCanteenの皆さんの底力を感じた。
そのためか、3人の友人から口を揃えて「お前がいなかったらフジロックこんな楽しくならなかったと思う、本当にありがとう」と私が感謝される状況にまでなった。
ダンスミュージックにすっかり惹かれた、私の友人3名は、その日の夜をPalsoundsで踊り明かし、翌日もRomy、私たちの中高大の先輩にあたる小袋斉彬で踊り明かした。
結果として、私のすごく身近で明確に生じた間違いのないこととしては、ロック好きな私の友人3名をMall boyzおよびCanteenの皆さんの尽力によって生まれた"良いカルチャー"が、彼らの音楽に対する意識を変革させ、彼らの人生を豊かにした。
また、あれほどステージで盛り上げていたTohjiチームの方々が、毎夜Ganban Square付近で遊んでいたのも、友人達(私も含む)にとっては、親近感とアーティストとしてのアティテュードのピュアさを感じさせる情景として記憶に残った。


Tohjiチームの皆様、この上なく楽しく、踊れるショーをどうもありがとうございました。
吉川翔洋
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
