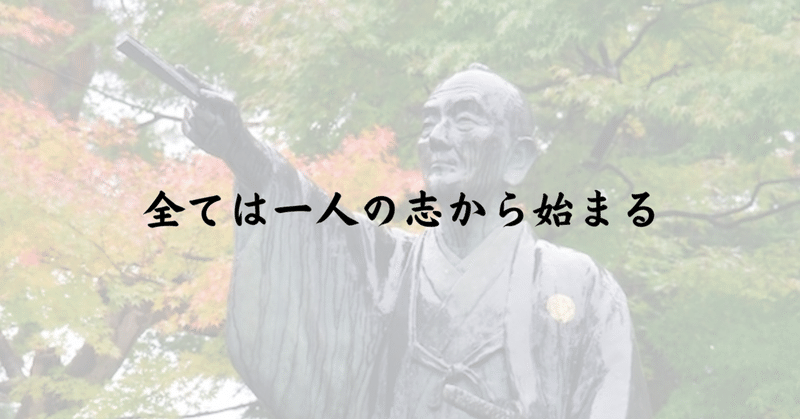
志の醸成と事業構造の成立の親密な関係性
32歳で起業した私の創業の志は「職人の地位向上」でした。それから20年以上の年月が過ぎましたが、今も基本的な想いは全く変わらず、志に向き合って事業を続けています。ただ、学なし金なしコネなしだった時から比べると年月を経た分、それなりの変化もあり、想いが少しずつ形になってきました。志を掲げ、それに根気よく向き合っているとそれが徐々に形になる(構造化されて行く)のだと最近、感じることが多く、一見、金儲けに繋がりそうにない「志」と持続的に収益を上げる「事業」の関係性について整理してみます。
志というのも烏滸がましい
私達は2001年、有限会社すみれ建築工房として大工3人で法人を立ち上げました。持っているのは現場技術と経験、あとは大工道具くらいの全くの徒手空拳でしたが、自社大工が在籍するフットワークの軽さと幅広い経験、大工としての建築技術に強みを持った施工会社として、大手ハウスメーカーや不動産会社、デザイン事務所の下請け工事店としてスタートしました。
創業の志は「職人の社会的地位の向上」でしたが、正直、自分たちが社会的に地位を認められる職業になりたい、もっと安定した不安のない生活を送れるようになりたいとの自分とスタッフメンバーの課題解決でした。今考えれば、志と言ってたのさえ烏滸がましいです。。
しかし、法人を立ち上げてからは、すぐに動く便利な大工集団として人気を博し、少しずつスタッフの人数も売り上げも増えて2005年には本社ビルを建設。それを機に元請け工務店へと転換し一般消費者向けの宣伝広告、イベント開催を行い集客活動を開始しました。同時に大工だけではなく、設計事務所として登録し、設計部メンバーの採用、育成もスタートして新築、リフォーム、店舗工事の3本柱の設計施工を自社社員でワンストップで提供する工務店に業態変更したのでした。

目的への糸口
その翌年、売り上げが安定しない建設業の経営を構造からなんとかしたいと考えて原理原則に則ったマーケティングへの取り組みをスタート。その分析の中で「自社職人での直接施工」という強みを見出し、建築会社としての本質的な地力をつけると共に、現場での顧客接点の強化を目指して職人の正規雇用と社員教育に踏み切りました。コーチング研修の導入や職人向けにマーケティング理論を紐解く社員職人の教育、顧客との繋がりを深めるシクミづくりを加速させ現場でのコミュニケーションの向上、積極的なアフターフォローの実践により、マス媒体による販促活動を一切取りやめても売上げ利益を維持するビジネスモデルを構築することができました。宣伝広告費を職人の福利厚生費に充てることで、正規雇用にかかるコストアップの一部を吸収することが出来る様になりました。それは職人の地位向上の糸口を見つけられた瞬間でした。
志の具現の可能性を見出せたのには、現場作業以外の慣れないことに懸命に取り組み、ついてきてくれた大工のメンバーに本当に感謝しています。

志の具現の胎動
社内教育の一環としてスタートした「職人起業塾」は、マーケティング理論の理解を深め、建築現場の実務に落とし込み自社独自のマーケットを構築するグループコーチングで、当時のすみれ建築工房本社で開催する職人起業塾に同業他社の経営者や職人が多数集い、その後、口コミで人気を博し異業種の経営者も参加するようになりました。
2015年には社員大工達に研修を始める当初、スタッフにに言っていた通り、自社で蓄積したノウハウを外部に展開する研修事業を開始。JBN(全国工務店協会)より依頼を受けて社内で行っていた研修を全国の建築実務者向けに事業化、研修内容を元にした書籍「職人起業塾」を出版すると共に研修事業として厚生労働大臣の認定を受けることができました。職人の社会的地位の向上は自社だけできれば良いのではなく、日本中の職人が安心して、生き甲斐を持って働ける環境作りだと視野を広め、視座を高めた一歩を踏み出しました。
2017年には鹿児島、大阪、東京、福岡、仙台にて塾を開講、活動を全国に広げ、自社で構築した人事制度も公開し職人の働き方の改革、工務店の業績と職人の地位の向上の両立の支援を開始しました。創業の志が全国規模で広がり出したのに胸を震わせたのを覚えています。
VUCAの波
研修事業で北は仙台から南は鹿児島まで全国を飛び回りながら、本業の建築事業では時代の大転換が押し寄せている危機感を感じて2020年の創立20周年を機に事業を再構築、二十年親しんだ社名まで変えて株式会社四方継に組織変更、地域への貢献を事業にする地域課題解決型事業モデルへと大きな転換を行いました。脱建築を掲げ、広く地域経済の活性化に取り組む事業は簡単に収益化出来るとは思いませんでしたが、新しい時代に適応するには、これまでの路線の踏襲ではなく、思い切った共感型ビジネスモデル、本気のCSV経営への転換が必要だと思いました。同時に株式の30%を社員に譲渡し事業承継プロジェクトをスタートして、持続可能な事業所への構造化に本格的に取り組みました。
その取り組みの甲斐あって、2022年には株式会社四方継が未来創造企業の認定を取得、持続可能性と社会性の高い事業を行っているとの評価を頂きました。長年、志と原理原則に向き合ってきて職人育成を基盤に置いたビジネスモデルが、日本最高峰のシンクタンクが監修して策定した良い会社の基準に適合したのは大きな自信になりました。
答えは内にあり、課題は外にあり
新型コロナによるパンデミックの影響で対面式の研修事業はほぼ止まりました。次々に押し寄せるVUCAの波に戸惑いと怖れを抱きましたが。同時にこれまでの歩みを見直す機会になりました。職人の社会的地位の向上を掲げた取り組みを続けて来たのが、実は身の回りの限られた人だけに情報を伝える程度の影響しか発揮できていないことにも気づきました。そのタイミングでCSV経営の研究会である経営実践研究会に入会し、社会課題解決型モデルを実践されている経営者の方々から教えを頂き、本当に社会課題を解決するならスケールするスキームを構築すべきだとの示唆を頂きました。建設業界の狭い範囲だけに囚われていては、本質的な課題解決に繋がらないと気づき、視野を広げ、視座を高めるべく研究に乗り出しました。その結果、職人になりたいと思える若者がいない根本に目を向け、圧倒的に増え続けている学歴社会からこぼれ落ちる子供達にチャンスを与えられるように、安心して、尚且つ将来を標榜して働ける受け入れ企業側の環境整備と、社会で活躍できる能力を身につけながら高校卒業資格を取得できる職学一体の学校の設立、全国への普及のアイデアを生み出し、同志を募りました。二つの社会課題を同時に解決に向かわせることで、建設業界だけでなく、教育業界や人材不足に頭を悩ませている製造業の方々にも共感され、一年をまたずしてそれが実現、現在、全国に広がりを見せています。
志の醸成と事業の構造化
志を立てて、以て万事の源となす。とは吉田松陰先生が遺した至言です。全ては一人の志から始まるとの文脈は現代の最先端の組織論、ソース理論でも同じことが語られます。それは確かにその通りかも知れませんが、自分の身の回りを良くしたいとの小さな志には誰も共感してくれません。私がこれまで、志の具現を目指して歩みを続けてきた20数年間を俯瞰してみると、多くの人に共感され、ムーブメントを起こすには志を何度も繰り返し練り直す醸成と、より高い視座、広い視野で多くの人への価値提供出来るように錬磨が不可欠です。本業そのもので社会を良くしたいと願うならば、厳しい市場原理の中で価値を生み出す実業を行い、持続可能性を高めながら、本当に解消したいと思える世の中の不条理、そこで体験した蹉跌を見つめて、次の世代に少しでも良い世の中を残せるようにとの、真摯で誠実な在り方を体得する学びを続ける必要があると、つくづく思います。
真のCSV経営へのシフトは厳しく、難しい課題をいくつも乗り越えなければなりませんが、志の具現を目指し、考え、学び、取り組み続けることで必ず道が開け、根本的課題解決=構造変容に結びつくと思うし、強く信じています。これからの二十年で日本の建設業界とキャリア教育のスタンダードを変えるつもりで歩みを進めていきたいと思います。
_______________
現場実務者の才能を開花させることで真の民主的な組織と事業を生み出すお手伝いをしています。ご興味がある方は是非、繋がってください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
