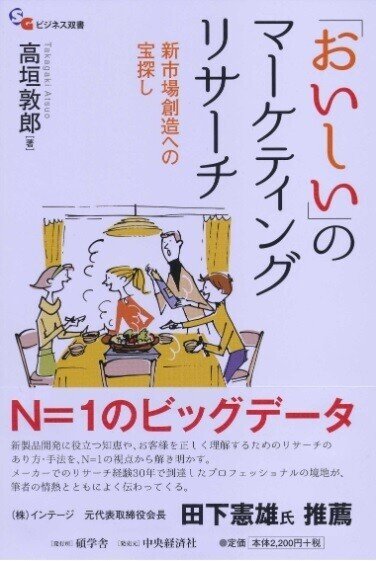『「おいしい」のマーケティングリサーチ』
【マーケティング定番書籍】その15
『「おいしい」のマーケティングリサーチ』
著著:高垣敦郎
出版社:碩学舎
第1刷:2016年1月10日
1. 本書を読んだ背景
2016年1月、本書を出版された高垣氏(1976年にハウス食品工業入社)がJMRX勉強会でご講演されることを知るまで、恥ずかしながら著者の高垣氏のことを存じておりませんでした。
(今からでも遅くはない)と読んだ次第です。
2. どんな人に向いているのか?
・マーケティングリサーチを志向する学生
・入社間もないマーケター、リサーチャー、製品開発者
・(N=1だけでなく)文字通りの「ビッグなビッグデータ」と格闘しているデータサイエンティスト
「はじめに」で元インテージの会長さまが「著者の言うように」と記した上記で「概ね」いいと思います。
私が「概ね」と言うのは、食品・飲料業界のリサーチ以外のセクションの皆様(新人・ベテラン関係なく)、製品開発以外の皆様にもお読みいただいたほうがいいのでは?
と思っているからです。
3. 本書のポイント
3-1. いきなり「我田引水」させていただきます(笑
「デスクリサーチなんて、ググればいいだけじゃん!?」とドヤ顔で仰せの(特にベテラン)リサーチャーが少なくない情けない状況の中、著者は、セカンダリーデータ収集・整理・分析を自らの手で行われ、その重要性を強調されていることは特筆に値することです。
それも「ググる」だけではなく、2か月間かけてなされた専門機関や有識者へのインタビュー、国立国会図書館での情報収集。
素晴らしい!
3-2. 心理学の知見を活かされた独自のモデリングでしょうか? ふたつめは。
【メンタルマップ ~なぜお母さんは料理を作るのか~(ラダリングによる分析)】
【認知行動を促進する要因と阻害する要因】
【食の心理学における学術的知見~総論】
【おいしさの意味 心理と生理】
【「香り」を使用することばの構造】
【「宝探しのキー」まとめ】
そして、、私の業務とも関係の深い、
【食の未来予想年表①~③】
勉強になります!
業務に携われて間もないリサーチャーの皆さまは、食品関連リサーチで調査票を作成する際、【図表29 デパートのお惣菜売り場メニューに使われている言葉】とかご参考にされればいいと思います。
ワーディングのいい勉強になることでしょう。
3-3. シンプルに、味のプロフェッショナルの著者が世の中のために出していただいた本、ということでしょうか。。
4. 感想
とても素晴らしい書籍(それも石井淳蔵先生の出版社・・)ですので、あえて自分の見解との相違点を一つだけ挙げさせていただきます。
たしかに、著者が仰せのように食事は一人より複数の人と食べたほうがおいしいのかもしれません(科学的知見もあるとは思います)。
でも、私は、純粋に味を楽しみたいのなら、一緒にいる人のことを気にしないよう、独りだけで味わったほうがいい、という考えも持っております。
(という意見とは関連ありませんが)私が気になったのは著者が、食品メーカーは小分けパック(個食用)とか発売すべきではない、と仰せのことです。
セカンダリーデータへの造形が深い著者のことですので、改めて言うまでもないとは思ったのですが・・。
単身者(未婚者や離死別者など)が増加しており、これからも増えていくことは言うまでもありません。
私も単身者です。
小分け商品のことではありませんが、この文章を書いている今現在、冷蔵庫の中の大根を余らせないために、腐心しながら買い物をしてきたばかりです。
単身者にとって野菜は、2分の1よりも4分の1に切ってあるキャベツ、なるべく短く切ってある大根でないと、余らせて廃棄せざるを得ないわけで切実なのです。
同じように、小分けされた惣菜とかも、単身者にとっては有難いのです。
繰り返し言うまでもなく、著者は人口動態のことは私よりもおわかりかもしれませんが、単身者のことについては、私よりお詳しくはないのでは? と思ってしまうこと、お許しください。
本書のカバーの素敵な絵も、家族4人の「標準世帯」なんですね。
それはそれで「理想の姿」なのでいいとは思うのですが。
(著者にとっては)若輩者の小生です、失礼いたしました!
以上です。
◆デスクリサーチ資料はこちらです(↓)
◆ホームページはこちらです(↓)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?