胃の血
弊社(私の好きな作家に準えて私は自分の勤め先をこう呼んでいる)には立派な枇杷の木がある。
夏が近づくとオレンジ色のぷくりとした綺麗な実がつき、それを虫やカラスが摘んでいく。時々、私も食べている。
話では二十年ほど前に植えたものと記憶しているが、それが今も生きているのだから、自然の力強さを感じずにはいられない。
ぼとぼとと落ちて潰れた枇杷の身は甘酸っぱくて土臭い独特の香りがするが、悲しくはない。
けれど来年、私はこの枇杷を食べるのだろうか。
植物にしても動物にしても、私は何かを育てるということが好きだ。
自分のことはどうでもいい。犠牲にしても構わないから、出来る限りの愛情すべてを注ぎ込んで育てたい。
世界は陰湿で、捻じ曲がっていて、正しくないものが正しいとされ、守られるべきものが守られずにいて、こんな世の中に存在していても仕方がないと思う。けれどその中に光があれば、人はそのために強く生きていける。それを紡いでいくのが人間の役目なのかもしれない。
闇の中に、いや、光の中に、どうか穏やかな顔で君が笑って立っていてくれますように。
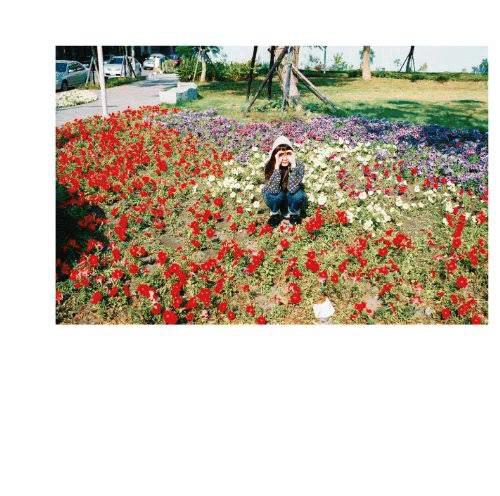
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
