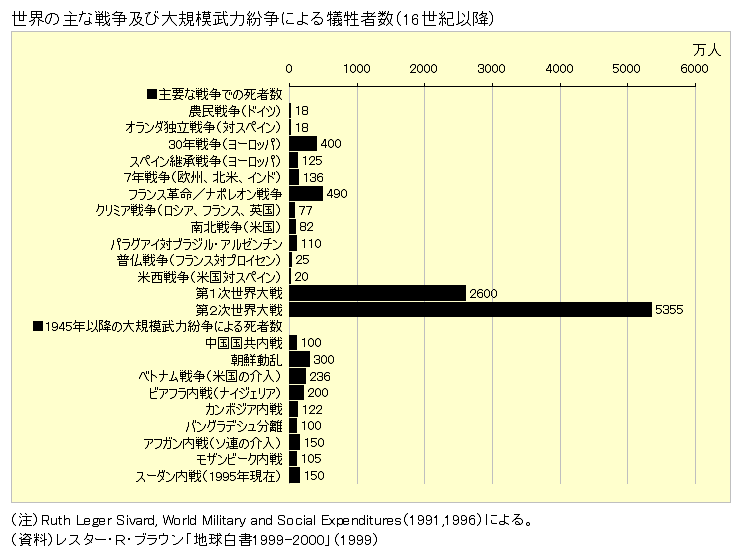戦争のメカニズムと対処の軍事学 ①
人は何故、争うことを止められないのか?
古代アテナイの歴史家トゥキディデスは、戦争が勃発する原因 として「利益」「名誉」「恐怖」という3 つの要素を挙げた。
プロイセンの高名な戦略家クラウゼヴィッツは『戦争論』において、「戦争は外交とは異なる手段を用いて政治的交渉を継続する行為」にすぎないと語った。
しかしその一方で彼は、戦争の本質を「拡大された決闘」だとも言った。
だからクラウゼヴィッツのいう「戦争は政治に内属する」という指摘は、シビリアンコントロールの観点から、"そうでなければならない、そうあるべきだ"ということのようで、実際に彼は「戦争における重大な企てとかかる企ての計画を純軍事的な判断に任せてよいといった主張は、政治と軍事を明確に区別しようとする許しがたい思考であり、それ以上に、有害でさえある」と言及していた。
戦争が「欲望」だとか「恐怖」などの感情によって支配されて引き起こされている限り、その暴走を引き止めることはできないので、クラウゼヴィッツとしてはあくまで「戦争」という行為を、人の本能ではなく「理性」のレベルでコントロールすべきだということを主張したかったのだろう。
クラウゼヴィッツが考えていた「戦争」という概念は、ナポレオン戦争以降の「主権国家」同士によって行われる戦争が想定されていた。
しかし、人類の戦争は過去の歴史や地域によってその形態は様々で、クラウゼヴィッツ自身、「戦争はカメレオンのように時代や地域によって多彩な変化を見せる」とも語っていた。
歴史学者の石津朋之氏は、絶対的な主権国家の登場にともない国家による暴力装置の独占状態が完成した後においてさえ、政治による戦争の管理は、現実には多くの国家指導者を悩ませてきたと指摘する。
イスラエルの歴史学者クレフェルトもクラウゼヴィッツに対する批判として、第一に、クラウゼヴィッツは、あたかも戦争が主権国家間だけで生起するものであることを所与のものと考えている点を挙げ、第二に、人類が起してきた数々の戦争は、必ずしも「外交とは異なる手段を用いて政治的交渉を継続する行為」ではなかったという点について指摘した。
例えば古代中国の戦争は、総じて、武力による衝突というよりも、むしろ道徳的価値観を競う試合のようなものであり、そこでは「名誉」が競い合われていた。
クレフェルトも、例えば、中世ヨーロッパでの王朝国家間の関係では、政治といった要素よりも「正しさ」の要素が重要視されていた事実を取り上げ、正義のための戦争が存在していた事実を主張する。
旧約聖書の時代や十字軍の時代は、宗教戦争の時代と位置付けられ、「宗教」が戦争のもっとも重要な原因だった。
スペインのフェリペ2世が何のために戦争をしたかといえば、第一に、それは「名誉」のための戦争であり、第二に、宗教的使命感に基く戦争、すなわち神へのサービスとしての戦争だった。
神へのサービスとは、カトリックに反する新興プロテスタント諸国、とりわけイギリスおよびオランダに対する戦争は、神に対する神聖なる義務であったと考えられていたのだという。
他に、「正義」や「宗教」の戦争に加えて、「生存」を賭けた戦争も存在する。
中世ヨーロッパ初期のフランク王国の時代には、戦争が「生計維持」の一手段で、戦争で生活資源を獲得すること、それが当時の戦争および兵士のエートスだったという。
また、クレフェルトは、史実を援用しつつ、人類が戦争に取り憑かれてきたのは、戦争が危険や歓喜といった不可測な何かと隣り合わせになっているからこそであると指摘し、戦争とは政治の延長などではなく、スポーツの延長として捉えられていた面もあったと主張する。
実際、第一次世界大戦前の戦争に関する文献を調べてみれば、狩り(ハンティング)やクリケットとして見た戦争、さらには戦争という栄誉ある教義といった表現がいたるところで散見されるといい、そこでは戦争という行為が、まるで「芸術」や「スポーツ」のような感覚で認識されていた。
特に、フランスのルイ14世の戦争は、政治とはほとんど関係なく、あたかも時期を迎えた狩りのようなものだったという。
石津氏によれば、19世紀には、「戦争はその本質においてすべてのくだらない計算や利己的動機の超越である」といった考えの戦争観が見られるようになり、そこでは戦争に臨んで、最高の「私利」であるはず生命そのものの放棄さえ構わないほどだった。
『戦略論』の著者で知られるイギリスのリデルハートは、「軍隊での生活こそ男性にとっての唯一可能な理想であり、男性のもっとも優れた特性を導き出すものである」と語り、また、イギリス国内での完全な徴兵制度を支持する旨を明言して、「もし徴兵制が熱心に施行されるのであれば、最高レベルの精神的、道義的、そして肉体的特性に発展させ得るのであり、同時にそうした発展を要求することになる」とも主張していたほどだった。
彼はまた、真の意味での男らしさとは何かについて理解しないただの思索家や読書に耽る学者に対して、むしろ軽蔑の念を抱いていたという。
ただしリデルハートのこうした主張は、彼がケンブリッジ大学に在学中の19歳のときに、志願して軽歩兵連隊の少尉として第一次世界大戦に参加するまでの発言で、リデルハートは大戦終結後、それまで抱いていた「戦争」に対する認識を、大いに改めさせられることとなった。
彼は、戦争に対する英雄的かつロマンティックなイメージと、実際に経験した惨禍の間の、あまりにも大きなギャップに衝撃を受けた。
実際それほど、「第一次世界大戦」とは、それまで人類が経験したこもないほどの、夥しい数の膨大な犠牲者を生み出した戦争となった。
ただしリデルハートは戦争そのものを否定したのではなく、彼は大戦前、「攻勢主義」一辺倒だった各国の軍事戦略のあり方を厳しく批判し、極力、機関銃によって武装された塹壕戦に対する被害を抑えることを基本とした「間接アプローチ戦略」と称する数々の新しい軍事戦略を打ち立てていくこととなる。
直接の戦闘の勝利によって自国の政治目的の達成を目指したクラゼヴィッツの軍事戦略思想に対し、リデルハートの主唱した「間接アプローチ戦略」は、直に敵軍と交戦して消耗することを極力避け、「攪乱」や「奇襲」など敵の弱点に対する力の集中を核とする方策を提示。
リデルハートは彼と同時代に活躍した『機甲戦理論』の主唱者として知られるイギリス軍人のフラーらとともにいち早く、戦車や自動車や航空機の機動力を活かした縦深作戦について着目し、そのアイデアがまたドイツ人将校に参考にされ、後の第二次世界戦におけるグデーリアンの「電撃戦」へ応用されるなど、その点において、第二次大戦では、第一次大戦で多大な犠牲を生み出した消耗戦を打破する結果へとつながった。
とにかくできるだけ敵軍の主力とまともに衝突する消耗戦を避けることを狙いとし、機甲戦以外には非通常戦争の「ゲリラ戦争」などにもリデルハートは早くから注目していた。
その他では、直接相手との交戦をまじえることなく「封じ込め」政策で対峙していく「冷たい戦い(冷戦)」(=「相互に武装したままの共存)といった概念や、「防勢の優位」の確立、「集団安全保障制度」の構築、「限定関与政策」といった戦略思想など、これらは皆、「相互破壊」をすることなく、互いの政治的な対立問題の解決を探っていこうという主旨のもとに考え出されていったもので、そして、このようなリデルハートの軍事思想は第二次世界大戦後、西側諸国では「リベラルな戦争観」として受け入れられ、広まっていくこととなった。
まだ記事は少ないですが、ここでは男女の恋愛心理やその他対人関係全般、犯罪心理、いじめや体罰など、人の悩みに関わる心理・メンタリズムについて研究を深めていきたいと思っています。