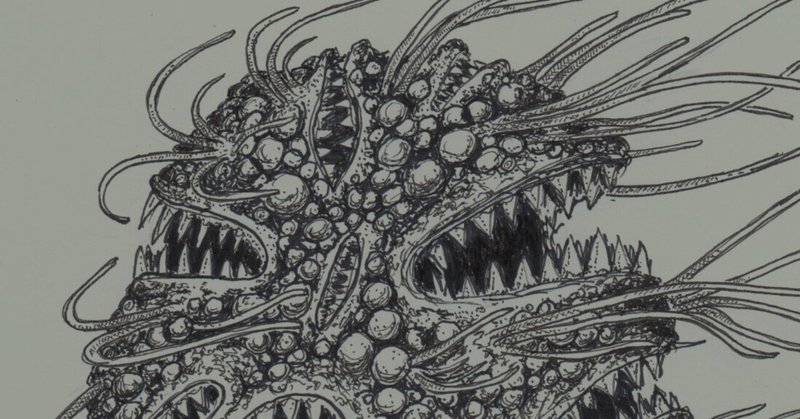
縄張り 第4話
枕元のアナログ目覚まし時計の文字盤が、ぼんやりと闇に浮かんでいた。時針や分針がどこを指しているのか、なかなか見定められない。それでもなんとか目を凝らし、午前一時前であるのを確認した。
タオルケットさえかけていないのに、わたしはこの蒸し暑さで目を覚ましたのだ。エアコンの電源は美凉が切ったらしい。暑さに強い美凉にリモコンを渡すべきではなかった。
「美凉、マジで暑いよ。エアコンをあと一時間だけ、だめ?」
熟睡中に起こすのは気が咎めるけれど、これ以上は我慢できない。
「ねぇ、暑くて死んじゃいそうなの」
もう一度声をかけて、美凉のほうを見る。
「え?」
テーブルをどかして敷いた布団の中に、美凉はいなかった。
トイレにでも行ったのだろう、と思ったそのとき、玄関ドアを閉める音がした。
わたしはベッドから飛び起きた。
明かりを点けずに、ベランダ側のカーテンを開ける。
家の前の道路に、Tシャツにストレートジーンズという後ろ姿があった。その長い黒髪の持ち主を見紛うはずがない。
そうしているうちに、美凉は山村さんの家の通用門からその敷地に入ってしまった。
窓を開けようとしたけれど、こんな夜中に大声を出すわけにはいかないだろう。
「美凉ってば、何を考えているんだか」
探偵ごっこにもほどがある。美凉にしてはあまりに稚拙な行動だ。
やにわに、スマホで呼び出そうと思いついた。着メロの音量だってそれなりにあるのかもしれない。けれど、窓を開けて叫ぶよりはましだ。
「――って、どうしてそうなのよ!」
目覚まし時計の脇からスマホを取ったわたしは、部屋の隅を見て愕然とした。スクールバッグやリュックと一緒に、美凉のスマホが置いてあるのだ。
わたしは自分のスマホを枕の上にほうり出し、部屋を飛び出した。階段を駆け下り、サンダルを履いて玄関ドアを開ける。
道路に出たわたしは、ふと、別の不安に襲われ、自分の姿を見下ろした。Tシャツにジャージのハーフパンツであるのを知り、とりあえず安堵する。肌の露出が多すぎるこの時期ならではの恥ずかしい姿だったら、迷わずに引き返していただろう。できるなら、この湿っぽく淀む空気の中では、一糸もまとわずにいたいのだけれど。
月のない天空が地上の闇さえ支配していた。街灯の明かりだけが頼りだ。
どこか遠くで何匹かの蛙が鳴いていた。それ以外には物音一つ聞こえない。
山村さんの家の通用門は、門扉が半分ほど開いていた。庭の奥では山村さんの車が番犬のように身を潜めている。
わたしは思いきって通用門を通った。サンダルでの忍び足に難儀しながら、玄関先を横切り、芝生の上を進む。そして家の裏まで回り込んだけれど、静寂に包まれた暗がりに美凉の姿はなかった。
山村さんの家の裏を回ってわたしの家に戻ったのかもしれない。玄関の鍵は開けたままだから、勝手に入れるだろう。もしくは、わたしが自分の部屋を出ようとしたのと同時に戻ってきて、トイレに入った可能性もある。とりあえずは自宅に戻ったほうがよさそうだ。
あまりの暗さに山村さんの家の裏を回っていくのはためらわれた。来た道を戻るのが賢明だろう。
再び山村さんの家の玄関先を横切ろうとして、わたしは足を止めた。
まさかとは思いつつ、玄関のドアノブを握る。
ドアに鍵はかかっていなかった。一瞬の逡巡ののち、静かにドアを開ける。
やはり杞憂では済まされなかった。乱雑に脱いであるのは、美凉のスニーカーではないか。
廊下の奥の闇に目をやると、美凉の姿があった。階段の上り口の手前、向かって右側の壁際に立っている。ペンライトの光をその壁に当てている美凉は、わたしには気づいていないらしい。
壁には高さ一メートルほどの観音開きの扉があった。左右の取っ手を大きな錠前が繋いでいる。
わたしは驚愕した。ペンライトの光で確認しながら、美凉がその錠前に鍵を差し込んでいるのだ。
「美凉」
声をかけたというよりも、つぶやきに近かった。
美凉がわたしに顔を向ける。
「澪……」
「何やってんのよ」
わたしは声を抑えた。とにかく美凉を連れ出さなくてはならない。
「早く出てきて」
トーンが上がりそうになるのを、ぐっとこらえた。
それでも、美凉は首を横に振った。
業を煮やしたわたしは、玄関に入ってドアを静かに閉じると、サンダルを脱ぎ、美凉の元へと進んだ。
「澪には関係ない。早く帰りな」
静かに言った美凉が、錠前を外した。そして、いくつもの鍵の束なったキーホルダーを、ジーンズの右後ろポケットに押し込み、ペンライトの光を下に向ける。
「今の鍵、何? まさか、玄関の鍵も美凉が開けたの?」
わたしは美凉に詰め寄った。
「早く帰りなって」
錠前を左手で握り締める美凉は、面倒臭そうにわたしを見た。
「一人で帰れるわけないじゃない」
募る苛立ちを、どうにかして美凉に伝えたかった。
「あのさ、澪」美凉はわたしの耳元に口を近づけた。「はっきり言っておくけど、ここで押し問答しているほうがやばいんだよ。あのおっさんに気づかれちゃうじゃん。一人で帰れないのなら一緒にいてもいい。だけど、もう何も質問しない、何も話しかけない……って約束して」
「わかった」
頷くしかなかった。美凉が何をしようとしているのか、さっぱりわからない。けれど、その何かを成し遂げるまでは、外へ連れ出すのは無理らしい。
美凉はわたしに背中を向けると、観音開きの扉を左右にゆっくりと開いた。そして、ペンライトの明かりを扉の内側に向ける。
美凉の肩越しに覗き込んだわたしは、危うく声を出すところだった。収納スペースかと思ったその中に、右方向へと下りていく階段があるのだ。
美凉は階段の下り口の壁をペンライトで照らした。小さなスイッチが見える。美凉が手を伸ばしてそのスイッチを入れると、階段と平行した傾斜の天井に明かりが灯された。
ソフトボール大の照明が二つしかないにもかかわらず、階段の一番下まで十分に見通せた。急な階段の高低差は五メートル以上はある。下り口の床は廊下と同じく木製なのだけれど、階段や壁、天井は、灰色のコンクリートで固められていた。
明かりを消したペンライトをジーンズの左後ろポケットに差し入れた美凉は、錠前を左手に持ったまま、身を屈めてその空間へと足を踏み入れた。こうなれば、わたしだって入らないわけにはいかない。
傾斜つきの天井は意外に高く、わたしたちが背を伸ばしても頭をぶつけることはなかった。とはいえ、二人が横に並ぶにはやや狭い。
窮屈な空間にもかかわらず、美凉はわたしの横にしゃがみ込んだ。静かに観音開きの扉を閉じ、再びわたしの前に立つ。地下への案内人、そんな雰囲気の後ろ姿だった。案にたがわず美凉がゆっくりと階段を下り始めたので、わたしはその後ろに従う。
コンクリートの階段が素足に冷たい。冷たすぎて痛いくらいだ。暑さが苦手なわたしでさえ歯を食い縛っているのに、わたしと同じく素足の美凉は、平気なのだろうか。
一直線の階段を下りると、正面に普通サイズのドアがあった。美凉はそのドアノブを握ったけれど、どうやら鍵がかかっているらしい。
美凉はすぐに鍵束を自分の目の前に掲げた。そして、迷わずに選んだ鍵を、ドアの鍵穴に差し込む。
「その鍵、どこで手に入れたの?」
思わず声を出してしまった。
美凉がわたしを睨む。
わたしは自分の顔の前で両手を合わせた。
許してくれたのかどうかわからないけれど、美凉は無言でドアを手前に引いた。
ドアの向こうには、深い闇があった。階段側から差し込むわずかな明かりのおかげで、そちらの床もコンクリートであるのがわかった。
美凉はその闇に足を踏み入れ、ドアの奥に向かって右の辺りを右手でまさぐった。照明のスイッチを入れたらしい。まばゆい光が闇を蹴散らした。
わたしもその光の中へと進んだ。ひんやりとした空気を頬に感じる。
そこは三メートル四方程度の部屋だった。階段側と同様に全面がコンクリート張りで、正面には今開けたばかりのドアと同じようなもう一つのドアがある。左側の壁の上部で静かに音を立てているのは、どうやら換気扇とエアコンらしい。天井で輝く三つの球体は、階段側のものと同型の照明だ。調度の類いは見当たらない。
振り返ってよく見ると、確かにドアの横にスイッチがあった。照明のスイッチなんて、おおかたドアの横にあるものだ。美凉がすぐに照明を点けられて当然だろう。けれど、彼女の行動の一つ一つがスムーズすぎるのだ。予め鍵を用意したうえでこの家に忍び込むなんて、それだけでも解せないのに、まるで手慣れた泥棒ではないか。
わたしが混迷していると、美凉は後ろのドアを静かに閉じた。
「ここなら、小声で話すぶんにはいいよ」
美凉はわたしに向き直り、声を押し殺した。
「いいの? 質問だらけだよ」
わたしもボリュームを下げた。
「だろうね。できるだけ答えるつもり。ただし、さっさと済ませないと、おっさんに見つかる確率が高まるよ。階段の明かりは点けたままで、鍵も開けっぱなし。ま、階段の照明のスイッチは上にしかないし、鍵だって外側からしかかけられないんだ。おっさんが目を覚まさないように、と祈るしかない」
左手に錠前を掲げた美凉は、それを軽く揺らした。
「なら、一番気になっていることだけを質問する」わたしは奥のドアを指差した。「そのドアを開けて先へ行くんだよね?」
美凉は頷く。
「そうだよ。そのドアの先に何があるのか確認するだけ。そうしたら、すぐに澪の家に戻ろう」
「諸々の事情は、あとで説明してね」
念を押した。状況が把握できない、という不安がそうさせた。
「了解」
覚悟を決めたわたしに微笑んだ美凉は、奥のドアの前に立った。
「いつもここまでだった」
美凉は意味不明な言葉をつぶやき、ドアノブを握って軽く揺すった。どうやらここも施錠されているらしい。
それを承知していたのか、美凉は鍵束を取り出すなり手際よく解錠した。
「行くよ」
鍵束を後ろポケットに戻した美凉は、振り向きもせずにドアを手前に引いた。
「うん」
すくむ足に活を入れ、わたしも美凉に続く。
沈黙する闇の中で見下ろすと、背後の明かりが、細かく織り込まれた薄茶色の床を照らし出していた。素足になじむそれは、コンクリートでなければ木でもない。
美凉が再びドアの横の壁をまさぐり、天井に十本ほどの細長い照明が灯された。その空間の全貌があらわになる。
前の部屋の五、六倍はある広い部屋だった。天井と四方の壁は同じくコンクリートだけれど、床一面には畳が敷き詰められている。正面の壁を見上げると、ここにも換気扇とエアコンがあった。やはりどちらも作動しているようだ。向かって右には奥行きがあり、その突き当たりの壁際に、白い屏風が立っている。
「んっ」
美凉が顔をしかめた。
わたしもすぐに気づく。
「美凉……この部屋、なんか変だよ」
複雑なにおいが漂っていた。その異臭の元が何かはわからない。さまざまなにおいが混然としている。お香や畳、洗剤、黴、糞尿など、それらのにおいだろうか。
「うん。絶対に何かある。澪、急ごう」
屏風を目指して歩き出した美凉に、わたしは並んだ。
「ねぇ、ここのドアは閉めなくていいの?」
「そんなのいいよ。てゆーか、早くしないと」
もっともな答えだろう。
けれど、ふと後ろに視線を流したわたしは、美凉の腕にしがみつくしかなかった。
じれったそうに立ち止まった美凉が、振り返るなりびくんと震えた。
開け放たれたままのドアのこちら側に、パジャマ姿の山村さんが立っていた。やや猫背ぎみの長身痩躯が、地下世界を徘徊する亡者のように見える。
「なんだ、おまえたちは!」
声を荒らげる山村さんは、右手に文化包丁を握っていた。
「あの……」
言葉を失ったわたしを、山村さんが睨む。
「向かいの関口とかいう家の娘が、なんでここにいるんだ!」
わたしが誰なのか理解したらしい山村さんは、表情をさらに険しくした。
「すみません。本当にすみません」
山村さんに頭を下げなければならないなんて、この上なく悔しかった。
「不法侵入というやつだな!」
息巻く山村さんを前にして、悔しがっている場合ではないと悟った。わたしたちのしていることは犯罪なのだ。通報されたら警察に捕まってしまう。学校だって退学だ。
「この子は関係ないよ」美凉がわたしの前に出た。「この子はあたしを止めようとしただけなんだ」
そう言ってくれるのは嬉しい。つかまりたくなければ、退学だって嫌だ。けれど、わたしはここまで来てしまった。美凉と行動をともにしたのである。それに、わたしにとってたった一つの友情は、何があっても守りたかった。ならば、下手な弁明なんてできるわけがない。
「おまえは、美凉――」
わたしを現実に引き戻したのは、山村さんの一言だった。
「なんで美凉の名前を?」
わたしは美凉の顔を覗いた。
「澪、そういうことなんだよ」
美凉のこんな悲しそうな顔を見るのは初めてだ。それに、言っている意味が、まったくわからない。
「美凉、この娘とはどういう関係なんだ?」
山村さんの右手の包丁が震えた。
「この子はあたしの友達。あたしがこの家に忍び込むのを見て、連れ戻しに来ただけだよ。だから、この子は何も悪くないんだ」
「ねぇ、美凉」
わたしは自分の疑問にも答えてほしかった。
「あのね、澪」美凉はわたしに顔を向けた。「このおっさんはあたしの父親……ううん、父親だった人なんだ」
「父親? じゃあ、わたしが前に会った、あのお父さんは?」
「今一緒に暮らしている父さんは、母さんの再婚相手。亜紀はその人の連れ子」
「美凉はこの家に住んでいたことがあるの? 十年前に出ていったのは、美凉と美凉のお母さんだったの?」
「そうだね」
美凉は力なく答えたけれど、あまりにも突飛すぎて、わたしの頭の中は混乱した。
「勝手に出ていったくせに、今さらなんの用だ」
山村さんが一歩、前に出た。骨張った素足が畳を踏み締める。
「本当にこの家は嫌なところだったよ」
美凉の挑発的な態度に、山村さんは口を引きつらせた。
「なんだと」
「あんたはこう言っていた。家長に認められた者以外は地下室に立ち入るのを許さない。我が家で飼う猫には敬意を払わなければならない……ってさ。そんなわけのわからないしきたりに縛られて、母さんをいじめて泣かせて。あたしが地下室に入ろうものなら、あんた、本気でぶったよね。いつもこの手前の部屋で見つかって、あたしはぶたれていた」
「それで、どうしても諦めきれなくて、今になって忍び込んだっていうわけか? 合い鍵まで用意しやがって。……どうせあの女には黙って来たんだろう。あの女が意図しておまえをここに来させるはずがないしな」
「母さんさえこの部屋には近づけなかった。けど、母さんは見てしまった。それで、あたしを連れてここを出たんだ。母さんをそうまでさせたものが何か、あたしはそれを見たいんだ」
美凉が左手の錠前で屏風を指すと、山村さんも同じように包丁でドアを指した。
「もうここはおまえの家じゃない。すぐに出ていくのなら大目に見てやる。合い鍵と錠前をこっちに渡すんだ。向かいの家の娘を連れて、さっさと帰れ」
「ふざけんな!」美凉は叫んだ。「あんたが家庭をめちゃくちゃにしたんだろう! あたしには知る権利があるんだ! 母さんが口をつぐむほどのものがあるはずだよ! それを見るまでは帰れない!」
激昂する美凉を見て、わたしはいたたまれなかった。
「でも、新しいお父さんは優しそうな人だし、今の美凉が幸せならそれでいいじゃない。山村さんに謝って帰ろうよ」
わたしがそう言うと、美凉は首を横に振って左手を下ろした。
「だめだよ。あたしと母さんには、心のしこりがあるんだ。昔の話やこの丘の話題にならないように、互いに意識しているくらいなんだよ。そんな毎日がつらいんだ。大好きな母さんと、ずっと一緒に笑って――」
言葉を切った美凉が、屏風に向かって歩き出した。
「おい、何をする気だ」
包丁を振り上げた山村さんが、わたしを押しのけて走る。
「やめて!」
わたしは叫び、山村さんの右腕にしがみついた。
「ええい、うるさい!」
山村さんはわたしを突き飛ばしたけれど、同時に包丁も落としてしまう。
足がもつれてうつぶせに倒れたわたしは、目の前に落ちている包丁を見て息を呑んだ。
見ると、屏風に右手をかけた美凉に、山村さんが飛びかかるところだった。
「美凉、そこから離れろ!」
山村さんは美凉の両肩を後ろからつかんで強引に引いた。その拍子に、美凉と屏風が手前に倒れる。重々しい音を立てて畳の上に転がったのは、美凉が持っていた錠前だ。
美凉を助けなければならない。わたしは包丁を右手に握って立ち上がった。
「美凉に乱暴しないで!」
包丁を突き出し、山村さんの背中に近づく。山村さんがまた美凉に暴力を振るったら、自分を抑えきれないかもしれない。そんな衝動が怖かった。
けれど、美凉に注意を向けている山村さんは、わたしに見向きさえしなかった。屏風を払いのけて立ち上がった美凉に至っては、そこに隠されていたものに目を奪われている。
「え?」
わたしはおそるおそる歩み出た。
一人の少女が布団の中で仰向けになっていた。小さな寝息を立てている。高級そうな掛け布団が覆っているのはみぞおちの辺りまでだから、真っ白な着物をまとっていることがわかった。
布団の足元の近くにはポータブルトイレが置いてあった。さらにその奥では、小さな香炉が薄い煙を上げている。
「なんであたしがいるの?」
布団の中の少女を見つめたまま、美凉がゆっくりとあとずさった。
そう、静かに目を閉じている少女は、美凉と瓜二つなのだ。長い黒髪や白い肌、年頃まで一緒のようだった。
わたしは声も出せなかった。包丁を部屋の隅に投げ捨て、美凉の腕を取って引き寄せる。
「アヤノヒメだ」
観念したような目つきで、山村さんは美凉を見ていた。
「アヤノヒメって、あの彩乃姫かよ?」
美凉は訝しげに問う。
「戦国時代の中期にこの一帯を統治していた千代川輝泰公、その姫君だ」
山村さんは静かに答えた。
「何を言ってんのか、わかんねーよ!」美凉が肩を揺らした。「なんで彩乃姫があたしとそっくりなんだよ! なんでそんな昔の人がここにいるんだよ!」
「彩乃姫は年を取らない。五百年間、ずっとここで生きてきた」
山村さんの言葉で、わたしはすぐに思い出した。
「黒岩城の井戸に湧いていた不老不死の水を飲んだんだ」
「不老不死の水か」山村さんは小さく笑った。「黒岩城には井戸が二つ存在した。昔からあった井戸が涸れたために、別の井戸を掘ったわけだ。しかしどちらの井戸にも、不老不死の水が湧いたなどという事実はなかった」
ため息をついた山村さんは、布団の中の少女、彩乃姫をじっと見つめた。
「不老不死の水はただの伝説……だったら、この子が彩乃姫だなんて、なおさら信じられないじゃん」
美凉はつぶやき、わたしの手を握り締めた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

