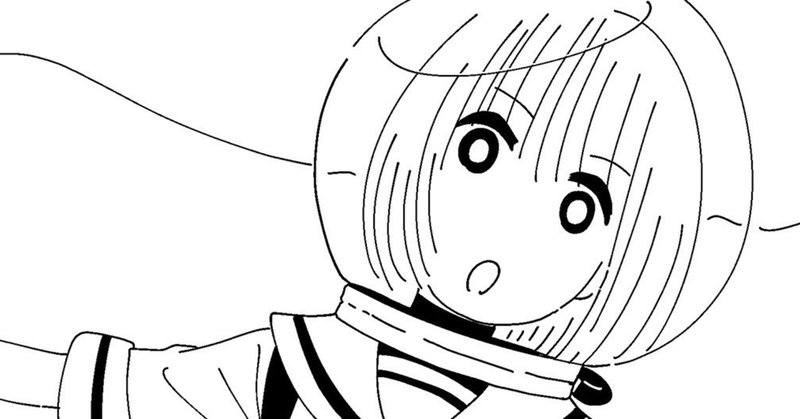
タイタンの彼女 3/8
タイタンの彼女は今日も僕の隣で授業を聞いている。
この時期は彼女が元気な時期だ。先日直接聞いて初めて分かった事だが彼女はおよそ十日程の間一睡もせずに起き続け、その後五日間程まるごと眠るらしい。
太陽から離れた場所にあるタイタンでは地球の十五日が一日だからだそうだ。この話を聞いた時僕は妙に腑に落ちてしまったのだが、そもそも彼女がタイタン人だなんて話は信じていないので取り消した。
起きている十日の内の後半に差し掛かると彼女は授業中でも居眠りを始めて、一日中意識がぼんやりとしていく。今日は起きている十日の内の真ん中辺りなので元気なのだ。
突然、教室に声が響く。
「君、私のこと見てるでしょう」
隣を振り向くと、タイタンの彼女がいつか見た笑顔でこちらを見ている。
いや、違う。彼女は黒板を向いてノートも取っている。二人の彼女がどちらも薄く透けて見えて、重なっていた。
「嘘だ!絶対嘘!私そういうの良く分かる方だもん」
半透明の彼女の姿はSF映画に出て来るホログラムの様で、まるで僕の過去の記憶を巻き戻して再生しているみたいに見えた。
「もしかして私のこと、好きなのかなあ」
しかし見えるのは彼女の姿だけで、会話をしている筈の僕の姿はどこにも無かった。あまりに彼女の方をじろじろと見ていたせいか、現実の方の彼女がこちらを向く。その顔には「また私の事じろじろ見てる」と書いてある。にやついたままこちらを観察する表情が、ホログラムの彼女と重なって見えて一層不思議だった。
僕はその事について授業後彼女に尋ねた。
それは僕ら人間とタイタン人である彼女とでは生きている次元が少しだけずれているせいで起こる現象との事だった。
更に詳しく話してくれたけれど、その内容は難しすぎて僕では百分の一も理解できなかった。とにかく次元がずれている為にたまに透けて見えたり残像がずっとあとに現れたりするらしい。
僕はこの頃から彼女は本当にタイタン人なのかもしれないと思うようになった。
彼女が話してくれた科学的な解釈は、僕の知識の遥か先を行っている。彼女がもし僕から生まれた幻なのだとしたらそれは在り得ない。
それでもやはり心の底からは信じられなかった。彼女は一風変わってはいるけれど、宇宙人というにはあまりに人間らしかったからかもしれない。
彼女は何をするにもいつでも唐突だった。
「マモル、星が見たい」
突然夜に電話をしてきたと思ったら、そんなことを言い出した。
「星?今は夜だから、外に出れば見られるよ」
「そうなの?今外に居るよ?」
受話器の向こうからは、大きなトラックとすれ違う轟音が聞こえてくる。多分彼女は今国道沿いに居るのだろう。
「じゃあ上を向けば見えるじゃない」
それからしばらく、がさがさと動き回る雑音が聞こえた。
「良く分かんないから来て」
何でだろう。彼女のお願いは何となく従ってしまう自分が居た。これもタイタン人の不思議な能力のせいなのだろうか。
「良いよ。じゃあ国道沿いのコンビニで」
家を出て、五分ほど歩くと国道沿いのコンビニが見えて来る。横断歩道の向こう側にコンビニがあるので、今は信号が青になるのを待っていた。田舎のコンビニ特有の広々とした駐車場に、ぼつりと街灯に照らされた人影が見える。
膝を抱えてうずくまり、空を仰いでいる。車が通る度にヘッドライトの光が被っているヘルメットに反射してきらきらと光った。
彼女の私服姿は初めて見た。やはりあのヘルメットとボンベを除けば、他のクラスメイトと同じ同い年の女子にしか見えない。白のTシャツにホットパンツというさっぱりとした恰好が彼女に良く似合っていた。
「よっす」
彼女は膝を抱えうずくまったまま、こちらに手を上げて挨拶をした。
「うん」
「で!星ってどこにあるの?」
「空に光る点が一杯あるでしょ。あれは全部星だよ」
彼女は顔をぱっと明るくさせた。
「ああ!全部そうなんだ!そういうことか」
彼女は立ち上がりしばらく黙って空を見回した。これを伝えるだけだったら電話で十分だった事に気付き、僕は少しブルーになった。
「何か、思ってたのと違うや。帰ろうマモル」
星をどんなものだと思っていたのだろう。彼女の頭の中が覗けたら、どんな景色が見えるのだろう。きっと僕には想像も出来ない光景なのだろうなと感じた。
帰り道、僕の家に向かって曲がる所まで国道沿いを西に二人で歩いた。
国道は大きな街頭に照らされ赤く光っていて、光はずっと先の方まで続いている。ここからずっと先、シロヤマの向こう側へ続くトンネルまではこの景色が変わる事は無い。
光の筋が少しずつ細くなっていく感じが妙に寂しく感じる。今日も変わらず国道の外は真っ暗で、まるで何もない宇宙の様だ。
彼女は僕の少し先を楽しそうに歩いている。装着しているボンベが小さくぷしゅうと音を鳴らした。この音を聞く度、やはり彼女はどんなに近くても僕等人間とは違った存在なのだろうなと感じる。
「こっちのが綺麗だね」
彼女は後ろを歩く私に背を向けたまま、国道沿いの大きな街灯を指さして言う。
その感覚も、僕には良く分からなかった。
「シロヤマの頂上から見ると、隣町の夜景が綺麗だよ」
「となりまち?やけいって何?」
「隣町は隣の町。夜景っていうのは、夜の街の光の事」
「そうなんだ。今度見に行こう?」
前にも言ったけれど僕等だけでシロヤマに行くのは無理だ。
その提案には、僕は結局答えなかった。
著/がるあん イラスト/ヨツベ
よろしければ、サポートお願いいたします! いつか短編集の書籍化も実現したいと考えております。
