
厭な話『呼び出し』 +後日談
■
「九時くらいです。夜の」
及川さんは細かく何度も頷きながら言った。
「正確ではありませんけれど、大体そのくらいの時間に、家のインターホンが鳴るんです」
及川さんがリビングでテレビを見たり、キッチンでやや遅めの夕飯を食べていたり、お風呂に入っていたりしている時、インターホンは鳴るのだ、という。
「確かに遅い時間ではありますが、そこまで非常識に遅いって程じゃありません。宅配の荷物なんかも、二十一時過ぎまで届けてくれる場合もありますし」
それが始まったとき、及川さんも、遅めの宅配かな、と思ったのだという。
「何かが届く覚えはなかったんですけど、一応、確認と思って」
及川さんの部屋は、マンションの八階の、一番端より一つ内側の部屋だ。
「廊下の右側には、隣の角部屋のドアと突き当たりの壁しかありません。そこに誰かいたらすぐにわかります。誰もいないことがわかったんで、すぐに反対側の、長い方の廊下を見てみたんです」
だが、そちらの廊下にも誰の姿もなかった。
「こんな時間にいたずら? と思ってムカつきました」
インターホンは、次の晩の九時過ぎにも鳴った。
「また見てみましたが、やっぱり誰もいません」
さすがに二日続けてとなると腹立たしさよりも気味の悪さが勝つ。
及川さんはもう二度とインターホンが鳴っても出るものか、と思っていたが、ふとあることに気がついた。
「右隣の部屋。つまり角部屋の家なんですけど、小学生の男の子が住んでることを思い出して」
及川さんの家の隣人が住む八階の角部屋には、母親が一人と、ミチルくん、という小学生の男の子が一人で住んでいるという。
「ああ、あの子がいたずらしたんだ、って。なあんだ、ってすっかり気が楽になったんです」
それから数日。時折、及川さんの家のインターホンが鳴る。
やはり夜の九時頃だ。
及川さんは、仕事が遅い母親が帰ってくるまで寂しいのだな、それまでの間であれば、とミチルくんの相手をしてやることにしたという。
「インターホンが鳴ったら、必ずドアを開けてあげることにしたんです」
及川さんは、ベランダで洗濯物を取り込んでいるときでさえ、わざわざ家の中を縦断して、ドアまで行って開けてあげたという。
ミチルくんのいたずらに、ちゃんと付き合ってあげる事にしたのだ。
「そんなことしてたから……あの子に気に入られちゃったんだな、って思うんです」
及川さんは少しだけ笑ったような表情をして言った。
「あの日、やっぱり夜の九時くらいに、インターホンが鳴りました」
及川さんは、またか、と思いつつも、リビングのソファから玄関まで歩き、ドアを薄く開けた。
「いつものように、誰の姿も見えませんでした」
しかしその日だけ、いつもと違ったことがあったと言う。
「ノートの切れ端みたいな紙が。折り畳まれて、こう、ドアの前の床に、置かれていたんです」
及川さんは、なんだろう、と思って玄関から出て、それを拾った。
「紙を開いてみて、なんか、ざわざわってして。それで、隣の家を訪ねてみたんです」
及川さんはミチルくんの家のインターホンを鳴らしたという。
「でも、誰も出ませんでした。ドアを開けてみようかとも思ったんですが、果たしてそこまでしてもいいものか、廊下で一人迷っていました」
そこへ、二軒隣のドアが開き、中年の男性が出て来て、及川さんに話しかけて来た。
「その男の人は、何度か挨拶をしたことがある程度の人だったんですが、どうかしましたか、って訊かれて。落ちてた紙を見せて、経緯を話したんです」
すると中年の男性は、ミチルくんの家に電気がついているかどうか、ベランダから確認してみてはどうか、と提案した。
「なるほど、と思い、私はその人に廊下を見てもらって、自分の家を突っ切ってベランダに出ました。で、首をこう、伸ばして、ベランダの仕切りの向こうの、角部屋を見てみました」
「電気はついてました」
及川さんはついでに反対側の仕切りの向こうも見てみた。左隣の家は真っ暗で、その隣は電気がついていた。
「その中年の男の人の家なんで、そりゃ当たり前なんですけどね」
及川さんが再び玄関から廊下に出たところで、廊下中程にあるマンションのエレベーターが開いて、ミチルくんの母親が出て来た。
「私と男の人とで、軽く説明をすると、お母さんは、ウチの子がすみません、って頭を下げてから、鍵を差し込みました」
だが、ドアは開かなかった。
チェーンが内側からかけられていたのである。
「お母さんは困った感じで、しばらくドアの隙間から、ミチル、ミチル、って名前を呼んでいました。でもその声もだんだん大きくなって、目に見えてパニックになっていって」
とうとう、大家さんが呼ばれて、チェーンを切ることになった。
「開けなければよかった、と思いましたよ。正直」
及川さんは言った。
「ミチルくん、死んでたんです」
死体は、リビングのテーブルの下で、全身を滅多刺しにされていたという。
「後で警察の人に聞いたんですけど」
及川さんはうんざりしたような表情で言った。
「ミチルくんの死亡推定時刻っていうんですか……殺された時間。夕方の、六時頃だったそうです」
インターホンが鳴ったときは、もう既にミチルくんは死んでいたのだ、と言う。
「私、よほどあの子に、気に入られちゃったんでしょうね……。それか私に見つけて欲しいと思ったのかな……なんて、考えたりもするんです」
及川さんは少し笑ったように、そう言った。
「隣の家は――お母さんはそのまま、いなくなってしまいました。警察の人は、引っ越した、と言ってましたけど」
及川さんは、鞄の中から折り畳まれた紙を取り出した。
「これ。警察の人が、もう持って帰っていいからって渡されたんですけど」
及川さんは、今にも消え入りそうな声で続ける。
「近いうち、ミチルくんが私を迎えに来るんじゃないかって、そんな気がして。……見ます?」
及川さんはそう言って折り畳まれた紙をこちらに手渡した。
紙を開くと、中には、ボールペンで簡単な文章が書かれていた。
ぼくは いえにいる こんどは おねえさんの ばん
ミチルくんを刺した人物は、まだ見つかっていない。
気分が沈む話を聞いた。
■
「――と、言う話を聞いたんです」
僕がそう言葉を結ぶと、湊町黒絵(みなとまちくろえ)先輩は、「へぇ」と言った。
「今度は、ヘぇ、だけですか。もっとこう……なんかないものですかね」
僕はたった今語り終えた話のメモが書き付けてあるノートを鞄にしまいながら言った。
「何かないものかと言われてもなあ――へぇ、が不満なら、はぁ、でもいいが」
「対して変わらないですよどちらも」
僕はジョッキに残った生ビールを飲み干し、新たなビールを注文した。
「あ、おねーさん、こちらにも一つ追加」
黒江先輩はそう言うと、まだ半分以上残っていた自分のジョッキの中身を飲み干した。
■
ここは新宿西口にある『やまと』という居酒屋の二階である。
出版社に勤めている僕は、担当作家であり、高校時代からの先輩である、湊町黒絵「先生」との打ち合わせを、頻繁にこの店で行う。
打ち合わせといっても、年に二作短編を書けば「今年は大漁だね」と言われるような作家である黒絵先輩である。
具体的な仕事の話をするようなことはほとんどなく、黒絵先輩の趣味、というかもはや生き甲斐でもある「恐い話」を、僕が聞いて集めて来て、それを黒絵先輩にお披露目する、というのが専ら最近の打ち合わせ内容となっている。
これで会社に領有書を切っていいものか、と罪悪感がないわけではないが、何しろ黒絵先輩の書く小説のジャンルは怪奇・幻想小説と呼ばれるものである。「恐い話」で盛り上がるのはある意味では立派な取材、と言えないこともない、と自分に言い聞かせて罪悪感など最初から覚えなかったことにしている。
それでも、喪服姿の若い男と、これまた全身真っ黒でダボダボの服を来たロングヘアーの美人が、大量の酒を飲みながら恐い話を互いに披露しあっている姿を見て、誰も「真面目に仕事をしているな」とは思わないだろう。心なしか僕と黒絵先輩の近くのテーブルについた他の客は、早めに店を出て行っているようにも思える。
ところで、僕は普段から喪服を着ているわけではもちろん、ない。
入社した時にお世話になった先輩のお母さんが亡くなったので、葬式に行ったのだ。するとそこで、当の先輩から「そういやお前、最近変な話聞いて集めてるんだってな」と言われ、先輩の後輩だという女性を紹介されたのである。さすがに式場で話を聞くのもどうかと思ったので、女性と二人で近くの喫茶店ヘ行き、そこで話を聞くことにした。
その女性が、及川さんである。
■
「しかしまあ、葬式の場で恐い話を集めるなんて、君も、くるとこまできてるね」
黒絵先輩は形のいい唇をニヤリと曲げて言った。
「さすがに僕だって自分から聞いて回ろうなんて思ってませんでしたよ」
そればかりか、「あいつは恐い話を集めてるらしい」なんて噂が式場に広まっては堪らない、親族にどんな目で見られるものか、とびくびくしてすらいたのである。で、あるのに、喪主から「こいつにこないだの恐い話聞かせてやってくれ」と女性を紹介されて、断るわけにはいかなかったのだ。
「全く君には常識ってもんがないのかね」
「先輩に言われたくありません」
なにしろ黒絵先輩は、どこから聞きつけてきたか知らないが、夕方に突然電話をかけて来て、「君は今日葬式に出向いたそうじゃないか。さぞかし面白くて不思議で恐い体験をしたのだろうね。さあすぐに来るのだ」と、会社に戻って着替える時間も取らさぬままに僕を新宿へ呼び出したのだ。
そればかりか僕の姿を見るなり「喪服で酒飲みに出るなんてどういう了見だよ君は。見なさいよ、他のお客さんが気味悪がってるじゃないか。ぼくだって気をつかって酒が不味くなってしまうよ。お店に迷惑かけた責任として今日は君のおごりだからね」と、とんでもない理屈を吐くなり生ビールを飲み干し、「ああ、ビールは美味しいなあ」とのたまったのだ。
喪服で居酒屋に入るのは自分でも申し訳ない気にはなっていたが、店へ迷惑をかけた責任の取り方がどうして先輩の分をおごることで果たせるのかがわからないし、そもそも毎回飲み代は僕が全部出している。いや、会社の経費で落ちるから、それは特に構わないし、打ち合わせでもあるのだから、いちいちそんなこと言わなくてもいいような気がするのだが、恐らく、先輩は先輩で一応、「今日こそは払えと言われるのではないか」と心配しているのではないだろうか。だからわざわざそんなことを言ったのだろう。我が侭で傍若無人で非常識が黒い服着て歩いているような人だが、こういう小心なところがあるのだ。
「じゃあ、まあとにかく」
僕は新たに運ばれて来た生ビールで喉を湿らせてから言った。
「今回の話は、特にお気に召さなかった、ということで」
僕が聞いて来た「恐い話」が全て黒絵先輩のお気に入りになるかというと、そうではない。むしろ、圧倒的に外れである場合が多いので、もはや気にしないことにしている。
「こないだの、美容師の女の子の話は中々良かったんだけどなあ」
黒絵先輩は唇を尖らせて目を瞑った。
「ああ、こないだの。先輩に言われたからもらった手紙、見ずに捨てちゃいましたけど、本当に良かったんですか?」
先日、僕は美容師の女の子に恐い話を聞いたのだが、帰り際にその子から、話の発端となった事件のことが書いてあるメモのような手紙を渡されたのだが、僕はそれを読まずに捨てて帰ったのだ。
「当たり前だろう。恐い話ってのは、聞いて語り継いでいくのが目的なんだ。怪異の真相を調べようとしたり深入りしたりするのを目的にしだしたら、君、それ戻れなくなるぞ」
「戻れなくなるって、どこにです?」
「人の道に、だよ」
真顔でそんなことを言う。
僕は二の腕あたりに薄ら寒いものを感じて、慌てておでんの大根を口に運んだ。
「じゃ、じゃあ、今回の話もこれ、真相を知ろうとしたりしない方が良いわけですね。犯人、まだ捕まってないみたいですけど」
「はあ? 今回の話のどこにも、怪異なんか現れてないじゃないか」
「え、だってミチルくんはもう死んでたのに、インターホンが鳴って」
黒絵先輩は普段の愛想の良くない顔を、より不機嫌にしかめてマルボロに火をつけた。
「君ね、日本の警察は君が思ってる百倍は賢くて優秀だよ」
「何の話ですか?」
「こんな杜撰な犯罪の犯人が捕まらないはずないだろう。もうとっくに捕まってるか、近いうちに捕まるか、だよ」
「黒絵先輩には、ミチルくんを殺したのが誰かわかってるんですか?」
「そんなの――母親に決まってるじゃないか」
眉間の皺を一層深くして、黒絵先輩は言った。
■
「これはあくまで憶測でしかないんだけど」
黒絵先輩は、何杯目かの生ビールをテーブルに置くと、そう前置きをした。
「及川さんの話から想像するに、恐らく、家の構造は、これに似た感じじゃないかな」
黒絵先輩は、自分のスマートフォンをテーブルの上に置いて言った。
「『家の中を縦断して』とか『突っ切って』と表現してるから、恐らく家は縦に長い造りになってるんだと思う。で、あるなら、こちらの聞く方、受話部の端がベランダで、喋る方の送話部の端が玄関ドア、なのだろう」
黒絵先輩はそれぞれを指差しながら説明する。
「で、マンションであるからには、これと同じスマホがずらっと横に並んでるわけだけど――ミチルくんの家は角部屋だということなので、このスマホの右横には、一台しか置けないものと、想像してくれ」
黒絵先輩はスマートフォンの右隣の空間を人差し指で叩いた。
「さて、先程も君に言ったように、日本の警察は優秀で賢いので、死亡推定時刻には間違いはないのだろう。つまり、夕方六時の時点で、可哀想にミチルくんは既に絶命してしまっているわけだ」
「そうなんですよ。だから、及川さんの家に、九時にインターホンが鳴らせたはずないんですよね」
僕は新たにハイボールを注文して言った。
「だからその、及川さんは、ミチルくんの、思い、みたいなものが鳴らした、と思ってしまって――君に、この話をするはこびとなってしまったわけだ」
「僕もそれが怪異だと思ったんですけど――じゃあ、先輩は誰が鳴らしたかわかってるんですね?」
「ミチルくんを殺したのと同じ人物だよ」
黒絵先輩が先程言っていた、ミチルくんを殺害した犯人と言うのは、つまり。
「母親、ですか」
「そう。ああ、全く想像すればするほど杜撰で稚拙で自分勝手な行動だよ。腹が立つ」
黒絵先輩はそう言って長い黒髪を左手でかきあげた。
そんなに腹立たしいのであれば想像しなければ良いと思うのだが、想像してしまう、のが黒絵先輩なのだ。こればかりは止めることが出来ない。
■
「その日、母親はミチルくんを刺し殺してしまう。理由も動機もわからない。そこはまあ、ぼくにはどうやったって知る由のないところなので、放っておこう。出来事として、母親は夕方の六時頃、自宅のリビングでミチルくんを刺し殺す。で、愚かな母親は、その罪を認めずに、逃げ切れないものか、と考え始める。で、思いついたのが、この家を密室のような状態にして、自分は外に逃げる、というものだった」
「そうか。及川さんは、ドアが開いた時に、チェーンが内側からかかってるのを見ています」
「そう。だからとりあえずの見た目は、密室のような状態、を作り出すことが出来ていたわけだ。でも厳密には密室でもなんでもなかった」
「そうなんですか?」
「ミチル君の家のベランダの鍵は、開いていただろうからね」
「そんなことわかるんですか?」
「わかるわけないけど――ぼくの憶測だと、そのはずだよ。で、愚かな母親は、内側からチェーンをかけて、自分は外に出ようと目論む。そして自分はベランダに出て――」
「ちょ、ちょっと待ってください先輩。及川さんの家のフロアは、八階にあるんですよ? 非常ハシゴかなんかでも使わない限り、下には降りれないと思いますが」
「非常ハシゴなんか使ったらドアのチェーンかけた意味が全くなくなるだろう。アホなのか君は」
黒絵先輩は三白眼で睨みつけてきた。
「じゃあ、どうやって外に」
「ベランダから、隣の家のベランダに移動しただけだよ」
「え、隣の家って」
ミチル君の家は角部屋。と、いうことは隣の家というのは、つまり。
「及川さんの家のベランダ、ですか?」
「そこしかないだろうね」
「いや、いくら何でも大胆過ぎませんか? でも、夜なら普通はカーテンを閉めてるか。だとしても」
「大胆過ぎるね。その上、及川さんは、夜の九時でも、ベランダで洗濯物を干すような生活をしていた人だったから、いつ及川さんがベランダに出てくるかわかったものじゃない」
「ですよね。ただでさえ八階のベランダを乗り越えて行き来するなんて危険な行為をするのに、鉢合わせたんじゃ洒落にならない」
「しかもその時はまだ、夕方の六時をまわったあたりだ。暗くなりはじめてるとはいえ、見られる可能性は非常に高い。単純にその日及川さんがその時間はまだカーテンを閉めてなかったのかもしれないね。とにかく母親は、ベランダからベランダへの移動を、なるべく確実に見つからずに行えるものにしたかった。だからそこで、ミチルくんに生き返ってもらうことにした」
「生き返ってもらうって、どういうことですか?」
「及川さんにだけ、ベランダの方を見ないようにさせる方法が一つだけあるのを、母親は知っていたのさ」
「ベランダの方を見ないようにさせる方法……」
僕はテーブルの上のスマートフォンを見つめる。受話部がベランダで、送話部がドア……。
「そうか。ミチルくんが夜の九時にインターホンを鳴らせば、及川さんは絶対に、ドアを開けてくれる」
「そう。そしてその間、及川さんはベランダの方を絶対に見ていない」
「つまり、こうですか。母親は部屋でそのまま九時になるまで待って、九時になったとき、廊下に出て及川さんの家のインターホンを鳴らす。そしてすぐに自分の家のドアを閉めてチェーンをかけ、部屋を突っ切ってベランダに出て、及川さんの家のベランダに移動……ちょっと苦しくないですか、これ」
「苦しいとは?」
「だって、及川さんがドアを開けるのは良いとして、その後、母親が移動を終えるまで時間が足りないような気もするんですけど」
「そうだろうね。母親も同じことを考えたに違いないよ。だから、もう一つ手を打ったんだ」
「もう一つ?」
「廊下に、手紙が落ちていただろう」
あっ、と僕は声を漏らした。
「そうか。ドアを開けるだけじゃ時間が稼げないと思って、手紙を置いたんだ。及川さんに見つけやすい場所を選んで」
「で、手紙には、なんと書かれていた?」
「ええと確か、『僕は家にいる、次はお姉さんの番』です」
「母親が考えて書いたんだろう。そう書けば、及川さんが、次は自分がミチル君の家のインターホンを鳴らす番だ、と気付いてくれると思ったんだ」
「及川さんは、正にその通りにしました」
「さて、母親はその小細工のお陰で時間を稼いでベランダからベランダに移動することは出来た。そして、及川さんの左隣の家は電気が消えていたらしいから、ここを通過するのは比較的安心だね」
黒絵先輩はスマートフォンの左の空間を人差し指で叩いた。
「ちょっと待ってください。どうして母親は、及川さんの隣の家の電気が消えていたことを知れたんでしょう。二軒先のベランダって、中々見られませんよね。それとも九時になるまでの間に、何か情報を仕入れていたとか?」
「母親がベランダから見る必要はないんだ。その家の隣の住人が確認して、そのことを教えていれば良いだけなんだから」
電気が消えていた家の、隣の住人。
「え、それって及川さんじゃないですか。及川さんがどうやってそれを――」
「違うよ。こっちだ」
黒絵先輩は呆れたように言って、テーブルの上のスマートフォンの左隣の空間の、もう一つ隣を指差した。
「え、その家ってつまり」
「中年の男だね——母親の小細工の手助けをした」
「ど、どうしてわかるんですか、そんなこと」
「出てくるタイミングが良過ぎたからだよ」
黒絵先輩は、何が楽しいのか、唇を笑顔の形に曲げた。
「及川さんがミチル君の家のインターホンを鳴らした時に、中年男は廊下に出て来ている。それだけでなく、話しかけているんだ。何度か挨拶しただけの関係の割にはちょっと唐突じゃないか。これは単純に、母親がベランダを渡りきって、中年男の家の中に辿り着くまでの時間稼ぎをする為だ」
「母親が中年の男の家に辿り着く……あれ、待ってください先輩。母親は、その後、エレベータのドアから出てくるところを見られています。いつの間に、下の階まで降りたんでしょうか?」
「中年男は、おかしなことを及川さんに言ってただろう」
「おかしなこと?」
「ベランダから、隣の家の電気がついてるか見ろ、って言ったんじゃなかったっけ?」
「確かにそうでした」
「いいかい? 及川さんはこの時点で別に、ミチルくんが家にいないかもしれない、なんて微塵も思ってないんだよ? インターホンを鳴らしたのにミチルくんが出て来ない、ってだけだ。なのにこの男は、電気がついてるかどうかベランダから確認しろ、なんて言ってる。及川さんは人が良いからその通りにしてしまうわけだけど――その間に、母親は男の家から廊下に出て、階段で一つ下の階に降りれば良いんだ」
聞いていて段々と、母親とこの中年の男に腹が立って来た。及川さんとは今日会ったばかりだったが、この二人は、彼女の人の良さにつけこんで計画を練っているのだ。
「で、何食わぬ顔をしてエレベータから出て来た母親は、及川さんの目の前で、鍵を使ってドアを開けて、チェーンが内側からかかっていることを目撃させる。これで密室のような状態、は成功で、及川さんの証言で自分は容疑者の範疇から外れる、と思ったんだろうな。甘い」
「全く甘過ぎるな」ともう一度言って黒絵先輩は新たに運ばれて来た生ビールで喉を潤す。
「ともかく、まあこれで、冷酷な殺人者から悲劇の母親に成り代わることができたわけだ」
■
「……先輩、この話警察に言わないんですか?」
「言うわけないだろう。なにしろただの憶測でしかないんだ。ぼくはそんな事件がほんとうに、実際に、現実に起こったのかどうかもわからないんだよ」
生ビールのジョッキに口をつけたまま黒江先輩はこちらを睨みつける。
もう大分酔いが回ってきているようだった。
子供が死ぬのは厭だけど、と黒絵先輩は呟いて、「実際に起きてしまった事件だとしたら、これも何度も言うけど、日本の警察は優秀で賢いから、とっくに母親とその中年男に目をつけているだろうさ」と言った。
「そうなんですか?」
「母親がいなくなったのを、及川さんは、警察から引っ越した、と聞いているだろう。監視してるのさ、ちゃんと」
「その中年の男は、何者なんでしょうか」
「さあ? 及川さんの話からはわからないけれど、恐らく――母親が息子を殺したことを受け入れて、更に逃げる為の道を作ってあげるような、そんな関係の男だったんじゃないかな」
黒絵先輩はつまらなそうに言った。
「もう一度念のために言っておくけど、僕がさっきからずっと喋ってるこれは、ただの憶測でしかないからね? 君の聞いた話が全部、及川さんの作った嘘の作り話かも知れないんだから。いいね、そう思って聞いとくれよ」
僕は頷いた。
「母親に、夜の九時頃にインターホンを鳴らせば及川さんは必ずドアを開けてくれる、と教えたのも、恐らくこの男だろうね。二軒隣であれば、物音でそのことに気付くこともあるだろうし、フロアの一番端の家の母親と、仲良し、であればなおさら普段から気にもしているだろうさ」
黒絵先輩は「仲良し」を吐き捨てるように言った。
「母親は知らなかったんですか、そのことを」
「教えてもらうまでは、ね。だって知りようがないじゃないか。ミチルくんがインターホンを鳴らすとき、母親はまだ帰宅してないんだから」
思い出した。及川さんはミチルくんがインターホンを鳴らすのを、「仕事が遅い母親が帰ってくるまで寂しいのだな」と思ったのだった。
「優しい及川さんは、それで、ミチルくんのその呼び出しに、応じるようになったんだ。そのことを、二軒先の男は知っていたのに違いないのさ」
黒絵先輩は何本目かの煙草に火をつけて、紫の煙を細長く吐く。これで話は終わりのようだった。
■
僕は、一つだけ気になっていることがあり、訊いてみることにした。
「ミチルくんは、どうしていつも、九時だったんでしょう?」
「なんの話だい?」
「インターホンを鳴らすのは、どうしていつも、夜の九時頃だったんでしょうか? なにか決まり事があったのか、それとも、なにかのメッセージとか」
「ああ、それか」
黒絵先輩は面白くなさそうに眉をしかめて言った。
「クソ面白くもない憶測だけど――九時頃って時刻は、及川さんにとっては何でもない夜の時間だけど、ミチルくんと母親にとっては、共通の時間なんだ」
「なんですか、それは」
「九時頃っていうのはね、母親が、大体いつも、仕事から帰ってくる時間なんだよ」
「そうなんですか?」
「及川さんは『母親が帰ってくるまで』と言っていただろう。『それまでの間であれば』相手をしてやることにしたと言っている。彼女には、母親がもうすぐ帰ってくる時間であることがわかっていたんだ」
それまでの間であれば。
確かに、いつ母親が帰るのかわからないのであれば、子供のいたずらの相手をするのは相当にしんどいだろう。及川さんには、母親が九時過ぎ頃に帰ってくることがわかっていたから、相手をしてやることに決めたのだ。
母親と中年男の計略とはいえ、実際に抜群のタイミングで母親がエレベーターから出て来たときも、大して驚きもせずに母親に事情を、軽く説明している。あれは、その時が九時過ぎだったからなのか。だとしても――
「――だとしても、母親が帰ってくるであろう時間に、どうして隣の家のインターホンを鳴らしりしたんでしょうか、ミチルくんは。及川さんになにか伝えたかったんでしょうか?」
黒絵先輩は煙草を灰皿に押し付けながら重く口を開いた。
「いいや、違うと思うな。及川さんには申し訳ないけど、彼女には何もメッセージは送ってなかったと思うよ」
「じゃあどうして」
「及川さんがたまたま隣に住んでいたから、ミチルくんはインターホンを鳴らしただけさ。彼の目的は、インターホンを鳴らすこと、そのものにあったんだよ」
「インターホンを鳴らすことそのもの?」
「いいかい。呼び出して、人がドアから出てくる頃には、もうそこにはいない。これって何かな」
「何かなって……ピンポンダッシュ、ですよね、いわゆる」
「そうだね。じゃあもう一つ。ピンポンダッシュって何かな」
「だから単純に……他愛もない、いたずらですよね」
「そう、ただのいたずらだ。でも、そのいたずらを、親に見られてしまったら、どうなるかな」
「どうなるかなって、そりゃ」
そこまで言って気がついた。まさか。ミチルくんは。
「母親に、いたずらしてるところを見つかって、怒られたかった、て言うんですか?」
「恐らくね。だから、ミチルくんの行動の目的は及川さんじゃない。母親に見つけてもらうことにあったんだよ」
「でも、なんでわざわざ怒られるようなことを」
「叱ってくれるというのは、愛情がないと出来ないことでもあるからね」
そうか。
「ミチルくんは、いつも一人で留守番をしていることで、母に愛されていないのではないか、と思い始めてしまったんですね」
「母親が家から出て行くのはなにも仕事の時ばかりじゃないだろうしね」
中年の男性の家にも行っていたのだろう。自分の子供を連れて行くことなく。
「つまり。だから、夜の九時頃だったのさ」
黒絵先輩はそう言うとジョッキに半分以上残っていた生ビールを飲み干しはじめた。
「……僕は、この話を、及川さんに教えるべきでしょうか」
「やめときな、どうせただの憶測だよ。趣味が悪いや。いや、でもな」
黒絵先輩は眉間の皺を一層深くして腕組みをした。
「彼女、ミチルくんの幽霊が自分を連れにくるかもって、憑かれてしまってるからなあ。それだけは祓ってあげた方が良さそうだ。まあ、君が何か適当な嘘をでっちあげてそれを伝えてあげたら良いよ。間違っても呪いが強くなるようなことは言わないようにしなさいよ」
黒絵先輩は左手の平を軽く降りながらそう言った。
「ええ、先輩が何か考えてくださいよ」
「嫌だよ面倒臭い。関わったのは君なんだから君が救ってやるのが筋ってもんだ。障りを広めるんじゃないよ」
そう言われて途端に僕も面倒臭くなってしまったが、及川さんはなにも悪くない上に、本当に良い人なのだ。そんな人が死者の影に怯えて生きるのは可哀想だ、と思った。
「……まあ、何か考えて伝えますよ」
「そうしてやるといい。どれ、うん、まだ電車が動き出すまで時間があるな」
黒絵先輩はスマートホンを持ち上げ、時間を確認してそう言った。
「え、電車が動き出す?」
僕も慌てて時計を確認した。既に終電が出て行ってしまっている。やってしまった。明日もこの喪服のまま出社しなければいけないのだろうか。
「では、他の――なにか面白くて不思議で怖い話は、ないのか?」
新たな生ビールを注文して、黒絵先輩は、にまーっと笑った。
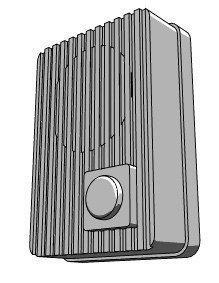
おしまい。
(11,740字)
■一年前の投稿を、一つにまとめたものです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
