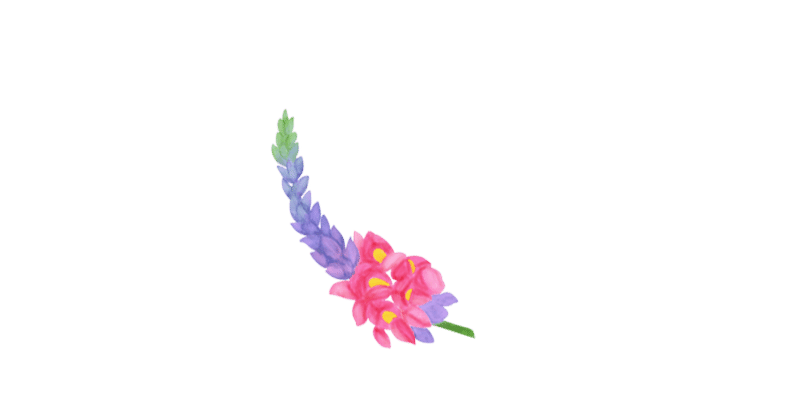
藍色のスカーフ
人の大切なものを奪うことの、なんと甘美なことでしょう?
私には年の近い妹がいる。
昔からよく一緒に遊んでいた。小学生の頃までは私が友達と遊ぶのにも妹はついてきた。
私は妹が好きだった。だから一緒に遊べて楽しかった。しかし、ある時学校で友達に言われたのだ。
「妹ちゃん、同じクラスにちゃんと友達はいるの?」
盲点だった。その時まで私は妹が学年で孤立しているかもしれないということに考えが至らなかった。
その時から私は妹が周囲に馴染めているのか心配になった。
やがて高校生にもなると私にも彼氏ができた。
彼は野球部で彼の部活が終わるのを待って、一緒に帰るようにしていた。帰り道ではいろんなことを話した。クラスのこと、担任のこと、部活のこと、宿題のこと。そうした取り留めのない会話が楽しかった。私の言葉に相槌をうちながら、はにかむ彼の目元に胸を高鳴らせた。心臓の音がうるさくて、彼に聞こえやしないかと思ったほどだ。
夏も終わりに近づき、蝉の声も小さくなった頃、私は妹についての心配を彼に打ち明けた。
彼は私の手を握りながら言った。
「心配ないよ。君の妹になんだから、そんなことはありえない。」
部活の練習でたこのできた硬く大きな手が頼もしかった。
彼にならどんなことも相談できると思った。
そう思っていたのは私だけだと気づいたのは、ある雨の日だった。私は委員会の用事があったため、彼と帰る時間がズレることになった。
雨の中、もしかしたら相合い傘も素敵だな、なんて思いながら家に帰ると男子学生の靴があった。その靴には見覚えがあった。
妹の部屋から女の媚びた声と男の何かを堪えるような声が漏れ聞こえてきた。
私は妹な部屋の扉を開けた。
そこには着衣の乱れた妹にのしかかる彼氏の姿があった。
彼氏の驚いた顔よりも妹の勝ち誇る視線が印象に残った。
「君の話を聞いて、放ってはおけなかったんだ。」
彼氏は弁解じみた言葉を口にする。
「君はあまり僕を頼ってくれないし。妹さんには僕が必要なんだ。」
「お姉は気持ちいいこと、させてくれなかったんだよね?かわいそうな彼氏くん。」
私は、妹の心配などしている場合ではなかった。
妹は立派に女として成長していた。
私は少女のまま、妹に先を越された事実に打ちのめされ、雨の中へと駆け出した。
私にカフェオレを飲ませるためにサポートしてみませんか?
