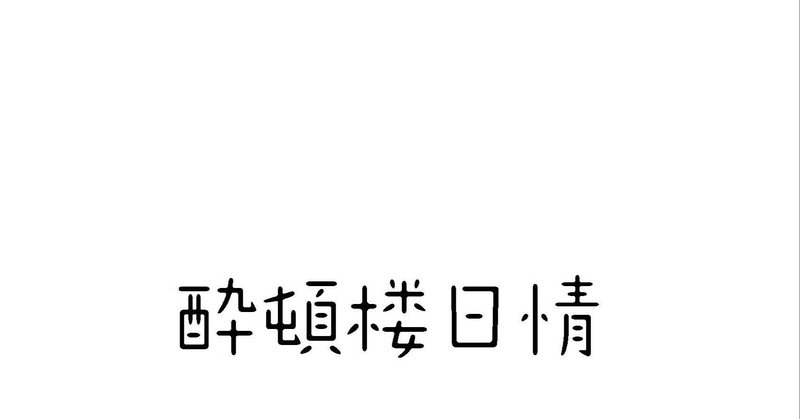
12月17日
「帰りの路線で迷う」のがこのところの定番だが、今朝の夢は「惜しくも辿り着けない」だった。
マンハッタン計画の責任者だったグローブスが来日しているという情報をつかんだので、取材という名目で抗議してやろうと思いついた。名刺を持っていないのに気づいて躊躇したが、ママよと出掛けてみたら途中の峠道(広い砂利道)で大事故があったらしく惨劇の現場になっていた。これではとてもたどり着けないと取材は断念(夢のなかでも自分は自分らしい)。そのまま知人の若い女性の部屋に泊めてもらうことになった。なぜか姉も一緒。そのせいか最悪感めいたものはなく、またスケベ心も希薄だった。彼女は埼玉あたりの辺鄙なところに部屋を借りていた。池袋から乗り換えて先の路線図を見たらとんでもなく遠いので「おれはどこかにホテルを見つけるよ」と遠慮することにした。それでも姉は行くというので、意を撤回して同行する。やって来た車両は一両編成だった。混雑した車内に乗り込むと数席空いていたが、すぐに生きのいいヤツが占拠した。後部に移動すると、そこだけ広場ほどもあるスペースで、彼女が彼女の店の客だった連中と車座になっていた。彼ら彼女たちは「常連に比べて待遇がゾンザイだった」と不満めいたことを漏らしていたが「当たり前だろ」と、お節介にもたしなめた。なかに若いカップルがいて、ハーフらしい女性の後ろ姿が魅力的で少しソソられた。そのうち何かの用があるらしく知人女性が途中下車するために座を外すと、連中も姉も一緒に降りていった。そのとき知人が顔見知りに何かを買わないかと勧めていて、それはサッカーのグッズか何かで、その商売熱心に感心する。どうやらその周りはサッカーのサポーター連中が集まっていたらしい。
あたりに身内がいなくなって、ようやくひとり静かにイヤホンで音楽か取材録音かが聴けるわい、とセットしたところで目が覚めた。ということで残念ながら知人女性の部屋に辿りつけず。
開高健「ベトナム戦記」の読後整理。12月13日に同書を読みはじめた際、「イメージとは違う内容に戸惑いつつ」と書いた。その疑問は結局、176ページまで読み進んで氷解した。
「〝最前線〟の〝現地〟に迷いこんでからも戦争はどこにあるのですか、最前線はどこですかと聞いて、そのたびにたしなめられた。(中略)最前線がどこにもない、いや、全土が戦場だというのがこの国の戦争の特長である」
そのカオスの只中で開高は右往左往していた。真実の所在がわからないままリアルタイムで週刊誌に原稿を送っていたために〝ルポルタージュ的〟に書けなかったのだ。そのへんの経緯は、同時期に共にベトナムに従軍した経験をもつ日野啓三の解説に詳しい。
「この開高のルポルタージュが、いわゆるルポルタージュの即物的明確さと調子が違うことを読みながら感じとったとすれば、あなたはこの本をよく理解したことになる」
「この戦争はサイゴン政府とアメリカ政府が言うように、〈国際共産主義勢力に支援されたハノイ共産政権の侵略戦争〉なのか、〈サイゴン傀儡(政権)の圧政と腐敗に抗して起ち上がった南ベトナム知識人と民衆の反政府ゲリラ戦〉なのか——という根本の姿が確かに見届けられないだけでなく、日毎夜毎に(あまりにも悲惨な現実を)見続けなければならなかったからである」
「明確な構図のない大状況の中で、事実らしきものを追い、最小の筋道でも読みとり浮かび上がらせたい、とする報道者としての誠実さが(卓越した修辞家である開高の)、言葉の、文章の全性能を不可避的に呼び出)したことで、〝開高ルポ〟とでもいうべき特異な作品として結実したのだ。
それは言い換えれば、もともと大義などはなく、そのために実態が見えない戦争というものの本質に直接触れえたルポということでもあって、いみじくも日野も言っているように、1965年に書かれたこの作品が今も古びていないのは、そんなところに起因しているのだろう。
日中、気分転換に「ボルグ/マッケンロー 氷の男と炎の男」をつまみ観する。夜のマイシアターは「ブラックホーク・ダウン」。ソマリアの内戦に介入した米軍が一敗地に塗れた作戦の戦闘ドラマ。和平を実現するどころか、民兵という民衆を殺傷することで民衆をさらに反米に向かわせるという地獄のスパイラル。大義なきカオス状態は、まさに「ベトナム戦記」そのもの。あまりの惨めな敗走シーンの連続に反戦映画なのかと期待したが、最後はやはり英雄群像仕立てでジ・エンド。お約束の「立派に死んだと伝えてくれ」のあとにひとこと、「それから、息子には決して俺と同じ道は歩ませないでくれ」と語らせてもバチは当たらぬと思うのだが…。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
