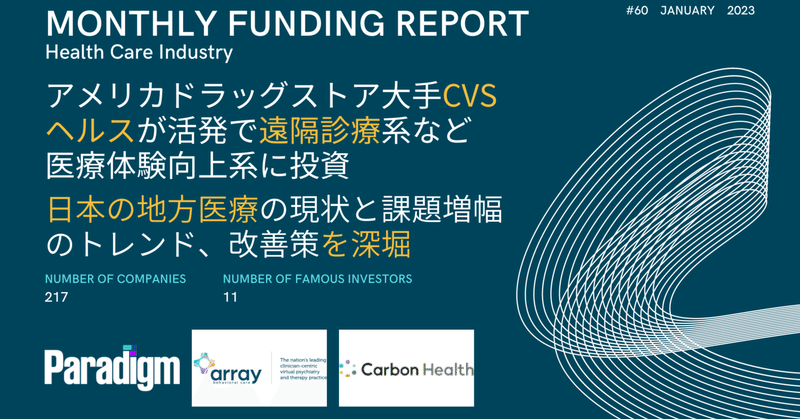
【Monthly Funding Report】2023年1月アメリカヘルスケア領域
前回から新フォーマットでのnoteになりまして、変更したてということもあり、いつもより多くの方に読んでいただけてうれしかったです。
当面大きな変更はせずにこのままやっていこうかと思っておりますが、もしお気づきの点や良かったところ悪かったところなどフィードバックしてもいいよという方は是非ご連絡いただけたら嬉しいです!
今回はヘルスケア領域を見ていきます!
ーーー告知ーーー
Monthly Funding Reportの更新情報はTwitterでもお知らせしております!
事業のディスカッションなどもDMで受け付けておりますので、
Twitterのフォローお願いします!
DMもお待ちしております!
https://twitter.com/internet_boy53
ーーーーーーーー
リサーチの範囲

前回の建設不動産領域同様に、デットファイナンス、補助金・助成金、IPO後のファイナンスは除外してリストを作成しています。
また、薬そのものの開発を行う創薬系スタートアップも自分自身の知識が(ほかの領域以上に)あまりにも浅すぎるので除外しております。(創薬活動におけるバリューチェーン・サプライチェーンの効率化に当たる創薬支援領域のみ入れております。)
画像の通りで、除くものを除いても200以上の会社が出てきていまして、本来であれば1つ1つチェックすべきなんですが、そこまでできないので、もしかするとDBのデータの関係で一部全く違う領域の会社が含まれてしまっている可能性があることをご容赦いただければと思います。(元データはCrunchbaseなのですが、カテゴリーを絞っても全く関係ないものが入ってることがちょくちょくあります….)
今月のサマリー

建設不動産は昨年末あたりからパワポを作っていたので過去データもありだったんですが、ヘルスケアは23年分から作り始めているので1月のデータしかなくてすみません。
不明が多いんですが、ステージのわかっているものだけで見るとやはりシードが半分くらいを占めているような感じになります。
今月の著名VC投資先一覧


著名投資家が入ったスタートアップをリスト化したのですが、1月に投資を受けたスタアートアップのうち5%ほどに著名投資家が入っていました。
今月を見るとアメリカでドラッグストアなどを運営すCVS Health本体やそのCVCの存在感がすごいですね。11社中3社に入っています。
ざっと見渡してみて思うのは、まず、著名投資家が入っているラウンドがアーリー以降が多いなということ、割とライトなヘルスケア含めディープテックまで幅広に投資を受けているなということを感じます。
ステージの話でいうと、今月の全体の分布を見ると34.5%がシードステージになりますが、著名投資家が入ったラウンドを見ると27.2%がシードということで、不明ステージを抜くとぐっと差が出るので、たまたまなのか、何か領域に紐づく特性からアーリー以降が多くなるのかというのは、今後追いかけながら見ていきたいなと思います。
今月のPick up
建設に関しては、その月に調達した企業すべての中から気になって企業をピックする感じにしていたのですが、ヘルスケアはそれをやると無限に時間がかかるので、著名投資家の投資先からピックして書いていこうと思います。
今回は3社をご紹介します。
【Paradigm】医薬品開発における臨床試験のアクセス再構築による効率改善

ステージ:Series A
ファイナンス履歴:
見方:ステージ リードVC等(ファイナンス時期)
Series A ARCH Venture Partners他(2023年1月)
サービス概要等:
ラウンドをリードしたARCH Venture Partnersが考案し立ち上げられたサービスで、主に医療提供者、研究者、製薬会社の治験に関わる業務を簡素化、また患者のマッチングプラットフォームも提供。
サービス利用費用は医療提供者からは取らずに製薬会社のみから徴収する形で提供。
将来的に臨床試験にかかる費用や時間の負担削減を目指す。
実績:オンコロジー領域における臨床試験に利用中
【Array Behavioral Care】臨床医や地域医療施設と連携したメンタルヘルスケア

ステージ:Series C
ファイナンス履歴:
見方:ステージ リードVC等(ファイナンス時期)
不明 Impact Engine他(2021年1月)
Series B Wells Fargo Strategic Capital(2021年2月)
Series C CVS Health(2023年1月)
サービス概要等:
病院や診療所をネットワーク化しオンライン中心でメンタルヘルスケアサービスを提供する。
個人だけでなく医療機関向けにもサービス提供を行っており、専門医のいない病院等でもオンデマンドで専門医によるオンライン診療を提供
遠隔診療にあたる医師は全米の優秀な候補者の中から独自の審査を経て選定されトレーニングを受けている。
また、全米最大のネットワークを有しており、全米50州すべてでのサービス提供が可能
直近の事業等数値:
遠隔医療提供数:350,000+(2020年)
NPSスコア:55(2020年)
【Carbon Health】予約から処方薬受け取りまで統合した診療サービス

ステージ:Series D
ファイナンス履歴:
見方:ステージ リードVC等(ファイナンス時期)
Series C Dragoneer Investment Group(2020年11月)
Series D Blackstone Group(2021年7月)
Series D CVS Health Ventures(2023年1月)
サービス概要等:
リアルの病院等をネットワーク化しオンライン・オフラインのハイブリットで医療提供を行う。
診療後、薬が必要な場合には自宅まで薬の配送を行う。
救急医療のネットワーク化にも成功しており、急を要するものから慢性疾患、継続サポートが必要な疾患まで幅広い対応が可能。
直近の事業等数値:
診療施設のある州の数:13州(2023年)
診療施設数:125(2023年)
今月の深堀~地方医療~
実は、このnoteを書きながら投資先の起業家さんにご紹介いただいた地方医療と地方交通に関するイベントを聞いていました。
個人的にも注目してるところで、地方交通については既にイベントを紹介してくださった会社に投資させていただいてるんですが、地方医療のところはまだまだこれからかつ、今後投資もしっかりやっていきたいなと思っています。
上で取り上げたArray Behavioral Careは説明だけ読むとそこまで地方医療感なかったと思いますが実は非常に長い会社で1999年に田舎で遠隔医療のサービスを提供したのがこの会社のルーツになります。
今回の深堀では、逆に日本の地方医療の現状について掘り下げてみようかと思います。(もう、その中にいる方や、興味をもって調べてらっしゃる方には釈迦に説法どころではない話を書いてますので、飛ばしてください。)
前提としての過疎化と高齢化
地方医療といっても、人口が一定存在していて、医療施設を作っても採算が合うのであれば不採算による医療崩壊みたいなものは起こらないのかなと思います。

しかしながら、ご承知の通り過疎地域の割合自体は年々増加しており、2022年に初めて全体の5割を上回っています。(市町村数の推移ではなく割合を出したのは市町村合併等もあり正確に比較することが難しいため)
過疎化が進むことによる医療インフラへの影響
人口減少によりインフラの維持が難しくなっていくというのはイメージしやすいかと思いますが、医療もそのうちの一つで人口に対する医師の数を比較してみるとこんな感じになっています。

全国と比較してみると、人口減少の影響を最も受けやすいであろう小児科、産婦人科は倍前後の差があり、一番さの小さい内科でも30%近い差があります。
一方で面白いのはこのデータでして

※無医地区とは、医療機関のない地域で、当該地域の中心的な場所を起点として概ね半径4Kmの区域内に人口50人以上が居住している地域であって、かつ、容易に医療機関を利用することができない地区
無医地区と呼ばれている地区は増えているのかなと思いきや「へき地診療所」の開設等により地区数自体は急減少していることがわかります。
へき地医療拠点病院と呼ばれる病院の内訳を見てみると下記のような形になっていて、公立の病院が6割を超えており、公的病院まで含めると8割以上がそれにあたることがわかります。

公立病院の経営状態
過疎地は増えてるけど、病院がないわけじゃないから、なんだかんだ言いながらも医療は安心じゃんとも思うのですが、この中身が大事なのかなと思っていて、令和5年に全国公私病院連盟が出した「令和4年 病院運営実態分析調査の概要」によると自治体病院のうち88.8%が赤字という現状があります。
過疎地域における高齢者割合が高いことを考えると、医療ニーズは非過疎地よりも高いはずで、その中においてほぼほぼ赤字病院となってしまうと、これを補填する公的資金が絶えれなくなるのが先か、効率化が追い付くのが先かという、継続が危ぶまれる状態なのかなと思います。
経営や体験の改善、リソース不足対策としての遠隔診療と現在地
平成9年に離島やへき地における遠隔診療が認められて以降、ルール化等が進み、H30年度の診療報酬改定では「オンライン診療料」が作られ徐々に改善に向けた取り組みが進んでいます。

結果として上記表のように遠隔医療の実施割合は令和2年時点で34.2%まで高まっています。
が、この表見てちょっと違和感ありませんか。
素人感覚でいう遠隔医療=オンラインでの診察みたいな感じがあるかと思いますが、もちろんそれも含んでいるのですが、その割合は表のように4.5%、その他は下記のような医療従事者間の遠隔医療ということのようでした。

今月のPick upで取り上げたArray Behavioral Careが行っている医療機関向けのサービスというのは、まさにこの上の図の部分になると思います。
ここまで、地方医療の現状と課題が深刻化するトレンド、その課題対策の現状を簡単にではありますが見て来ました。本当は進んだ事例等あると思うのですが全体感としては課題はありつつもまだまだ遠隔医療自体も医療従事者間、従事者-患者間ともにこれからという状態で、USの事例で取り上げるような予約から薬のデリバリー、経過管理まで垂直統合で!といった状態には遠いなということが見えた気がします。(なんとなく思ってた通りではあったけど)
じゃあ、ある程度効率化やもっと簡単に質の高い医療へのアクセスを作っていこうぜということなんですが、医療保険制度がかなりしっかりしている日本において参入の仕方はちゃんと考えないとまずいのかなと思っています。
一番ありそうなのは、今ある既存の病院を支援する形で参入するタイプですが、医師の方を巻き込んだり、医師の方自身が起業する形で直接参入する形など、超えないといけない壁を越えつつ事業の広がりを作っていくにはどう入っていくのが良さそうか、それを考えるための引き出しとして、USの事例をインプットしていくのはかちがありそうだなぁと思いました。
また、この辺は今後注力してやっていきたいところなので、この辺取り組まれているスタートアップの方はもちろん、医療従事者の方、研究者の方、自治体の方、国の中の方などぜひディスカッションさせていただけたら嬉しいです。(よろしければ、Twitter、Facebookなどからご連絡いただけたら嬉しいです。)
編集後記
今回はフォーマット変更後初めてのヘルスケア領域noteとなりました。
わかってはいたのですが、尋常じゃないほど数が多いですね(笑)
今月は試運転ということで、月2本にしていたんですが、来月から教育領域を追加して、元に戻してみようと思います。
一方でもともとやっていた欧州の建設不動産については、一旦ストップで、半期に一回程度まとめてやる感じにしようかなと思っています。(教育は建設不動産並みに少ないと予想してるのですが、ヘルスケアが多すぎるので、ペースをちょっと落としたい。)
余談をあまり入れなくてもやっぱり長いので、短めに終わろうと思いますが最近、よく地方に行っておりまして、今年始まって2か月ですが、すでに昨年の6割ほどのフライト回数をこなしております(笑)
ぜひいろいろな方とお話しできたらと思いますので、うちにも来てくれとか、お茶でもしようよと言ってくださる方は是非ご連絡ください!
今回も長文読んでいただきありがとうございました。
-----------------------------------------------------------
ファーストラウンドを中心に事業に関するディスカッションや資金調達に関するご相談をとてもとても、それはとてもお待ちしております!
プロダクトのないアイデア段階でも全然大丈夫です!
事業領域も幅広にお待ちしてます!
もしご興味のある方はTwitterのDMオープンしておりますのでこちらから、その前にどんなとこに投資をしていたり、どんな領域に興味を持ってるか知りたいと言う方は下記のnotionをご覧ください!記載してる注力領域以外にも投資させていただいてますのであまり気にせずお声がけください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
