
片岡義男『アイランド・スタイル』①月夜のサーフィン後、合奏を楽しむ。
湾に月が昇った。
海から昇ったばかりの月は狂気のように大きい。夜の海が、その青さを映した。月から湾の入口にむかって、月光を反射させている波の道が長くのびた。
月の光を受けて5本の波の峰が白く輝いた。
湾の南で高さのピークができ、チューブ状の波になる。
☆
せりあがった峰は、アーチとなり、まっすぐ進む。湾の北側の岬ちかくで閉じるまで、150mをこえるチューブが、生まれては消え、また生まれる。
南太平洋の広がりは、はるか遠くまで、その生命力をおよぼしている。波がこの島と触れ合うとき、海が永遠にかかえている生命力の一部分が、華麗に燃焼する。
☆
ぼくはサーフボードにまたがって、湾の入口にむき、海面に浮いている。
手をのばせば届きそうなところに、狂った月が丸く青い。
ふりむくと、暗い底なしの海から、うねりがくる。
すさまじい力で、ぼくは夜空にかかえあげられる。無重力のように自分が軽くなる瞬間、湾の奥のすべてをぼくは見渡す。
☆
ぼくは下へ降ろされる。前方に盛りあがる波をその背面から見上げる。
チューブ波は北側の岬にむかって走りきり、平らになる。
月や星空、海岸ぞいの椰子の林のむこうの山裾に点在する民家の明かりをながめて、小さな波を3つ、やりすごした。
そのあと、ボードに腹ばいになりパドリングでまえに出た。

暗い海を、ふりかえった。
横に一直線のうねりが、こちらにむかっている。充分な高さと底に秘めたパワーが感じられる。
この波だ。
ボードに腹ばいになり、波の接近を待った。
しっかりひきよせてから、ぼくは猛然とパドリングをはじめた。
波が、ぼくに追いついた。
☆
夜空にむかって高くほうりあげられながら、ぼくはパドリングに最後の力をこめる。
波のスピードにおくれることなく、サーフボードごと、へばりついている。
波が限度までのびあがったとき、両腕を立て、利き足からボードのうえに立ちあがる。
ボードの前部に重心をかける。逆落としのテイクオフだ。
☆
オーバーハングになりかかる波のてっぺんに、無重力のまま、ぼくはいる。
波のエネルギーがぼくを支えている。
ボードのスケッグが波にくいこむ。
波のパワーがサーフボードぜんたいにいきわたり、両脚をとおして、ぼくの体に乗り移ってくる。波とサーフボードとぼくとが、ひとつにつながれる瞬間だ。
☆
急スロープの波の腹を、まっすぐにボトムまで滑り降りる。
加速でたくわえたスピードでターンをする。
ボードの右側のレールが波にくいこんだ。
スロープをのぼり、ショルダーの上限で切りかえし、全身でローラーコースターに飛びこんだ。波の斜面ののぼり降りをくりかえし、スピードをたくわえる。
☆
オーバーハングはアーチをつくって頭上をこえ、ぼくはチューブのなかを走る。
スピードを落とす。チューブが前方にのびる。
楕円型の出口が前方に見え、その出口から月光がさしこんでくる。
チューブが小さくなり、ぼくをつかまえようとする瞬間、出口をすりぬけ、波の頂上を突き破り、波の外に出る。

月の位置が低いあいだに、ぼくはもう一度、チューブ・ライディングをおこなった。
青く丸い月が、もう一度チューブに入れ、と語りかけていた。
沖に出て、チューブ波をつかまえる地点までひきかえし、波を待った。
田舎町の明かりが、夜のなかに、輝く宝石のようだ。
☆
サーフボードとぼくを操るのは、海の呼吸のリズムだ。
今夜の海は、ぼくを許し、つき合ってくれているようだ。もし海が機嫌をそこねたら、ぼくなど、ひとたまりもない。
波が来た。
サーフボードごとぼくを高く持ちあげる。高さのピークをつかまえたまま、波のスピードに負けないようパドリングする。
☆
そして、両腕をボードに立てようとする瞬間、ぼくは音を聞いた。
聞いたとたん、言いようのない戦慄が全身をつらぬいた。
重い音だ。大きな岩どうしが海底でぶつかりあうような音だった。
全身がすくみあがりつつも、ボードに立ちあがった。オーバーハングの頂上を突き破り、空間へ飛び出していく。
☆
その一瞬、ぼくは再び音を聞いた。
硬くなった体で波のスロープに飛びこんだ。
スケッグとテールが波の腹にくいこむ瞬間、またあの音が聞こえた。
海や波、月や星空が怖いものに変わった。
チューブに入るのをあきらめた。
ボードの先端に重心をかけ、波を一直線に滑り降り、いけるところまでいった。

サーフボードをジープに積んで、町の裏側を抜ける道路へ走りはじめた。
なだらかな丘の斜面は日本人墓地だった。
北にまわりこむと、眼下に川が見えた。
橋を渡った。川ぞいの小さな平野はタロイモの畑だ。
また橋を渡った。まっ赤なアンスリアムの花が咲いていた。
☆
道の片側に牧場が広がった。
反対側は畑だ。キャベツができている。
風の香りや肌ざわりが変わった。標高のある谷間の風だ。
遠く眼下に、湾が見えた。押し寄せてくる何本ものうねり波が月光に輝いた。
道路の分岐点の三角地帯に、オヒア・レフアの樹が何本も立っていた。
左の道に、ジープをむけた。
☆
のぼっていくと、このジープを貸してくれたサンフォード・カマカニの家がある。
彼は、60歳をこえ、ハワイ系の血をひく。誰もがパニオロと呼んでいる。
パニオロはハワイ語でカウボーイのことだ。
彼は、ハワイの伝統音楽を愛するミュージシャンでもある。
涼しい谷間の風に乗って音楽が聞こえてきた。
☆
道のいきどまりにパニオロの家があった。うっそうたる熱帯樹林のなかに埋まるようにして木造2階建ての家が建っている。
昔、ハワイに渡ってきた宣教師の子孫が住んでいた。
事情あってアメリカ本土に帰ることになったとき、送別パーティで聴いたパニオロの音楽に感激し、彼にこの家をプレゼントした。

手すりのついた階段を2階へあがった。そして、テラスに出た。
いつもの常連がテラスで合奏をしていた。
パニオロの奥さん、マティルダがぼくを見て、足もとのアイスボックスを示した。冷やしたビールがつまっていた。
プリモを2本とりだし、栓抜きでふたをあけた。
☆
谷間の涼しい風がテラスに吹き渡った。ビールが、気絶しそうなほど、おいしかった。
中央にパニオロ。左側に4人の息子たち。右側には古くからの友人がふたり。その右にダナ。そのとなりに娘のセシリア。
半円型に椅子をならべている9人のむかいに、ボブ・ラインハートがあぐらをかいてすわっている。
☆
ラインハートは、白人のミュージシャン。アメリカの伝統音楽を掘りおこし、現代に生きつづける音楽として紹介しつづけている。
西海岸でラリーからパニオロたちの音楽を聞かされて感激した彼は、自分も加わったかたちで現代のハワイ音楽を現地録音するのだ。
録音器材やスタッフがあと数日で到着する。
☆
音楽をやるとき、パニオロたちにはリーダーというものが存在しなくなる。気心を知りつくした連中だから、ハーモニーの素晴らしさは比類がない。彼らの音楽は、音楽をやるときの状況、いまなら星空、山から吹く風、花の香り、樹々の匂い、夜の時間の流れ、宇宙をあおぐ空間意識などに溶け合って一体だ。

ハワイの夜の青い月明かりについての歌を、彼らは演奏しはじめた。ぼくの大好きな歌だ。
パニオロのスティール・ギターは神技のようだ。いまテラスに降り注いでいる月光を音楽に変えたら、このような音になるはずだと誰もが確信する音色だ。
☆
マーカスやダナのギターは風。ハイラムのベースは、かすかに聞こえる海の音。息子たちとセシリアの楽器が出す音は、花の香りであり、風にゆれて触れあう葉の音だ。
このうえもなくゆったりしたなかで、すべての音が緊密にからみ合う。
聴いているぼくも、緊張が溶解し、月光や風になってしまいそうだ。
☆
歌が終った。ぼくはラインハートのそばにすわった。
「チューブは、どんな様子だった?」とダナ。
「素晴らしかったけど、最後に奇怪な音を聞いたんだ。海底で大きな岩がぶつかりあうような」
「海がよろこんで声をあげたんじゃないか」とレイモンド。
「だとしたら、ぼくをあんなに怖がらせはしない」
☆
「ダンがいるといいんだがなあ」とパニオロ。
ダンは、カフナ(僧侶)の家系。タヒチから双胴のカヌーでハワイに渡ってきた人たちまで家系をだどることが可能で、ハワイの古い伝説や宗教儀式に詳しい。
息子たちが演奏をはじめた。
ぼくはその場に横たわった。星を数えようとしていたら眠ってしまった。
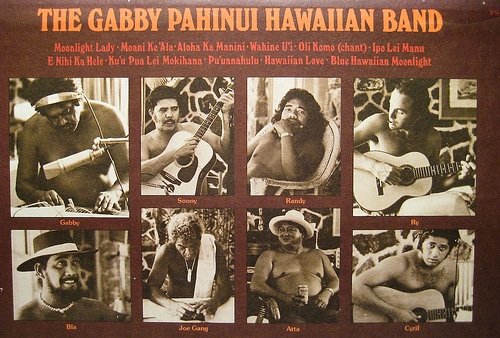
湾に面したこの小さな町は、現存する古き佳きハワイとしては最後のものではないだろうか。
観光地としての開発はゼロだし、ホテルは木造2階建てが1軒あるきりだ。
メイン・ストリートは歩いて20分かからないみじかさだ。
建物はほとんどが木造で相当の年代ものだ。
☆
日没の時間、メイン・ストリートの端に立って町の中心を見ると、海に面した建物はくすんだ黄金色に染まり、海を背にした家なみは淡いシャドーのなかだ。
人どおりが早くもなくなっている。だが店はまだ開いている。建物のたたずまいは1920年代のハワイと言っても通用する。
ぼくは郵便局へいった。
☆
パニオロあての郵便物を箱から出した。奥さんに頼まれたのだ。
雑貨店のとなりに玉突き屋がある。奥の台で、ラリーが常連を相手にローテーションをやっていた。
「よう。海に哮えられたというじゃないか」
「ほんとだ。ラッセルが言うには、個々の人間の運命を超越した、不吉な出来事の前兆だそうだ」
☆
「そのうち空でも落ちてくるんだろう」
冗談のような口をきいているが、ラリーは、ぼくが聞いた奇怪な音を聞いてみたいと、やって来たのだ。
「そうだ。忘れるところだった」
とラリーはポケットから航空便を出した。
日本のサーファーからだ。ハワイ音楽を演奏する日本人青年たちが訪ねてくるという。

関連する投稿
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
