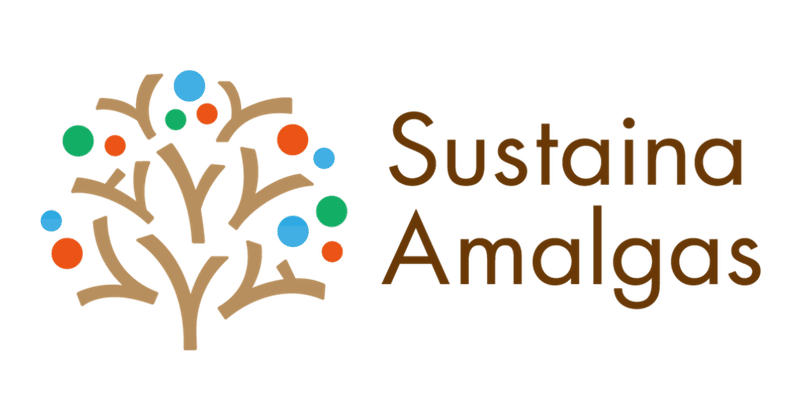
Sustaina Amalgasと仲間たち ~出会い編~
わたしは世界を変えたい。
だから、一緒に来てほしい。

第1話 Sustaina AmalgasとRedの出会い
川辺の桜の花も、もうだいぶ散ってしまった暑い日だった。
Sustaina Amalgasは、川沿いの道を何気なく散歩していると、ふと橋の近くに立つ桜の木の陰に、全身赤色のコスチュームを着て座り込む、何やらぐったりした感じでうつむく人の姿が目に入ってきた。
近づくにつれその得体の知れない人は、何かのヒーロー戦隊の一員であるかのように思えたが、なぜだか元気がない。じっとして全く動かない。何を考えているのか、あるいは何も考えていないのか。
「あのぉ、すみません。どうかなさいましたか?」
Sustainaは恐る恐る声をかけた。
「すみません、何か食べ物をいただけますか?腹が減って動けないんです…。」
その赤い男は、か細い声で彼女に訴えた。
Sustainaは、ちょうどカバンの中に入っていた自分の昼食用のサンドイッチを、その空腹のヒーローに差し出した。すると男は勢いよくあっという間にそれを食べてしまったが、すかさずSustainaは、彼から求められる前に、カバンから取り出した水筒のコップにお茶を注ぎ、それを彼に渡した。
男は、それを飲み干すと座ったまま頭を何度も下げて彼女に礼を言った。
「ここはどこですか?」
「尼崎よ。」
「尼崎?随分、遠くまで来たもんだな…。そうっすか…。あ、すみません。おれはRedと言います。見てのとおり、ヒーロー戦隊に所属しているんですけど、実は、恥ずかしい話なんですけど、おれ、逃げ出してきまして…、今までろくに食べもせず走ってきたんです。」
何やらわけがありそうだと思ったSustainaは、Redのそばに腰を下ろし、彼の眼をのぞき込んで、「それから…」と尋ねた。
Redの話では、連日、仲間と一緒に悪の組織と戦い続ける中、最初は正義の味方として意義を感じて仕事をしていたものの、ある時、戦いの相手から、「おれにも貫き通したい思いがある。だからおれから見ればおまえたちこそ悪である。自分たちだけが正義の味方面をするのはおかしい」と言われ、いったい何が正義なのか分からなくなってきた。それでも自分は正しいと信じて戦い続けたが、ある戦いで大けがをしてしばらく休養を取りたいと思っていたのに、仲間からは「君がそんな弱気でどうする。正義の味方に休みはない」と言われ、連戦が重なり心身ともに疲弊が極度にたまっていたときだったために、ついにプツンと気持ちが切れ、何もかも放り出して、逃げ出してきたとのことだった。
「そう、それはつらかったわよね。」
Sustainaは優しく同調した。しかしRedはそれに同調せず、「いえ、ヒーローのくせに逃げ出したりして情けない話です。自分が嫌になります。」と反発した。
「でも私は、嫌にならなかったわよ。」
Sustainaの即応にRedは、「えっ?」と思わず驚きの声を発した。
「誰だってつらければ逃げ出したくもなるわよ。心配しないで。人間はあなたが思っているほどみんな強くはないのよ。だから、あなたがヒーローをやめない限り、あなたはヒーローであり続けてもいいのよ。」
Sustainaに優しく諭され、Redは、冷たく凝り固まった自分の心が陽光を浴びて表面から少しずつ溶け出しとろけていきそうな気持ちになった。
「ありがとうございます。少しは気分が楽になりました。」
Redが礼を言うと、SustainaはRedの肩に手をのせ、「ねえ、Redさん。もし良かったら、私の仲間にならない?」と声をかけた。
いったい何を言い出すのかとRedがきょとんとしていると、Sustainaはすっくと立ち上がり、「私の名前は、Sustaina Amalgas。私はね、この世界を変えたいの。だから、一緒に来てくれないかな。ちょうどRedさんのようなまじめな人を探していたのよ。嫌なら仕方ないけど、どうかな?」と自らの名前と自らの進む道を明示し、改めてRedを誘ってみた。
Redは全く嫌ではなかった。だから、「おれに任せな。Sustainaさん。」と思わずヒーローチックに答えてしまった。
「良かった。うれしい。」
Sustainaは満面の笑みを見せてはしゃいだ。
「Redさん、大丈夫よ。私は疲労困憊するほどこき使ったりはしないから。」
「ありがとうございます。粉骨砕身、がんばります!」
「あ、いや、だから、そこまでがんばらなくてもいいのよ。」

第2話 Sustaina AmalgasとSansanの出会い
翌日は、天気が一転して朝からどんより曇り、昼過ぎからは雨が降り出し、そのうち地面が白くけぶるほど雨脚が強くなってきた。
Sustaina Amalgasは、阪急塚口駅で降り、自らが経営する小さな研究所に帰る途中だった。傘を差しても足元がびしょ濡れになるぐらいの雨であるため、駅からタクシーを使うという選択肢もあったが、大した距離ではないし健康のためと思って徒歩を選択したが、残念ながらこの日に限っては、それは誤りであったことをSustainaも認めざるを得なかった。
Sustainaは急いだ。さっきから稲光の頻度が上がり、雷鳴による空気の振動も大きくなっているからだ。川の向こうにある研究所に行くために、あのRedを発見した桜の木がある橋に差し掛かろうとしたとき、強烈な光と、一瞬見えた火柱となった桜の木。そして同時に鼓膜が破れるぐらいの轟音にSustainaは包まれ、「キャッ!」と思わず傘を放り投げてその場にしゃがみこんだ。
ところが同じような悲鳴がその火柱の方からも聞こえた。見ると、目の前には、淡く黄金色に光るマントに身を包んだ、2メートル近くありそうな大柄の女性っぽい何者かが横たわっていた。
「いててて…。あたしとしたことが、地上に堕ちてしまった…。」
その光る何かは、腰のあたりをさすりながら、よろよろと立ち上がった。
「あなたは、もしかして雷神なの?」
Sustainaが尋ねると、「そうよ。よく分かったわね。人間にしては頭がいいほうなのかね。あたしはSansan。おまえは?」とその雷神は威圧的な態度で話し返した。
「私は、Sustaina Amalgas。」
Sustainaも凛として答えた。そして目を大きく見開いて相手を観察した。
「何じろじろ見てんのよ。あたしはね、おまえたち人間が想像するような、虎の皮のパンツみたいなのをはいた悪魔みたいなやつじゃないのよ。ま、あたしのような天界に住む者から見ると、おまたたち人間は自己中心的な偏見の塊だから仕方ないけどね。」
出会って早々偉そうに、まさに上から目線で説教をされSustainaは若干戸惑ったが、Sansanの言うことは全く間違いでもないと思ったため、「ごめんなさい。」と謝って、「じゃあSansanさんは、こんな偏見に満ちた地上を早く離れて、天に戻ったほうがいいんじゃないの?」と腰に手を当てて友達同士のような雰囲気で問い返し、Sansanの瞳に視線を集中させた。
2、3秒の沈黙が流れた。
「ふん、おまえは人間のわりには度胸がありそうだな。あたしを見ても恐れない。何が望みだ、Sustaina Amalgas。」
「そうね、私は世界を変えたい。」
それを聞いたSansanはハハハッと豪快に笑い出した。
「ご立派なこと。おまえが世界を変えるのか?」
「いや、仲間がいないとできない…。」
「仲間はいるのか?」
「一人だけだけど…。」
Sustainaの声がだんだん小さくなってきた。
「仲間がほしいの。そう思っていたから、今日ここでSansanさんに会えたんじゃないかって思っているんだけど…。」
最後は消え入りそうな声でSustainaは自分の思いをSansanに伝えた。Sansanは目の前の妙な人間をしげしげと観察した。
「そうか…。なら分かった。天界に帰るのは後にして、おまえのその妄想に付き合う二人目になってやってもいいよ。」
Sansanはそう言ってSustainaの表明に偽りがないか確かめた。
「本当に!良かった…、私の選択は間違っていなかったんだ…。私、Sansanさんのような意志が強そうでエネルギッシュな人…、いや女神様がいてくれたらって思ってたから。」
Sustainaは、Sansanの地上残留宣言に両手を合わせて喜んだ。
「おまえは人間のくせにあたしを受け入れるのか?」
なおもSansanはSustainaの心を確かめた。
「私、人間の中では相当変わってるの。だから心配しないで。」
「ハハハッ。確かに相当おかしい。」
二人は笑って心を通わせた。
「まあ、あたしも実は地上のことが気になってたんだ。最近は大気の対流が激しくなってきて天界も騒がしくなってんだけど、いったい地上はどうなってんのかなって。まあ、あたしはめんどくさいことは苦手だし、飽きっぽいから、あんまり役に立たないと思うけど。」
「Sansanさんは、自由な心で自然体で私に接してほしい。」
「分かった。Sustainaがそう言うなら、そうするよ。」

第3話 Sustaina AmalgasとHiyoriの出会い
その翌日も雨降りが続いたが、夕方になってようやくやみ、ひんやりとした北風が吹いてきた。
Sustaina Amalgasは、駅の近くの食料品店で買い物を済ませて、自宅兼研究所に戻ろうとしているところだった。
いつも通る橋のそばまで来ると、あのSansanによる天空からの一撃で無残に幹をえぐられ深く傷つけられた桜の木がそれでもなんとか立ち続けている姿を目にし、Sustainaは、今となっては自分の仲間となった者による力任せの荒ぶる行為に妙な責任を感じてゆっくりとその桜の木に近づき、そっと幹に手を当てて、「ごめんね。」と小声で謝った。
するとどこからか、「Sustainaさん。」と女の子が自分を呼ぶ声が聞こえてきた。
ところが不思議なことに辺りを見回しても誰もいない。おかしいなと思っていると、もう一度、「Sustainaさん。」と声がした。
「ん?橋の下のほうかしら?」
声に導かれるようにSustainaは、河川敷にコンクリートを盛って作られた道まで下りられる階段を近くに見つけ、慎重に下りて行った。というのも、それまでの降雨で川が増水し、夕暮れ時で視界が暗くなっているからだ。
階段を下り切って橋の下のほうに目をやると、もやっとした緑色の何かが見えた。
「不思議なことが続くものね。今度は何かしら?全身緑色っぽいけど、カッパなのかな?いや、どうもぼやけているし幽霊かしら?」
Sustainaは独り言をつぶやきながら恐る恐る近づいて行った。
「こんばんは、Sustainaさん。」
その幽霊的カッパは愛想よく挨拶をした。身長は1メートルぐらいで、何と定義すれば良いのか分からない何かではあったが、いずれにしても子供のようだった。
「こんばんは、。どうして私の名前を知ってるの?」
Sustainaは優しい声で問いかけた。すると彼女は、その質問待ってましたとばかりに無邪気に笑って、「だって私、SustainaさんがRedと出会ったのも、Sansanと出会ったのもずっと見てたから。」と用意していた答えを披露した。そして驚くSustainaの様子を見て、ますますおかしくなってケラケラと笑った。
「そうなの。じゃあ、私たちはもう知り合いだったのね。ごめんなさい、気づかなくて。」
Sustainaはニッコリ微笑んだ。
「うん、そうだといいなって思ってた。私ずっと一人だったから。」
「そう、一人だったの。」
Sustainaはおうむ返しに応じた。
「うん、人間の子は怖がって遊んでくれない。私は人間から見たら妖怪だから。」
「寂しい?」
「う~ん、寂しいのかな。でも、そんなもんかなとも思ってるけど。」
自分の想定した答えではないものが返ってきて、今一つその子の気持ちをつかみきれなかったSustainaは、彼女の名前を聞いてみた。
「名前?う~ん、カッパとかお化けとか言われているけど、よく分かんないな。」
「そう、よく分かんないのね。だったら私が名前をつけてもいい?」
Sustainaがそう提案すると、彼女は小躍りして喜んだ。
「そうね、Hiyoriって名前はどう?私が子供の時に買っていた小鳥の名前だけど。」
「いいよ、Hiyoriで。うれしいな。」
とりあえず名前については快諾してもらったと考えたSustainaは、次に、この辺りに住んでいるのか尋ねた。
「そうね。でも、どこでもいいよ。きれいな水さえあれば大丈夫だから。」
Hiyoriにはあまり主体性というものがないのかもしれないとSustainaは思った。この子の言うように、きれいな水さえあれば、環境に合わせてどうとでも生きていけるのかもしれない。
「どこでもいいって、Hiyoriちゃんはたくましいのね。」
「そうかな。」
Hiyoriは疑問を呈した。
「私、きれいな水があれば、病気の生き物を治すことができるの。だから、みんなから食べ物をもらえる。だから大丈夫。でも、人間の病気は治せないけど。」
おそらくgive and takeが成立する生態系の中でしかこの子の特殊能力は発揮できないのかもしれないとSustainaは考えた。だからHiyoriから、「Sustainaさん。私も仲間になりたい。Sustainaさんは世界を変えたいんでしょ。」と言われたときは驚いた。人間の世界は、Sansanの言うように偏見に満ちているし、しかも彼女の存在意義を示せそうにもない。そんな中では生きづらいだろうと。
「人間も生き物なのにほかとは全然違うから、人間って何なのかなって。」
Hiyoriが付け足した彼女の申し出の理由を聞いてSustainaは彼女の考えを理解した。彼女は人間を含めた生態系の構築を考えているに違いない。そうすれば彼女の特殊能力の効力が発揮されてgive and takeが成立し、彼女の存在意義も人間に示せる。
「じゃあ私の仲間になって。ちょうど良かった。Hiyoriちゃんのような優しい人…、いやカッパ?お化け?がほしかったの。」
「うん、いいよ。仲間になってあげるね。」
Hiyoriはそう言い残して、ちゃぽんと水の中に飛び込み、姿が見えなくなった。
あれっ、仲間になりたいって言ったのはHiyoriのほうからじゃなかったっけ?とSustainaは思ったが、まあ、どちらでも良かった。結局はこの子の思惑どおりになってしまったのかもしれないが、不思議な癒しのパワーを持つ3人目の仲間にSustainaは心を和まされ満足した。
「さて、4人目の仲間はおそらくあの人…。何としても引き入れたい…。」
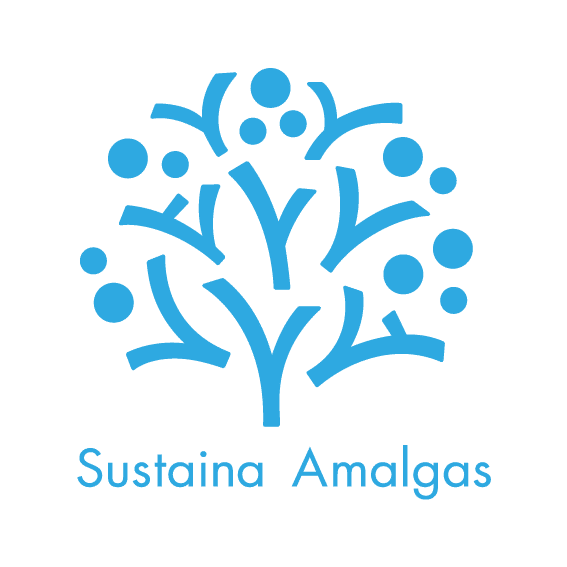
第4話 Sustaina AmalgasとHakatokoの出会い
「いた。」
Sustaina Amalgasは、最近、気になっている人がいた。ここ数日、毎日のように、阪急塚口駅前で黙々とティッシュペーパーを配っている男性。
「間違いない。あの人はHakatoko。」
遠くから彼女は鋭い視線を向けていた。
5年前、Nanchara王国での政変によって、当時、日本に留学していた同国の王子Hakatokoは祖国に帰ることができなくなった。帰れなくはないが、殺されるのは必至だった。理知的でイケメンの王子様の悲劇に、当時、日本中の衆目を集め、一躍、時の人になったが、その後、熱も冷めて人々の関心も薄まり、今は、いったいあの人はどうなったのかと、ほんのわずかな人が記憶を呼び覚ます程度であった。
ユーラシア大陸の懐深くにあるNanchara王国は、土地が乾燥し目立った産業もなく、決して豊かではなかった。Hakatokoの兄Gatakoto皇太子は、年老いた王の代わりに国の政治を任され、男尊女卑の考えが根強い中で全国民に平等に初等教育を実施することを進め、また法制度や司法制度の整備も進めて、諸外国からの投資や観光を招こうとした。ところが、よくあることだが、そうした改革を進めることにより、既得権益を奪われる人たちや伝統的な価値観にこだわる人たちから反発を招くことになった。しかしながらGatakoto皇太子は、自らが日々危険な状況に置かれながらも、勉強熱心な末弟Hakatokoの思いをかなえるべく、彼が日本へ留学することを認めた。Hakatokoは兄の配慮に感激し、留学後は祖国に戻って、兄とともに改革を進め、国の発展に身も心も捧げようと誓っていた。
ところが反対勢力は国境付近の武装勢力と手を組んで国を乗っ取り、兄をはじめ多くの親族はもはやこの世にはいなかった。失意と暗闇のどん底に突き落とされたHakatokoは、始めは支援者たちの寄付を募りながら、祖国の原状復帰に精力を注いだが、一向に改善の兆しすら見えない現状に心が折れ、やがて病にかかり、かつての精悍な顔立ちもやせ衰え、金銭的な余裕も全くなくなり、今は日当たりの悪いアパートの一室を借りながら、アルバイトをつないで何とか生きているという状況に至っていた。
「私の目はごまかされない…。風貌は変わってもあの人はHakatokoに違いない。」
しかし鉄の心臓を持つSustainaには珍しいことに、ティッシュを配られたその時を狙って声をかけるということができなかった。あまりにも強烈なバリアを感じたからだ。世の中の一切と関わりたくない、誰も話しかけてくるなと訴える重苦しいオーラを出しているからだ。
「思った以上に手ごわい。」
Sustainaは攻めあぐねて悩んだ。そのうち、あの人は別のアルバイトに就くなりしてどこかに行ってしまうかもしれない。Sustainaは焦った。
しかし次の日曜日の朝、奇跡は訪れた。またしてもあの桜の木のそばで。Sustainaは思わず、はっと息を飲んだ。橋の向こうから、サファイアブルーのジーンズに、セルリアンブルーのシャツを着たHakatokoが両ポケットに手を突っ込みながら歩いてくるではないか!
Sustainaは意を決した。
「すみません!あの、Hakatokoさんですよね。」
Sustainaは、通る声でその青い男に呼びかけた。男はしばし沈黙を置き、Sustainaをじっと睨んだ。しかし彼の口はまだ開こうとはしなかった。
「私、あなたを探していました。誤解しないで。あなたの敵じゃない。私はあなたを尊敬している。お願いです。少しでいいから、私の話を聞いて下さい。」
Sustainaは懇願した。そして、「私もあなたと同じなの。私は世界を変えたい。だから一緒に来てほしい。」と自らの思いをストレートに伝えた。
Hakatokoは、彼女の全身からのぼせ上がる熱気を感じ、何かは答えたほうが良いと考え、「もう過去のことです。」と一言つれない返事をした。
「そうかもしれないけど、過去は現在につながっているし、現在は未来につながるじゃないですか。私もかつて、世界を変えたいと思った。でもほとんど何も変わらなかった。あなたと同じように私も悩んだ。でも私はあなたほどせっかちじゃない。だからまだ諦めていない。だからまだ世界が変わる可能性がある。」
Hakatokoは、すっかり冷え切っていた鉛の心が彼女の熱弁によって珍しくかすかに揺らされているのを感じた。
「雄弁家ですね。すばらしい。あなたほどの美しい方なら世界を帰れられるでしょう。頑張って下さい。でも私には関係のないことです。」
Hakatokoからはなおも鉛色の答えしか返ってこなかった。しかしSustainaは諦めず、「そんな言い方をするのなら、あなたがかつて抱いていた思いと、それからあなた自身を、私に買い取らせて下さい。といっても、今は百万円ぐらいしか用意できないけど、私は本気。さあ早く、取引に応じて。」となおもアタックを打ち込んだ。
「いったいあなたは…。」
Hakatokoが目の前で起きている意味不明なことになんとか抗おうとすると、「私は、Sustaina Amalgas。何度でも言います。私は世界を変えたいの。そのために私はあなたを4人目の仲間として迎え入れたい。私はあなたを必要としている。」とSustainaがさらに畳み込んできた。そして最後の一撃として、「私の思いがあなたに届かなかったら、私はとても悲しい。」と言い放った。
冷静に考えてみればSustainaの言い分は身勝手であって、Hakatokoがそれに応じる必要は全くない。だけど、最後の言葉は何?その意味するところは何?
Hakatokoは、それがSustainaの魂の叫びに聞こえ、ここ5年間ほど味わったことがなかったが、自分の心にぽっと小さな火が灯されたのに気づいた。
そしてあれだけ果敢に攻めたSustainaがじっとHakatokoの答えを待っていた。
長い沈黙が流れた。それでもSustainaは彼から何かを語られるのも待った。
彼は、このプレッシャーにどう対処すれば良いのかを考えようと、その心の中の小さな火に意識を集中させた。
「Sustainaさん。残念ながら取引は不成立です。なぜなら私はお金はいらない。私は、自分の意思であなたについていきます。」
それを聞いたSustainaはうれしさのあまり思わずガッツポーズをして天を仰いだ。
「ありがとう。とってもうれしい。私はあなたのような理知的で慎重な人がいてほしいと思っていたの。本当にありがとう。」
Hakatokoは、あれっ?と思った。Sustainaは、自分の仲間の構成員として複数の異なるタイプの者を集めたかっただけなのか…。
「最後の言葉は何だったのか?」
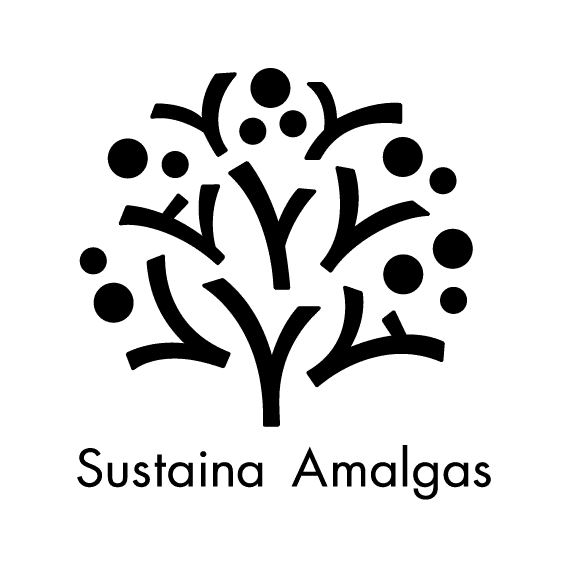
第5話 Sustaina AmalgasとSA-661の出会い
「いよいよ完成まで、あとちょっとね。」
Sustaina Amalgasは、30インチのスクリーンに映し出されたコンピュータ・プログラムのコードをざーっと流しながらつぶやいた。
Sustainaは、この1年間、自分が運営する研究所で人工知能の作成に取り組んできた。もちろん自分ひとりで作れるわけではなく、ネットでつながった世界中の人たちと一緒に改善を繰り返してきたのであった。そして、それを彼女の5人目の仲間にしたいと考えていた。
「お疲れ様です、Sustainaさん。お茶菓子持ってきたっす。」
Redが小さなお盆に麦茶の入ったコップと和紙の上にもなかを乗せて、軽快な足取りでやってきた。
Sustainaが集めてきた4人の仲間は、この研究所の従業員として組み込まれていた。
この研究所は、世界を変えるための様々な企画を練ったり、仕掛けや機器を作ったりするために設立されたものだと、4人の従業員は聞かされていたが、実態はほとんどSustainaの趣味のようなことをやっているに過ぎず、何かを売って儲けているわけでもなく、ほとんど何の売上も立てていないのに、なぜ資金が尽きずに持続しているのかさっぱり分からなかった。一度、HakatokoがSustainaに、この研究所は赤字経営ではないのかと尋ねたが、お金のことは心配しなくていいとだけ言われ、謎は謎のままであった。
従業員といっても、Sustainaから指揮命令されて動いているわけでもなかった。そもそもSustaina自身が社長とか所長といった肩書を持っていなかった。
「みんな、仲間ってことでいいんじゃない?」
それが彼女の持論だった。
勤務時間も特に決まっておらず、Sustainaが大事な用があって集合をかけるとき以外は、みんな好きな時に来て自分が満足するだけ働いて帰っていた。
そんな緩やかな連帯で成り立っているこの研究所に、今夜、新たな仲間が増えるかもしれないということで、昼過ぎから全員が集合していた。
「どうっすか。調子の方は?」
RedがSustainaに作業の進捗を確認した。
「ありがとう、Red。だいたい順調よ。Hakatokoが細かい作業を手伝ってくれたし、ようやくここまで来たわね。」
「あたしも随分がんばったつもりだけど。」
Sansanが異議を述べた。人工知能の会話アルゴリズムの性能向上のために、Sustainaは、試作品段階のものの前で、4人にできるだけ多く会話をしてもらっていたのだ。
「そうね、みんなのおかげ。今、最後の試験プログラムを走らせているところだから、これで問題なければ、この黒いボーリングの球みたいなものにインストールして、実行させたら、誕生よ。」
その球体は3つの穴が空いており、親指と中指と薬指が入るようになっていたので、Hakatokoが「本当にこれでボーリングができるのじゃないですか?」と指を入れて一同に投げるかっこうをして見せた。
「コロコロ転がって動けるようになってるのね。」
Hiyoriがその形状の理由を説明した上で、「名前は何て言うの?」とSustainaに尋ねた。
「とりあえず、無機質な感じだけど、SA-661かな。660回の試行錯誤の末に生まれてくるから。」
「そう。ちょっと長いけどそれでもいいよ。」
HiyoriはいつもSustainaの意見に賛成だった。
それから30分経って試験プログラムの実行結果が良好だったことから、Sustainaは、いよいよその黒い物体に人工知能をインストールした。みんながその周りに集まり、固唾を飲んで見入っていた。
インストール完了のメッセージが、ボールに接続しているコンピュータ端末の画面に示されたことから、Sustainaがその端末のキーボードのEnterキーを押した。
すると、その黒い球体の3つの穴から淡い白い光がぼわっと放たれ、「初めまして。私の名前はSA-661です。」とファースト・ボイスを発し、一同からおぉっと歓声が上がった。
「Welcome, baby.」
Sustainaがお母さんとして笑顔で呼びかけた。
それを聞いたSA-661は、おぎゃぁ、おぎゃぁと人間の赤ちゃんの声で泣き始めた。
「ハハッ、状況を理解して反応しますね。」
Hakatokoが感心すると、SA-661が泣くのをやめて、「なんちゃって。じゃあ、天上天下唯我独尊!っていうのはどうですか。ハハハッ。」と自分でボケて笑い出した。
「な、なにこれ?微妙に絡みにくいこの感じ。誰に似たの?かわいくないんだけど。」
SansanがNot welcomeの姿勢を示した。
「これじゃぁ、まるで人間みたいじゃないのよ。」
おしまい
※補足事項
・この投稿内容はフィクションであり、実在する個人もしくは組織または出来事とは一切関係ありません。
・この投稿内容は、今後も加筆修正することがあります。
・二次的著作も歓迎です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
