
大人になる 【短編小説/あらすじ】
お題「もみじまんじゅう」で考えた話のあらすじです。その1
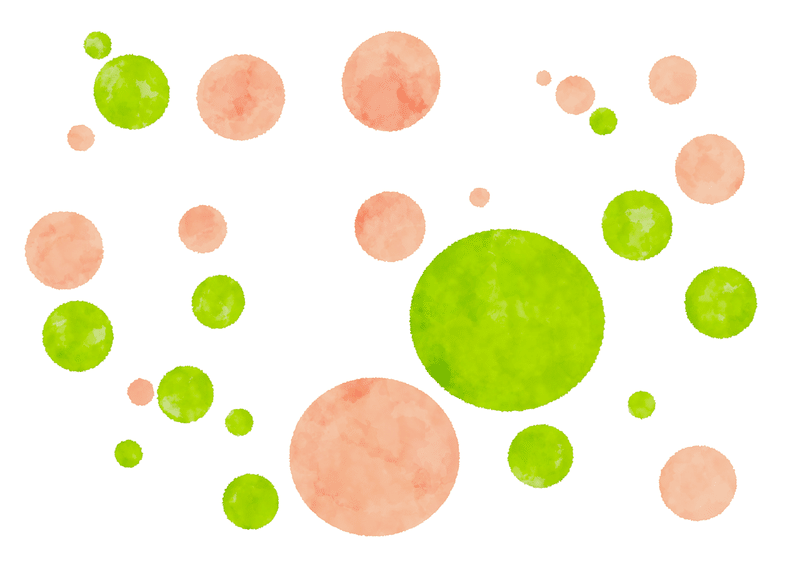
三十歳の会社員、小岩井 杏は中学校の同窓会に出席するため久々に実家へと帰省していた。母、姉と共に杏の買ってきた土産を食べながらお喋りに興じる。
現在恋人のいない杏に対し、母は「誰かいい人が見つかるかも。同窓会で再会して、そこから結婚に結びつく人って意外と多いのよ」などと言う。
はいはい、と適当にあしらう杏に姉が尋ねる。
「ねえ、あの子も来るの?」
「あの子って?」
「あんたの元彼よ。中学の時に付き合ってた子。あれ、名前なんだっけ?」
杏よりも先に母が反応する。
「ああ、山下くんでしょ。山下 歩くん。懐かしいわあ」
「止めてよ、そんな昔の話。だいたい、付き合ってたっていっても、ほんの少しの間だけだったし」
いやがる杏に、姉と母は笑いをこらえるような表情で顔を見合わせた。
「山下くんとの話、未だに覚えてるわ。だって面白かったんだもん。ねえ、お母さん」
「そうねえ」
中学生の杏と山下が付き合いを解消した原因は、もみじまんじゅうだった。
付き合い始めてすぐの修学旅行。「自由行動のときは一緒に過ごそうね」という約束通りに落ち合った二人は、もみじまんじゅうの店先で足を止めた。
店頭には様々な種類のまんじゅうが並んでいる。
「ねえ見て、山下くん。色んな味があるよ」
「うわ。抹茶味とかあるじゃん。俺、抹茶は苦いから嫌だ」
「うーん……私も抹茶はちょっと苦手だけど……。あ! カスタードがある! こっちはチーズ味だって。芋あん! うー、全部食べたい」
種類の豊富さにはしゃぐ杏に対し、山下は呆れたような顔をしていた。
「俺、普通の餡子だけでいい」
「え、なんで? どれも美味しそうなのに。私、カスタードとチョコ食べたい」
「いやいや、こういうのは絶対に餡子だろ、その方が間違いないって」
「えー、そんなのつまんないよ。たい焼きだって今川焼きだって、私カスタードの方が好きだもん」
「うわー、信じらんねー。それだって餡子が一番うまいじゃん!」
「それは定番なだけでしょ。他のも美味しいよ」
「いいや。ありえない、絶対餡子だって」
それで喧嘩になり、二人はそのまま別れることになった。
姉がうひゃひゃと声を上げて笑う。
「ひゃー! いかにも中学生って感じ! あはは、かっわいい!」
「もう! ちょっとお姉ちゃん! やめてよもう」
同窓会当日。
早めに到着した杏は、会場であるホテルのラウンジでソファに座り開始を待っていた。
そこへ山下が現れ、杏に「久しぶり」と声をかける。十五年振りの再会だった。
「はいこれ。皆に配ってるんだけど、土産。よかったら」
山下から手渡されたのは、抹茶味のもみじまんじゅうだった。
「……なんで?」
「俺さ、今仕事で広島にいるんだ。転勤で」
「へぇ……そうなんだ。……抹茶味か……」
「それ、うまいよ。……ああ、小岩井はカスタードが好きなんだっけ?」
山下が、手にした袋からもう一つもみじまんじゅうを取り出す。
「はい、これもやる。カスタードもうまいよな」
「……餡子以外はありえないんじゃなかったの?」
杏が少し皮肉を込めてそう言うと、山下はバツが悪そうに目を逸らした。
「いや、まあ……。食べてみたら予想外にうまかったというか」
「ふうん」
「今でも餡子が一番好きなんだけどさ。……他のも、まあ、うまいよな」
「そうでしょ? ……私ね、今は抹茶味も好き」
ソファに並んで座り、杏は包み紙を開く。
今なら分かる。あんなくだらない喧嘩をしなくても「他の味も一緒に試してみようよ」と言って笑えばよかったのに。
すべてに対して答えは一つしかなくて、それが同じではないと嫌だ、駄目だと思っていた。 ──ああ、本当に子どもだった。
「お互い大人になりましたねえ」
「そうだな」
杏と山下は笑い合う。
あんなふうに些細なことで喧嘩をすることなんて、今はもうない。
あの頃は苦くて苦手だった抹茶味も、いつの間にか好きになっていた。
例えば杏が地元に帰ってホッとするように、定番の餡子が一番だという気持ちも、いやというほどに分かる。
「私はやっぱりカスタードが一番好きだけど、あなたが一番好きな味は餡子なんだね。うん、それも美味しいよね」とすんなり認められる。
それぞれ好みや考え方が違うことを受け入れる余裕がある。
もみじまんじゅうを持つ彼の左手には、まだ新しそうな指輪が光っていた。
「……」
杏の視線に気が付いたのか、山下が照れたように笑う。
「ああ、先月結婚したんだ、俺」
「そっか……。おめでとう」
隣に並んで口にした抹茶味は、少しほろ苦い。
けれどそれもまた、人生の味。
ああ、こういうのが、大人になったっていうことなんだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
