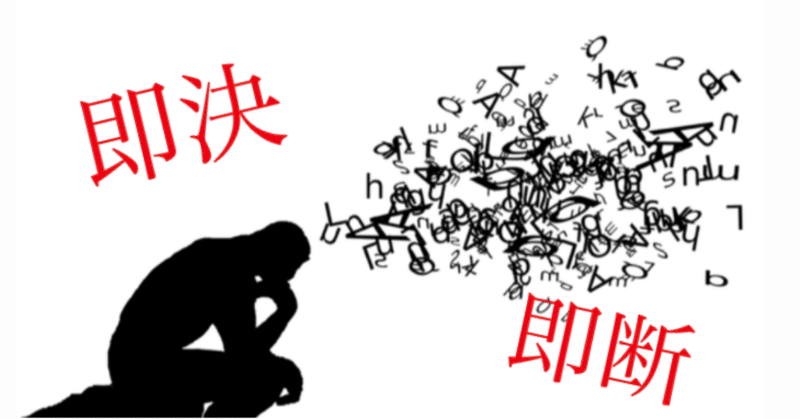
時間をかけて考えるは割にあいません
時間管理が難しいタスクの一つが、「考える」ということ。物事の判断や決断、アイデア出しなどは、なかなか満足がいかず、時間だけが過ぎていきがちだ。
※本稿は『THE21』2020年12月号より一部抜粋・編集したものです。
時間をかけてする選択が正しいとは限らない
「熟慮に熟慮を重ねた結果」という表現があるように、「あらゆる選択肢を考慮したうえで、時間をかけて検討するほうが、正しい判断ができる」と考えている人が多いでしょう。しかし、必ずしもそうではありません。
ラドバウド大学のダイクスターハウス氏の実験
4台の中古車を用意し、参加者たちにそれぞれのスペックを説明して、その中から「お買い得な1台」を選び出せるかどうかを調べる実験を行ないました。
参加者たちは、(1)「よく考えて選ぶグループ」と、(2)「選ぶための時間が少ないグループ(制限時間が設定され、パズルを解く課題をしてから選ばなければならないグループ)」に分けます。
まず、「燃費」や「エンジン」など、4つのカテゴリーについての説明をしたところ、(1)はほとんどが、(2)も半数以上が「お買い得な1台」を選びました。これは、意外な結果ではないでしょう。
ところが、次に、説明するカテゴリーを12に増やして実験をしたところ、(1)で「お買い得な1台」を選んだのは25%以下でした。当てずっぽうでも25%なので、考えていないのと大差ありません。さらに驚くべきことに、(2)では60%の人が「お買い得な1台」を選んだのです。
この実験からわかること
この実験から、情報が多い状態では、考える時間がたくさんあれば正しい判断ができるわけではないことがわかります。
むしろ、限られた時間内で考えるほうが、重要だと思われる情報を絞って判断することになり、正しい判断をできる可能性が高まるのです。別の言い方をすれば、情報が多すぎると、些細なことが気になって判断を誤るということでしょう。
スワースモア大学のシュワルツ氏によると
より多くの情報を集めたうえで選択したいと考える「マキシマイザー(追求者)」は、自分が満足できる選択ができればいいと考える「サスティファイサー(満足者)」に比べて、後悔が多く、自己肯定感が低い傾向にあります。
情報を集めることに時間を費やすよりも、自分の中に判断基準を作り、それをクリアすればよしとするほうがいいでしょう。
どんな決断をするかより「決断すること」自体が大事です。
シカゴ大学のレヴィット氏は、「コイン投げサイト」と呼ばれるウェブサイトを作りました。閲覧者たちが「今決めかねていること」を書き込んだうえで、画面上のコインを投げるというものです。表が出たら「実行」、裏が出たら「実行しない」というメッセージが表示されます。
すると、書き込まれた悩みで最も多かったのは「今の仕事を辞めるべきかどうか」、次に多かったのが「離婚すべきかどうか」でした。そして、63%もの人が、コイン投げの結果に従って行動しました。
さらに、コインの裏表にかかわらず、悩みの解決に向かって何かしらの行動を起こした人は、半年後の幸福度が高いこともわかりました。つまり、幸福度に影響を与えるのは、「どちらの決断をするか」ではなく、どちらであっても「決断すること」だったのです。
コーネル大学のギロビッチ氏らによると
人間は、短期的には「やってしまった」ことの後悔をよく記憶している一方、長期的には「やらなかった」ことの後悔をよく覚えていて、さらに、やらなかったことへの後悔は時間を経ることで高まっていくということです。
また、「何かに集中している人は、そうでない人に比べて、幸福度が高い」という研究もあります(ハーバード大学のキリングズワース氏らの研究)。
ですから、何かをしようと思っているけれども行動できずにいるなら、コイン投げでも何でもいいので、まずは決断して、とにもかくにも一生懸命やってみてはいかがでしょうか。そのほうが時間の節約になるだけでなく、幸福度も高まるでしょう。
考え込むよりもボーッとしたほうがいい
考えすぎて時間がなくなるのには、「良いアイデアが思い浮かばない」「ひらめかない」というケースもあるでしょう。歴史上の偉人たちの発明や発見には、根を詰めて考えているときではなく、ボーッとしているときに頭に浮かんだものが少なくありません。
例えば、「アルキメデスの原理」は、アルキメデスが入浴中に思いついたと言われています。また、木からリンゴが落ちるのを眺めていたニュートンが万有引力についてひらめいたという逸話も、真偽は定かではないとはいえ、ボーッとしているときに名案が浮かぶ好例と言えるでしょう。
読者の皆さんも、アイデアや問題の解決策を、ボーッとしているときに思いついた経験があるのではないでしょうか。
ワシントン大学のレイクル氏らの研究
「行動しているとき」よりも「ボーッとしているとき」のほうが、記憶や価値判断に関する脳の部位が活発に働いていることがわかっています。
「デフォルトモードネットワーク」と呼ばれるもので、近年、研究者たちの間で注目されています。無意識の状態のほうが、物事の意外なつながりや新たな発見が生まれやすいと、科学的にも考えられるようになりました。作家の村上春樹さんが「作家になろう」と思い立ったのも、野球場で、ある選手の2塁打を目の当たりにしたときだったそうです。
リモートワーク中に考えるときの注意点
もちろん、単に何も考えないほうがいいというわけではなく、考えすぎても良い結果は生まれない可能性が高いということです。根を詰めて考えすぎずに、「コイン投げで決めてみよう」くらいの軽い気持ちで、まずは行動に移してみてはいかがでしょうか。
リモートワークが広がる世界でのストレス
特にリモートワークの場合、Zoomなどを使ったテレビ会議はできるにしても、コミュニケーション量が大幅に減少します。すると、脳内で分泌されるセロトニンの量が減少し、うつっぽくなりやすくなります。
私自身、大学でリモート講義を担当するなかで感じるのは、精神的に疲れてしまっている学生が一定数存在しているということです。その状態で考えすぎることは、精神衛生上、よくありません。
考えすぎてしまうなら、身体を動かすことに時間を使うのがいいでしょう。例えば、ジムに通うことで、ストレスが減るだけでなく、感情のコントロールができるようになったり、学習習慣も身についたりと、様々な効果があることがわかっています
マコーリー大学のオートン氏らのリモートワークの研究
リモートワーク中は、インターネットで情報を得られるとはいえ、自分が知りたい情報にばかり接するようになるため、思いも寄らないものに出くわす可能性が低く、新しいことを学ぶのには適していません。
その点、トラブルを含めて、多くの体験をすることできる外出を意識的に増やすのは、ニューノーマル時代にこそ、大切になってくるのではないでしょうか。
人間が集中できる時間は金魚以下
集中力を高めることによって、考える時間を短縮する方法もあります。
マイクロソフトのインターネットやばい説の研究
インターネットの発達などによって情報が爆発的に増えている今、人間の集中が持続するのは、なんと8秒だということです。
これは、金魚よりも短いそうです……。8秒では仕事になりませんから、集中力を高める方法をいくつかご紹介しましょう。1つ目は、集中して行ないたい作業と関係のないことをすること。
今を集中するマインドフルネスは覚えておいた方がいい
イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の有賀氏とレラス氏の研究では、短い休憩を取るよりも、今やっている作業と関係ない作業を挟むようにすると、いったん脳がリセットされて効率が上がるし、作業のことも記憶に残りやすくなることが明らかになりました。
2つ目は、子猫や子犬の写真を眺めること(広島大学の入戸野氏の研究)。3つ目は、日本でも話題になった「マインドフルネス」。グーグルなどでも導入されている、「今」に集中する方法です。
「なかなか作業に取りかかれない」という人は、余計なことを考えずに、「とりあえずやってみる」ことをお勧めします。一生懸命やり始めると、勝手に「今」に集中できることが多く、次第に集中状態に入っていけるものです。
まとめ
正しい判断をしよう、失敗をしないようにしようなどと過度に考えすぎるのではなく、すべてを前向きに捉えたほうが、人生という時間を豊かに使えるのではないかということです。
ネガティブなことも含めた様々な経験を通して、より多くの感情を味わったほうが、精神衛生的にもよく、幸福度も高い――。これは、ポンペウ・ファブラ大学のクオイドバック氏らによる研究結果です。
ずっとハッピーであることだけが幸せだというわけではなく、つらいことも悲しいことも、全部ひっくるめて、自分の人生だと受け入れることが、何よりも大切な生き方なのではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
