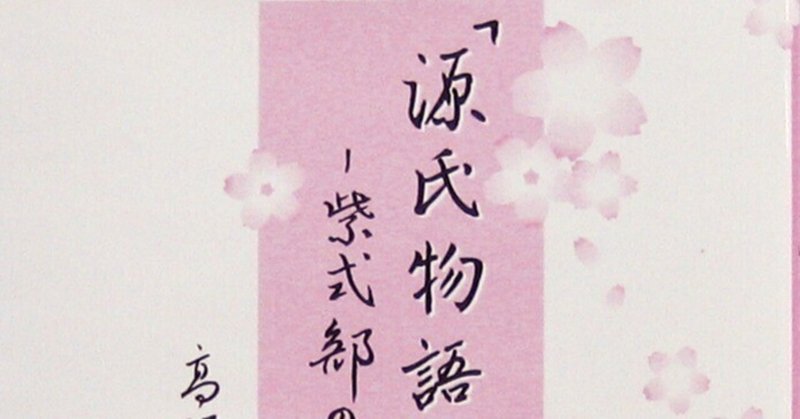
第121回 藤原実資の死
寛徳3(4月に永承と改元:1046)年正月18日、大御所的存在であった右大臣で小野宮流の藤原実資が90歳で亡くなりました。
遡る事約100年、天暦元(947)年、関白太政大臣忠平の長男実頼が左大臣、異母弟の師輔が右大臣に昇進し、三大臣を父子で独占するという栄華を成し遂げました。
兄の実頼が小野宮流、弟の師輔が九条流と二人は何かにつけて張り合いました。師輔の娘安子が冷泉天皇・円融天皇を産み、次第に政権は九条流にいきましたが、それでも小野宮流は摂関家の長子としてのプライドが高かったのです。
実資は実頼の孫ですが、幼少より聡明で、実頼の養子となって小野宮家の後継ぎとなったのです。
道長が天下を取り、娘の彰子が入内する時に、屏風に歌を求めた時、公卿は我れ争って歌を贈り、花山法皇までが歌を寄せたと言います。実資一人が
「どうして歌を贈らなければならないのだ」と、歌が余り得意でなかったせいかも知れませんが、道長の要請にも拘わらず贈りませんでした。
香子(紫式部)には再従兄に当たり、いろいろと交流があった様です。
道長と不仲だった三条天皇は、実資を頼りました。
実資は道長と敵対する訳ではなく、筋を通すという感じだった様です。そして筆まめで『小右記’(しょうゆうき:小野宮の右大臣の記録という意)』にあの道長の「この世をば」の歌が記載されています。道長本人の『御堂関白記』には載っていません。余りに気恥ずかしかったのでしょうか?
1016年の刀伊の入寇が終わった際も、部下への恩賞の懇請をした隆家に対して、大納言公任と中納言行成(いずれも道長に追従する人)らは「朝廷からの勅符が届くまでに戦ったので私闘であるから該当しない」とかつて道長の政敵であった隆家の功績を認めようとはしませんでした。まるで後年、白河法皇が源義家を妬んで「後三年の役は私闘である」として恩賞を与えなかった事と似ています。
しかし実資は「勅符があろうがなかろうが、壱岐・対馬が甚大の被害を出し、大宰府まで迫っていたのを防いだのだから十分に功がある」と力説し、賛同する公卿も出、公任・行成も翻意し、連絡が行った道長も認めたという事で恩賞が認められたのでした。
私生活では花山法皇の美貌の女御・婉子女王を妻にしたりしましたが、男子に恵まれず(一人僧籍あり)、別の女性に千古という女児が生まれ、溺愛しました。他に男子を養子に迎えたりしましたが、ほとんどの財産を千古に渡し、千古は高松方の頼宗の長男兼頼の妻となりましたが、一女を儲けただけで早世し、実資を悲しませました。その一女は結局尼となり。小野宮家の莫大な財産は院政期には空中分解してしまったという事です。
道長の後を継いだ左大臣頼通とは良好で、よく相談に乗っていたと言われます。逸話では、晩年すっかり理性に歯止めがきかなくなった実資の家には良い泉があり、そこに水を汲みに来た女性を実資が邸に引っ張り込んでいたそうです。それを聞いた頼通が、美しい下女に桶を持たせ、実資に引っ張りこまれそうになったら、桶を捨てて逃げて来いと言い含めその通りになりました。後日、頼通は実資に「それはそうとあの水桶を返して頂きたいのですが」と言うとさすがの実資も赤面していたそうです。
実資の遺した『小右記』ですが、現代訳を少しずつ読んでいますが、膨大な量です。いずれ『一条天皇の后妃たち(仮名)』に役立てたいと思います。
※連絡:明石アスピアでの『平家物語の人々』の講演に合わせて、2月26日17時まで『平家物語誕生』の無料キャンペーンを行っております!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
