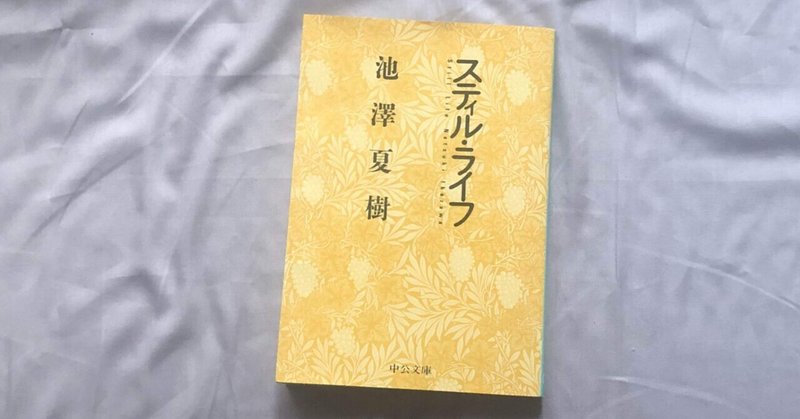
池澤夏樹「スティル・ライフ」
新しい本を買いに行く時、買う本は前から決めてある。本屋に行って面白そうなタイトル、良いカンジのジャケットを見て衝動的に買うことはない。ではどうやって買う本を決めているのかと言うと、主に3つのルートがある。
①芥川賞受賞作の一覧をネットで見て、面白そうなタイトルの本の選評を読む。選評はこの時代どこかに書いてある。そこで大絶賛されていたり、選評が僕の興味をそそれば決定。
②好きな作家がオススメしてた本。太宰治なんかは、僕が好きな又吉とか森見登美彦がオススメしてたので読んだ。
③好きな作家の読んでいない本。これが一番多いんじゃないかな。
今回は①だ。第98回芥川賞「スティルライフ」。選評を見てざっくりとした系統は予想できた。仕事帰りに紀ノ国屋に行って購入。
3ページくらいでどういう作家なのか把握。一言で言うと、頭が良すぎて逆に好かれるタイプの人。今まで読んだ作家では村上春樹が一番近いけど、もっと機械的。共感をこっちに求めていない。自分が誰よりも賢いと分かってるし、読者もそれにすぐ気づくから、何を言っても「確かに池澤先生の言う通りです」ってことになる。教授みたい?
冒頭の、コップに宇宙の粒子が降ってきて混ざったみたいな、一見かっこつけた始まり方。これも無理してかっこつけて書いているわけじゃないことがすぐに分かる。短い文章のくせに内容が具体的なので、こっちから文句をつける隙がない感じ。具体的っていうのが一番の特徴な気がする。形容詞が少ないんだと思う。形容詞が多い=幼稚な作家ではない。海外の古典作家だって形容詞を連発するし、感情を表現するには手っ取り早いので、それはよろしい。でもこの池澤夏樹を読んで、「形容詞を使わないとこれだけクールになるんだ」ってことが分かった。この本のページ数が少ないのも、余計なことが書いてないからだと思う。余計なこと=悪いわけじゃない。純文学ではその余計なものがあるからこそ「この作者何言ってんだ(笑)」というおかしみが生まれる。
リズムとしてはコンビニ人間に似ていた気がする。でも一文一文がもっと誌的。登場人物の性格は村上春樹っぽいが、偏差値がもっと高いので「なんでやねん」というツッコミが入れれない。
共感した部分はある。五年間の株の取引を終えた佐々井が時効を獲得しそうな時、寂しい気持ちになった終わりの部分。ああ、ちゃんとこういう部分も終盤に入れてくるのね、と。ところどころ人間味があるんだけど、全体的には機械が書いたみたいな文章。抜け目がなくて、サラサラっとした感じ。そういう点で今まで読んだ日本人作家の中ではかなり印象に残るクラスの人でした。お気に入りの作家の仲間入りということになるだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
