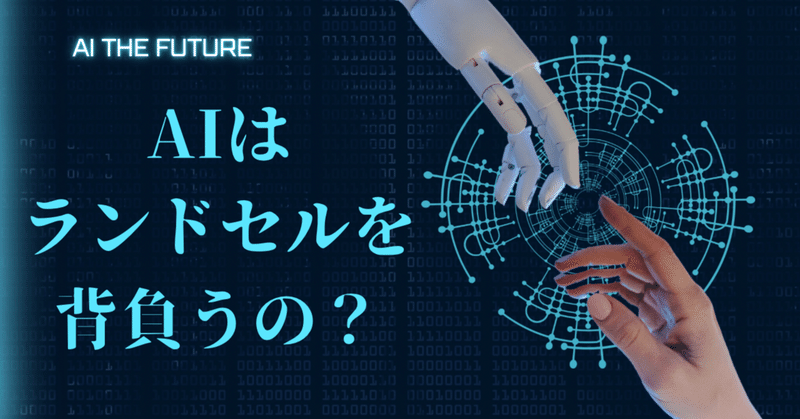
A12.AIはランドセルを背負うの?
ご覧いただき、ありがとうございます^_^
all 🍎 小学校教師 です。
最近、国語の授業で、chatGPTとBardを使った実践を行いました。
今回はそちらを紹介していきたいと思います😊
自分が書いた感想文と、AIの感想文を比較すると見えてくるものが…!
AIが書いた文章は一見とても良いのです。
でもある子が「AIはランドセルを背負うの?」と発言してから展開が変わり始め…。
早速、見ていきましょう!!
光村図書の4年国語の教科書に
『事実にもとづいて書かれた本を読もう』という単元があります。
まず、子供達は、ノンフィクションという言葉の定義を学びます。
教科書には、『事実にもとづいて書かれた本(ノンフィクション)を読むことで、心が動かされることがあります。』と書いてあります。
そこで、本時のめあてとして、
「ノンフィクションの作品を読み、感じたことを交流しよう」と設定しました。
ノンフィクションを読んで、どんなところに心が動かされるのか。
みんなで、交流しながら確かめてみようということです。
教科書には、内堀タケシ,文・写真の『ランドセルは海をこえて』が掲載されています。
以下、Bardで要約した内容です。授業では出していません。この記事の読者向けです。
ランドセルは海をこえては、使わなくなったランドセルを途上国の子どもたちに寄贈する活動「ランドセルは海をこえて」を支える人々の物語です。2002年に内堀タケシが立ち上げたこの活動は、現在では世界中の子どもたちにランドセルを届けています。ランドセルを受け取った子どもたちは、学校に通い、夢を叶えるために努力しています。
デジタル教科書を電子黒板に投影し、
読み上げ機能を使って『ランドセルは海をこえて』のお話を聞いていきました。
その後、自分でもう一度読み直し、感じたことをPadletにまとめていきます。
数分間記述した後、私がこんな提案をしてみました。
「ねぇねぇ、みんな。あのゲストに登場してもらって自分の文章と比べてみない?」
すると子供達。
「あ!AIか!いいねいいね!どんな文章を書くんだろう?」
「本当のこと書くかなぁ?」
「AIに負けたくないなぁ!」
と前のめりになって提案を受け入れてくれました。
自分のクラスでは、道徳においてたびたび対話型AIに登場してもらい、話し合うテーマについて問いかける場面があります。ですので、chatGPTやBardは初めてでは無いのです。
まずはchatGPTから。こんな回答になりました。

「えー!全然違うお話になってしまっているよ!」
「今回は失敗だね!」「僕たちの方がいい文章だな!」
なんと、ランドセルを使った冒険譚になってしまったのです。
完全にフィクションです。
次に、Bardに聞いてみました。
こんな回答に。

子供達は
「うわー、すごい。」「いい文章かも。」
「こんな表現方法もあるんだ!いいね。」
といった反応を示しました。
そこで私が、
「それっぽい良い文章になったんだけど、本当にこの文章でいいかなと思うことも大切だよ。Bardに聞いてみたいことはある?」
と問いかけました。
すると、子供達から意外な返答が。
「AIってランドセルを背負うんですか?」
予想外の問いかけです。私はこう返してみました。
「その質問で、どんなことが知りたいのかな?」
すると、こう返してくれました。
「AIはランドセルを背負わないのに、なぜランドセルを大切にしようって感想を書くのかなと思ったからです。」と返答がありました。
周りの子たちも
「あー!確かに!」「そうだよね!これは感想文と言えるのかなぁ?」
というつぶやきが。
子供の発想って素晴らしいと思いました。
それと同時に、物事の本質をよくみているなぁと改めて感じました。
私は、そのままBardに「AIはランドセルを背負いますか?」と聞き返してみました。
するとこんな返答になりました。

まさかの対話型AIから、謝罪の言葉が。
こんなAIの返答は初めてみました。
その後、クラスで話し合ったこととして、
「AIが作った文書そのままでは、自分の心が動いたところを表したものにはならない。」
「AIの使った表現をヒントにしたり、似た言葉を使ったりして
本当に自分が言いたいことを表すのは良い。」
ということになりました。
「では、学んだことを生かして自分の文章を見直してみよう!」と促し、子供達は、AIからもらったヒントをもとにブラッシュアップさせていきました。
その中で
「AIよりいい文章を作る!!」
「AIの表現もヒントにしてよりよくする!!」
と意気込んでいた姿が印象的でした。
最後には自分が書いた文章を友達と読み合い、感想を伝えながら交流していきました。
授業を終えて、対話型AIの返答を鵜呑みにせず、自分のスキルアップに役立てる子供達の姿に、未来のAIとの付き合い方のヒントを感じました。
毎回、AIを登場させるわけにはいきませんが、効果的だと思われる場面を選び、今後も活用していきたいと思いました。
ご一読いただき、ありがとうございました🍎
ぜひぜひ、Twitterにも遊びにきてください🍏
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
