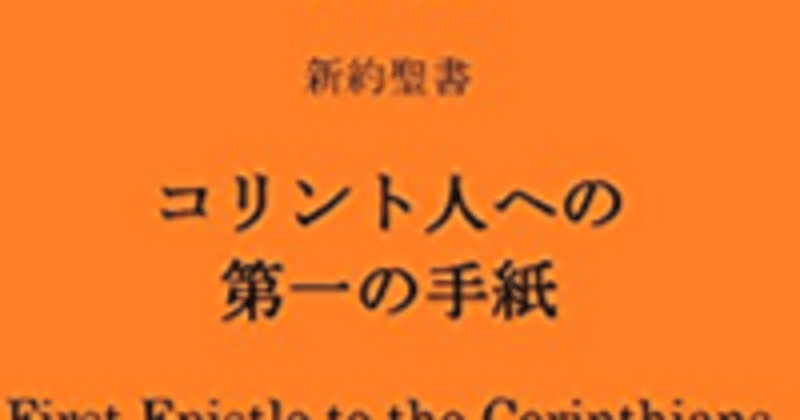
無報酬の香り
―― では、わたしの報酬とは何でしょうか。それは、福音を告げ知らせるときにそれを無報酬で伝え、福音を伝えるわたしが当然持っている権利を用いないということです。 ――
アメリカ大陸にあって暮らしていた、思春期の頃の出来事だった。
ある年老いた牧師を乗せた小さな車を運転して、草深い山奥の田舎町まで出かけたことがあった。
いったいなんの用事のために、運転免許を取ったばかりの年端もいかない若者が半日以上もハンドルを握りしめたのか、ほとんど覚えていない。
しかし、その経験は今なお、私のためには忘れらない出来事となっている。
――老いたる牧師は、少年たる私に向かって、こう言った。
「どうだい。なんとも美しい景色、素晴らしき「神の恵み」じゃないかーー?」
その時、老牧師と私の瞳の中にあっては、同大陸においても有名な、雄大にして崇高とも形容すべき某山脈がその頂の冠雪を夕間暮れの斜陽にさらされて、飴色に染め抜かれていた。
しかし私は、ほとんど本能的に、私の隣に立ったその者に強い反感を覚えた。私が、というよりも、私の中の”霊”が、と言った方が適当である。
それゆえに、私はこう答えたのだった。
「私の故郷には、これよりももっとずっと美しい山々があり、はるかに佳美しき河川と湖と海とがあります。だから今、こうして目にしている景色も、この大陸の風土も、小さな町の醸しだしている「香り」も、私には一抹の感動をば与えるものではありません――。」
まるで私ではない存在が、私の口唇を通して語ったようだった。
幼い頃から、学校においても塾においても、英語を学ぶことが嫌で嫌でならなかった少年が、それからわずか数年を経て、自ら陶酔するほどの発音と、今でも忘れられないほど見事な文体をした――すなわち「完璧な異言(と威厳)」をもって、上のような言葉を口にした時、――心底驚愕したような表情の中にも、確かな嫌悪感と怒気のこもった反感を、つがいの碧眼に同居させた老牧師のまなざしを、私は今でも大変愉快な気持ちで思い出すことがある。
さながら、神に祝福されたような気持ちとでも表現してさしつかえないだろうか。
あるいは、偽善者の偽善を言い当てたような、バカのバカさ加減を一刀両断したような、
あるいはまた、積年の本懐をついに遂げたような、
そんな、げに清々しい気分だった。
だから私は、あえて言うならば、あのとき私の唇を通して語った存在が神であったとしても、仮に神でなかったとしても、別にどうだっていい。
その時、少年たる私の心が揺るぎなく確信したこととは、
教会とか、牧師とか、レビ人とか、クリスチャンとか、――こういった類の世界とは、おおよそかくも軽蔑すべきシロモノでしかないという、その確信に今もいささかの変化もないのだから…。
「牧師業」をリタイアしたら、壮麗なる連山をのぞむ、静けき湖畔のほとりの家をあてがわれて、ゆったりとした余生を過ごす――
別にやればいい。
好きにすればいい。
いつもいつも言っていることだが、「どうぞご勝手に」――。
それが「神の恵み」であるというのならば、どうかそれが永遠に続きますように。それが素晴らしき晩節であり、人も羨む「クリスチャンライフ」の結果であり、今の今までの「伝道の報酬」であるというのならば、どうかどうか永遠なれ――ハレルヤ、ハレルヤ…!
しかししかし、
「牧師業」をリタイアした暁に、壮麗なる連山をのぞむ、静けき湖畔のほとりの家をあてがわれて、ゆったりとした余生を過ごす――
私にとっては、そのようなウルワシキ「余生」よりも何よりも、
妻帯もせず、福音の伝道も「無報酬で行った」という、使徒パウロの生き様の方が、ずっとずっとずっと、賞賛すべき、記憶すべき、倣うべき「クリスチャンライフ」であることを、知っている。
偏屈で、頑固で、愚かと言えば愚かだった、愚直といえば愚直すぎたパウロとかいう、変わり者のクリスチャンの死に様の方が、その大陸でももっとも美しいとうたわれる山麓の、まるで小さな碧海のような湖のほとりに約束された、「神の恵みたる老後」なんぞよりも、ずっとずっとずっと、「ハレルヤ」であることを、知っている。
『歴代誌』なんかを読んでいると、各時代の「王」についての記述の最初の一文が、「主の目に適っていたか否か」を書き分けている事実に行き当たるが、これはまことに示唆に富んでいる。
一国の王であれ何であれ、わずか数十年の話でしかない「人の一生」が、「主の目に適っていたか否か」――という「ものさし」によって、次々にダイジェストされていく様子を読み進めるとき、「最後の審判」などという言葉で信じられている「この世の終わり」においても、人の子たちはきっとこんなふうに「分けられて」いくのだろうと、想像せられるのである。
それゆえに、
そんな歴代誌になぞらえて、アメリカ大陸にあって暮らした我が思春期を「ダイジェスト」するとしたならば、私は私が教会へ行ったのは「主の目に適っていない教会」とはどんなものかを、この身をもって、知るためだった――、当代において牧師や神父やといった名をもって知られる「レビ人」や「クリスチャン」なる存在が、いかに堕落した者たちであったかを、この身をもって、知るためだった――、ついでに言えば、後年になってユダヤ民族や、ヘブライ語や、イスラエルの祭りなんかについて学んだことは、そんな場所ではない場所にあってこそ、「わたしの神」と邂逅した最初の頃のことを思い起こす(神に立ち帰る)ためであったと、――そのように確信しているのである。
あくまで個人的な話にすぎないが、私が「わたしの神」であるところの「キリストたるイエス」に出会ったのは、教会の礼拝堂の中なんかではなかった。「憐れみ深い父なる神」を知ったのも、聖書の中でもなく、レビ人たちのする話の中でもなく、クリスチャンとの交わりの中でもなく、ユダヤの伝統や祭りの中でもなかった。
『アダムとイエス』という文章の中でも書いたことだが、あくまでも私の場合は、イエス・キリストにも、父なる神にも、「わたし」という”霊”が出会ったのであり、そんな「わたし」とか”霊”とかいうものとは、国や民族や…といった「上乗せ」のなくなった、「裸の人間」のことだった。
それゆえに、そのような「わたし」にしてみれば、「ユダヤ人ごっこ」に熱を上げるなんて、ひっきょうマトハズレなアプローチにすぎないし、遠藤周作なんかのこだわった「日本人とキリスト教」というような議論自体、不毛かつ無駄かつ蒙昧かつトンチンカンでしかない。
こういう人々は、
―― 主なる神は土のちりで人を造り、命の息をその鼻に吹きいれられた。そこで人は生きた者となった。――
という聖書の言葉がろくすっぽ分かっていないのだろう。
それ以上に、
―― 「最初の人アダムは命のある生き物となった」と書いてあるが、最後のアダムは命を与える霊となった。 ――
とか、
―― 神の霊以外に神のことを知る者はいない。 ――
とかいう、もっとも大切な言葉についても、まるで分かっていないのだろう。
分かっていないから、「ユダヤ」とか「西欧」とか「日本」とか、そういう「上っ面」の話ばかりをしたがるのである。
分かっていないから、「教会」とかいう共同体の中にあって、バプテスマなんかを授ければ、それが立派な「伝道」であるものと、カンチガイしているのである。
分かっていないから、学校で「聖書のお勉強」を修了すれば「召し」を受けたものと思い込み、口先だけの「お説教」を垂れ流せば、当然のごとく「献金」を「投げ銭」してもらえるものと信じ込んで、生活の資を得ているのである。
分かっていないから、そんな「投げ銭」によって、山麓の湖畔のほとりにあてがわれた「老後」なんぞを、「神の恵み」とのたまって、恥もはばかりも知らないのである。
―― では、わたしの報酬とは何でしょうか。それは、福音を告げ知らせるときにそれを無報酬で伝え、福音を伝えるわたしが当然持っている権利を用いないということです。 ――
とかくに偏屈だったパウロの言ったこの言葉は、「教会」で「投げ銭」してもらって生きている(有報酬にて伝道している)すべての「牧師」や「神父」らにとってみれば、あるいは「死から死に至らせる香り」のようであるかもしれない。
がしかし、あくまでも個人的な、あまりに個人的な事情にすぎないが、この同じ言葉は、私にとってはまさに「命から命に至らせる香り」にほかならない。
理屈っぽくて、文章下手で、偏屈で、頑固で…私にとってはそんな人物像しか連想させないような存在であったとしても、「無報酬で伝道した」パウロというキリストの使徒がこの地上にあって立派に生きてくれた事実こそが、「神の恵み」だからである。
だから私は、『ローマ書所感』という文章の中でも書いたのである。「投げ銭」してもらって生きている「レビ人」なんかよりもずっと「何らかの報酬」を得る資格がある者と、私は私について確信している、と。そして、揺るぎなき自信を持ってそう確信してはいるが、「人からの投げ銭なんか、一切興味がない。それくらいなら死んだ方がマシである」、と。
もう一度くり返すが、
私はいかなる神学校の机の上で学んだこともなければ、ついぞ聖書という書物についてもマトモに勉強したこともない。それでも、どうして、どうして、そうでありながらも、巷をウロウロしている教会の牧師や神父といった連中なんぞよりも、私は私について「何らかの報酬を得る資格がある者」と、確信している。
もしもそれに反発を覚える人に対して、何か答えるとするならば、
ではたとえば、
モーセが葬られたのは「永遠の命」という「真の約束の地」であると、私以外の誰が言っただろうか?
モーセを葬ったのはほかでもない「イエス」であると、私以外の誰が書いただろうか?
また、「永遠の命」とは、「わたしの神」と「顔と顔を合わせて語り合う」ことだと、私以外の誰が言い表しただろうか?
だからこそ、「真の約束の地」とは、「荒野の旅」の中にこそあったのであって、「ヨルダンの向こう側」のことではなかったのだと、私以外の誰が、ハッキリと書き得たのだろうか?
(もし反発する人の中で、似たような主張をご存知の方がいたら、ぜひ教えてください。)
少なくとも、私は私以外の人間から、こんな「当たり前と言えば当たり前」な話をば、聞いたことがない。
まだ16,7歳の、幼き子どもだった頃に自らの意思で教会を訪ね、聖書の表紙を開くようになってからというもの、有名無名、老若男女、人種国籍を問わず、実に多種多様な「クリスチャンたち」に出会って来たが、――ただの一人として、たとえば「モーセの葬られた場所」を正確に口にすることのできる人間に、邂逅したことはない。
あれから、静けき湖畔の家で「幸せなる老後」を過ごしたことであろう、かの牧師様のひび割れた唇の奥の、丈夫な白い歯のすき間からも、私は聞いたことはない――
「モーセの葬られた場所」よりも大切な、「イエスはキリストである」という真理も、「憐れみ深き父なる神」という名前も、
いっさい、いっさい、いっさい、聞いたことがないのである。
聞いたことはないが、その「生き様」を通して、「言葉」以上に雄弁に語る「声」をば、ハッキリと耳にしたことはある。
「牧師業」をリタイアしたワシは、これから壮麗なる連山をのぞむ、静けき湖畔のほとりの家をあてがわれて、ゆったりとした余生を過ごすのだ――
それがこれまでのワシの「伝道の報酬」であり、そしてまた、ワシの「約束の地」なのだ――
そんな、浅ましくも汚らわしい、「死から死に至らしめる」ような、「肉の声」を。
だからあの時、私の中の”霊”は、私の口唇にあやかって語ったのである。
「私の故郷には、もっと美しい山々があり…」、と。
私の中の”霊”と、同じ”霊”を受けている人々には、自明のことだろうが、蛇足として書き加えておく。
「私の故郷」とは、「日本国」のことではなく、愛すべき日本の風土や山川草木のことなんかでもない。
「私の故郷」とは、「モーセが葬られた場所であり」、「極めて良い神の国」のことである。
―― では、わたしの報酬とは何でしょうか。それは、福音を告げ知らせるときにそれを無報酬で伝え、福音を伝えるわたしが当然持っている権利を用いないということです。 ――
たとえば、パウロによるこんな言葉を耳目にする度ごとに、
そんな「真の約束の地」や、「永遠の命」や、「極めて良い神の国」がただよわせる、うるわしき「香り」をば、胸いっぱいに吸い込むのである。
――そんな人間は私だけだろうか?
むろん、そんなはずはない。
私はそう信じているから、いかなる教会にも属することなく、いかなる神学校や宣教学校においても学ぶことなく、いかなる「アーメンごっこ」も「ユダヤ人ごっこ」も「聖書ごっこ」もなぞらえることなく、このような文章を「無報酬で」書き続けているのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
