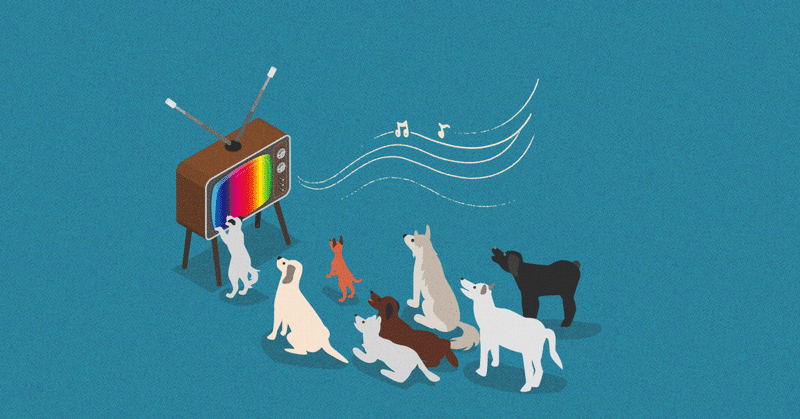
第33回:シュガーレスガム全米売上No1.に貢献したCM徹底解析!
さて、前回一本のテレビコマーシャルが弱小ガムメーカーを売上ナンバーワンに導いたCMをご紹介しました。
何気ない1分間CMですが、これは「感覚」で創られたものではなく、心理学を駆使し、音楽理論を総動員して科学者が監修をし、計算づくで制作された極めて戦略的なCMです。
(これのどこがどう科学なのよ・・
という肝心要のところを本日ご説明いたしましょう。
♪ララララ・・・♪ソソソソ・・・

♪ファファファファ・・
科学的実証:下降のメロディは時を遡ることをヒトに想起させますので、これにより父と娘の思い出へと視聴者を導きます。実際に、下降する音型を聞かせるとヒトは後進したり、下に下がったり、過去に戻ったりすることを感じるという実験データがあります。

視聴者の注意喚起=BGM効果:気が付きましたか?音量が絞られました。お嬢さんのお誕生日会の楽しく華やかな画像のイメージに視聴者の注意喚起をするため、あえて音量を絞ります。お誕生日に音量を絞っているのは、音がいらないから、ではなくお誕生日の方を目立たせたいから。音を急に静かにすることで、視聴者の注意を映像にもっていくことができます。

またまた科学的実証:ビートが加わり、楽器層が増えテンポや音量も上がることで、お嬢さんの成長を視聴者が自然に感じる事ができます。打楽器が加わったり、楽器層が深まり、低音のサウンドが入ってくるとエキサイティングな気持ちが助長されるという実験データがあります。


時が流れお嬢さんが親元を離れる日、物語のクライマックスを映像が見せると同時に曲調も最高に盛り上がります。

効果音:気づきましたか?折り鶴が箱から落ちるときに効果音としてトライアングルの音が入っており、視聴者の注意をひきます。


唯一のナレーションとプライミング効果:「Sometimes little things, last the longest(何気ないものがずっと続く)」のナレーションは、大きな贈り物ではないが、父がガムを食べるたびに折ってあげた折り鶴をすべて大切に保管していた娘の思いとつながります。また、「Last Longest=長く続く」イメージは、父娘の愛情を通じ喚起された視聴者の感情により、記憶に刻み込まれます。そして、お客様がお店で実際に商品を見たときに、これがプライミングとなり、「ガムの味が長く続く」という感覚を呼び起こし、商品を手に取る効果へと導かれます。
企業理念の発信とオーラル戦略
また、「チューインガム」という人生を揺るがすような壮大な何かではなく、いわば「日常の小さな幸せ」であるお菓子はSometimes little thingsに過ぎないかもしれませんが、「どうでも良いような、小さなことかもしれませんけれど、あなたの人生に寄り添っていますよ。」という企業のメッセージがソニック・アンセムとして発信されています。当初は「Just little things」というコピーでしたが、企業のキャッチコピーの最初の音に破裂音や濁音を入れない方が心理的にスムーズに視聴者が受け入れることができますので、最終的にJustをなくし、”Sometimes little things”がキャッチコピーとなりました。

まとめ
筆者はいつも感じているのですが、日本のCMは「大音量で製品名や値引き率を連呼する選挙カー方式」か、「この冷蔵庫の何段目は野菜室です、の説明方式」に終始しており、ブランドに対するヒトの心の共感や同調、即ちロイヤリティを生んでいないケースが多いと思うのです。今回のガムのCMが音楽的・心理的効果を科学的に構築した上で制作されたことは上記の通りですがその他にも大切なポイントがあります。
・最初からがなりたてるような、感情を高ぶらせる音楽やナレーションを使わない。大音量でパワフルな音楽や音声が始終続くようなCMは一時的に売るためだけの目的は果たすかもしれないが、永続的なお客様のエンゲージメントは生まない
・ヒトの心にポジティブな印象を与えるシンプルな音楽やリズムを用いる
・企業名をすぐには出さない
・セリフは最後の商品のナレーションのみ。音楽の途中に人の声で企業名を入れると「異質物」と認識されるため、基本的には入れない方が良い。
・メッセージ発信=「ExtraガムでExtra(特別)な思い出を」
さて、このCMで弱小ガムメーカーであったエクストラガム社はトライデント社を抜き、チューインガム市場全米ナンバーワンの売上高となりました。

「音声コンテンツを科学的・総合的・戦略的に構築する」とこのような効果を得る事ができるのです。
企業にはTVコマーシャルだけでなく、YouTube、ラジオ、ポッドキャスト、タクシーの動画広告、街頭の大型ビジョン広告、キャンペーンや商品発表、店舗のサウンド、ソニック・ロゴ、お客様相談室の保留音など、数えればきりがないほど消費者との「音のタッチポイント」があります。これらすべてを「科学的・総合的・戦略的に構築する」にはどうしたら良いのでしょうか?「科学に基づいて音声コンテンツをリリース」していますか?
次回、「どうして音のブランディングガイドラインがないの?」と題してちょっとした疑問を呈してみようと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
