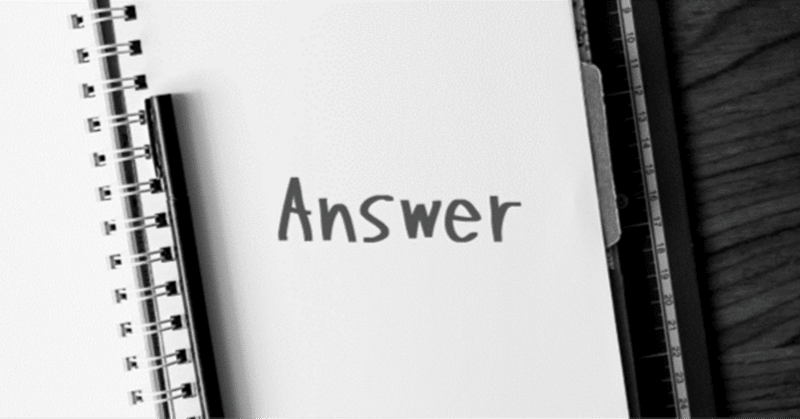
Answer「後日談」
「p0」「p1」「p2」「p3」「p4」「p5」
「p6」「p7」「p8」「p9」「p10」
2023年10月14日。
月曜の早朝から取材旅行に同行することになったはるかは、その日の午後から思わぬ休暇が舞い込んだ。ちょうど美咲も戻ってくるということで、夕方から萌の家に向かうことになった。
(大丈夫だろうか)
予告通り美咲は、仕事から戻ったその足で「お土産を届ける」という名目で萌の自宅に押し掛ける算段だったらしい。
なにかやらかすのではないかとハラハラしていたが「下の子がぐずって仕方がない」と幼子を胸に抱き、足元には眠そうな上の子がへばりついた状態で姿を現した萌が気の毒になり玄関先で話をするだけに留まった。
「――ちゃん、お邪魔しちゃダメよ~。ばーばのとこいらっしゃ~い」
猫なで声で上の子を呼ぶ姑の声が部屋の奥から聞こえてくる。なんとなく美咲と目を合わせると、こちらも「長居は無用」と悟ったようだ。
「梶先輩いないの? てか、在宅じゃなかった?」
「そうなんだけど、たまに気晴らしって言って出掛けるんだ」
「へえ」
「――萌さん。あがっていただいたら」
先ほどとは打って変わり、明らかに機嫌が悪いであろう姑の声に、萌の顔色がかげる。そこをすかさず、
「あぁおかまいなく~。忙しい時間に申し訳ございませーん」
学芸会の素人演劇よろしく、棒読みで美咲が返す。
「ごめんね、萌。美咲がどうしてもっていうから」
とはいうもののはるか自身、気がかりではあった。
「また改めて寄せてもらうね」
お姑さんがいないときに…という言葉を飲み込み、だが果たしてそんな日が訪れるのだろうかと苦笑いを隠せない。
そんな帰り道、タイミングよく「気晴らし」から戻った梶先輩と遭遇した。
「ホントに帰ってきたんだな~」
美咲の帰国を珍しがった梶先輩は、あろうことか「お茶でもどうか」と家とは逆方向を指す。
「え~あたしたち、萌に会いに来たのにぃ…時間が時間なんで玄関先で失礼しましたよ。もっと早く帰ってきてくれたらよかったのに」
遠慮のない美咲の言葉に「相変わらずだな」と笑う梶先輩ではあったが、さすがにバツが悪そうに素直に踵を返す。そんな先輩の背中も、幾分疲れをしょっていた。
「先輩。お義母さまと同居なさったんですか?」
すかさず直球を投げつける。
「あぁ…いや、そういうわけじゃなくて。手伝いに来てもらってるんだ」
「手伝い…ねぇ」
「下の子が意外と手がかかってな」
意外に父親らしい顔を見せるものだ…と、しかしこの時間の「気晴らし」を考えると、実益を兼ねるとは言い難い。
「あぁさっきもぐずってましたね」
「だろ。おまえらも子どもが出来りゃ…ぁ。わりい」
「構いませんよ。確かに萌、疲れてましたもん。先輩、自分ばっかり気晴らししてないで、萌と一緒に出掛ければいいのに」
「ちょっと美咲」
「なーに言ってんだよ、オレは仕事。だからおふくろがいるんじゃないか」
「実の母親でもないのにそう易々と『お手伝い』なんて頼めませんよ。かえって仕事増えてるんじゃないですかー? あのやつれよう」
「そうか?」
「とにかく梶先輩。来月の会合にはふたりで来てくださいよ。わたしたちも行きますから」
「あぁ。そうだな、行くよ」
「それまでにあの疲れた顔、なんとかしてあげてくださいネ。あのままだと梶先輩、ななみ先輩たちにいじられますよ」
ななみ先輩は、梶先輩の同窓であり唯一頭の上がらない相手だった。
「あぁそうするよ」
「なに今の。ななみ先輩と連絡取ってんの? てか、くるの?」
会合の日時は回ってきたが、だれが出席するかまでは開示されていない。
「あれくらい言ってやれば、自分がなにを見て、なにを見てなかったのかわかるでしょうよ」
(なるほど)
援護射撃。
だが意外と、これがうまいこと梶先輩の胸に刺さったようだった。
2023年11月4日。
テニスサークル会合当日、はるかは美咲とふたり、少し遅れて会場に到着した。というのも、美咲曰く「主賓は遅れて登場する」という、社会人としてはどうかと思われる信念のもと、待ち合わせからやきもきさせられていた。
いつものこととはいえ、本音は出席を辞退したいはるかにとって、まぁ複雑な心境であることには変わりなかった。まして会合のあと「会わないか」と言ってきたタクミが、会場にやってこないとも限らないのだ。
ざわざわ・・・・
がやがや・・・・
意外に人数の多いことに驚くとともに、タクミの姿がないことにほっとするはるか。
「カナタ・クミ先生はいらっしゃらないようね」
わざとかしこまった言い方をする美咲に「いい加減にして」とクギを刺す。
タクミからのDMのことは、もちろん言ってはいない。
「ぁ、いた。萌~」
視線の先に手を振るはるかは、とにかく美咲の意識からタクミを切り離したかった。
美咲の予告通り、梶先輩はしっかりとななみ先輩に捕まっていた。
「よし!」
妙な合図とともに、
「出てこれたんだね、よかった」
そう言って萌の腕を掴み、今まさにタジタジ…という梶先輩のもとへ向かった。
「美咲?」
まずは食事させてよ…と言いたいのを我慢してついて行くはるか。
ひとしきり挨拶と感動?のハグを交わしたのち、
「でもよかったね~萌、話の解るお義母さまがいてくれて。これで仕事にも戻れるんじゃない? 惜しまれて辞めたんだもんね、会社のひとたちも首を長くして待ってるよ~」
美咲は、興奮した様子で意気揚々と話し始めた。
「え、萌復職するの?」
はるかにとっても初耳で「いつのまに」と目を丸くするも、当の発言者である美咲のいたずらなwinkに戸惑う。
「いいじゃない、萌。やりたいことがあるならどんどん外に出なー」
なにも知らないななみ先輩も賛同して、萌の肩を叩く。
「おいおい、そそのかさないでくれよ~」
梶先輩においては冗談に聞こえるらしい。
「先輩のお義母さまも、こ~んな友だちもいない土地で、子育てのお手伝い?…しにきてくださるだなんてそうそうできないですよね~」
梶先輩の田舎はどちらだったか…尊敬するわぁと、白々しく持ち上げる美咲の意図が解らない。
「あたしだったら息がつまっちゃう。あ、つまっちゃったから離婚したんでしたー」
(え、自虐?)
あはははは…と漫画の吹き出しのような笑いをのせ、ところどころおかしな強弱をつけて話を続ける美咲。
「おまえは辛抱がたりないんだろー」
はるかと美咲がやってきたことで気が大きくなった梶先輩は、途端に饒舌になった。
「やーだ、先輩。わたしだって努力しましたよ~。苦手な料理も必死に。向こうはホームパーティーが最低週一でやってきますから、必死でアテンドしました。でもね、いくらあたしでも仕事してるだけですべてを担ってるつもりの旦那さましか知り合いがいないんじゃ、耐えられませんよ~」
隣のななみ先輩に「がんばったね~」なんて言われている美咲は、涙も出ていない目頭を押さえる。
「なんだよ、それだけで戻ってきたのか?」
「そんなわけないじゃないですか。話し相手どころか、言葉の通じない場所じゃ、先輩みたいに気晴らしもできないんですよ。買い物だって一苦労。一番困ったのは歯医者と美容院。チリチリにされたときには丸坊主にしてやろうかと思いました」
「だっておまえ、好きでついて行ったんだろうが」
「えぇだから! 努力したんですってば~。でも、たったひとりで言葉やら環境やらを克服するにはキャパオーバーで。家の周り散歩するのがせいぜいでしたよ。気が狂う寸前で」
「おまえはいちいち大げさなんだよ」
「そうですか? その点先輩のお義母さまは、田舎から出てきて友だちがいなくても、とりあえず言葉は通じるし、子どもが病気になってもすぐ対応できるからいいですね」
だんだんと美咲の言葉に棘が生えてきた。
「いや、お袋は方向音痴で、この辺の交通機関はひとりじゃ無理だよ」
「じゃぁ早く慣れてもらわないとですね! 保育園とか、かかりつけのお医者さまとか、これから予防接種とかめんどくさいイベント盛りだくさんですもん。ぜ~んぶやって下さるんでしょう。すごいわぁ」
「バカだな、それは母親の仕事だろ」
「え。先輩はなにもしないんですか」
「そうだ、梶。あんた、父親として機能してんのー」
うまいこととななみ先輩ものっかってくれたようだ。
そこでようやっとはるかは、美咲の目的を悟った。
(さらし首…)
「いや、オレだって」
「ですよね~。お義母さまがいるからって甘えてばかりもねぇ。萌だって仕事始めたら家事も今まで通りにはいかないし」
「萌は仕事はしないよ。する気もないだろ今さら」
ここでようやっと、萌に発言権が与えられた。
「あ。ぅぅん。今のままお義母さまがいてくださるなら、そろそろ…とは思ってるよ」
「だって、生まれたばかりだぞ。この先、お袋に任せっきりにする気かよ」
「ふふ…。任せたつもりは、なかったんですけどね」
遠慮がちに、小さく萌が答えると、
「あらあら。なんだか夫婦で食い違ってるみたいね」
ななみ先輩が前傾姿勢で食いついてきた。
「いや…そろそろおふくろにも、帰ってもらおうとは思ってるよ。でも、」
「え~そうなんですかぁ? てっきり萌に仕事させてくださるために同居なさるのかと思ってました」
「だから同居なんて。でもその方が女は楽だろ」
「そんなもんですかね」
「いや、それは聞き捨てならないな」
(あ、ななみ先輩スイッチ入った)
「いや、だって。おふくろにだって孫の世話する楽しみがあるだろうが」
「楽しみ?」
そこで美咲の眼光が鋭くなった。
「楽しみだけで子育てに係れるなら、わたしがベビーシッターしてもいいんですよ、センパイ」
それまでの明るい声とは違い、若干のトーンダウンからの上目遣い。
(これはヤバイかも)
「もう、美咲…ってば」
「おまえ子どももいないくせに、そんなえらそうなこと…!」
「えぇ解らないわね。子どもの夜泣きだの、突然の発熱だの、はじめて笑った、歩いた、喋った…そういう楽しみや苦労? 出来れば経験したかったけど、家にいるより職場が落ち着くと言われてしまったあたしは、ホームパーティーのためのかりそめの主婦ですよ。亭主元気で留守がいいなんて時代もあったかもしれないけど、それは裕福な時代を経験した人たちの絵空事。今どき共働きでもなきゃ、子どもに充分な将来を用意してあげることなんてできないんですよ。でも先輩はぁ、先輩ひとりの稼ぎで、家の中になにもしない女をふたり囲って、充分な暮らしができるとおっしゃってるんですよね?」
だんだんと語尾に力が入る美咲の声に反比例するかのように、まわりのざわめきが静寂に飲まれていった。
「ちょっと、美咲」
さすがにそれは言い過ぎじゃ?
「あら、ごめんなさい。つい興奮してしまったわ」
「他人の家のことに首突っ込むなよ」
だが、既に不機嫌極まりない梶先輩は無意識に萌を見据えた。萌もすっかり委縮してしまっている。
「ま、いろいろと誤解があるようだな」
うまいことななみ先輩がフォローしてくれた。しかし、
「そうだよ。おまえ、酔ってるのか?」
梶先輩は負けず嫌いだった。
「飲んでません!」
「空気壊すなよ」
「すみません、つい。――でもね梶先輩。お義母さまの楽しみっていうけど、そりゃ孫の面倒見るのは楽しいでしょうよ。最初は萌の負担を考えてのことだったかもしれない。でもお義母さまが孫と楽しんでいる間、実の母親である萌はなにをすればいいんですか? ただ家事をこなして、お義母さまの楽しみを見守ればいいの? 本来なら自分がするはずの子どもの世話を横目に『やってもらってLUCKY』って寝てればいいの?」
「いい加減にしろよ!」
「だったら、せめて仕事させてやっても罰は当たらないんじゃないですか!」
「それとこれとは…」
「ごめんね萌。あたしてっきり、大学時代あ~んなに大事にされたうえにそのままゴールインしてたから、もっと大事にされてると思って皮肉のひとつも言ってやろうと思ってここに来たの。でも大事されてる意味がこれじゃぁ、離婚して惨めなはずのあたしの方がしあわせに見えるじゃない」
そう言って美咲は一粒の涙を流して見せた。
パチパチ…
パチパチパチパチ・・・・
「え?」
そんな美咲の啖呵に対し、まわりの女性陣の拍手が沸き起こった。
「な、なんだよ…」
「梶。あんたに勝ち目はないみたいね」
ななみ先輩のひとことで、ひとまずその場は終息した。
「ごめん、萌。自分のこと棚に上げて」
そんな時でも美咲は、自分を卑下した言い方をする。
「ぅぅん、美咲。ありがとう、あたしも頑張るよ」
「ふふ――あ~お腹減ったー」
「美咲、子ども欲しかったの?」
「ぜんぜん。なんで? あたしが子ども嫌いなの知ってるじゃん」
確かにそう聞いていた。
「じゃぁなんで」
「そのままのことよ。赤ん坊の鼻水もよだれもヤだけど、母親になるってことはそれを汚いと感じないくらいバカになれるってことでしょ」
「バカって、美咲…」
「あぁ言葉の綾。そういう積み重ねがあっての夫婦だったり家族なわけでしょ? それが楽しかったりするんじゃないの?――ババぁは時々、スパイス程度に睨み利かせてたらそれだけで威厳があるってもんじゃない? わかんないけど」
「肉団子頬張りながらいうこと?」
「うん、これ美味しい。だからさ、そういうの。あたしには全っ然っわかんないけど、萌には愚痴聞かされても『結局それがしあわせなんでしょー』って言ってやりたいじゃない? 笑ってて欲しいじゃない」
「うん」
「結婚や出産だけがしあわせじゃないけど、さ。鼻水もよだれも喜びに変えられる、そういう子でしょ萌は」
「だから言い方…」
「そういう子でしょ、萌は」
「なんでもう一回」
でもまぁ、言いたいことは理解できる。とどのつまりは美咲も、梶先輩やお姑さんの対応が「悔しかった」ということだ。
「これでなにか変わるといいね」
「変わらなきゃ何度でも言うわよ」
「それはやめな」
「ねぇはるか。今そっちで聞いたんだけど、」
「ん? どうした、萌」
「タクミが乗ったタクシーが、こっちに向かってる途中事故…にあったらしくて」
「え?」
「ちょっと、はるか。連絡してみなさいよ」
「連絡って…あたし番号知らないよ」
「あ、多分知ってる」
そういうと萌は、梶先輩のところに向かった。
「来るつもりだったんだね」
「そう、だね」
まだ、このあと会うかどうかも決めかねるはるかに一抹の不安が走った。
「これ、番号」
よりによって、紙ナプキンにかかれた数字に見覚えがあった。
「掛けてみれば?」
美咲が急かす。
「え、だって。出ないかもしれないじゃん」
「あ、でもね」
「だったら、行けば? 死んじゃうかもよ、漫画みたいに」
「ちょっと、美咲。怖いこと言わないでよ」
心がざわついた。バッグを取り上げ、駈け出さずにはいられなかった。
「さ~て、こっちはどうなる?」
「美咲、楽しんでるでしょ」
「悪い? はるかは一度ぶつからないとダメなのよ」
「かもしれないけど」
「ホントに死んじゃったらこの先立ち直れないよ」
「そうだけど。でも、事故に遭ったのはタクミじゃないよ」
「え?」
「事故渋滞にあって――途中で車下りたんだって」
「はぁ? そういうことは早く言いなさいよ」
「そう言ったよ」
「どうすんの、はるか。出て行っちゃ…ま、いいか。飲も飲も」
《 了 》
まだまだ未熟者ですが、夢に向かって邁進します
