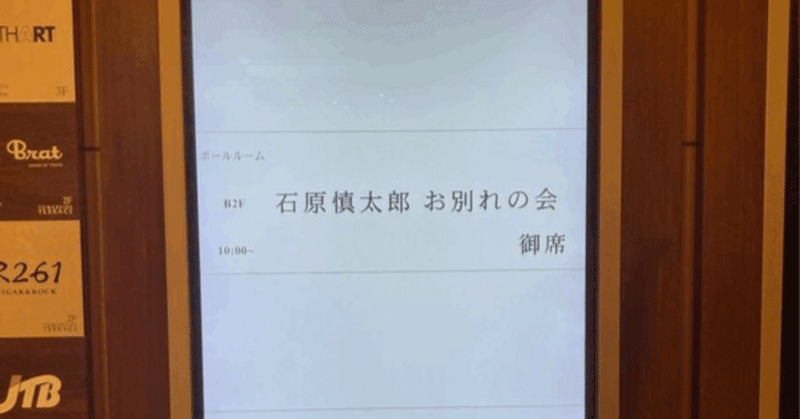
石原慎太郎『生還』の書評
ヘルシンキの図書館には、ぼくが知る限り、石原慎太郎の本は一冊しかない。その本は今、ぼくの手元にある。
この本を近所の図書館に取り寄せるとき、ヘルシンキの図書館システムはもちろん日本語に対応していないので、『Shintaro ISHIHARA, SEIKAN』とだけ記されていた。手に取ってみて、『生還』という日本語をはじめて眺めた。なるほど、『星間』でも『精悍』でもなく、『生還』か。表紙の挿絵も、なんだか神秘的だ。
このように、ぼくとこの本の出会いは、非常にロマンチックだった。ロマンチックな出会いによって、本の内容までいいものだと思えることは、よくある。そういう話だと思って聞いてほしい。
この小説では、主人公の男が末期がんの診断を受ける。大学病院からは手術もできないと言われ、余命はおよそ一ヶ月。この小説が書かれたのは八十年代のはずで、当時はがんを本人に宣告することはタブーだとされていた。しかしこの主人公の中年男は、家業の製薬会社を継いで社長になっていることもあり、自身の病状を知ることとなる。会社に出入りしている、動物を専門とする医者に相談する。この男から、病院での治療をやめて、コハク酸を飲み、一人で孤独に病気と向き合うことを提案される。いわゆる民間治療で、あえて怪しく描かれているようにも読める。
主人公は、「自分は死んだものと考えるように」と言い残し、妻と子供と別れる。死んだように生き、三度訪れるとてつもない下痢を経て、四年後のある朝、男は勃起する。がんは消えている。
主人公が暮らしているアパートは、海の近くにある。時折このアパートから、男は海を眺め下ろす。この辺りの描写は、ボート乗りで海を愛し、海と生きた男、石原慎太郎ならではという感じがある。
物語の最後、家庭に戻った男は、動揺する妻を目撃する。村田喜代子の傑作小説『あなたと共に逝きましょう』の結末を、男の側から描いているのだと思った。いちど、夫の死を覚悟した女が、蘇った男と、どのように生きるのか。このテーマを若くして描いた、当時おそらく四十代後半の石原慎太郎は、やはり天才小説家だったと思う。
石原慎太郎のエッセイと短編をいくつか読んだ後に、『生還』を手に取って、やはり石原慎太郎は大いに誤解されている作家だと思った。いや、人間石原慎太郎としては、正しく理解されている、と言ってもいいのか。石原慎太郎は、正義とか、善とか悪には興味がない人だったろう。そんなもの、人間の生と死の前では、ちっぽけだということが直感的にわかっているような。
ベランダから見下ろす海で、一人の男が海に飛び込んで、ぶつかる波間に沈む場面がある。主人公の内面に落ち込んでいく描写が続く、読んでいても辛く先の見えない治療生活のなかで、引きのショットで遠くの誰かの、声なき死を眺めるシーン。ああいうシーンを差し込んでしまうのが、やっぱり天才だ。凡庸な言葉で説明すると、人間がいかに小さな存在か、海を愛した石原慎太郎は、よくわかっている、といったところか。
自分はインテリだと自覚しつつも、オカルトや宗教など人智を超えた「偉大なもの」への畏怖がある。いや、畏怖というよりも興味だろうか。じっと観察し、決して冷笑しない。慎ちゃんはそんな人物だったのではないか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
