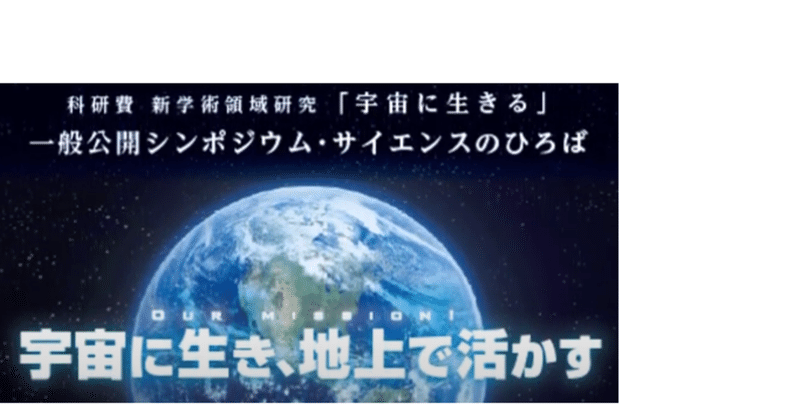
宇宙開発の救世主?最強生物クマムシ
以下はJAXAからのプレスリリースの一部。
新型コロナウイルスの影響で中止になった公開シンポジウム・サイエンスカフェの発表資料をせっかくなので、公開しようというもの。
古川聡 宇宙飛行士と研究者が「宇宙に生きる」という新たな研究領域を立ち上げ、5年間取り組んできた成果のようだ。
クマムシという生物を知っているだろうか。
あったかいイメージがあるかと思うが、そっちではない。
緩歩動物門(Tardigrada)に属する動物の総称で、
4対8本のずんぐりとした脚でゆっくり歩く姿から緩歩動物、また形がクマに似ていることからクマムシ(熊虫、Water bear)と呼ばれている方のクマムシだ。
Wikipediaより引用
もしかしたら、クマムシ博士の影響で知っている人もいるかもしれない。かくいう私もその1人だ。
クマムシは極限環境微生物の一種で、深海・高山・極地(南/北極)・放射線下といった極限環境でも生きていける生物だ。
以下、東京大学 理学系研究科 生物科学専攻 細胞生理化学研究室 クマムシ研究グループHPより引用
陸生クマムシの多くは乾燥耐性を持ち、周囲が乾燥すると脱水して縮まり乾眠と言われる状態になります。この状態では水含量は数%にまで低下しており、生命活動は見られません。驚いたことに死んだわけではなく、水を与えると速やかに活動状態に復帰します。
クマムシの示す耐性能力は、生息環境から考えると明らかに過剰であり、生き残るために必要だったとは考えられません。こうした過剰な耐性能力は、頻繁に乾燥する環境に住み、乾燥耐性を持つクマムシで観察されます。
乾燥に耐えるために獲得した様々な保護や修復のしくみが、副産物として過剰な耐性能力を生んだのかもしれません。
すごすぎる、、かっこいいクマムシ!
私たちヒトをはじめとした、いわゆる高等生物は、多細胞生物で、それぞれの細胞が分業していて、1つ1つ違う機能を持っている。
たとえば、
・胃の細胞⇒食物の消化
・腸の細胞⇒栄養物の吸収
・腎臓の細胞⇒排泄物のろ過
といった感じだ。
対して、その細胞1つだけで、そのまま1つの生物(単細胞生物)である微生物では、たった1つの細胞しかないため、すべての機能を1つの細胞が担うことになる。
すると、その分仕組みが単純になるため極限環境でも生きていくことができる。
(微生物の中でも構造が複雑なカビや酵母は、単純な構造の細菌類ほど、過酷な環境では生きられないらしい)
上記のような極限環境は、人間やその他の多くの生命が生きられない環境という意味での、"極限"だ。
だが、地球の外=宇宙に出てみると、その"極限"が当たり前の世界になる。
クマムシは極限が当たり前の宇宙でも生きていくことが出来る最強の生物なのだ。
冒頭のJAXAの発表資料によると、
クマムシ独自の放射線耐性遺伝子(DSup;Damage Suppressor)をヒトの培養細胞に取り入れると、放射線耐性が上がったことが分かったみたいだ。
元の論文はまだ読めていないが、スライドを見ると、培養たった12日で生き残る細胞数に100倍もの開きが出たようだ!
今後クマムシのDNA解析が進めば、人類の宇宙進出での放射線の課題も解決できるかもしれない。今後に期待だ!
※記事を書き終えてから、ナショジオでおもしろそうな別記事を見つけてしまった。笑
ノースカロライナ大学チャペルヒル校の生物学者ボブ・ゴールドスタインさん達によるゲノム解析の結果、
全く異なる複数の生物界に由来するDNAが含まれることが判明したそう!
クマムシの最強の特性は、もしかしたら外部からDNAを獲得して(外来DNA)、手に入れたのかもしれない。
<参考>
・Wikipedia 緩歩動物
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%A9%E6%AD%A9%E5%8B%95%E7%89%A9
・東京大学 理学系研究科 生物科学専攻 細胞生理化学研究室 クマムシ研究グループHP
http://www.bs.s.u-tokyo.ac.jp/~saibou/kuma/research/research.html
・ナショナルジオグラフィックHP
https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/20140415/393082/
https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/a/120100053/
・極限環境の生き物たち ~なぜそこに棲んでいるのか~ (知りたい!サイエンス) 大島泰朗
頂いたお金は幸せになるために使わせていただきます!😊😊Have a nice day!🍀
