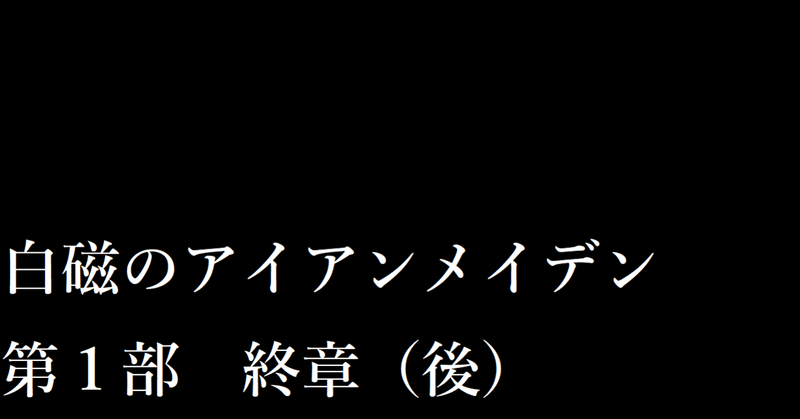
白磁のアイアンメイデン 第1部 終章(後) #白アメ
王都クストルより西へ数里、地図では「サッガの森」と呼ばれる大森林地帯。鬱蒼と茂る樹々のため、昼なお暗いこの森は、ハンク王国内でも屈指の危険地帯だと言われていた。
森の東西を貫くように走る街道以外は、人の手が一切入らぬ文字通りの人外魔境。亜人も、魔獣も、怪鳥も、見目麗しい花でさえも、この森にうかつに入り込んだ愚か者を捕えて自らの糧としようと、虎視眈々と目を光らせている……そのような場所である。街道を外れ森に足を踏み入れる者は、よほど腕に自身があるのか、人の世から弾き出されてしまったか、物狂いか……そのいずれかであった。
そんなサッガの森に、達人でも悪人でも狂人でもない声が響き渡る。
声の主は、年端もいかぬ少年であった。少年は、頭から血を流す老人を背後に庇うように立ち、手に持つ木の枝を剣のように振り回しながら、目の前の相手に向かって叫び続けていた。
「く……来るな! 僕に近寄るな! おじいちゃんは、お前らなんかには絶対に渡さないぞ!」
少年の必死の叫びを、彼の前に立ちふさがるオークたちは嘲りの笑いで受け止める。
「ぶはははははあ! あんま笑わすなよクソガキィ。そんなもん振り回して、一体どうしようっていうんだよぉ、ええ?」
一体のオークがそう言うと、周りのオークたちも唾を飛ばしながら嗤い、口汚く囃し立てた。彼らにとっては久方ぶりの獲物であり、“御馳走”であった。乏しい脳みそは嗜虐欲と支配欲、そして食欲であふれんばかりだった。
故に、一体のオークが背後から飛んできた光の矢に貫かれ絶命したときも、すぐには気づけなかったのである。
音もなく飛来する光の矢に三体目の仲間をやられたとき、ようやくオークの群れは事態を悟った。周囲に目を凝らし、嗅覚を駆使して、襲撃者の姿を捉えようとする。
敵の正体はすぐに知れた。オークたちは自分たちからそう離れていない場所に根を張る大樹の陰に、一人の人間が身を隠しているのに気づいた。幼い娘のようだった。自分の背丈よりも長い杖を両手で握りしめ、恐怖に震えている――ように見えた。
残ったオーク共は猛り狂い、女に襲いかかった。嗜虐欲と支配欲、食欲に性欲を満たすために。
うつむく少女が、にやりと笑う。オークどもには見えぬように。
「やっちゃえシャビイ!」
「う、うん!」
その瞬間、オークたちの足元から地面が消失した。
突然の事態に対応できず手足を無様にバタつかせながら、オークたちは次々と穴に飲み込まれていった。穴の底には、几帳面に敷き詰められた針山の罠が待っており、オークたちを次々に刺し貫いていった。
死んだオークの血の臭いと、死に損なったオークの怨みの声が、森に満ち始める。酸鼻極まる様相であった。
「やった! へーい!」「へ、へーい」
そんな状況を作り出した当の本人たちは、穴の縁で高く掲げた手を叩き合わせていた。
「作戦、大成功だね! でも、オークなんてホントは、私の『光弾』だけで十分なんだけどなあ」
女の子はそういうと、不満げに口を尖らせてみせた。
「だけどシィナちゃん。先生が、二人でやれっておっしゃったし……」
答えるのは、シャビイと呼ばれた男の子である。女の子と同じく杖を持ち、顔を隠すように深々とフードをかぶっていた。
「そんなことわかってるって! なによ、とどめをさしたのが自分だからって、ちょっとお調子に乗ってない? あたしがあいつらを引きつけてあげたから、あんたの錬成陣にあいつらを誘い込めたんでしょ?」
「あ、そうだ……おじいさんたちを助けてあげなきゃ」
「聞きなさいよー! 聞け―!」
◇ ◇ ◇ ◇
シャビイが『治癒』を唱えると、老人の傷はすぐに癒えていった。幸いなことに、見た目ほど傷は深くなかったらしい。
「ええと、もう大丈夫ですよ」
「おお……ありがとうございます。何とお礼を申し上げればよいか……」
「ありがとう、お兄ちゃん、お姉ちゃん!」
「どういたしまして! あたしはシィナ。こっちの暗い子はシャビイっていうの」
聞けば、老人と少年はこの森にしかない野草を採取しに来たという。その途中で、うっかりオークどもの縄張りに足を踏み入れてしまったのだそうだ。
「あー、それでか。あいつら、縄張り意識メチャメチャ強いもんねー」
「この辺りのことは頭に入れておいたつもりだったのですが……やれやれ、もう歳ですかな……」
「シ、シィナちゃん」
シャビイが、慌てた様子で話しかけてきた。
「なに?」
「おじいさんの言うことが本当なら、ちょっとまずいかも……」
「なにが? はっきり言ってくれないとわかんないよ」
「せ、先生に習ったよね。縄張りを侵されたオークは、決して侵入者を許さない。群れ全員で地の果てまで追いかけてくる……って」
「群れ全員……シャビイ、それって!」
「うん……さっきのオークたち、それにしては少なすぎるんだ」
二人が顔を見合わせたそのとき、大音声が森を震わせた。
オークどものウォー・クライであった。叩きつけられるような音に驚いた不思議な色の鳥たちが、慌てて空に逃れ行く。
「わー!? なになに?」
「き、来た……!」
森の奥より、オークの戦列が一糸乱れぬ歩調で現れた。軍団の中央、他のオークに倍する体躯のオークが一体、冗談のような大きさの鉄斧を担ぎながら睨みを利かせる。着込んだ鎧にも、暴力に満ちあふれた四肢にも等しく刻まれた傷跡が、このオークの巨躯が単なる虚仮威しのものではないことを雄弁に物語っていた。
「オークチャンピオンだ! 先生が言ってたよね、『オークの中には時々、異常に体躯が発達した個体が現れる』って! ええと……そのあとってなんだっけ?」
「そ、そんなこと言ってる場合じゃないよシィナちゃん……そのあとは『卓越した腕力と耐久力を誇り、多少の攻撃では傷一つつかない、恐るべき相手だ』だよ」
「えー!? わたしの『光弾』通じないかもしれないってこと?」
「わ、わからないよ……でも、もし通じなかったら……」
「オメエら、わかってんなあ? 俺らの縄張りに入った挙句、仲間をやりやがったクソガキども……ゼッテー、生かして帰すんじゃねえぞ!」
「わかったぜ、カシラ!」
「おっしゃ、突撃準備!」
オークの王は戦斧を高く掲げると、大騒ぎしている二人へ向かい振り下ろした。戦列オークたちが咆哮を上げ、突撃の構えを見せる。
「来る、来るよ! えーい、とりあえずありったけの『光弾』撃ってやるんだから!」
「に、逃げようよシィナちゃん!」
「60点だな、二人とも」
真っ先に駆け始めた一体のオークが、派手に転倒した。続けて二体目、三体目。わずかの時間で、三十体ほどいた戦列オークたちは全員が地面に這いつくばらされていた。彼らの手足が、かすかに光る魔力の輪に拘束されているのに気づき、オークキングは目を見開く。
「まあ、とはいえよくやった。後は任せるといい」
魔力による『隠形』を解除して、一人の男がその場に姿を現した。若いとも老成しているともとれる、不思議な容貌の男だった。伸ばした髪を無造作に束ね、いかにも旅慣れた服装の上から粗末な外套をまとっていた。
「せ、せんせー!? どこから来たんですか?」
「どこからもなにも、ずっとついてきていたが」
「ぜ、全然気がつかなかった……」
「まだまだ、修行不足だな」
「テメエ……どこのモンだコラァ!?」
オークキングが鼻息荒く誰何する。
「私か? 私はこの子らの保護者、兼、教師だ」
「教師だぁ?」
「ふっふーん! 聞いて驚けオークども! 何を隠そうこの方は知る人ぞ知る、自称『百年に一人の天才』にして『辺境の知恵者』、または『森の大賢者』とも呼ばれる大魔術師……ヘリヤ様だぞー!」
「シィナちゃん、それじゃあんまり褒めてないような……」
「そしてあたしはその一番弟子にして先生の花嫁候補、そして二百年に一人の天才美少女魔術師ことシィナさんだ! どうだまいったか、ひれふしろー! あ、こっちのこいつは二番弟子のシャビイです」
「天才も花嫁候補も、それこそ自称じゃない……」
シィナの言葉を聞いたオークチャンピオンが、わなわなと震えだした。
「本気(マジ)か……本気でテメエ、”あの”魔術師ヘリヤかよ?」
「二つ名はともかく、私がヘリヤなのは確かだよ。さて、オークの王よ。選択肢は二つだ」
「ああ?」
ヘリヤはこれ見よがしに、二本指を立てみせる。
「一つ、おとなしくこの場を立ち去り、仲間と共に森の奥で静かに暮らす。二つ、敵わぬ戦いに身を投じ、名誉の戦死を遂げる……私としては、前者がお勧めだがね」
「テメエ……舐めてんのか!?」
「舐めてなどいない。彼我の実力を正確に把握した上での、ごくごく妥当な提案だよ」
「あ……あ? なに言ってんだか、わっかんねーゾコラァ!? クッソ、舐めやがって、皆殺しだボケがぁ!」
地団駄を踏み、チャンピオンがヘリヤに襲いかかる。大戦斧が唸りを上げて、ヘリヤの頭上に振り下ろされた。ヘリヤは、斧を見つめたまま微動だにしない。
「!?」
「届かんよ」
立つ地面まで真っ二つにせんとばかりに振り下ろされた戦斧は、だが何かにぶつかるような派手な音を立てて、ヘリヤの眼前で阻まれた。続けて二度三度、倍する勢いで振り下ろされる斧は、そのことごとくが彼の身には届かない。
防御結界術式。ヘリヤの周囲に張り巡らされたそれは、目を凝らさなければ見えないほどの薄さと、それでいて強烈極まる一撃を決して通さぬ頑健さを備えていた。
風聞に曰く――まだ若い頃の彼が、神話の“竜”から直接手ほどきを受け身に付けたという、ヘリヤお得意の術の一つである。
「力量の差がわかっただろう。敵わぬ相手に背を向けるのは、決して不名誉なことではないと思うぞ」
「だ、黙れコラァ!」
「やれやれ……仕方あるまい」
「――ごめんあそばせ」
目の覚めるような、一撃。
横あいから飛んできた何者かが、チャンピオンの首を綺麗に刈り取った。
「わー!? 今度は何?」
「ひ、人……?」
「……まさか」
肩まで伸びた黒髪。白磁の肌。青いビロードのような生地の服が全身を包み込み、美しい体の線を強調していた。
女が立ち上がる。その途端、服が解け、優雅なドレスへと変貌した。つややかな黒髪が、腰まで伸びた。
「えー!? なに、なんなのこの人?」
「わあ……キレイな人……」
「先生! せんせー! なんなんですかあの人……先生?」
ヘリアの世界からほんの一瞬だけ、目の前の令嬢以外の一切が消えていた。彼の脳裏に、あの日の光景が怒涛のように映し出されていく。
そして白磁の令嬢は、別れのときの記憶と寸分違わぬ笑顔で、見事な一礼(カーテシー)を決めてみせた。
「お久しゅうございますわ、魔術師殿。その後お変わりはございませんか?」
対してヘリヤは、ぎこちない笑顔を返しつつ答えた。
「……おかげさまで元気だよ。久しぶりすぎて、あんたの顔は忘れるところだったがね」
◇ ◇ ◇ ◇
「獲物を横からさらうようなご無礼、お許しくださいな。一刻も早くお会いしたかったにも関わらず、何やらお取り込み中のようでしたので、つい」
その物言いにほんの少し鼓動を昂らせ、だがそれは決して表に出さずにヘリヤはうなずく。
「構わんよ。それにしても久しいな。別れて二十年、といったところか」
「ずいぶんとお待たせしてしまいましたわ。申し訳ございません」
「……時が、満ちたんだな?」
「ええ」
「そうか」
「せ、先生! なんなんですかその女の人! 先生とどういう関係なんですかー!?」
「急に大声を出すんじゃない、驚いてしまうだろう……彼女は、その、私の古い知り合いだ」
「古い、知り合い〜? ホントですか〜?」
「な、何が言いたいんだ」
焦った様子で少女の追及をかわそうとする様子を見ておかしそうに笑い、令嬢はヘリヤに問いかけた。
「魔術師殿、その方たちは?」
「あ、ああ。この子らは、私の生徒だ。シィナにシャビイ。数年前から私の旅に同行させて、いろいろと教えてやっているんだ」
「まあ」
口元に手をやり驚く令嬢に対して、シィナは胸をぐっとそらしてみせた。
「そう! あなたがどこの誰だか知りませんけどね! わたしは魔術師ヘリヤ様の一番弟子にしてお世話係、兼、最有力花嫁候補、三百年に一人と世にうたわれた天才美少女魔術師シィナさんよ! 覚えておきなさい!」
「また言ってる……しかも増えてる」
二人を微笑みと共に見つめながら――それはとても素敵な笑顔だと、白磁の令嬢には思えた――ヘリヤはぼそりと呟いた。
「……私の見立てでは、二人とも千年に一人の大魔導師になれる素質を備えている――まだまだ未熟だがね」
「……え?」
「先生……今、何て言いました……?」
「まだまだ未熟だ、と言ったんだ」
「その前! その前ー!」
令嬢はくすくすと笑うと、花のような微笑みを二人に向けた。
「ご挨拶がまだでしたわね。はじめまして、未来の大魔導師様がた。わたくし、ベアトリス・スカーホワイトと申します。以後、お見知りおき願いますわ」
そう言って再び、見事な一礼を決めてみせた。
「わあ……」
「な、なによシャビイ。鼻の下伸ばしちゃって。かっこわるー」
「の、伸ばしてないよ!」
ヘリヤとベアトリスは、顔を見合わせて笑う。笑いながらヘリヤは、離れた木陰にこれまた懐かしい姿を見つけた。オートマタ執事とオートマタメイドは、やはり別れたときと寸分違わぬ姿でそこに立っていた。
「ふふ。さて、魔術師殿、再会を祝しまして、お茶でも一杯いかがですか? この先に森が開けた場所がございますの。そちらにお茶会の席を設けてありますわ」
「ああ、ぜひご相伴に預かろう。そちらのご老人たちを、安全な場所まで送り届けてからだがな……」
「もちろんですわ。そうそう、お弟子さんがたもご同席いただけると、わたくし嬉しく思うのですが……」
わいわいと騒いでいた二人が、その言葉を聞いてぴたりと静かになった。
「紅茶……飲んだことない。美味しいの?」
「もちろんですわ」
「変な薬とか、入ってないでしょうね」
それを聞いたヘリヤは、思わず吹き出してしまった。
「先生!? 何がおかしいんですか! 『いかなるときも万全の注意を払わなければならない』『上手い話は、その裏を疑う必要がある』っていつも言ってるのは先生じゃないですかー?!」
「いや、すまんすまん……味は私が保証するよ」
「せ、先生がそういうなら……でも、美味しくなかったらわたしの『光弾』が炸裂しちゃうからね!」
「じゃ、じゃあ僕も……」
「ふふ――では皆様の分、ご用意させますわね」
身を翻し歩き出すベアトリスの姿を眺めながら、ヘリヤは物思いにふける。
再会できたことは、素直に嬉しい。だが、彼女との再会とは即ち、新たなる戦いに身を投じるということだ。
私は、変われただろうか。この二十年間、ひたすらに己の魔術を磨き続けてきた。辺境各地を旅してまわり、数多の試練を潜り抜け、人を助け、助けられ――いつの間にか、なにやらくすぐったくなるような二つ名で呼ばれることも増えてきた。
私は、変われただろうか。毛嫌いしていた術式のいくつかを身に着け、究めようとしてきた。だが、深遠なるかな魔道。つかんだと思った深奥が手をすり抜けてしまったことの、なんと多かったことか。
だが、それでも。己の身を守るだけでなく、他者を護るだけの力を得ることができた。それどころか弟子を取り、教え導くことまでやれているではないか。
そうだ、あのときとは違う。こんどこそ、私は。
彼女と肩を並べて、戦ってみせる。
ヘリヤは力強く足を踏み出した。自信に満ちあふれた笑みとともに。
◇ ◇ ◇ ◇
「……せんせー」
「なんだ」
「なんだかわかんないけど、あそこのメイドさんがすっごいあたしをにらんでる気がするんですよ。あたし、なんか変なこと言ったのかなあ? 先生分かります?」
「……さあな」
白磁のアイアンメイデン 第1部 了
そんな…旦那悪いっすよアタシなんかに…え、「柄にもなく遠慮するな」ですって? エヘヘ、まあ、そうなんですがネェ…んじゃ、お言葉に甘えて遠慮なくっと…ヘヘ
