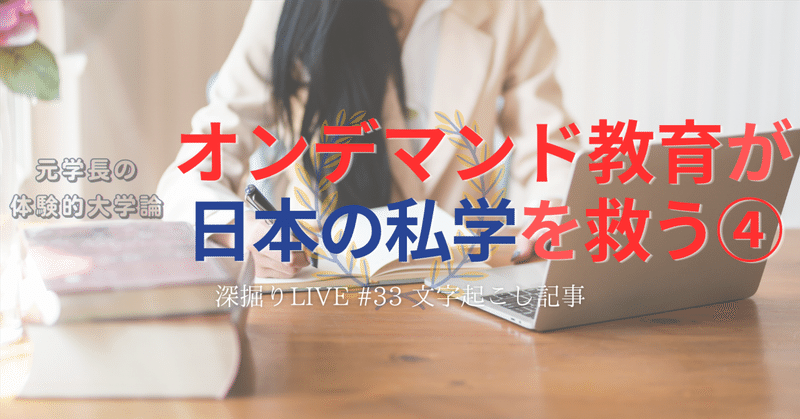
オンデマンド教育が日本の私学を救う④(深掘りLIVE #33 文字起こし記事)
LISTENで聴く、LISTENで読む
深掘りLIVE #33 オンデマンド教育が日本の私学を救う④
深堀ライブの33個目になります。「オンデマンド教育が日本の私学を救う」のその4ですね。このシリーズはこれで完結にしようかなと思っております。これまで3回話してきて、これが4つ目になります。
深堀ライブの配信について
その前に、この深堀ライブですが、これはLISTENというプラットフォームをホストに配信して、そこで音声を試し聞きすることができます。有料エピソードですので、それを購入していただくと文字起こし記事を読むことができます。さらにこの音声は、同じものを私のnoteというプラットフォームに音声記事として同じものをアップロードしております。さらにそれをより読みやすい形でnoteの記事として、文字起こし記事として掲載しているのがこの深堀ライブということになります。
イノベーションとしてのオンデマンド化の効用
さて、「オンデマンド教育が日本の私学を救う」その4、完結編ですが、これまで何を話してきたかの振り返りをして、まとめに入りたいと思います。
オンデマンド化とは最新の技術革新の成果を活かした時空からの解放である(その1振り返り)
まず1回目が1月27日ですね。深堀ライブの20個目として、「オンデマンド教育が日本の私学を救う」ということで、これは特にコロナですね。コロナ禍においてオンデマンド教育に日本の大学は取り組んだのに、これをすべて元に戻してしまったということは非常にもったいないことなんだっていうね。オンデマンド・オンラインの最大のメリットは時間と空間からの解放なんだと。そしてそこでは自由な学びが可能になるんだ。しかもそういったオンライン化、オンデマンド化っていうのは最新の技術革新の成果を最大限生かしてる話なんだと。
なぜこれを利用しないのか。なぜ、いまだに教室と時間割に縛られた大学の旧来型の授業にこだわるのかと。それが効率的ならばいいけれども、私も大学教育やってましたが、講義室型の大人数の講義授業がすでに意味を失っているというふうに、だいぶ前に思ってますので、これをなぜ続けるのか。さらにそこでレポート課題を課していると。この生成AIの時代に。そんなことをする意味があるんだろうかっていうふうに真面目に思ってるので、そんなことをベースにしながら1回目、概論的に話させていただきました。
オンデマンド化は大学経営の効率化につながる技術革新である(その2振り返り)
そしてその2はですね、2月19日でしたかね。ここではむしろ「オンデマンド教育が日本の私学を救う」ということで、主に経営面ですね。大学経営の効率化と人件費の削減につながるということです。つまり教育の充実を図れる一方で、いわゆる教員資源ですね。教員資源の有効活用につながるという話です。つまり、時間割と教室に縛られて教員資源を無駄遣いしていると。日本の大学はね。
これ大学教員やってる方はわかると思うんですが、とにかく今日は授業があるのでもうあと何もできませんと、授業3コマぐらいあるとね、いう話になっちゃうわけですよ。それ毎年、大体同じことやってて、毎年違う学生に同じことを繰り返してるわけです。なんでこれをオンライン・オンデマンド化しないのかっていうね、毎回。
今やAIが喋ってくれるわけですから、AIに喋らせたっていいわけですよね。なのに教員が、高等教育の貴重なスタッフがね、講義に、毎年同じことを繰り返すために時間と労力を費やしているというね。これに意味があるのかと。これだけ言うと誤解が生じるんですが、もっと違うことに教員資源を使うべきじゃないかっていうことなんですけどね。
オンデマンド化は教員資源の有効活用につながる技術革新である(その3振り返り)
これをその3で、少しお話ししました。単なる予算削減、経営改善じゃないんだよということです。つまり教員の時間資源、知的資源をより有効に効果的に活用するには、オンデマンドの方がメリットが大きいという話をしてるわけですね。しかも教育効果も上がると。
対面で大人数の講義授業をやったときに、学生との一対一のコミュニケーションなんて取れないわけですよね。学生もあまり質問に来ないんですが、もし質問に来る学生、学習意欲に燃えた学生だったら、行列ができちゃって、休み時間10分、15分ではこなせなくなってしまう。
ところがこれがオンデマンドだと、一対一のコミュニケーションが取れるわけですね。特に学習意欲を持った学生に対する、一対一のコミュニケーションが、オンライン・オンデマンドだとより取りやすい。しかも一人一人に合わせた学修成果が可視化できるっていうね、こういうことがあるんです。これ講義型の授業ではできません。
さらにレポート課題なんか、年に1回じゃない、半年に1回、最後にレポート課題を出させても把握できるもんじゃありません。なので、講義の途中で中間レポートとかやる先生もいますが、それだけで把握できるものではありません。これはオンライン・オンデマンド化した方が間違いなく学生一人一人の顔が見れるようになるというふうに私は思っているということです。
学修者本位の自由な学びの場としての大学へ
そんなことを前提にしながら、今日はですね、これまでの時間割り、そして教室割り、つまりオンデマンド教育は時間と空間からの自由。時間と空間に縛られない。そういう意味では裏返せば、時間資源と空間資源を有効活用できるようになるということです。さらに教員資源ですね、これも有効活用できるようになるということです。
単位の自由化、授業の自由化
今日はそれに加えてさらに、単位ですね、単位、授業とか単位、学部学科の中にカリキュラムがあって、そこで必修単位とかがあるわけですが、これは本当に15回聞かなきゃいけないものなのかっていう授業もあるわけです。もちろん15回聞かなきゃいけない授業もあるわけです。それを理解しないと次に進めないという授業もあるわけです。これはこれでやればいいわけですが、そういう授業ばっかりではないというのが一つですね。
つまり、本当に15回聞かなきゃいけないのかっていう、こういう問題があるわけです。つまり1回90分聞いて、それで学習する人もいるわけですよね。あるいはそこだけを、例えば他学部、他学科にいて、そのコマだけ、その時間だけ聞きたいという人が、教室に行ってその時間割に行かなきゃ聞けないわけですよね、今のやり方では、対面型では。だけどこれ、オンデマンド化すれば聞けるわけですよね。
なんでそういう自由な学びを阻害するのかと、なぜクローズするのかと、時間と空間に縛り付けるのかと、さらに学部、学科の枠に閉じ込めるのかと、さらに学年の枠に閉じ込めるわけですね、その教育資源をね。
教育資源と学修コンテンツの自由化
だから教育資源をもっと有効活用して、時間と空間から解放することによってそのコンテンツがね、より有効な形で学修者の糧になるわけですよね。なぜそれをやらないのかと。教育コンテンツ、教員資源、教育資源のオープンソース化と言ってもいいと思います。
さらに単位に関連して、124単位取らなければ大学卒業できないっていうのはいいんですが、124単位以上取ったっていいわけですが、だいたい低空飛行で、124単位取ったらもうあと取らないっていう学生が多いわけですよね。これ124っていうのは設置基準上の縛りなので、それを取らなければ大学卒業資格は得られないっていう、ここはいいんです。これはもう最低基準であって。ただそれを超えてどんどん学んでもいいじゃないかということですね。
量的評価から質的評価へ:単位認定基準の自由化
例えば、今は対面授業にこだわった形で単位修得を適正に行うべきだという、文部科学省の指導なんかもあって、1年間で履修登録できる単位数の上限っていうのが定められてるんですが、こんな馬鹿げた話はないわけです。能力のある学生は半年、1年にもっとたくさん履修できるはずなんですよね。なぜ上限を設けるのかと。これは対面授業っていう発想に縛られてるからそういう時間縛りになるわけです。
ここから先は
おだちんちょうだい!頑張って書いたよ! お駄賃文化を復活させよう! ODACHINを国際語に! オダチン文化がSNSを救う! よいと思ったらサポートをお願いします!

