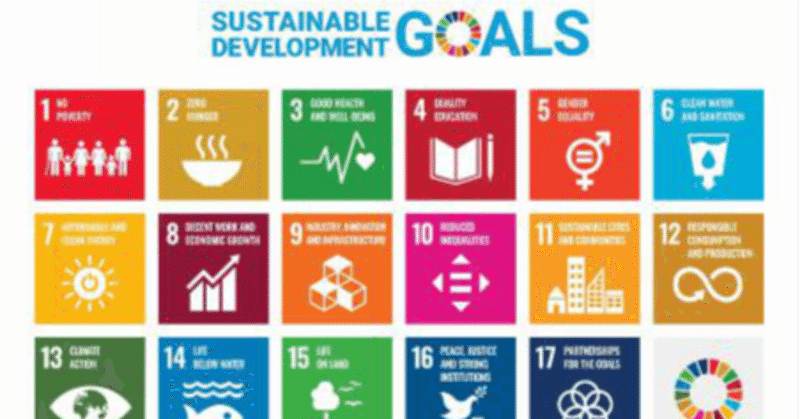
SDGsアイコンの問題点を考える(その3)
はじめに
その3では、残りのアイコンのうち、見直したほうがいいと思うものを理由とともに説明していこうと思う。当初は普及を図る上でわかりやすい表現をしたのかもしれないが、現時点では修正した方がいいものばかりだ。
SDG3すべての人に健康と福祉を

問題としたいのはwell-beingの訳を「福祉」とした言葉の選択である。これは、2030アジェンダの仮訳でも「福祉」としており、博報堂のせいではない。ただ、日本語で福祉といった場合、連想するのは高齢者福祉や障害者福祉といった文脈で使われる「福祉」であり、英語だとWelfareに相当する概念だろう。
Well-beingというのは非常に重要な概念で、訳としては、「健康で安心なこと」「満足できる生活状態」「幸福」といったものが考えられる。決して新しい概念というわけではなく、1946年のWHOの設立の際に「健康の定義」において、「病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態(well-being)にあること」として使われたことによって広まったものだ。そして、コロナ禍を経験した現在、ウェルビーイングを社会的な指標とする考え方は欧米を中心に急速に広まっている。2024年9月の国連未来サミットでも主要なテーマとなる見込みと報じられている。日本においてもウェルビーイングは一定程度広まっているが、SDGsにおいても実は目標になっていることはほとんど知られていない。これは「福祉」と訳しているためその存在に気がつかないからである。定訳が確立していないのが問題とも言えるが、確立を待っていられない事情がある。それはこのwell-beingがポストSDGsの有力候補の一つであるからだ。前述の国連未来サミット後にポストSDGsの議論が活発になると見込まれているが、その際に次はウェルビーイングだといわれて、「ああ、SDGsの3番ね」と言える日本人は何割であろうか?今からでもこのアイコンはウェルビーイングに変えて欲しい。切にそう思う。
SDG6安全な水とトイレを世界中に

英語版と見比べて気づくのは、sanitationが「トイレ」に置き換わっていること、「世界中に」が加わっていることだろう。このうち後者は、目標そのものの全文が「すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する」となっていることから、「すべての人々」→「世界中に」と解釈してわざわざ付け加えたのだと考えられる。
まず、sanitationについては、下水道などの衛生(設備)を指しているわけだが、博報堂としてはトイレを代表的な例として提示してわかりやすくしたそうである。このSDG6を途上国だけの問題として捉えるならば、そういう表現もわかるが、SDG6は日本にとっても切実な問題である。日本の下水道普及率は浄化槽なども含めた汚水処理人口普及率が約9割で、いまだ880万人が未処理のままである。他の先進国ももちろん100%ではないが、日本は人口が多いこともありそんなに威張れる状況ではない。また、雨水処理と一緒の合流式の比率が高く、東京がその代表例だが、大雨が降ると処理が追いつかず、汚水を海に垂れ流している。東京オリンピックのトライアスロン会場が問題になりましたよね。その様なわけで、「トイレ」→日本は関係ない、「世界中に」→日本は関係ない、というイメージに誘導されてしまうが、SDG6は日本にとっても重大な問題だ。それを覆い隠してしまう現在のアイコンは修正すべきと考える。
SDG12 つくる責任つかう責任

「つくる責任つかう責任」は明らかに他のゴールとは違う。これは唯一、体言止めの目標提示となっているのだ。だが、ここで問われているのは消費や生産の中身ではなく「責任」のほう。責任が目標(ゴール)というのは何とも奇異である。キャッチコピーとしての完成度については認めるところであるが、やはり正しい理解という意味でそろそろ疑問を感じる時期がきている。
あらためてSDG12を見てほしい。「持続可能な消費と生産形態(パターン)を確保する。Ensure sustainable consumption and production patterns.」とある。注目してほしいのは「パターン」。なぜ、「サステナブルな消費と生産」に「形態(パターン)」もくっついてくるのか考えたことありますか。それは、最初のターゲット(12.1)に出てくる「10YFP(持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み)を実施する」に由来している。10YFPは”10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns”のことで、ここに「パターン」が出てくる。10YFPは2012年のリオ+20で採択されたが、このときの問題意識は「長期的に持続可能な開発を達成するには生産と消費の形態(パターン)の根本的な変化が不可欠」というもの。つまり生産形態や消費形態を根本的に変えましょうねが10YFPの問題意識でそれをSDGsでも引き継いでいる。10YFPでは根本的に変化(fundamental changes)した消費形態と生産形態に移行せよと促し、SDGsではそれを確保(Ensure)せよと言っているのだ。
再び「2030アジェンダ」に戻ってほしい。パラグラフ28がSDG12の土台となっているが、責任を持てというゴールではないのが一目でわかる。わかりやすさの追求はそろそろ終わりにして、正しい理解を追求してほしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
