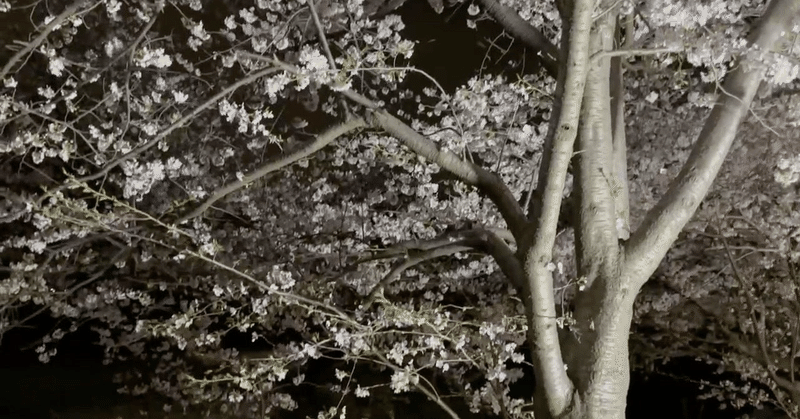
【道と歴史】船橋宿の謎
船橋は江戸時代の中期以降、佐倉街道最大の宿場町として賑わった宿場町だ。
「佐倉街道」以外にも、徳川家康が九十九里方面での鷹狩のために土井利勝に命じて整備した「東金御成街道」や館山まで通じる「房総往還」の起点であり、成田詣でも賑わった「行徳道」とも繋がる交通の要衝であった。
しかし、なぜか船橋宿は正式は宿場ではなく、間の宿と呼ばれる休憩施設という位置付けの町だったというのだ。
船橋市西図書館郷戸資料室のサイトには、「公式文書には「船橋宿」と書けないので、弘化元年(1844)には交通業務を円滑に進めるため「船橋宿」と唱えさせて欲しいという訴訟を起こしているが、承認されなかったもようである。」との記載もある。
なぜ、船橋宿は公式の宿場町として認められなかったのだろうか?
江戸時代の宿場町
江戸時代に五街道や脇往還に設置された宿場町は、原則として道中奉行の管轄下にあり、駅逓事務を取り扱うため設定された町場をいう。
東海道の宿駅伝馬制度を例に取ると、
1)幕府老中の奉書の送達
2)伝馬朱印状を持つ公用の書状や荷物の運搬のための人足と馬の無償提供
3)幕府役人の公務出張のための人足と馬を御定賃銭で安価に提供
などが課されていた。
その見返りとして公用以外の荷物や人の運搬や宿泊業務の独占が認められていた。
船橋宿と旅籠屋
船橋宿は、佐倉街道になる「間の宿」で、八幡宿(市川市)と大和田宿(八千代市)の間に位置した。八幡宿とは1里15町(5.6km)、大和田宿とは3里9町(12.8km)の距離があり、町場は海神村、九日市村、五日市で構成されていた。
船橋は佐倉街道以外にも、御成街道や房総往還、行徳道の起点でもあり、江戸時代中期以降になると、江戸の人々の間で成田参詣でが流行するようになったことから、佐倉街道最大の宿場として発展するようになったという。
宿泊施設の営業は九日市村だけに許可され、本陣が1軒あった他、旅籠屋も
1800年(寛政12年)に22軒、1818年(文化15年)に25軒、1830年(天保元年)には29軒と増加していったが、一方で、九日市村の旅籠屋の営業権は株式で規制され、新規に開業する際は譲渡、買い取り等によって株式を取得する必要があるなど、既存の旅籠屋の既得権が守られるようにおなっていたそうだ。
船橋宿には「八兵衛」と呼ばれる飯盛女(遊女)を置く旅籠屋もあったそうだ。
船橋宿の駅逓事務
船橋宿では、人足15人と馬15頭までは公用の通行者に提供したそうで、問屋場についても九日市村と五九日市村に1軒づつあって交代で勤め、公用文書の継立も業務に含まれていたそうだ。
また、助郷制度についても1721年(享保6年)や江戸後期の村明細帳があるそうで、伝馬制に関して助郷制度まで整っていたとすると、なぜ、宿場として許可されなかったのか疑問が残る。
ひとつ考えられることとしては、機を逸したということか・・・。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
