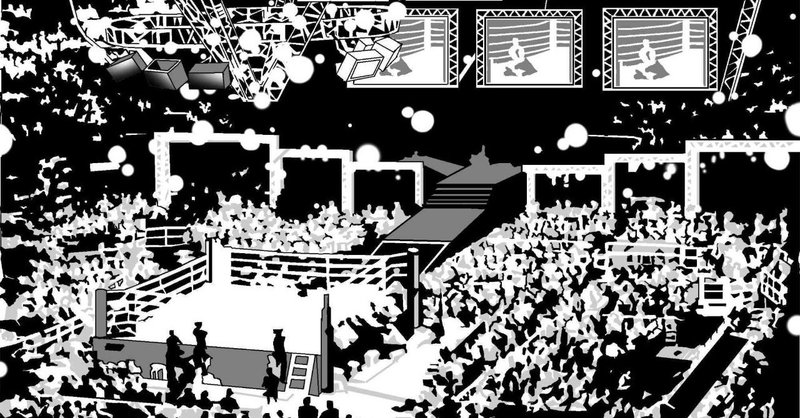
四角いマットの人食い狼(1)
声が響く。響いてくる。地鳴りとなって、空気を揺らして。
後楽園ホールの階段下は寒い。それでも熱気はここまで降りてくる。今、試合の真っ只中だ。
阿久津はメーン・イベントをスルーして、寒空の下タバコを吸おうとこうして出てきた。そうしなくてはならなかった。
「恨むぜ」
男にごちる。
目の前の男は、メーン・イベントを行っている団体──『リブレ』の営業部長の小田島である。細い目をした小男だが、不思議と目の光が強い男だった。
「ローン・ウルフの試合前には終わらせたかったのさ」
ローン・ウルフ。RWGPのヘビー級チャンピオン。リブレのスター選手だ。
「俺には関係ない」
「ところがそうでもなくなる」
小田島はスーツのポケットからくしゃくしゃのタバコを取り出し、くわえた。
「タバコは吸わんのだろ。鍛えてるし、よく節制してる」
「何が言いたい」
火が灯る。東京ドームから吹き下ろすビル風が冷たく、か細い炎を揺らす。
「チャンピオンは逮捕される。すぐに」
「今まさにリングに上がってる男がか? 寝言にゃ早いぜ」
彼のタバコに釣られるように、阿久津は自分のタバコを取り出す。
「禁煙してたんだと思ってた」
「鍛えてはいるさ」
阿久津にとって、リングはそういう場所だった。追い出されても、干されても、いつか帰る場所として頭の中にある。
「ローン・ウルフはリブレのエースで大黒柱だ。一番客も呼べる。それがパクられたら団体はおしまいだ。だから君が必要なんだ」
「ローン・ウルフに逆らった男をか? 小田島さん、あんたも相当首が締まっとるらしいね」
阿久津は忌々しげにそう呟いた。ホールからそれをうわ塗るように歓声。
黒い狼。孤独のカリスマ。業界では五、六番手のプロレス団体リブレが、後楽園ホールをいっぱいにすることができたのは、ひとえにローン・ウルフのお陰だ。空中殺法の一つ一つが、人間で真円を描くように美しい。
彼を見るために客が押し寄せた。これからは違う。
「彼、何やったんだい」
「つまらん暴力沙汰さ。警察には鼻薬を嗅がせて、あくまでもローン・ウルフの中の人──取るに足らんうちのいち職員が懲役を二年食らうことになってる」
小田島は苦々しげに言った。灰を落とす仕草まで忌々しそうだった。
「リブレは小さい。チャンピオンが二年もいなくなるなんて考えられない」
「そこでだ。……阿久津くん、チャンピオンにならんかね」
小田島はなんとか絞り出すようにそう言った。阿久津にそう言わなくてはならないのは、彼やリブレという団体にとって屈辱に違いなかった。
無理もない。公然とローン・ウルフ一強体制と化したリブレを批判し、さっさと出ていったのだから。
「そんなに簡単になれるんなら苦労しなかったよ」
阿久津は半年前までリブレのレスラーだった。ローン・ウルフに反発して、日本のプロレス界に居場所をなくした阿久津は、そのこと自体に反発し──一時姿をくらましていた。
「俺はリングから降りた男だ。今更のこのこ上がってけるかい」
「たしかにそのとおり……君は狼(ウルフ)と言うよりは負け犬だな」
阿久津は笑わなかった。事実を提示されても動じるような男ではなかったが、それでも内側から掻きむしられるような思いだった。
リングから降りたレスラーの、なんと惨めなことか。それも、後ろ指を指されて──。
「どうするね。負け犬が狼になれることなどそうはない」
小田島は笑みすら見せながら言った。俺が負け犬なら貴様は狸だ。自分がリングに未練を持っているのを見越して、わざわざ呼び出したのだ。
もっとも、降りたからこそまた上がりたいと思うのも人間である。逃せばチャンスはもう巡ってこない。
「まさかチャンピオンでござい、と上がるわけにもいかんだろ。あんたの話がホントなら、ローン・ウルフはこの後お縄だ。マッチメイクにゃ時間が足りないぜ」
阿久津は冷静になんとかそう絞り出した。本当なら、叫びたかった。畜生、俺はリブレに頭を下げさせたぞ。くそったれのローン・ウルフに。
「なるんだよ、阿久津くん。君が『ローン・ウルフに』なるんだ。幸い君は彼と背格好がそんなに変わらない。体幹やジャンプ力も申し分ないしね」
ふざけるな、とぶん殴ろうと考えるほど、阿久津は子供ではなかった。
プロレスラーの阿久津は干されてしまっている。それを代用スターにはできない。
だが、ローン・ウルフなら。あの人を食ったようなデザインの、狼のマスクを被ればそれもチャラになる。
それは阿久津の死を意味していた。プロレスラーとしてマスクを被ることは、即ち素顔を捨てることを意味する。
今回はそれ以上の意味を持つだろう。バレれば、何もかもおしまいなのだから。
「文字どおりの人食い狼になれってかい」
「そうだ。君の実力とローン・ウルフの人気が合わされば、少なくとも彼が戻ってくるまでは安泰だろ」
小田島は掴みかかるようにして言った。悪魔の囁きだった。俺はファウストで、彼はメフィスト・フェレスだ。柄にもなく昔読んだ本のことを思い出していた。
「乗ろうじゃないか。なってやるよ、ローン・ウルフに。目の上のたんこぶが勝手に取れてくれるなんて、これほどありがたいこともない」
阿久津は口角を上げて言った。プロレスは強いだけで渡っていける世界ではない。華も必要だ。それが俺にもあるかどうか、試してやる。
四角いマットの上で。
【続く】
