
建築学者・延藤安弘【2】|1964年、絹谷助教授の死が京大西山研にもたらしたもの
東京オリンピックを翌月に迎えた1964年9月、京都大学西山夘三研究室に一大事件が起きます。西山の後継者として将来を嘱望された助教授・絹谷祐規(1927-1964)が遥かオランダの地で不慮の事故により客死したのです。
そのショックと悲しみがどんなに大きなものだったのかは、絹谷の死の翌年に刊行された遺稿集『生活・住宅・地域計画』(勁草書房、1965)に収録された西山夘三(1911-1994)による「あとがき」を読むとヒシヒシと伝わってきます。西山は50頁弱にもおよぶ、愛情と無念、そして決意の思いが入り交じった「あとがき」を書き連ねているのです。
この西山研究室にとって嘆きの年となった1964年に京都大学大学院へ入学し、西山に師事したのが、後にまちづくりの研究・実践で活躍することとなる延藤安弘(1940-2018)でした。
北海道大学工学部で建築を学んでいた延藤は、『これからのすまい:住様式の話』(相模書房、1947)に強い感銘を受けたことから、西山の教えを乞うため京都大学大学院進学を決意したのでした。
延藤安弘が大学院へ入学したその年に、絹谷祐規が不慮の事故で亡くなったことは、その後の延藤の人生に大きな影響を与えたのでは中廊下。そんな問いを持ち前のカングリー精神で増幅してみたお話しです。
絹谷祐規の死、巽和夫の出戻り
遺稿集に西山が寄せた「あとがき」には、なかなか絹谷とじっくり会話もできなかった状況を振り返る西山の思いが書き留められるなか、次のような文章がでてきます。
やがて、6ヵ月もすれば帰って来て、新しく京大に作られる「地域生活空間計画」の講座の責任者として、八面六ぴの活躍をしてくれるのだと思い、一時の不自由は忍ばねばならぬと自分に言い聞かせていた。
(西山夘三「あとがき」『生活・住宅・地域計画』1965)
西山夘三の研究室は「建築計画講座」。当時、都市的な視点から生活空間を研究・構想することの必要性が叫ばれていたことから、いわば暖簾分けのように「地域生活空間計画講座」新設が準備されていたのでした。
西山はその責任者に絹谷を据えることにし、段取りも用意万端整ったところでオランダでの客死の報が舞い込んだのです。その結果、西山は自らが「地域生活空間計画講座」へと移り、「建築計画講座」の後任には建設省建築研究所へ巣立っていた巽和夫(1929-2012)を呼び戻すことになります。
西山の遺稿集へ寄せた「あとがき」には、絹谷と巽のことも登場します。それは熊野灘沿岸の漁村調査での出来事。
絹谷君は卒業前の旧制最後の3回生として、新制の同じく卒業を前にした巽和夫君やその他の人々とこの調査に加わった。(中略)調査方法について同僚の巽君と議論がおこり、果てはつかみかからんばかりの激論になったそうだが、恐ろしいことでもいやなことでもやろうと思ったことはやる。そこに彼は後年指導者としての資質をすでにあわわしていたという。
(西山夘三「あとがき」『生活・住宅・地域計画』1965)
絹谷と巽。ともに西山の教えを受けた二人の研究者は、「つかみかからんばかりの激論」を生むほど研究姿勢になんらかの違いがあった。そう思わせるエピソードです。
絹谷祐規と延藤安弘
絹谷祐規の突然すぎる死とそれにともなう玉突き的な巽和夫の着任。この一連の出来事を、同年に入学した延藤安弘の立場から見てみるとあれこれ興味深い。
教えを乞うたはずの西山夘三は早々に別の講座へと異動してしまう。しかも、僅かな期間ながらも時間を共にし、研究に対する情熱的な姿勢を教えてくれた絹谷助教授は亡くなってしまいます。
絹谷は持ち前の人なつっこさから、フィールドワークにも情熱を注いだ人物。後にまちづくりの研究・実践へと打ち込むことになる延藤にとって、絹谷の研究姿勢はとても親しみのもてるものだったのではないかと思います。
西山は絹谷の研究姿勢を次のように評しています。
単に研究者だけでなく建設に関連する技術者や労働者、あるいはその使い手・住み手、いわば開発と建設の主人である地域住民、労働者やおかみさんとの交流の中で研究をたしかめ、解決の道を探していくという社会的・組織的な活動と結びつけてきたことである。
(西山夘三「あとがき」『生活・住宅・地域計画』1965)
延藤と絹谷の関係を考えると、延藤の大学院入学が4月、絹谷がオランダの国際会議へと旅だったのが8月末だったので、それほど関わりをもったわけでもなくみえますが、チームで研究に取り組む西山研ゆえ、短期間でも濃厚な時間があったにちがいりません。
そして、やはりなによりも西山研を絹谷祐規の圧倒的な「喪失」が支配したであろうことを思うと、むしろ、より強い影響を延藤へ与えたのかもしれません。
ちなみに、延藤は絹谷の遺稿集出版に際して、収録論文「世帯構成およびその住宅との対応関係(抄)」の解題を担当しています。
巽和夫と延藤安弘
巽和夫研究室の助手をつとめていた延藤は、1983年に著書『こんな家に住みたいナ:絵本にみる住宅と都市』(晶文社、1983)(図1)を出版します。この本は絵本を住宅・都市論にまで高めた名著として知られるもの。

図1 こんな家に住みたいナ
住み手を主人公に位置づけて、皆が協働して環境改善に参加する大切さを欧米の絵本に見いだす内容は、住宅改革からまちづくりへと離陸していく延藤の軌跡を追うエポックに位置します。
試しに『こんな家に住みたいナ』の前後に著された主だった著書・論考をならべてみると・・・。
「ハウジング論序説」(1974、『現代の生活空間論・上』)
『都市住宅供給に関する計画的研究』(1976、学位論文)
『計画的小集団開発』(1979)
「イギリスの環境教育の動向」(1982、『住教育』)
「人間的規模の共同性によるコーポラティブ・ハウジング」(1985、『市街地整備の人間的方法』)
「ハウジング序説」(1985、『新建築学大系一四』)
「ハウジング研究作法覚え書」(1986、『現代ハウジング論』)
『集まって住むことは楽しいナ』(1987)
「コーポラティブ住宅の計画研究としての方法的位置づけ」(1989)
などなど。
やけに目につく頻出語句「ハウジング」。このキーワードは延藤が属した巽和夫研究室のメインテーマでもあります。延藤は「ハウジング」についてつぎのように定義しています。
ハウジングとは住み手が人間的居住に足る、かつ、都市的脈絡の中に位置づけられた、一定の質の住居・環境という空間的側面と、それを社会のあらゆる階層・地域において実現するための目的と手段の体系という社会的側面、および、住み手が居住しつつ住みよさを付加し、近隣関係を育てていくという生活的側面を統合した、有機的概念である。
(延藤安弘「ハウジング序説」1985)
やはりここにも「住み手」に温かなまなざしをむける著者の姿勢が垣間みられます。こうした「住み手」へのまなざしは、時代を経るにつれより豊かな表現に彩られ今に至ります。では、この温かなまなざしは当時所属した巽研究室に共通した特徴だったのかというと、どうもそうでもないよう。
西山研からの研究課題を継承・発展させて幅広いテーマを手がけていた巽研究室とはいえ、80年代後半の研究成果をとりまとめた、巽和夫編『行政建築家の構想』(学芸出版社、1989)(図2)では、「民間活動が旺盛であればあるほど、それとカウンターバランスをとるだけの力量を行政が備えなければいけない」との問題意識に立ち、建築行政の再編・強化を謳っており、著者のまなざしとはかなりの隔たりが認められます。

図2 行政建築家の構想
その隔たりを象徴するように『行政建築家の構想』が出版される2年前に『集まって住むことは楽しいナ』(鹿島出版会、1988)が、そして翌年には『まちづくり読本-「こんな町に住みたいナ」』(晶文社、1990)(図3)が出版されます。延藤と巽の距離を思わせる何とも対照的なできごと。
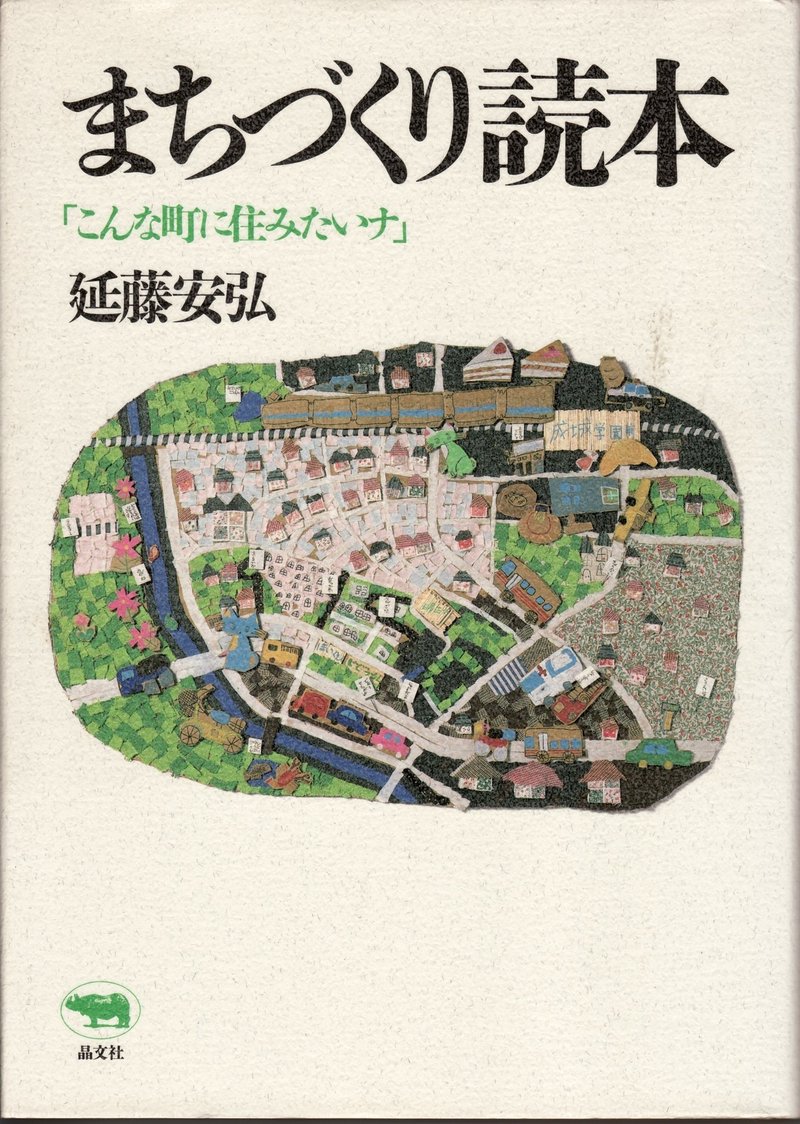
図3 まちづくり読本
ふたたび、絹谷祐規と延藤安弘
だとすると、延藤の研究姿勢のルーツはどこかと思うと、やはり絹谷にあると思われてきます。あるいは西山夘三の広汎な問題関心のうち、絹谷が継承したであろうフィールドがそのルーツといったほうが正確なのかもしれません。
ではそのフィールドとはどんなものなのか。それを知るために絹谷の研究姿勢や人となりを遺稿集から拾い上げてみたいと思います。
たとえば「単にいわゆる工学技術的・自然科学的アプローチのみでなく、しつような人間関係の追求にうらうちされた社会科学的な立場からのとりくみ、また単に現状の調査・分析、モデルの設定や計算におわることなく、そこで生活しつつある人々との交流を深めつつ、空間創造を任務とするアーキテクト・プランナーの創造的立場の自覚をもって、正しい政治の展開と共に要求されるであろう新しい科学と技術を創造しようとしていた」といった評価がみられます。
また、「すぐれた聴覚型の人」であり「音として読み、人の心を聞き分け、自らしゃべることを感じる中で考えを練り、構想を発展させるというタイプの人」、「すぐれた研究者・書斎人であったが都市の街頭や雑踏の中で、裏町や長屋で、車中や駅頭で、あるいは草深い農家の庭や漁村の浜で、イキイキとした調査マンであった」といいます。ほかにも学部生を喫茶店に連れてミックスジュースを初体験させたなんてお茶目な一面も持ち合わせたそう(西村一朗氏ブログ)。
このような人となりの絹谷が思い描いた都市ヴィジョン「四次元の都市計画」はどのようなものだったのか。絹谷はいいます。固定されたイメージに現実を合わせるのではなく、「そこに住む人たち-労働者やオッサン、オバハンたち-が自らをかえつつ都市をかえていくもの」だと(論考中、唐突にオッサン、オバハンという語句があらわれるあたり、ニヤリとさせられます)。
それは「そこに住む人たち」を主役に据え、調査研究と設計デザインをつなぐ提案であり、西山研究室が探究し続けてきた「国民的建築学」の模索に連なるものでしょう。
「国民の住宅をよりよくするためには(中略)国民自身の住宅をよくしようとするうごきと一体となることがなによりも大切である。」これは絹谷の遺稿集に収められた文章です。ほかにも次のような一節も。「歴史は教える。市民は都市計画に発言することによってのみ、その環境を確保しうることを」などなど。
絹谷のこうした言葉たちは、延藤が好んで自著のタイトルに用いた「住みたいナ」という思い、意思、発言、うごきが結実した表現とも呼応しています。西山から継承された絹谷的路線と巽的路線。この両者のあいだにある延藤安弘。そんな構図で、京都大学巽研究室助手・延藤安弘を追ってみようかと思います。
(つづく)
サポートは資料収集費用として、今後より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。スキ、コメント、フォローがいただけることも日々の励みになっております。ありがとうございます。
