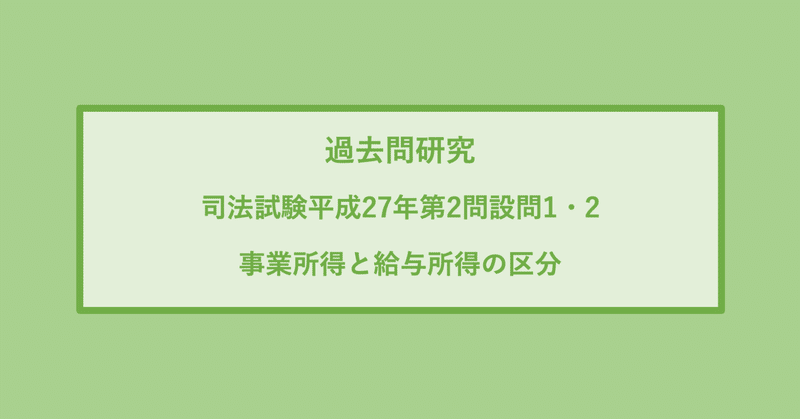
【過去問】 事業所得と給与所得の区分
1.問題
Aは、コンピュータのソフトウェアの開発を目的とするX株式会社(以下「X社」という。)に勤務した後、独立してY株式会社(以下「Y社」という。)を設立し、その代表取締役に就任し、毎月定額の報酬を受けていた。
Y社は、主にX社の下請会社として、同社が受注したソフトウェアの開発に関連する作業について委託を受け、報酬を受け取っていた。Y社は、Bらを雇用し、毎月給料を支払っていた。
Y社にはC法律事務所の弁護士Cという顧問弁護士がおり、Y社は、Cから法律的な助言を定期的に受けていた。具体的には、元請であるX社との契約条件の内容や契約書の内容さらには資金調達の方法やY社の従業員の雇用問題などについて、AがCの事務所を訪問するなどして相談していた。なお、顧問契約により、Y社は、Cに対して毎月定額の顧問料を支払うことになっていた。
X社(事業年度は暦年としていた。)は、平成26年10月1日、甲株式会社(以下「甲社」という。)の業務について、ソフトウェアの開発を3000万円で請け負い、同日、これに着手した。完成したソフトウェアの引渡しは平成28年2月を予定しており、報酬の支払は同年3月15日とされた。
X社は、開発に関連する業務のうち、甲社の業務の現状把握及びその改善並びにソフトウェアに対する甲社の要望を確定する作業をY社に委託し、Y社はこれを受託した。
X社が甲社に提示した開発スケジュールでは、Y社が担当する作業は、開発着手後1か月をめどに終了させることになっていた。Y社の作業が終了しなければ、その後のソフトウェアの仕様の確定やソフトウェアの基本設計さらには開発作業やテスト作業を行うことはできない。Y社の作業が遅延すれば、開発全体が遅延することになるため、Y社は、X社からスケジュールどおりに作業を終了させるように厳命を受けていた。
Aは、上記の作業をスケジュールどおりに終了させるためには、A及びY社の従業員Bらだけでは人手が足りないと判断し、Dに対して作業の一部を委託することにした。DはAとともにX社に勤務していたが、その後独立し事務所を賃借して、「ワークスD」という名称でX社を始めとする大手の開発業者の下請や孫請として業務委託を受けて収入を得ていた。Y社とDとの間には「業務委託契約書」(特に「兼業禁止」の条項はない。)が作成され、そこでは、Y社の作業が終了した時点で「業務委託契約書」に定める金額を、Dに対して支払うことになっていた。
Y社が委託を受けた作業の進行スケジュールはAが定め、その進捗状況も厳しく管理し、BらやDの作業が遅れると厳しく指導するなどしていた。
A、Bら及びDは、Y社が委託を受けた作業を行うために、X社の従業員とともに、何度も甲社の事務所を訪れ、甲社の代表取締役、担当部長、エンドユーザーとなる甲社の従業員などから意見を集め、甲社内の意見の調整にも奮闘した。甲社の意見聴取に際して、BらはY社所有のノートパソコンを利用していたが、Dは自分のタブレットパソコンを利用していた。
また、A、Bら及びDは、Y社内の会議室で連日打合せを行い、共同して甲社に対する説明資料などを作成したり、甲社がソフトウェアに対して要求する仕様の内容を取りまとめる書面を作成したりするなどの作業を行った。その際は、BらもDもY社のデスクトップパソコンを利用していた。
Dは、Y社までは自分の自動車で移動していたが、Y社から甲社まではY社の自動車に同乗して移動していた。
Aの進行管理が良かったため、Y社は、X社の定めたスケジュールどおりに作業を終了することができた。
以上の事案について、以下の設問に答えなさい。
〔設問1〕
Y社は、A、Bら及びCに対して毎月金員を支払う際に、所得税を源泉徴収する必要があるか。源泉徴収制度について概要を述べた上で、それぞれについてY社との間の法律関係に留意しつつ検討しなさい。
〔設問2〕
Y社は、Dに対して金員を支払う際に、給与所得に係る所得税を源泉徴収する必要があるか。Y社との間の法律関係に留意しつつ検討しなさい。
2.出題趣旨
本問は、会社が代表取締役、従業員、顧問弁護士及び業務委託をした外注先に金銭を支払う場合の源泉徴収の要否と、法人税法上の収益の帰属年度に関する原則的基準及びソフトウェア開発のような長期請負契約に適用される例外的基準について問う問題である。本問において検討すべき論点は多く、その1つ1つはどれも重要な問題点を含んでいるが、特定の論点だけに比重を置いて解答するだけでは必ずしも高得点は望めない。全体のバランスを見ながら、時間内に、必要な情報を的確かつ簡潔に説明することが大切である。設問1は、「給与所得」と「事業所得」の区分が源泉徴収制度との関係で問題となることが多いことを踏まえた出題である。
まず、源泉徴収制度に関する基本的理解を問うている。次に、「給与所得」と「事業所得」の区分に関して、最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決(民集35巻3号672頁)を踏まえて、所得税法第28条第1項の「給与所得」の概念及び同法第27条第1項の「事業所得」の概念を明らかにしつつ、両者の区分についてどのような基準を定立するのか、その基準に則して具体的な事案について矛盾なく判断できるのかを問うている。
出題において法律関係に留意することとしたのは、課税関係が私法上の法律関係を基礎としていることを踏まえたものであり、私法上の法律関係を基礎にして課税関係をどのように判断するのかを試すものである。
設問2は、設問1で定立した基準を比較的複雑な事案に適用する能力を試すものである。
問題文に現れたDを取り巻く諸事実は、A、B、Cとそれぞれ共通する部分であり、給与所得の要件に親和する側面がある一方で事業所得の要件に親和する側面もある。そのため、自分の導いた結論に説得力を持たせるためには、自分の主張に有利な事実だけを抽出して評価するだけでは不十分であり、不利な事実についても評価することが求められる。
3.採点実感等
公表済みの「出題の趣旨」の中で述べた主要な論点に即して、所得税法及び法人税法の基本的事項に関する理解の正確さ、関連条文の解釈適用能力及び事実に対する評価能力を重視して採点した。ただし、結論の当否そのものよりもその結論に至る論証を重視した。採点結果の実感は以下のとおりである。
全体の実感として、まず、記述のバランスの悪い答案が予想以上に多く存在した。本問では記述すべき事項が多い。そのため、余事記載が多かったり、特定の事項のみを多く記述すると必然的に他の事項の記述が少なくなり、その事項の記述に与えられる点を得られなくなる結果となる。結果的にみると、全体をバランス良く書いている答案は総じて高い評価を得ており、内容的には短くてもポイントを押さえた答案は一定の評価を得たが、他方、論点相互の記述に大きな落差があったり、未完成だった答案は総じて低い評価となった。
次に、最高裁判例に言及しない答案が予想以上に多く存在した。本問では二つの有名な最高裁判例があり、解答においても、当然これらに言及されるものと予想していたが、二つの判例の両方に言及していた答案はほとんどなかった。法律家にとって関連する最高裁判例を前提とすることは当然であって、無視することは許されないものである。有名な判例については答案で言及すべきである。
次に各設問について言及する。
設問1のうち源泉徴収制度の概要について、制度の内容などについて正確に説明できていない答案が多かった。例えば、「徴収する制度」、「受給者に代わって納税する制度」、「給与所得者」に関する制度、個人事業者に適用されない制度などとするものである。
制度の理解は基本であるので、正確に表現できるように留意すべきである。
答案では、次に給与所得と事業所得の定義とその区別の基準を明らかにした上で、その基準に基づきA、B、Cの所得の種類を判断し、源泉徴収の要否を判断することになる。最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決(民集35巻3号 672頁)は「給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指 揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付」としているから、これを前提とする限り、給与所得かどうかを判断するには支払者と受給者との間の法律関係が何かをまず検討する必要がある。この点は、設問においても、「それぞれについてY社との間の法律関係に留意しつつ検討しなさい。」と明示していたところである。また、その法律関係が同じ委任ないし準委任契約でも所得の種類が給与所得と事業所得とで分かれる場合にはその理由について説明する必要があった。
しかし、給与所得及び事業所得の説明と区別について、定義を記述していない答案が予想以上に多く存在していた。ただ事実だけを摘示してからA、B、Cの所得の種類について結論のみを記述するだけで、定立した基準に基づき事実を評価して結論を導くという基本的な思考のプロセスを示していない答案が予想以上に多く存在していた。本問の特にCについては給与所得に該当することが明らかな事案ではないから、給与所得や事業所得の定義をしないでいきなり事案について判断することはできないはずである。結論のみを記述するだけでは説得力が全くないことに留意すべきである。
事実を法的に分析して結論を導くには法的三段論法という形式にのっとった思考のプロセスが必要不可欠であり、答案でもそのような思考をする能力があることを示さなければ高い評価を得ることはできない。答案においてはもっと「法的な分析、構成及び論述の能力を有する」(司法試験法第3条第2項)ことをアピールすることが重要である。
次に、A、B及びCに関する源泉徴収の可否について、まず、そもそも法律関係の内容を説明していない答案が予想以上に多く存在した。法律関係に留意することにした出題の意図を把握できていなかったものと思われた。
また、Aについて「委任だから」給与所得であるとしながら、Cについて「委任だから」事業所得であるとするような、Aに関する説明の論理とCに関する説明の論理が一貫していない答案もあった。
答案の中には、Aについて、「役員(法人税法第2条第15号)に該当するから」、「役員報酬(法人税法第34条第1項)に該当するから」、「定期同額給与(同項第1号)に該当するから」、「定期同額給与に該当し損金に算入されるから」給与所得(所得税法第28条第1項)に該当するという趣旨の説明しているものがあった。
しかし、一般に法人税法の規定に該当すれば所得税法第28条第1項の給与所得に該当するということはできないので、上記の説明は所得税法第28条第1項を解釈適用する思考としては誤っている。また、損金に算入されることを根拠とすることは、読む側に損金に算入されない場合は給与所得にならないと考えているのかという疑問を抱かせることになり、やはり説得力に欠けるものといえる。
同様に、毎月定額の金員を受け取っていることを理由に給与所得に当たると説明する答案も、ピアノ教室で生徒を教えて定額の月謝を受け取っている場合など、毎月定額の金員を受け取っている場合は他にもいろいろあり得るが、その全てを給与所得であると考えるのかという疑問を抱かせる。
理由を考える場合、それを一般化した場合には疑問が生じないかを考慮する必要がある。一般的にそのような判断をすると他に多くの不合理な事案が発生するような場合には、当該事案の説明としては一応筋が通る場合であっても、理由の内容に対して読む側に疑問を感じさせる結果となる。それでは結論に対して説得力に欠けることになるので注意が必要である。
Cについては、「顧問契約」の性質を明らかにしている答案が余りなかった。「顧問契約」というだけではそれがどのような性質の契約なのかが明らかにならないので、当事者間の法律関係を明らかにしたことにはならないというべきである。
またCは(それから設問2のDも)、Bとは異なりYと雇用契約を締結したわけではなく、またAと異なりYの機関でもない。Cは(それからDも)Yとは独立した経済主体である。そのためCが受け取る顧問料は事業所得と評価されてもおかしくないはずである。そのような事情があるにもかかわらず、顧問料を給与所得と判断する以上は、「事業所得ではなく給与所得であること」を説明しないと説得力に欠ける。逆に、顧問料を事業所得と判断するには、上記最高裁判決(弁護士顧問料事件)がある以上、「給与所得ではなく事業所得である」ことを説明しないと説得力に欠ける。
したがって、Cについてはいずれにしても給与所得と事業所得について言及する必要があった。
さらに、Cについて、依頼された法律相談などでCが時間を拘束されているので給与所得であると評価する答案もあった。しかし、およそ債務者は債務の履行のために時間を拘束されるのであるから、このような理由で時間的拘束を認めて給与所得であると評価すると債務者は常に給与所得者になりかねないのではないかという疑問を抱かせる。この点についても理由の内容について慎重に考えてほしかった。なお、顧問料を事業所得とした場合、弁護士報酬の源泉徴収について気が付かなかった答案が多かった。源泉徴収を給与所得者固有の制度と誤解していると思われる答案が多かったことの帰結だったのかもしれないが、もう少し制度全体を広く見てほしかったと思う。
設問2については、多くの答案で自分の判断に不利に働く事情への言及が不十分であった。
例えば、「本問では、(従属性を基礎付ける事情)があるので従属性が認められる(と思われる)。しかし、(独立性を基礎付ける事情)があるので独立性が認められる。したがって、事業所得である。」、あるいは「本問では、(独立性を基礎付ける事情)があるので独立性が認められる(と思われる)。しかし、(従属性を基礎付ける事情)があるので従属性が認められる。したがって、給与所得である。」という構成をしているものがあった。
しかし、これではどちらの考え方に立っても記述する内容はほぼ一緒であり、結論に対して説得力に欠けることは明らかである。自分の判断に対して説得力を持たせるには不利な事情をただ摘示して並べるだけでは足りない。自分の判断に対して不利に働く事情の持つ意味を減殺する必要がある。不利に働く事情の持つ意味を減殺するには、このような事情があっても独立性(または従属性)を認める上で障害にならない理由を説明する必要がある。それゆえ、独立性を認める立場であれば、従属性を基礎付ける事情があっても独立性が否定されない理由について、また、従属性を認める立場であれば、独立性を基礎付ける事情があっても従属性が否定されない理由を明らかにする必要があったのである。
答案の中には、自分の判断に不利に働く事情について、創意工夫を凝らして減殺しているものもあり、このような答案の評価は高くなった。
4.解答例
設問1について
1.源泉徴収制度の概要
(省略)
2.源泉徴収の必要性
(1)所得分類
本件では、A、Bら、Cに支払われる金員について源泉徴収の必要性を判断するうえで、その金員の所得分類が問題となる。
そして、事実関係を踏まえると、それらが給与所得(同法28条1項)にあたるのか否かが問題となる。そもそも、給与所得とは、非独立的に、従属的な労務提供の対価として稼得された所得である(弁護士顧問料事件判決)。なお、従属性の要件は一般に外形的に明らかであるため、手がかりとして機能するが、従属性が決め手とならない場合には、非独立性の要件が重要となるという関係にある。また、裁判例においては、報酬支払いの基礎となる法律関係の性質によって、給与所得への該当性をストレートに判断する枠組みは採用されていないと考える。以下、A、Bら、Cへの金員の支払が給与所得への該当性を検討する。
まず、Aは、Y社の代表取締役としての立場で金員を受け取っており、Y社との法律関係は、委任関係である(会社法330条)。AはY社を設立しており、一人株主であると認められる。このため、Aは、誰に対しても従属的な立場には立たない。しかし、Aは、Y社のために業務執行しており、Y社への労務提供の対価として毎月定額の金員を受け取っている。受け取る金員の額は、Aの業績などによって変動せず、Y社の計算と危険に依存している。このため、Aの非独立的な労務提供の対価であると考えられ、給与所得に該当するものと考える。
次に、Bらは、Y社の雇用契約に基づいて、金員を受け取っている。雇用契約の下では、Bらは、従属的な立場に置かれている。また、Bらは、雇用契約で決められた給料の支払いを受けていたものと認められ、Bらは、自己の計算と危険により、給料を受け取っていない。したがって、Bらは、従属性と非独立性の要件を満たし、支払われた給料は、給与所得に該当するものと考える。
そして、Cは、Y社との間の顧問契約は、委任関係に基づく法律的助言を提供である。この点、AがCの事務所を訪問し、相談しており、CがAの指揮命令下に入るなど、従属性は認められない。また、法律的助言に間違いなどが認められれば、Cは、その金銭的・社会的責任を問われる立場にあり、自己の計算と危険において独立的に行われている業務と認められる。このため、Cによる法律的助言は、Cの弁護士業務の一部として提供されており、従属性と非独立性の要件を満たさず、給与所得に該当しないと考える。そして、Cが自己の計算と危険で、反復継続して提供する業務であるから、事業所得(同法27条1項)に該当すると考える。
なお、委任関係という法律関係からストレートに所得分類を決めるべきではなく、従属性と非独立性の要件を、事実関係に照らして検討し、給与所得への該当性を決めるべきであるから、AとCは、ともに、Y社と委任関係であるものの所得分類は異なると考えた。
(2)Y社による源泉徴収の要否
まず、AとBについては、給与所得の源泉徴収義務がY社に課される(同法183条1項)。そして、Cについては、弁護士に関する報酬の源泉徴収義務がY社に課される(同法204条1項2号)。
設問2について
Y社は、Dに対して支払う金員について給与所得に係る源泉徴収義務を負うのか(同法183条1項)。Dに対する支払いが給与所得となるのか問題となる。
なお、DとY社との法律関係は、請負関係であると考える。なぜなら、Y社は、X社が甲社から請け負った開発案件を、X社からのスケジュールどおりに終了をすることを厳命されており、DとY社との業務委託契約書には、報酬がY社の作業終了時点で支払うこととされており、仕事の完成が約束されているからである(民法632条)。ただ、前述のとおり、法律関係からストレートに給与所得への該当性を判断すべきではないため、以下、Dの業務提供態様を踏まえ従属性と非独立性を検討する。
Dは、AとBらと共に、甲社を訪問し、意見収集、意見調整に関与している。また、Dは、AとBらと共に、Y社の会議室で連日打ち合わせを行い、資料作成、仕様書の作成等の作業に従事している。Dは、この際、Y社のデスクトップパソコンを利用している。また、Dは甲社に訪問する際は、Y社の自動車に同乗している。これらの事実関係に照らすと、Dは、Y社のチームの一員として、Y社の指揮命令の下、従属的な立場で、業務に従事しているようにも思われる。
他方で、Dは、甲社での意見収集にあたっては、自分のタブレットパソコンを利用しており、Y社までの移動には自分の自動車を利用していた。このため、Y社のチームの一員として行動したことは、Dが仕事を完成するうえで、効率的な方法を、Dの意思で選択した結果であり、Dの従属性を示すものではないとも考えられる。このため、従属性の要件が決め手とならない事案であり、非独立性の要件を精査する必要がある。
Dは、自らの名義で、Y社以外から業務委託を受けて収入を得ている。また、Y社との業務委託契約書でも兼業は禁止されていない。さらに、Dは事務所を自らの名義で賃借している。これらのことを踏まえると、Dは、自己の計算と危険により、Dワークスという名称で独立した事業を営んでおり、Y社への業務提供も、その一部として行われていると認められる。したがって、Dは非独立性の要件を満たさないと考える
以上より、Y社からDに対する金員の支払いは、給与所得ではないため、給与所得に係る所得税の源泉徴収の必要はないと考える。
5.ケースブック租税法〔第6版〕との関係
採点実感等において、かなり具体的な解説が行われており、勉強になった。勉強したところでは、「少なくとも裁判例においては、報酬支払いの基礎となる法律関係の性質によって、給与所得に該当したりしなかったりする、というストレートな判断枠組みは採用されていないと考えるべきであろう」との指摘がある(佐藤〔第3版〕161頁「▶︎給与所得発生の基礎となる法律関係」参照)(「§223.01 給与所得の意義⑴ ––––– 事業所得との区別」「2.給与所得の意義」⑷(ケースブック租税法〔第6版〕219頁))。このため、法律関係にふれることを問題文が要求する理由を、十分に汲み取ることができなかった。解答例では、なるべく、関連性をもたせながら、ふれようとしてみた。
また、勉強したところでは、「給与所得とは、従属的な労務提供により、非独立的に稼得された所得である」と考えられる。そして、従属性の要件が必ずしも決め手とならない場合には、非独立性の要件が重要となってくる。(佐藤〔第3版〕161-164頁参照)なお、「この説明からは、従属性の要件は不要であるように見えるが、非独立性よりも従属性の方が、一般に外形的に明らかであるという事情を考えると、思考の節約という点では、「従属性」の点も、なお、有益なメルクマールだというべきである。」とされる(佐藤〔第3版〕166頁参照)。(「§223.02 給与所得の意義⑵ ––––– 雑所得との区別」「4.給与所得の判断要素」(ケースブック租税法〔第6版〕228頁))
これらの点を踏まえて、Dについて、従属性は決め手にならないとしたうえで、非独立性の検討を行うかたちをとった。
なお、源泉徴収制度は、「§250.01 源泉徴収の法律関係」と「§250.02 支払いの無効と源泉徴収義務」で勉強する予定であるため「(省略)」とした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
