
最悪で最高なチリサーモンの渦にハマる
四六時中、チリのサーモン産業について考えている。それもそのはず。文献を読んだり、事業者や有識者と話す毎日なんだから。一昨日も地元紙で6年サーモン産業を取材してきた業界通の記者と情報交換。ついつい話が盛り上がり2時間弱も話し込んでしまった。自分でも、何でこんな誰も興味が無いであろうテーマを取材しているのか分からなくなる。テーマ自体に新規性はなく、今更感が否めない。とはいえここで歩みを止めるわけにもいかない。今では、このどうしようもない産業に魅力すら感じてしまっている。最悪で最高な産業のマーブル模様の渦に完全にハマってしまった。現地取材も折り返した感触があるので、その最高と最悪を少し整理しておこう。
サーモン最悪!

2016年、チリにおけるサーモンの養殖は個人的に最悪な産業だった。赤潮が大発生し、大量死したサーモン39942tのうち、9000tを事業者がチロエ島沖約120kmに捨てたからとか、そういう理由じゃない。
趣味のカヤックを提げてチリの首都・サンティアゴに降り立ったのは、16年12月だった。チリ領パタゴニアの沿岸を旅行する計画だった。これは自分にとっては夢みたいな旅行で、カヤックをやる人だったらみんなこの計画に沸き立つだろうと思う。大小無数の水路が島々を分断するフィヨルドの中を、カヤックで分け入っていく。入江の奥は鏡のような海面と圧倒的な静寂が、イルカやクジラ、トドといった海の哺乳類の呼吸音、人の侵入を観察する無数の海鳥の声が放つ躍動感を際立たせる。ひとたび主要水路に出ると、ひしゃげた木々、シワ寄せられた海面によって、暴風を思い知る。そういう野性味に満ち溢れた世界が待っているはずだった。

実際にカヤックで海をいくと、確かに前述した全てがパタゴニア(チリ領北域)にはあった。それまでに経験したことがない世界を、毎日興奮しつつ穏やかに500kmほど一人で旅行した。ただ野生の世界だったからこそ、人工物の存在はひときわ目立った。特にそれは養殖業に紐付くもので、視界を埋め尽くすムール貝を吊るしたブイに何度も進路変更を強いられ、サーモンの生簀に横付けされたハウスボートの発電機の音はせっかくの静けさを破って、シュラフの中でぼくはがっかりした。毎日ではないけれど、そういうことを何度も経験するうちにチリの養殖業はぼくの中で最悪な産業に分類されつつ、頭の中にはナショナルジオグラフィックのウエブサイトに掲載されていた赤潮の写真が浮かんでいた。
サーモン最高!

サーモン産業が「最高」の舞台に踊り出るまでに、そう時間はかからなかった。
カヤック旅行の終点は、氷河を抱くサン・ラファエル国立公園近くの湾内にあるグロッセ港に設定していた。ところが、そのグロッセ港にどうしてもたどり着けない。港にたどり着くには迷路のような葦原を超えねばならず、そのフィヨルドの縮尺版のような葦原が描く地図は絶えず変化し、初めてやってきた探訪者に正解である道を見いだすのは困難だった。小さな湾で右往左往し、情けなかった。
グロッセ港に到着する予定日の朝には、最後の食料である粉末スープを飲み干していた。午前中、じんわりと変化していく葦原の景色に「お、ここが正しい道筋だな」と何度もアハ体験をしながら迷いに迷ったあげく、強風が吹き始めた午後にはすっかり疲れ果て、葦の茂みに身を収めた。野営した海岸に戻り、とりあえず明日からのことを考えようと再びカヤックを漕ぎ始めたときに忽然と現れた一隻の小型船。思わず足元に収めていドライバッグの中から、100均で買った緊急用ホイッスルを取り出して息を吹き込み、同時にパドルを掲げて左右に振った。明後日の方向に進んでいた船が、カヤックに向き直った。

船内から何人かの男が姿を現した。「グロッセにいくなら、葦原の真ん中を進まないと着かないよ。カヤックごと乗せていくこともできるけど、どうする?自力でいく?」とメガネをかけた男が言った。少し逡巡したのち、事実上の「救助」をお願いした。カヤック内の荷物を端から男たちに渡し、カヤックを船に引き上げた。メガネの男が右手を出して「ホルヘ・ウィルソン」と名乗った。サーモン養殖会社クプケラン(現クック・アクアカルチャー・チレ)の海面養殖部長で、これがサーモン養殖との初めての直接的コンタクトとなった。ウィルソンはリンゴとスプライトを差し出し、食べるように勧めた。驚異的にスカスカなリンゴは、今まで摂取してきたどんな食べ物よりも体に染み渡った。
聞くとその日は週に2回、シフト制で働く従業員たちが入れ替わる日で、船を捕まえられたのは本当に偶然だった。葦原の中の正しい水路は、満潮時のみに現れるもので、なるほど迷ったわけだと納得した。さらにグロッセ港から最寄りの街までは90kmの未舗装林道で、カヤックを畳んでしまえば50kgの荷物を抱えた身動きの鈍い旅行者になってしまうぼくには途方もない道のりだった。ほかの乗組員が恵んでくれたサンドイッチやクッキーを咀嚼するうちに、荒れた林道を走る紺色のミニバンに揺られるうちに、サーモン養殖は「最悪」の足枷を引きずりながら、どんどん「最高」への階段を登っていった。そのときからチリサーモンは、個人的により深く知らなければならない対象へと変わってしまった。
サーモン最高!part2

帰国して金もなくなったので、働くことを急いだ。慢性的な人材不足状態にある経済紙を発行する新聞社に、事情も知らないまま入社し、記者として働き始めた。仕事自体には充実感があり、給与にも不満はなく取材を繰り返したが、結局は2年で辞めた。理由はもちろん、チリ滞在。就職した当初のことは思い出せないけれど、もしかしたら今回のチリでの取材活動のために、新聞社に入社したのかもしれなかった。少なくとも勤務開始から1年経ったころには、国会図書館で文献を調べたり、アマゾンで関連書籍を購入したりして、情報を集めていたと思う。
チリに到着してすぐ会いにいったのは、ウィルソン氏だった。彼の助けを借りながら、サーモン産業のメインプレーヤーである養殖事業者や、サポーター的な飼料会社、種苗会社を取材した。地元紙「エル・ジャンキウエ」はサーモン関連の記事を毎週掲載していたので、記者に直接連絡をして情報をもらった。別ルートでも養殖事業者に取材を申し込み、孵化から出荷までが、どのようなプロセスを辿っているかを直接目にし、仕事に携わる人たちともたくさん話した。「チリサーモンは抗生物質まみれだから、現地人は食べない」という趣旨のネット記事とは違い、地元でそこそこ金のある人の中には、サーモンを消費する人がたくさんいる。消費の選択は、抗生物質が人体に与える影響についての知識からではなく、食文化と価格にある。肉の方がサーモンより断然安い。

知れば知るほど、日本にとっては輸入品目の一つでしかないサーモンには多くの人々の暮らしが紐付いていた。生簀のメンテナンス会社に勤務する潜水士と父の日を祝い、半径50kmに街がない隔絶された養殖拠点で料理人として働く同年代の若者と一緒に酒を飲み、ときには深夜まで酒場で踊り、冬だというのに汗だくになった。そうした日々を過ごすうちに、サーモン産業はぼくの脳内で最高の舞台に立ち、その足かせをガチャガチャと外しにかかっていた。
サーモン最悪!part2

ただ、サーモンが「悪しき産業」のレッテルを振りほどくにはまだ早い。そもそもの始まりとして、サーモンはチリにとって外来種であるという前提がある。黎明期以降、養殖生簀から逃げ出したサーモンはすっかりパタゴニアに帰化してしまった。18年には、たった一つの拠点から80万尾のサーモンが大脱走した。これがパタゴニアの自然史のなかで、ポジティブな出来事になり得るだろうか。なり得るはずもない。産業の代償としてどうかといえば、養殖事業者が報告した流出サーモンの動向を説明する報告書や、外来種に関する専門書を読んでいるが、まだ自分なりに腑に落ちる答えにはたどり着いてない。
チリのサーモン養殖会社が外資系企業に買収されていったように、サーモン万歳派がぼくの脳内議決権の過半数を抑えようとしていたので、最近は意識的に批判的な文献を読んでいた。そうするとやはり、産業の功罪は認めざるを得なく、手放しで「サーモン最高!」とは叫べなくなってくる。例えば、サーモンの排泄物や食べ残しによる海底汚染が指摘されて久しい現在でも、事業者が海底に石を投下しまくって汚染を上書きするような行為が行われ、現地で問題視されている。
最高と最悪の渦中で

最高と最悪は共存できる。実際にはそんな極端な二項対立ではなく、良い点もあれば是正すべき課題もあるよね、くらいの感覚が建設的な塩梅じゃないかと考えている。環境汚染のリスクをゼロにできない一方で、確かに人々の暮らしに灯る明かりがある。搾取を想起させる外資系企業の太った幹部だけではない。プラントで輸出用サーモンをひたすら捌くおばちゃんにも暮らしがある。
プラントで20年働いてきたというノルファ・アルバラド氏は「すぐに辞めていく人がいるのも確か。でも、いつでも学ぶ姿勢を忘れてはいけない。私はどんな風にしたら良い仕事ができるかを好んで学んできた。それを会社も評価してくれていると思う」と話した。
サーモン産業は劣悪な労働環境をテクノロジーで乗り越えてきたし、生簀に設置したカメラで常にサーモンの様子を観察しながら給餌することで、効率の良い肥育を実現すると同時に食べ残しを減らし、環境への影響も軽減してきた。先日、産業の黎明期を知る人物から見せてもらったサーモン導入時の写真に写る養殖生簀は、本当に心もとない代物だった。強風に煽られれば海に落ちるわけだ。
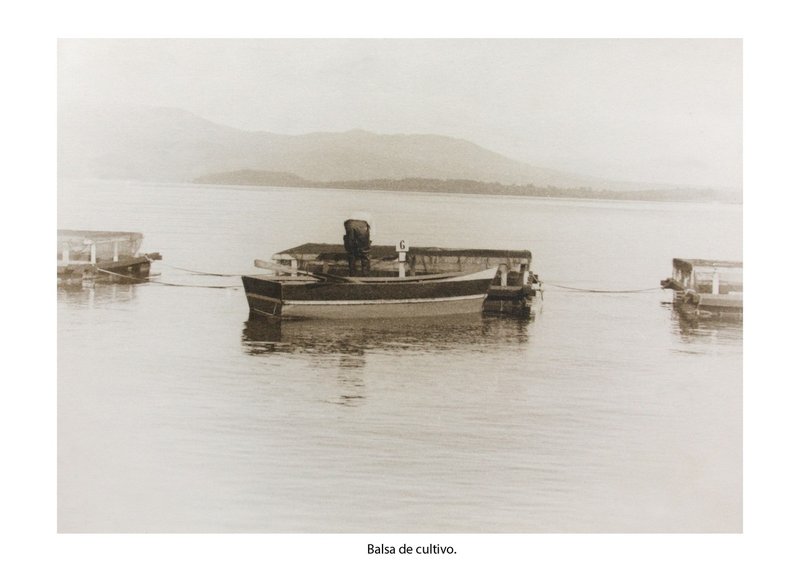
ノルウェー、アメリカ、そして日本も加わりグローバルな潮流のもとで導入されたチリにとっての「外来産業」をやめるという選択肢はそもそも存在してこなかったに違いない。数多の活動家がその所業を糾弾しても、なんとかそれを改善しようとしてきた。抗生物質の使用量は減少しているし、「サーモン養殖のために大量の魚が犠牲になっている」と言われてきた魚粉も世界的には生産量が下がってきている。地域住民を置き去りにしてきた産業の中には、積極的に地域コミュニティーとのコンタクトを図り、教育・就労の機会を提供している事業者も存在している。
これからも批判は産業の監視役として機能していくだろうし、真面目な事業者はそれを克服しようと努力していく。チリサーモンを現地で取材する中で、この産業はいままでとは違った味わいを持ち始めた。フレッシュだったサーモンは、噛めば噛むほど味が出る鮭とばのように熟成してきた。なんというか、チリのサーモン産業には「人間の仕業」という言葉が良く似合う。それは決して批判的な意味だけではなく。少なくともぼくは、この産業が持つ可能性を感じている。万人を魅了してきたパタゴニアの自然と調和した産業になれたなら素晴らしい成功事例になると、割と本気で思っている。

もしよかったら、シェアもお願いします!
