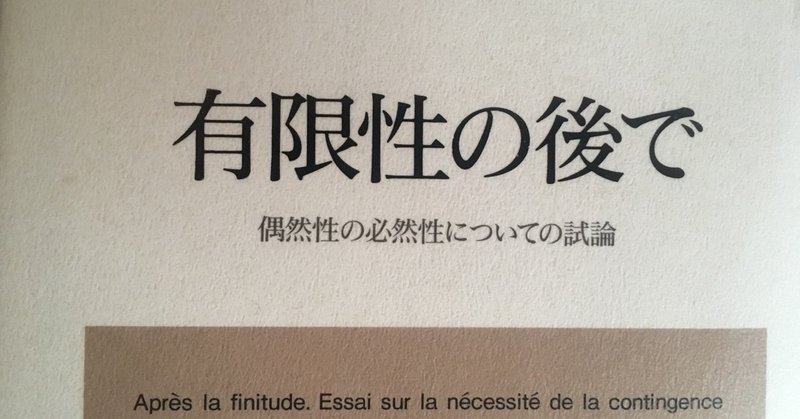
有限性の後で/カンタン・メイヤスー
しばらく前から続いてる新しい哲学書を読み進める私的プロジェクト。
新たに読み終えたのは、思弁的実在論(Speculative realism)の地平を開いたカンタン・メイヤスーの『有限性の後で』だ。
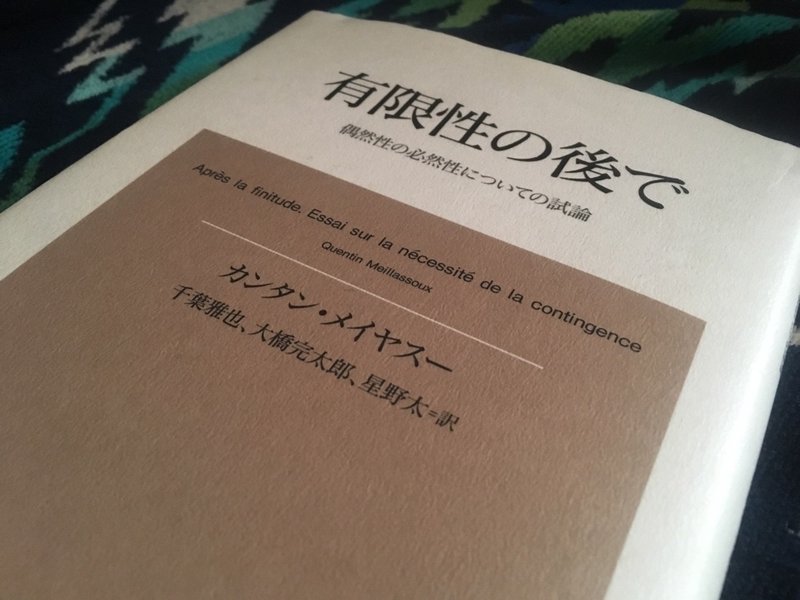
2006年に書かれたメイヤスーの処女作である本書では、カント以降の哲学が、「相関主義[correlationisme]」に支配されているとされ、それとは異なるあり方として思弁的実在論が提唱されている。そのことをメイヤスーは非常に数学的・論理的な方法をもって証明していく。
前提はこうだ。
カント以来の近代哲学の中心概念が相関[correlation]になったのはいかなる点においてであったか、ということを把握できる。私たちが「相関」という語で呼ぶ観念に従えば、私たちは思考と存在の相関のみにアクセスできるのであり、一方の項のみへのアクセスはできない。したがって今後、そのように理解された相関の乗り越え不可能な性格を認めるという思考のあらゆる傾向を、相関主義[correlationisme]と呼ぶことにしよう。そうすると、素朴実在論であることを望まないあらゆる哲学は、相関主義の一種となったと言うことが可能である。
ここでメイヤスーは、相関主義の特徴として、「私たちは思考と存在の相関のみにアクセスできるのであり、一方の項のみへのアクセスはできない」という形で、人間と世界(物自体)との関係がどちらが欠けても成り立たないような状況で規定してしまうことを指摘している。カントが物自体に人間は近づけず、認識することはできないが、物自体はかならずあるとしたのは、よく知られていることだが、カント以降のより「強い相関主義」においては、認識できない存在(物自体)を考えること自体、不可能であると主張するのだと、メイヤスーは指摘している。
ようはポストカントの相関主義できない哲学では、次のようなことが主義される。
思考不可能なものが不可能であるということは、思考不可能である。

これに対して、メイヤスーが思弁的実在論の立場で主張するのは、こうだ。
私は、思考不可能なものは思考できない、しかし私は、思考不可能なものが存在することは不可能ではない、とは思考できるのである。
メイヤスーがこう考える必要があると考える理由は、僕らにはむしろ、当然であるように思うことだ。
相関主義のように、人間と世界との関係がどちらが欠けても成り立たないというのであれば、メイヤスーが「祖先以前的」と呼ぶような、人間が誕生する前の宇宙論的、進化論的世界のことは考えることもできなくなってしまう。だとしたら、単純に、科学が現に行なっているそうした「祖先以前的」な人間がまだ存在していない時代についての思考はなぜできているのか?を相関主義的哲学は説明できない。
いかなる条件のもとで、祖先以前的言明が意味を保持するのか。けれどもこの問いがもうひとつの問いを覆い隠していたことも、私たちはよくわかっている。その問いはより根源的で、最初の問いの真の射程を解放する--すなわち、祖先以前のものについての知を作り出す経験科学の能力をどのように考えればいいのか、という問いである。というのも、祖先以前性を通じてここで問題になっているのは、まさしく科学の言説、とりわけ、そうした言説を特徴づけている数学的な形式だからである。したがって私たちの問題は次のようになる。人間のいない世界、現出に相関しない物や出来事で満ちた世界、世界への関係と相関しない世界、こうした世界が数学的言説によって記述可能になるのは、どうしてなのか?
こうした問題だけではない。
祖先以前的なものを考えられない、人間の存在を前提としてしか思考は不可能であるとしてしまうということには、もっと根本的な問題さえある。
それはつまり、相関主義的な考えでは、人間は自分の死のこと、自分が存在しなくなることさえ、思考できなくなってしまうという問題だ。
私が自分を可死的と考えるには、私の死が実際に起こるためには、私の死はそれについての私の思考を必要としないのでなければならない。そうでなければ、私が自分をもはや存在しないものとして考えるためには、私が存在し続けるという条件においてのみ存在しなくなることができる、というのでなければならない。これは、他界することなく無際限に死に瀕した状態であり続けることができるというようなものである。
相関主義的な哲学は、それ以前の形而上学的な哲学が前提とする、絶対的な存在を極限まで否定する。神を代表とした独断的な存在を否定しつくすために、あくまですべてを相関的な関係においてのみ存在し、思考可能なものであると主張する。
その結果、祖先以前性の問題や死後に関する思考の問題が生じるのだが、さらにそれは結局、そうした思考を哲学の外に置いてしまうという結果をもたらした。人間誕生以前の問題は、科学や数学の領域に任せっきりになってしまったし、一方で、相関主義的な哲学が思考することを放棄した領域が、宗教的なものの回帰という形で思考されるようになっていることをメイヤスーは指摘する。
「思考の脱-絶対化」と見なされる形而上学の終焉は、絶対者への任意の宗教的(あるいは「詩的-宗教的」)信念を理性によって正当化することに存する、なぜなら宗教の信念はそれみずからに立脚するしかないのだから。言い換えるなら、こうなる--形而上学の終焉は、絶対者への権利要求の合理性を放棄した結果として、宗教的なものの激しい回帰という形をとることになった。あるいはまた、こうだ--イデオロギーの終焉は、全面的な宗教性の勝利という形をとることになった。
一方で科学的思考で世界が語られ考えられ、また別の一方で宗教的な思考により世界が語られ考えられる。この2つの正反対とも言えるような思考のあり方をつなぐものが何もないまま、いまの世界はさまざまな対立を生みながら、ギクシャクと動いているのだろう。
哲学者以外がここまで極端で徹底的な相関主義的な思考をすることはないだろう。しかし、科学的な思考と宗教的な思考の分裂をつなぎとめる思考の不在ゆえに一般的なレベルにおいても、この対立の延長にある対立が世の中をギクシャクさせ、世界にさまざまな混乱を生んでいるというのは、確かなことのように思う。
この分裂を生む相関主義の問題を打破するためのメイヤスーの回答としての思弁的実在論が示すのは、絶対的なものをとにかく全否定しようとする相関主義に対して、ただひとつの絶対的なものの存在を示すことだ。けれど、それは決して相関主義が否定した独断的な形而上学が前提としたような絶対者を呼び戻すことではない。
そうではなく、メイヤスーが採用するのは、独断的な絶対者を前提とする形而上学も、絶対者を全否定しようとする相関主義も、ともに思考の基盤に置いていた〈理由律〉=「あらゆるものはこのようであり別様ではないことの必然的な理由をもつ」というもの自体を疑うことだ。
メイヤスーは、次のような形で〈理由の不在〉こそが相関主義の問題を打破する鍵であることを示す。
あらゆるものに内在する〈理由の不在〉を、究極の理由を求める思考が逢着せざるをえない〔思考の〕限界と考えるのはやめて、そうした〈理由の不在〉が存在者の究極の特性である、そうであるしかないのだと理解せねばならないのである。事実性は、あらゆる事物そして世界全体が理由なしであり、かつ、この資格において実際に何の理由もなく他のあり方に変化しうるという、あらゆる事物そして世界全体の実在的な特性として理解されなければならないのである。私たちは、理由の究極的不在--これからそれを非理由と呼ぶことになる--は、絶対的な存在論的特性であり、私たちの知の有限性の印ではない、と考えなければならない。
もちろん、この〈理由の不在〉は、科学的な意味での因果関係などを否定するものではない。あくまでメイヤスーのいう〈理由の不在〉は、人間的な意味での理由であって、人間がそこに理由を見出せなくても、人間がそこに存在するかしないかに関わらず、宇宙は人間以前に誕生できるし、人間が滅亡しようともそれとは無関係に(人間的な理由なく)そこに存在し続けるものがあることを認めるという極めて当然とも言える答えだ(逆に、なぜこれまでの哲学がここに行き着かないのかがわからない)。
理由のなさ、偶然性こそが絶対的なものだ、というのが、メイヤスーの示す答えである。この偶然性を絶対的なものと見ることで、人間はカントが閉ざした物自体へのアクセスが可能になる。
一般に、絶対的なものにアクセスできると主張するあらゆる思考を思弁的と呼ぶことにしよう。他方、何らかの絶対的存在者へのアクセス、あるいは、理由律を介しての絶対的なものへのアクセスを主張するあらゆる思考を、形而上学と呼ぶことにする。あらゆる形而上学が定義において思弁的であるとしたら、私たちの問題は逆に、あらゆる思弁が形而上学であるわけではないということの立証である。つまり、あらゆる絶対的なものが独断的であるわけではないのだ。
スペキュラティヴ・リアリズム。
それは、形而上学や相関主義の理由律に従う方法を転回し、理由がないこと=偶然性それ自体を絶対的なものとしてアクセス可能にすることで、科学と信仰のあいだの溝を生む思想的姿勢だ。
その思想は、理由なき偶然性を絶対とする、非人間中心主義的な思考姿勢であり、その点において、最近紹介したようなデ・カストロのアンチ・ナルシスな人類学、ラトゥールの「物神崇拝」などにもつながるものである。
また、この姿勢そのものが、現在のグローバルな世界、オープンであることやダイバーシティが重視される世界において、ひとりひとりの物事に臨む姿勢であるように思う。それは、外に自分の理由を押しつけることなく、外の示すことを受け入れた上で、ともに行動を起こすことができるか?という点において。
いかなるものにも、今そうであるように存在し、そのようであり続ける理由はないのであり、すべては、いかなる理由もなく今そうであるようではなくなりうるのでなければならない、そして/あるいは別様になりうるのでなければならない。
そう。これが新しい哲学の示す思考姿勢なのだ。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
