
届かない言葉
感じていることを言葉にしようとする時に、うまくぴったりはまる表現がないと感じることがごく稀にだが、ある。
まったく表現を思いつかないという話ではない。いろんな言い方で感じてることを言葉にすることはできる。いや、むしろ、言葉はいくらでも出てくる。それなのに、どんなに言葉を重ねても言い足りないような、ちゃんと真意を言い表せていないような、そんな気持ちになるケースがあるという話だ。本当にごく稀なことだが、そんな風な思いを感じるケースがある。
いつまでも届かない言葉
いろんな言葉で言ってみても、常に自分の感じていることがそこから逃げていくような感覚。そういうシーンでは言えば言うほど、言葉を重ねれば重ねるほど、言葉と感覚のズレばかりが目立ってくる。
そんな時ほど、言葉の記号性を感じることはない。記号は決してそれが示すものそのものにはなり得ないのだということを。
といった言葉と対象のズレをこれ以上にないくらい、うまく表現したのが、モーリス・ブランショの小説だ。
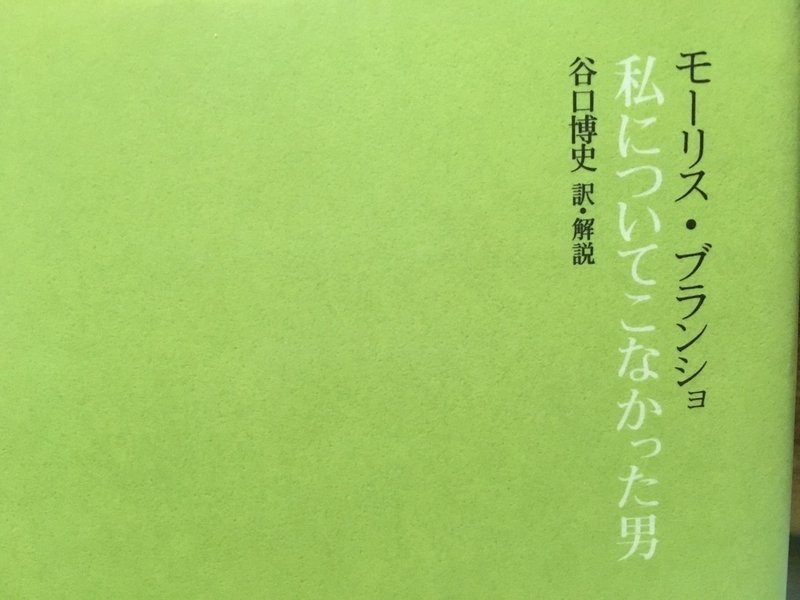
ブランショの小説は、言葉があまりにどこにも届かず、辿り着かず、悪戯に時間ばかりが過ぎていく印象が半端ない。まさに、僕が感じることのある、言葉を重ねれば重ねるほど、対象が逃げる様を巧みすぎるくらいに表現している。
読んでいると、言葉の本来の機能は、対象からズレ続けること、何も指し示せないこと、そのものではないかと感じられてくる。
この感覚はすこし引用しただけでは、なかなか伝わりにくいが、例えば、『私についてこなかった男』の中のこんな文章。
だが、この企てのすべてはただ私ひとりに任せられているのだと私は感じていた。そして言っておかねばならないのだが、私にはそれをやりとおすことなどできなかった。私にはそれができなかったのである。「むしろあなたはうまくやっていた。あなたは驚くべきひとだ。そうでしょう」と彼は指摘した。そう、私はうまくやっていた。だがまさしくそのために、自分が行なっていると私が想像していたことがらのどれもが、ほとんど魅力のないものになってしまっていた。私はうまくやりすぎたのだ。
「できなかった」と言っていたかと思えば、いつのまにか「うまくやっていた」に言葉が滑ってズレていく。ひとつひとつの文章におかしなところは何もないのだけど、すこしずつズレていく様が全体の雰囲気を「どこにも辿り着かない」感に満ち溢れたものにする。
おしゃべりのようなズレが丸見え
全編にわたってこの調子なのだ。
言葉がすこしずつズレていく、この様子は、実は、日常的な会話の中では割とよく起こっていることである。よく全体を通してみると、さっきまでと違う話をしてるよねということも、日常のおしゃべりの時間差のある発言の連なりの中ではさっきの話といましてる話のズレや場合によっては矛盾しあう内容さえ、あまり気にされることはない。ズレや矛盾などはおかまいなしに会話は進んでいくことも少なくない。

けれど、それが文章という形で時間差なく俯瞰できる状態で示されると、途端に、あれ、この話、どうなってるの?と違和感を感じるようになる。ズレてズレ続けていくと、中身がない文章に感じられる。
いや、むしろ常に中身がズレ続けると、中身を示すはずの言葉が常に対象を見失い続けるために機能しているような印象になりはじめるのだ。
主人公が辿り着かない
『アミナダブ』ではすこし事情が違う。辿り着かないのは同じだが、言葉がズレていくせいというより、主人公トマが勝手にズレていくせいだ。

冒頭トマは、ある建物を見つけて、そこに入るかを迷う。
夜はすっかり明けていた。トマはそれまではひとりきりで歩いてきたので、がっしりした身体つきの男がひとり、戸口の前を静かに掃除をするのに余念がないのを見て、愉しい気持ちになった。(中略)「お入りなさい」戸口のほうに腕を伸ばしながら、男はこう言って、進むべき道を示した。
けれど、トマは結局、この「お入りなさい」を受け取っても、その建物に入らず、向かいの建物を気にしはじめる。トマの関心がズレて、当初の計画だった建物に入る計画がズレる。
そして、トマは上の方の階の窓越しにカップルの姿を見つける。
若い女のほうが、この期待に気づいたかのように、片方の手で招き入れるような合図をして、それからすぐさま窓を閉めると、その小さな部屋は暗闇にまた戻った。
この様子に「トマはひどく当惑」する。
女性の仕草は何の意味があったんだろう、と仕草の意味を読もうとする。けれど、その推論もズレる。
この仕草を本当に呼び招いていると考えていいのだろうか。それは招待というよりはむしろ友愛のしるしだ。お引き取りを願うという仕草というふうでもある。
解釈がズレて、ズレて、ズレていく。トマは何を目指しているのか?
何を目指しているのか、いっそうわからなくするのは、トマは結局、当初、掃除をしていた男に「お入りなさい」と誘われて入ろうとした建物とは、通りを隔てて反対側の「お引き取りを願うという仕草」にも見えた合図をした女がいた建物のほうに入っていく。
中に入ると、長くひろびろとした廊下で、驚いたことに階段がすぐには見あたらなかった。彼の計算によると、めざす部屋は4階か、いやたぶんもう1階上にあるはずで、できるだけ早く階段をあがって、その部屋に近づこうと気持をはやらせた。
何に対して気持ちをはやらせるのか、トマ。そのトマのはやる気持ちをいなすように、建物はトマの求める階段の在り処を見せない。

この小説では、女も、男も、建物も、トマを引きつけるような合図を見せつつ、トマが手を伸ばすと、すんでのところで、その誘いの手を引っ込める。トマの意思は常に対象には届かない。
『アミナダブ』は、ひたすらトマの意図が失敗し続ける小説だ。
廊下は果てしもないように思えた。いそいで廊下の端まで行ってから、ぐるりと身をひるがえした。それから出発点に戻って、こんどは歩き方をのろくし、仕切壁にへばりついて、その凸凹のひとつひとつに従って進んだ。この2回目の試みも最初の試み同様に成功しなかった。
ひたすらトマの意図をいなし続ける対象たち。けれど、トマの連続した意図の失敗は、トマの側にも原因がある。彼の欲望がころころ変わりすぎるからだ。上の例でも、はやっていた気持ちはどこへやら、トマの動きはいきなり緩慢になる。
そして、挙げ句の果ては、こうだ。
けれども、最近に探索したときから、ある扉に分厚いカーテンがかかっていて、その扉の上に粗雑な書体で、入口はここです、と書いてあるのを眼にとめていた。つまり入口はそこなのだ。
何ということか、トマは最初のトライで、入口を見つけていたくせに、それをやり過ごしていたのだ。いったい何に気持ちをはやらせていたのか、わからない。その罰か、見つけた入口の取っ手に手をかけてもすでに遅し。入口はトマを入れてはくれない。
手の届かぬ、もどかしさ
モヤモヤ、モヤモヤ。
ブランショの小説は、主人公たち以上に、読者である僕らを拒む。いや、単純に拒むのではなく、誘っておいて、魅了しておいて、手を伸ばそうとすると、するっと手を引いて逃げていくのだ。
このもどかしさ。最初に書いた、いくら言葉を費やしても届いた感じがしないのにそっくりだ。感情はあるのに、それを表現した言葉のズレが、自分自身の感情を裏切る。届かぬ恋心。まさに、そんなのに似ている。
だが私の生活にとって、その帰結は災厄のようなものだった。普通の生活とひとが呼ぶようなものをあきらめねばならなかったというだけでなく、私は自分が何を優先させるか、ということにたいする制御を失ってしまったのだ。それに私は語句にたいして恐怖心を抱くようになり、だんだんと語句を書くことが少なくなっていった。それでいて私の内部では、私に語句を書かせようとする圧力が急速に眩暈のようなものと化していったのである。
これは『私についてこなかった男』の方からの引用。私は書くことこそが常に自分をすり抜けていくように感じられていた「彼」と自分をつなぐ一番有効な方法だ!と言ったすこしあと、すぐに上のように、書くことを嫌がりはじめる。
まったく、このタイトルどおり。いつまでたっても意図の対象となるものは、「私についてこない」。そして、その要因はどうやら意図である言葉そのものにあるようだ。

読んでいる身としては、このいつまでたっても届かぬ意図がもどかしい。でも、それが言葉の本性かもしれないと思うのは、日常においても、ごく稀ではあるものの、そういうもどかしさを言葉が感じさせてくるからだ。
ひとつ前の「読みやすさについて誤解されていること」では、読解のためには文脈の理解が必要だと書いた。相手の文脈を理解することで、何を伝えたいかがわかるようになる。自分の手の届くようになる、と。
けれど、そうじゃないこともあるということだ。ブランショの小説は、その誘惑する言葉そのものが文脈を明かすような仕草をしつつ、手を伸ばせば常にその手から求めるものはすり抜けていく。
ブランショはそれが本来、言葉というものだということを教えてくれているのかもしれない。
届かない言葉は、言葉そのものの本来の姿なのだと。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
