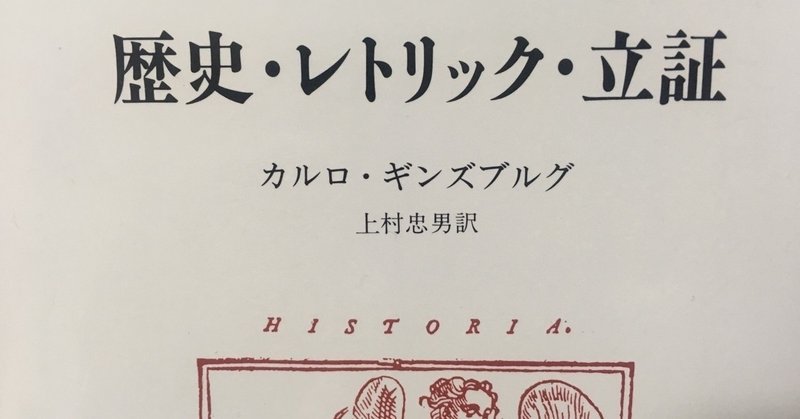
歴史・レトリック・立証/カルロ・ギンズブルグ
あらゆるものがセンシングされ、ログとして残される。誰がいつ何をしたかがあとからいくらでも確認できるようになる、そんな世界に刻一刻と近づいている。
ここでひとつ疑問がわく。
その時代における現代史とはなんなのだろうか?と。いや、その世界が訪れて以降の時代の歴史とはなんなのか?と。
歴史とは、そうしたログがないことによって失われていく過去があるからこそ、成立しているのではないか。
だが、逆にこうも思う。
あらゆるログがありさえすれば、本当に歴史は不要になるのか?と。ただでさえ、数値化されて残されたログをどう読むか、どう解釈するかはそう単純なことではなく、元のログがどんなに事実であったとしても、その読み=解釈は必ず事実に少なからぬ歪みを生じさせるし、その歪みは解釈者ごとに異なるはずだ。
だとしたら、そもそも歴史とはなんなのか?という話になる。それは事実の記述なのか、解釈を含むレトリックなのか、と。

カルロギンズブルグの『歴史・レトリック・実証』という本は、こうした問題を先取りしているように思った。
本書で、ギンズブルグは、歴史学における2つの立場、実証主義的な立場と懐疑論的な立場が、残された過去の資料を前者が過去に対して開かれた窓として扱うのに対して、後者が視界をさまたげる壁として捉えることの対立に対して、その中間的な立場として「歪んだガラス」として歴史的資料をみることを提案している。
つまり、実証主義者の資料を立証としてみようとする立場と、懐疑論者の同じものをレトリックとして疑う立場のいずれでもない立場をギンズブルグは模索する。
ひとつひとつの個別的な資料の個別的な歪みを分析することは、すでにそれ自体構築的な要素をふくんでいる。しかしながら、以下の諸章において明らかにしたいとおもっているが、構築とはいってもそれは立証とは両立不可能なわけではない。また、欲望の投射なしには研究はありえないが、それは現実原則が課す拒絶と両立不可能であるわけでもないのである。知識は(歴史的知識もまた)可能なのだ。
結論からいえば、事実なのか、解釈なのかという単純な二項対立ではないのだということだ。はじめに書いたコンピューティングなログの場合でも、データから何かを読み解く際はもちろん、現実世界で起こったことを何かしらの形でセンシングを行います、ログデータとして残すデータ化の過程も解釈でしかない。ただし、解釈といっても事実と無関係なわけではないことも確かだ。
ギンズブルグはこう言っている。
わたしは歴史的ナラティヴへの現在流行のアプローチはあまりに単純すぎるようにおもう。というのも、それは通常、最終的な文学的生産物のみに焦点を当てていて、その生産物を可能にした調査研究(文書保管所での調査や文献学的研究や統計調査等々)を無視しているからである。だが、そうではなくて、わたしたちは注意の眼を最終的成果から準備的諸段階へと移行させ、調査研究の過程それ自体の内部にあって経験的データとナラティヴ上の束縛とのあいだでとりかわされている相互作用を探査してみなければならないのである。
ようするに、事実と解釈は常にそのプロセスのなかで相互作用をはたらかせ合っているのだ。それを二項対立のようにいずれかの側に寄せようとすること自体がナンセンスなのだと思う。
ガラスは常に歪んでいる。しかし、それは歪んでいようと透明性があり、事実をまったく覆い隠しているわけではない。今後僕らの生活を覆うであろう、さまざまなライフログデータや人々のプライベートやビジネス上の活動のデータも完全な透明なガラスであることはありえないし、かといってまったくのフィクションというわけでもない。
そもそも高解像度のVRはもはや現実と区別がつかないという話もそこに加わる時、ますます歴史とは何か?という話が生じてくるだろう。ギンズブルグが本書中、何度も比較参照しているように、歴史と関連したところがある法廷での弁論や審議なども同様の問題にあたることになる。
つまり、これは記述の問題であり、記録やその扱いに関する新たな問いなのだと思う。事実をわかりやすくシンプルにひとつの答えしかないように考えるやり方は、すべてのガラスが歪んでいる以上、成立しないが、かといって、すべてが歪んだ創作的なレトリックだとこれまた単純化してしまえるほど、その創作的で構築的な記述は完全に人工的なものではなく、歪んでいるとはいえガラスとしての事実とつながる透明性は保持することが求められるのである。
今後、求められる記述はそうした複雑さをデフォルトとして抱えたものになる。記述がそうであれば読解の姿勢にも同等の姿勢が求められるのはいうまでもない。それをギンズブルグはこの2000年に発行された本で先んじて問題視していたのである。
ここ30年ほどのあいだに歴史学と人類学とのあいだの相互交換からいくつもの重要な研究が産み出されてきた。ところが最近、この状況にすこしばかり変化が見られる。2つの学問のあいだの関係はさらに文学理論という第3のパートナーを巻きこみつつあるのだ。
ギンズブルグはこう、いまから20年弱前に言っているのだが、ようするに記述に関する専門領域間の区別が完全に分断された状態から、互いに混ざり合ったような状態に変化してるということなのだと思う。歴史学、人類学、文学という領域がなくなるわけではないが、これまでのように排他的なものではなくなる。
とはいえ、これは何もまったく新しいものというより、古代ギリシア的な知のあり方に回帰しているのだと思う。アリストテレスに代表されるように、古代ギリシアの哲学者たちは領域を想定して思考を展開しつつも、複数の領域をひとりで横断し論じることは、普通のことだったのだから。むしろ、学問領域が厳密に細分化されて互いに不可侵のような関係になったのは近代以降のことでしかありえない。ギンズブルグはここで3つの領域を挙げているが、これが記述の問題である以上、ここにコンピューティングや数学的な記述が統合されはじめているのは現代の僕らなら気づいているべきだろう。
この3人世帯の成立そのものは、歓迎すべき出来事である。が、成果のほうはどうかとなると、これまでのところ、どちらかといえば両義的である。テクストは多くの場合、一個の自立した世界であるとみられている。あるいは、テクスト外的現実とわたしたちには結局のところ規定不可能なひとつの連関によって結ばれているものとみられている。しかしながら、このような懐疑論的結論にはなお再考の余地があるとわたしにはおもわれる。わたしはむしろ正反対のテーゼを論証してみようとおもう。すなわち、テクストの文学的次元についての自覚がより深まれば深まるほど、このことは現実への指示関係を獲得しようという歴史家と人類学者の双方がかつて抱いていた野望にいっそう堅固な地盤を提供するようになるというのが、それである。
文学との関係が強化されるにつれ、歴史への懐疑論的な視点もつよくなったことをギンズブルグは本書で伝えている。だが、ギンズブルグの立場はこの引用でもわかるように真逆で、文学との関係が強化されれば本来、事実と記述の関係はより制御可能性を増して良いはずだというのだ。
このギンズブルグの思考の延長線上にこそ、今後のAIやXR的なものと歴史的なものの捉え方を置いてみる必要があるのではないか。人が関与しない記述がますます増えてくる時代において、世界と人との関わり合いの事実を探る歴史(あるいは人類学)というものの見方の意味はこれから増してくるのではないかと思う。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
