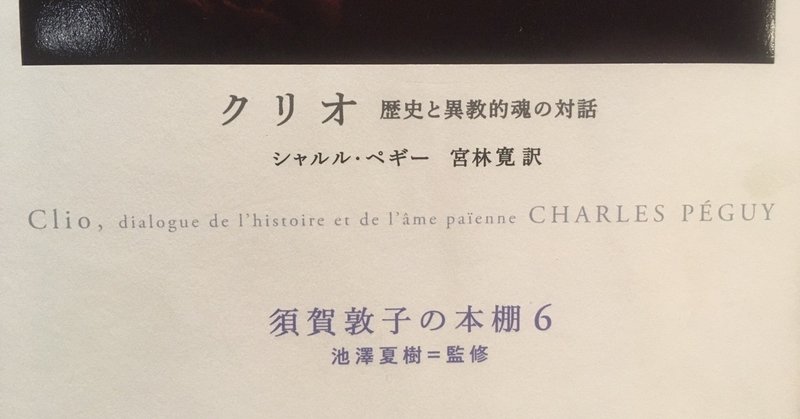
クリオ 歴史と異教的魂の対話/シャルル・ペギー
昨年の秋くらいからだろうか。
読む本の雑多性が増している。
面白そうと思えればジャンルなど気にせず読んでいる。特に読んでいる本のなかで紹介されて興味をもった本があれば、その瞬間にamazonで調べて購入することも多い。
残念ながら絶版になってる本も多いのだけど、売っていれば基本的に買う。届いてすぐ読むかは別物だ。
だから、読みはじめるときには、どんなきっかけで買ったのかを忘れてることもしばしば。何かの本で紹介されてて買ったのは覚えてても、それがどの本だったか思い出せない。そのくらい、そういう買い方をすることがしょっちゅうだし、あまり考えずに直感的に買っているからだ。
そうして読書遍歴は雑多な様相を呈するようになる。
クリオ: 歴史と異教的魂の対話
この遍歴がかたちを成すというところにも興味がある。
時間をともない動的に生み出される「遍歴」のようなダイナミックな「かたち」。
先に何が起こるか考えて生きてない人が多いように感じるし、そういう人たちに限って過去に何が起こったかにも興味がなく、それはひとえにこの動的な時間をともなう「かたち」というものがまったく見えてないのだろうなと最近思う。
そういう人は残念ながら、自分から動こうとせず、何かのプログラムによって動かされているかのように、自分の行動にも、まわりの行動にも、そして、それらによって生じる変化についても気にしていないように見える。
だから、先を見据えた行動の企てがないし、責任がないのではと疑ってしまいそうになる。もちろん、本当に企てがなかったり、責任感がない人はそう多くはない。ただ、知識がなかったり、考えたりする範囲が狭いので、どうしてもありきたりのプログラムの中で動いているように見えてしまうのだ。
自分が行うことの結果、何が生じてしまい、そもそも自分が行なっていることが何の影響下でみずからも気づかぬまま行なってしまっているかを一切考えられない人たちのことを「完新世的か!」と揶揄してみたくなる。もちろん、先を見据えて、責任をもった行動ができていないのは僕自身含めてそうだ。
でも、それではいけなくなっているのが、現代の社会状況だろう。
人それぞれが常に持続可能性を問いながら生きることがまさにデフォルトなものになるよう移行しつつある社会は、まさに大掛かりな気候変動や生態系の破壊など、人間の行うさまざまな活動が結果として地質年代を完新世から人新世へと変えてしまうほどのものであるがゆえ、変化を余儀なくされている。
そうした自分たちの生きる社会の環境を意識することなく、生きられるということ自体、あまりに時間をともなう動的なかたちというものを見る目に欠けているのではないか?と思う。
まさにそれは1地質年代レベルで過去の生物の生き方だとさえ感じてしまう。
もちろん、その見方はあまりに大袈裟すぎる。
とはいえ、時代は令和である。それまでの考え方をちょんとリセットして、新たに時代にあった考えや行動ができるよう、ひとりひとりが自分の生き方を見直して良いタイミングだ。
令和はじめての誕生日の次の日である今日シャルル・ペギーの『クリオ 歴史と異教的魂の対話』を読見終えても、「そうだ」と感じた。
そうだ、というのは、最初に書いたようにどの本で紹介されてていて買ったのかわからないという本の1冊という点でもそうだし、読書遍歴の雑多性を広げる1冊という意味でもまさに「そうだ」だった。
そして、この時間をともなう動的なかたちというものを感じさせてくれるという意味でも「そうだ」だし、時間をともなう動的な環境において生きるということを考え直さなくてはという意味でも「そうだ」なのだ。
そんな意味で楽しい本だった。
ちょっと内容を紹介してみよう。
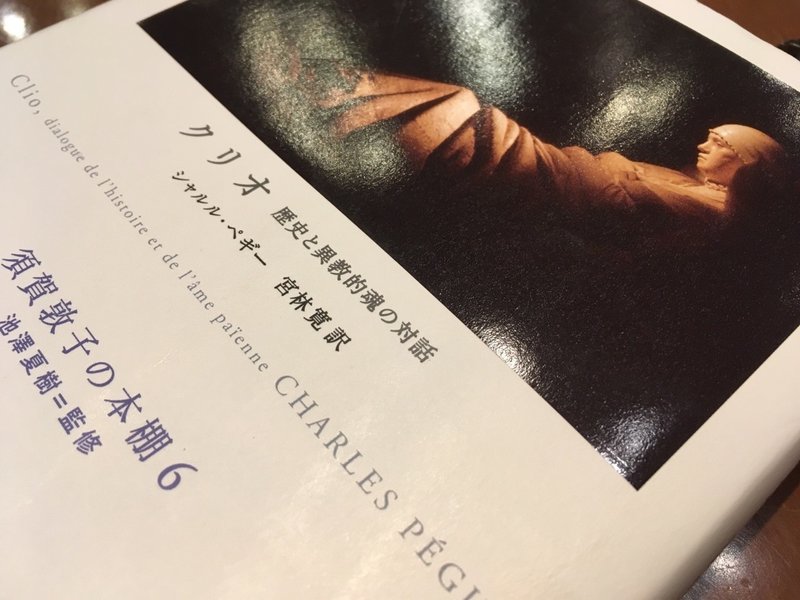
歴史とは何か?
著者のペギーは、この『クリオ』を1909年から1910年にかけて長大な歴史論として書きはじめ、1912年に中断していた執筆を、冒頭以外の大部分を改稿して1913年以降に書き終えたようだ。
歴史論として書きはじめられた本だが、いま読む限り、単純な歴史論としては読めない。だが、歴史論ではないといいきるのは十分に躊躇われるくらい、歴史についても考察されている。
小説でもないし、エッセーというには内容が重厚だ。
サブタイトルに「歴史と異教的魂の対話」とあるが、語っているのは、一方的に歴史を司る女神のほうだったりもする。とはいえ、歴史自らが語れば歴史論というわけでもないだろう。
そもそも「歴史」とは何か?
歴史が語るものはいったい何なのか? 歴史において真実なるものはあるのか? そんなことをちゃんと疑問に思うことが必要だということに気づかせてくれる。
歴史が描くはずの時間をともなう動的なかたちは、動的であるがゆえに本来、ひとつの固定のかたちを成さないはずである。過去の時間だから固定されているのではないか?と考えるなら、では、歴史とは過去のそれぞれの瞬間の物理的状態を描いたものなのか?と問うことができる。
自然史であればそういう見方が可能になることもあるかもしれないが、通常の歴史が扱うのは「人」が関わるもので、人の思惑や思考が絡んだものであるはずだ。その思考はゆらぎもするし、人とと人のあいだで異なる解釈が生じる。
となった途端に過去であろうとかたちは容易に定まらなくなるのではないだろうかと思う。過去が未来に影響を与えるだけでなく、未来もまた過去を書き換えることで影響を与える。
そういう意味で過去を扱うものであろうと、歴史というもの相対するには、時間という謎めいたダイナミックさをともなう不定形のかたちに対する感覚が必要になるのだと思う。過去は唯一ではない。
ムーサの1人で歴史を司る女神**
そうそう、ところで、クリオというのは、ギリシア神話に登場する記憶の女神ムネモシュネの、9人の文芸を司る娘たちムーサのうちの長女にあたり女神で、歴史を司っている。
ちなみに、ムーサはフランス語でミューズmuse。ミュージアムとはミューズたちの館という意味だ。
そのムーサの1人が語るのは、とにかく雑多な話題である。この雑多な話題の流れによって、ペギーはまさに、時間をともなう「かたち」というものを見事に描きだしていると感じた。
それはプロットのような静的に固定したかたちとは異なる性格をもつものとして感じられる。
女神が語るというので思い出すのはエラスムスの『痴愚神礼讃』だが、まあ雰囲気は似てる。対話といいつつ、一方的に語るところは、痴愚神の公衆の面前での大演説会と雰囲気は似ている。まあ、クリオの方が痴愚神よりはまだ上品ではあるが、女神が一方的に語っていくという表現は似ている。
クリオの語りは反復が多用される。
同じことをすこし違えた言い方で繰り返す表現が数多く現れる。反復の多用が反復されながらも、少しずつ異なる表現が採られたクリオの言葉が面白いリズムをつくっていく。反復生まれるからリズムがなんとも心地よい流れをつくっていく。
老い死にゆくものにとってのかたち
かたちというものをどんな風に考えるか。
固定された静的なかたちがあるというものを、いまこの人新世の時代、持続可能性が問われる社会において、いまなお信じられるのか。
固定されたかたちがどれだけ、いまなお持続可能なのか?
いや、そもそも固定されたかたちなど、この老い死にゆくからだをもったダイナミックな生を生きる人間にとって、存在した試しが本当にあったのだろうか?
何かを行えば何かが起こり、何もしていないつもりで、ただ存在しているだけでさえ、何かに影響がおよび、そこに変化が生じている。
そういう影響関係と変化の連鎖から逃れることなど、いまだかつてできたことなど、なかったのに、何か静的なかたちのようなものを想定していたのは何故だろう?
「今後も一貫しているベルクソン的持続の名で呼ばれる持続は、有機的な持続であり、出来事と現実の持続でもあるわけだから、本質的に老いを含みもっている」と女神はいう。
老いは本質的に有機体とかかわりをもつ。持続の中にある老いは有機的組成の核心部分に取り込まれている。誕生し、成長し、老いること。生成した末に死んでいくこと。大きくなった末に縮んでいくこと。それが全部1つになっている。同じ1つの運動になっている。有機的な、同じ1つのふるまいになっている。
ここにある「かたち」。「大きくなった末に縮んでいく」。かたちの変化というより、この変化を含めて、かたちと見る視点。持続可能性が問われたとき、見るべき視点は、この老い的な、変化するかたちを見ることのできる目による視点だろう。
そうした老いて死にゆく生き物が静的なものとして歴史を描くのか? それはあまりにも実際に自分たちが生きた時間とは異なるのでないか。
歴史という時間をともなうかたちを描くのにも、それを不定形のかたちとして描くのと、何か固定化されたかたちとして描こうとするのでは雲泥の差があるはずだ。
時間をともないながら生み出されるかたちというものを、歴史という記録の固定化として描くのは、老い死にゆくからだをもった常に不定形な僕らがやることなのかはきわめて疑わしくはないだろうか。
老いはその本質からして平面(単一の平面)の欠落を招く活動であり、そこでは無数に重なる現実の平面に沿って、すべてが遠くへ押しやられていく。そうした無数の平面はまた、出来事が継起的に、というよりもむしろ連続的に完了した平面でもある。
と、女神はいう。平面を欠いた活動としての老い。あるのは無数の平面も連なり。しかし、それらは次々と「遠くへ押しやられていく」。実際、昨日ひとつ歳をとった僕自身、それらの遠くに押しやられた無数の平面なるものを実感的に感じとることはできない。老い死にゆくものである僕のなかに残る記憶は、やたらとあやふやで、濃淡がつきすぎていて、時間軸にそって描かれた記録としての歴史のように整然とはしていない。
歴史の根底には不正義がある
歴史論ではないと書いたが、女神がこんな風に歴史について語るシーンもある。
ここには当然ながら大きな謎が隠されているだろうと思うのよ。歴史と、歴史の領域とをめぐる本来的な謎。歴史の根底には不正義がある。歴史の領域も、その根底には不正義がある。
女神は、歴史と記憶を区別する。
「歴史は出来事と並行し、記憶は出来事の中心軸となる」と女神は言った。
今風にいうなら記憶は自分事として出来事を経験することだろう。出来事に距離をとって批評家的な姿勢で論じれば、それは歴史的な語りとなる。
だからこそ、歴史の根底には不正義がある。
歴史である女神は自分は何もできないと嘆く。それはそうだ。批評家、評論家といった立ち位置からでは何もできないし、本当に起こっている出来事を何ひとつまともには語れない。
いま何かをなそうとすれば自分事として成すしかないといわれるのも同じことだろう。仕事として、クライアントの依頼を受けて行うことであろうと、そこで行うことが自分事になっていなければ結果は出ない。すくなくともつまらない結果しか出ないことを避けようとすれば、自分も打ち込めることをしないと、おもしろい結果にはつながらない。
歴史は出来事に並行してすべっていく。記憶は出来事の中に入り込み、深く潜り、探査する。
すべっていくだけの形式的なかたちを求めるだけなら何も変わらない。何かが変わっていくのを自分で実感をともなった形で経験したいのなら、「出来事の中に入り込み、深く潜り、探査する」ことが必要なのだろう。
そうした関わりのなかでつくられた記憶が、老い死にゆく生き物である僕らに時間をともなうダイナミックなかたちを見せてくれるようになる。
それには自分で考え、出来事のなかで自分で感じ、そこで起こっていることを仮説と検証の繰り返しのなかで記憶していくことが必要だ。そこに濃淡はあれど、きちんと折り重なった記憶の平面が作られれば、人は批評家然とした歴史家ではなく、自分が生きた時間(の変化と生成)を語る年代記作家となるだろう。
時とともに動いていく「かたち」を見ることのできる目
女神は言った。
作品にとっての名誉も、作品の評価も、作品の寿命も、すべて私たちの一存で決まる。たかが評価とも思うかもしれないけど、作品をめぐる評価は、作品が存在することそれ自体に等しいから、決して軽視すべきではない。
と。そう、すでにつくられた作品であれど、固定化したかたちを持っているのではない。過去の作品の評価は、すべて後の時代にそれに接する「私たちの一存で決まる」。時をともなうかたちというものはそういうものだ。
生きている人は、過去に生きた人たち、そして、後の人たちに連なる「時をともなうかたち」に関する責任をもつ。そのことを意識すれば、これからより課題となる持続可能性や、人間が自分たちの生きる環境にいかに負荷を与えるキーストーン種であるかということももっと実感をもって捉えることができるようになるだろう。
時とともに動いていく「かたち」をしっかり見ることのできる目をもつ必要がある。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
