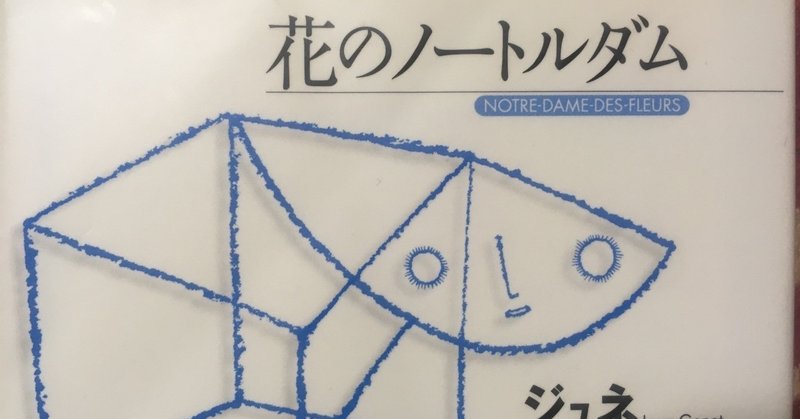
花のノートルダム/ジャン・ジュネ
クリエイティブ。
その言葉が視覚表現偏重にあるのは、どうにも気にくわない。
特に、言葉で表現された小説や詩などが置き去りになっている傾向は、クリエイティブの言葉を深みのないものにしてしまうようにも思える。
視覚表現のように、それほど時間的な労力や思考をするという労力をかけずに済むものに対して、書かれたものを読むという作業を伴う言語表現芸術はなるほど時間も思考コストもかかる。
けれど、だからといって、それらをそれだけの理由で鑑賞の対象から除外して、コストのかからないものにばかり逃げる怠惰さによって、言語表現芸術がクリエイティブという領域の外へと忘れ去られる事態はなんとも馬鹿げていると思う。
いまは拡大解釈されてしまって意味がよくわからなくなってしまっているが、そもそもリテラシーとは読み書きの能力を指す言葉だ。けれど、読み書き能力が乏しく、そこに時間も労力もかけられない人が平気でリテラシーを語る。
そもそも、時間や思考労力のコストを払う余裕すら自分の人生においてつくりだせないような貧しい人生の時間の使い方をなぜ受け入れてしまうのか。そんな時間すら創造できない人生のどこがクリエイティブなのか。
その点、処女小説である、この『花のノートルダム』を刑務所に投獄された身で書いたジャン・ジュネのことを見習ってほしいと思う。

知的受刑者ジュネ
31歳のジュネは、少年期から窃盗などの犯罪と放浪を繰り返し、何度も刑務所に投獄された人生を送ってきたにもかかわらず、この豊かな創造力と多彩な知によって構成された作品を書いている。そもそも、このジュネという服役者は、書店で本を盗んで捕まったりしている。
普通に社会において比較的知的な生活を送っている人よりもはるかに優れた創造力と知識がこの作品に充満していることにまず驚きを覚える。
作品のあらゆるところにジュネの知性が感じられるが、それがただの知性として終わらず、穢れや苦痛、醜怪さや不快さなどをともなった生と結びつけられるところにジュネの作品の美しさはある。
たとえば、作中、こんな表現がある。
神が魂に入りこむ方法は――むかし、イエズス会の僧に聞いたのだが――千差万別だからだ。金粉、白鳥、牡牛、鳩、その他いろいろ、何にでも姿を変えて入りこむ。公衆便所(タッス)でおかまと一発やるジゴロにたいしては、神は神学書にも載っていない方法を考えだして、タッスに変身するかもしれない。
「タッスに変身する」と書かれた「タッス」は16世紀のイタリアの詩人トルクァート・タッソのフランス語読みだ。
ゲーテにその生涯を作品の題材にされるなど、ヨーロッパ文学史において著名といえるタッソだが、やはり犯罪と放浪を繰り返してジュネの筆からその名が出てくると心が動く。
しかも、それが公衆便所を示すタッスと並べられるのが小気味良い。
世に認められた芸術と下卑た下ネタが並置されるという表現としては、こんな一文もある。
ノートルダムの白い手(爪は喪の色)はセック・ゴルギの前腕にそれを包むように置かれていた。ふたりの腕はこすれあい(そこにはたしかに映画の影響があった)、繊細な触覚に作用したので、その触れあいの様子を見ると、ラファエロの聖母像と、彼女たちのまなざしを思いださないわけにはいかなかった。だが、ラファエロは、その純真な名前の含意のおかげで、こんなにも清らかさを感じさせるのだろう。というのも、同じく名前の天使がトビア少年の目を輝かせていたからだ。
男同士のイチャつく様子がラファエロの聖母像に並置される。そして、旧約聖書の「トビト書」における大天使ラファエルと旅する少年トビアへの連想に至ることで、男同士のイチャつきは「清らかさ」を感じさせるものに変異する。
これがジュネの詩的創造力だ。
主人公の葬儀に集うオカマとヒモ
この小説で描かれるのは、社会の裏側の世界、昼の光の世界に対する夜の闇の世界であり、男娼、オカマ、ヒモ、男色家、スリや万引の常習犯、クスリの売人、強盗、殺人犯などなどが織りなす街の景色、そして、刑務所の生活だ。
物語は、主人公といえるオカマの男娼ディヴィーヌの葬送のシーンから始まる。彼女(?)が暮らしたモンマルトルの墓地を見下ろす屋根裏部屋に、「ミモザ1世、ミモザ2世、ミモザ4世半、初整体、アンジェラ、殿様、カスタネット、レジーヌ等々、派手な源氏名を記すのにさらに長いリストが必要なほどの、群衆ともいえるような人の集まり」が集う様子が描かれる。
そして、ディヴィーヌとこの屋根裏部屋で暮らしていたヒモの小足のミニョンもやってくる。あるいは、ディヴィーヌがまだルイ・キュラフロワだったころ、彼の母親だったエルネスティーヌも。
一方で、キュラフロワだった頃のディヴィーヌが好きだったアルベルトも、ミニョンとともに屋根裏部屋で暮らしていたこともある若いヒモで、クスリの売人で、殺人犯でもある「花のノートルダム」も屋根裏部屋にはやってこない。いや、彼らはディヴィーヌの葬儀に立ち会うことはすでにできなかった。
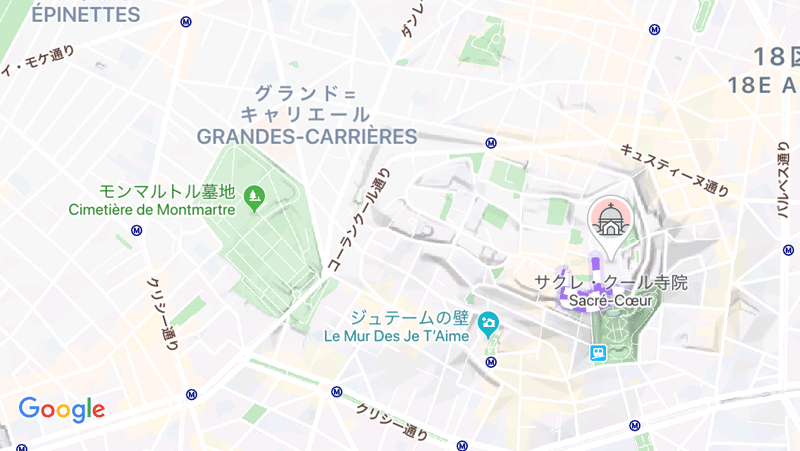
もちろん、ディヴィーヌの葬儀にやってきた者も、来ることができなかった者も、ジュネの創作だ。そう、創作。特徴あるおかまの源氏名も、それは「どこから来るのだろう」と自分で問いつつ、「その理由は正確にいうことはとうてい無理だ」と言いつつ「いい加減に思いついたというわけでもない」と書いている。
それらの名前にはいわば血のつながりがあり、お香や蝋燭の溶ける香りが共通している。
とジュネは書く。
そう。この小説には、血をはじめとする体液のどろっとした湿り気ある触感や、さまざまな香りや臭いが染みついている。
ベトベトした触感と臭気が充満する
視覚偏重の過度に衛生的な現代社会が排除し隔離し無きものにしようとしたがる、触感や臭いといった生々しいものがこの言語表現による作品には充満している。
どこまでもドロドロ、ベトベトして、強い臭気といやな熱気に溢れた読み心地があるのだ。
繰り返すが、この生気が過剰すぎて物質化したような触感と臭気に溢れた小説は、どんなに生々しい感触をそこから受けたとしても、ジュネの創作である。
おかまの源氏名にも「5月の聖母マリアの礼拝堂に置かれた生花や造花のあいだで拾ったり」「アルベルトが大好きだった食いしん坊の石膏の彫像の下や周囲から集めてきた」ような印象がこびりついているし、「その石膏の彫像の後ろに、子供のころの私は、自分の精液を入れたガラスの小瓶を隠していた」という記憶がまとわりついている。
だが、その印象そのものはジュネの自身の経験にオリジナルをもつかもしれないとしても、それは彼の創造力によって小説として昇華したものだ。
こんな風に描かれるディヴィーヌその人も、何か素材となるものはあったとしても、ジュネの創作だ。
ディヴィーヌにとって、ミニョンはすべてだ。彼女はミニョンの性器のお世話に余念がない。愛情たっぷりにそれを撫でさすりながら、すけべな正直者たちが好む別名で呼びかける。「おちびさん」「ゆりかごの赤ちゃん」「飼葉桶のキリスト様」「熱いちびすけ」「きみの弟」。ディヴィーヌがはっきりと発音しなくても、その言葉の意味は明白だ。彼女の心はそれらの表現を文字どおりに受けとめる。ミニョンのさおは、彼女の純粋な贅沢の対象であり、純粋な贅沢品。彼女だけにとって、ミニョンの全体なのだ。
全体という言葉をジュネの巨大な重力をもった創造力が歪ませる。
生物的な熱と湿り気と臭いを凝縮させた、ブラックホールのような引力をもった「さお」に向けて時空は大きく歪み、そこに向かってすべてが収束させられるのだ。明らかに、それはアインシュタイン以降の物理宇宙で書かれた小説である。
死と詩と聖性と
ジュネは、この作品をそんな主人公ディヴィーヌの葬儀からはじめた理由をこのように記している。
ディヴィーヌは死んだので、詩人は彼女のことを歌に歌い、彼女の伝説を、叙事詩を、物語を語ることができるだろう。ディヴィーヌ・サーガは細かい指示をつけてダンスやパントマイムにもなるにちがいない。いま私がバレエにすることは不可能なので正確な考えをあらわす重い言葉を用いるほかない。だが、この重い言葉を、月並みで、空虚で、上っつらだけの、目立たない表現によって軽くしてやろう。
この小説において、体液のドロドロした熱をもった触感や強い臭いの印象を色濃いものにしているのは、一方で、そうした生気あるものを欠いた死が隣で大きな口を開いて、それらすべての生あるものを飲み込もうとしているからだろう。
死は、さまざまな人をたぶらかし、誰かを死に引きずりこむ手伝いをさせて殺人犯にする。
「変な感じだったなあ、ジャンさん、そこでソニアを抱いたときは。ほっぺたに血がついてたよ」と、「私」に言う、黒人のクレマン・ヴィラージュは、私と同じ監房に入れられ、死刑の日を待つ。
彼は妻を殺し、死体を、黄色地に緑の花束の模様のついた絹のクッションに座らせたまま、壁に塗りこめ、塗りこめた部分をベンチの形に仕上げたのだった。
という殺人の罪を犯したからだ。
しかし、この罪も、ジュネ、あるいは「私」によって次のようなかたちで聖性を帯びる。
その瞬間、長い英雄的人生が始まり、それが丸一日続いた。強い意志の力で、彼は凡庸ななりゆきを避けることができた――精神を超人的な領域に保ち、そこで神となり、自分の行為が道徳的制限から脱する特異な世界を一気に作りあげたのだ。彼は自分を崇高なものにした。将軍となり、司祭となり、犠牲を捧げる祭司となり、聖務の執行者となったのだ。命令し、復讐し、生贄を差しだし、奉献したのであって、ソニアを殺したのではなかった。彼は予想外の本能を用いたこうした技巧を駆使し、自分の行為を正当化したのだ。
この死と触れる聖なる行為が、クレマン自身の強い体臭という生とのコントラストで描かれる。
わたしがクレマン・ヴィラージュを知ったころ、彼は監房を死よりも強烈な匂いで満たしていた。孤独は甘い。孤独は苦い。孤独のなかでは過去の記憶がすべて頭から失われ、この衰弱に続いて精神の浄化がやって来るのだと思われているが、この本を読んでいるみなさんは、ぜんぜんそんなことなないとよくお分かりだろう。私は激しく苛立っていたが、あの黒人がすこしだけ落ち着かせてくれた。彼の人並み外れた性的能力が私をなだめるのに効いたようだ。彼は海のように強かった。彼の光輝は薬よりも鎮静作用があった。彼の存在そのものが魔除けだっな。私は眠りについた。
そう。その強い臭いは、性的な行為を伴いつつ、エロスとタナトスのコントラストをさらに強くする。
美醜の境が溶解する
生と死のコントラストを描きつつも結局は両者は一緒くたになって、敵対する関係というより共犯者の関係であることを告白しはじめるように、美と醜の関係もその境を失う。
ミニョンがまだ屋根裏部屋にいた頃、彼が本物のヒモだったら、こうしたディヴィーヌの飾りをすべて嘲笑っただろうが、ミニョンは天からのお告げの声を聞くようなヒモだった。彼は嘲笑いもしないし、微笑みもしない。美男で、自分が美しいことに執着していた。美貌を失ったら、すべてがおじゃんになるのだ。だから、美を自分の体に引きとめておく秘宝の数々を見せられても、ミニョンは感動もせず、冷静に見守るだけで、残酷な笑いを発することなど一度もなかった。
そのヒモのミニョンが美醜の境が溶け、互いにまざりあう様子をつぶさに目撃している。
それは当然の技術なのだ。ミニョンの面前で、多くの年とった情婦たちが化粧をしてきたので、剥げおちた美が公然と修復されることを彼は知っていた。連れこみ宿の部屋で、巧妙な修繕を見てきたし、口紅のペンシルを高くもちあげながら迷っている女の姿も目撃してきた。ディヴィーヌがかつらを着けるのも何度も手伝った。彼はそこで、巧妙な、というより、自然なそぶりを見せつけた。そんなディヴィーヌを愛するすべを学んだのだ。彼女を作りあげているあらゆる醜怪さに身をひたし、それらをとっくり検証した。
醜怪さと美は表裏一体というより、単に一体なのだ。醜怪さを隠すために美しく化粧をするのではない。
同じように、聖性も世俗の下卑たものと対極にあるのではない。少なくとも、美も、聖性も、穢れた部分や醜悪な部分を取り除いた純粋なものなのではない。それらと一体になったものなのだ。
そこにこそ、創造もあり、生死もある。触感や臭気を消し去って、衛生的な視覚的美を追い求めることの間違いがそこにある。
そんな退屈なクリエイティブとは無縁な、力強い怪物的なクリエイティビティをジュネのこの小説はまざまざと感じさせてくれる。
すると、こんな疑問も湧いてくる。教会などというものがなかったら、ディヴィーヌの聖性(救済の方法ではない)、また、すべての聖人の聖性は、どんな形をとるのか、ということだ。彼女がたんに面白おかしく生きているのではないことは、もうご理解いただけただろう。神が下した人生を、逃れるすべもないまま受けいれ、その人生ゆえに神に近づいているのだ。ところで、神は金色に輝いているとはかぎらない。神の神秘の玉座の前では、古代ギリシア人が見て好適だと判断するような、均整美にみちた体である必要はない。現にディヴィーヌの体は真っ黒こげだ。
神と男娼の聖性はここに来て出会う。30歳になったディヴィーヌがシワと化粧をその顔の上で混ぜ合わせるように、神は金色に輝いたり、均整のとれた身体をしている必要もなく、レンブラントが描く降架図のそれのように肉体的なみすぼらしや汚れと同化していてよいのだ。

聖と俗、美と醜は一体となってひとつの敬うべき存在となる。そこにおいてこそ、本当の奇跡が起きるのだ。
すると奇跡が起こった。奇跡はないという奇跡だ。神様はしぼんだ。神は空っぽだった。ただの空虚だ。容器はなんでもかまわない。形は美しいが、マリー=アントワネットの石膏の頭のようなものだ。兵隊の人形のように、まわりを浅い鉛の皮で包んでいる。
聖なる裁判
この小説において、特に詩的で、聖性を感じさせるのは、500ページ弱ある小説中の410ページを過ぎたところから開始される、花のノートルダムの裁判のシーンだ。
クスリの売人でもある、花のノートルダムは、少量のクスリを持っていたときに捕まってしまうが、何故か、自分から2年前の老人殺しを告白してしまう。
そして、殺人罪での裁判の場に彼は登場するのだ。
ジュネは、花のノートルダムの裁判所への登場シーンをこんな風に短く伝える。
あえていっておきたいのは、誰の目にも、花のノートルダムの後光に、こんな言葉が刻まれているのが見えたことだ。
「われは『無原罪のお宿り』なり」
「無原罪のお宿り」という言葉は、南仏ルルドに生きた聖女ベルナデッタ・スビルーの前に、1858年の2月から3月にかけて、聖母マリアが繰り返し出現する出来事があり、3月25日の14度目の出現の際に口にした言葉だ。
なるほど、「ノートルダム=私たちの貴婦人」という名にふさわしい言葉が後光に刻まれたわけだ。
ただし、それは殺人罪に問われる容疑者の背後に刻まれたわけだが。
花のノートルダムは、この裁判の席できわめて正しく聖なるものとして立ち振る舞う。
裁判長が「何か自分の弁護のために申したてたいことはあるかね?」と尋ねれば、偉大なノートルダムは「爺さんはくたばりぞこないで、ちんぽも立ちそうになかったよ」と言い放つことができた。
そう破廉恥に言い放つことで、裁判長はじめ12人の陪審員たちを見事に凌辱した彼は、その裁判の40日後の春の夜に「刑務所の中庭に」立てられた断頭台で、その次の日に「本物の刃物で首を斬りおとされた」。「それだけで、何も起こらなかった」。「神がひとり死んだからといって、神殿のとばりが下から上まで裂けることもあるまい」。空っぽの奇跡がまたそこでも起こったのだ。
そして、そういう神聖、聖性をまとった花のノートルダムの行動であるがゆえに、それは詩になる。
ノートルダムにとって、自分の言動は1篇の詩であり、つねに、つねに同一の象徴を用いなければ、自分の考えを表明できないからだ。そして、2年前の自分の行為に関しては、もはやすべて余分なものを殺ぎおとした表現しか残っていなかったのだ。年代記が何度も読みあげられるように、ノートルダムは自分の犯罪を読みあげたが、彼が語っているのは、正確にはもはや犯罪ではなかった。その間、彼の正面の壁にかかった振り子時計は規則正しく動いていたが、時間は狂って、1秒ごとに長い時と短い時を刻んでいた。
それはまさにかつてホメロスらが叙事詩で描いたものと同じものだ。
花のノートルダムは、叙事詩で語られる英雄、神聖をまとった存在になる。そのどこまでも俗にまみれて、ドロドロ、ベトベトで強い臭気に覆われた姿ゆえに。
血と糞便にまみれた死
そして、その聖性は、裁判所に証人として出頭したディヴィーヌの聖性も同時に輝かせる。
ディヴィーヌはほかの場所では決して大人にならせてもらえなかったが、ここでついに大人になった。そう、ここに証人として現れた彼は、たえずキュラフロワという子供でありつづけた自分から脱皮したのだ。彼がこれまで単純なことを何ひとつおこなわなかったのは、単純であることは老人にしかできないことだからだ。単純とは、純粋で、精錬され、設計図のように単純化されたもの、おそらく、イエス・キリストが「……おさな子にも似た」と語ったあの状態のことを意味するが、じつはいかなる子供もそうした状態に似ることはなく、身を削る努力で一生を費やしたとしても、その状態に達するとはかぎらない。ディヴィーヌは単純なことは何もしなかった。
この後、描かれるのは、冒頭の葬儀のシーンにつながるディヴィーヌの死の場面である。
ディヴィーヌはくつろいだ。汚物が、ほとんど水のような糞便が、彼女の体の下で、生暖かい小さな湖のように広がり、その湖のなかへ、静かに、とても静かに――瀕死の皇帝の体温でまだ温かい船がローマ近郊のネミ湖の水に沈むように――ディヴィーヌは沈んでいった。その安堵感からため息がひとつ漏れ、同時に口に血があふれ、もうひとつため息がもれた。最後の吐息だった。
そう。最後にあるのも、熱と湿り気と臭気をともなう生と死を併せ持つような存在感だ。
正直、この小説を読んでいて、これを良いものだなどという気には到底ならない。しかし、このおそろしく怪物的な負の存在を否定することはとてつもなくおぞましく感じる。どこまでも衛生的な社会が排除し蓋をしようとする、こうした怪物性は、実はそれがあってこそ聖性も可能になるし、本来的な美も可能になるものなのだと思う。
創造性とはなにか?
それを問うとき、このジュネの作品のとてもない重力をもった存在感は、日常的な時空間を大きく歪ませる。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
