
肖像に話しかけて
不在の者の代理としてのメディア。
ハンス・ベルティンクは『イメージ人類学』で、死者の代理として、その人のイメージを再現する太古のメディアの意味について書いている。
メディアには、死者崇拝という太古の範型が存在する。死者は失った身体を像と交換し、生者たちのあいだにとどまる。このような交換によって実現される死者の現前はただ像においてのみ可能であり、イメージ・メディアは死とイメージとの象徴的交換を遂行する生者たちの身体に対して存在していたばかりでなく、同時に死者たちの身体の代理も務めていたのである。
いなくなった死者の代わりに生者たちのあいだに置かれる像は、いなくなった祖先たちの代理をする。
ただ、不在の理由は、死でなくても構わない。いわゆるアバターも不在のユーザーの代理を行うものだ。

メディアとイメージ
ベルティンクは、メディアとイメージを分けている。
絵画というイメージは、壁やキャンバスや紙などをメディアとしてもつ。
だから、像はメディアとなって死者のイメージを映し出す。であれば、ある意味、人間の身体は生者のイメージを乗せたメディアとも言える。
メディアからイメージを呼び出すには、観者の力がいる。見る者がいなければ、メディアからイメージは立ち現れない。
メディア内でのイメージの現前はたしかに経験可能だが、イメージの現前とメディアの現前は同一ではなく、錯覚の可能性も存在するのだ。イメージはただ観者によって生気を与えられたときにだけ、イメージとなる。この生気の付与行為(アニメーション)によって表象されたイメージはあらためて支持体メディアから切り離される。
メディアは物理的に存在するが、イメージは観者の側の知覚によって生じる。
アンリ・ベルクソンが「知覚を事物の中に置く」と言ったことが思い出される。
イメージはメディアの中に置かれる知覚である。それは見る者がこれから行おうとする運動次第で、生気を得て、イメージに変わりうるが、見る者を動かさずに至らず、変わらないこともある。
メディアは現前していても、イメージは現前しない場合もあるということだ。

イメージを仮装する
「イメージとメディアの問いは身体を呼び戻す」とベルティンクはいう。
先に生者の身体は、生者のイメージのメディアであると書いたが、生者は自らそのイメージをある程度、コントロールすることもできる。
そう、衣服を纏うことによって。さらには仮装することによって。
われわれが仮装するというとき、たとえそれが着脱可能な仮面ではなく、通常の服装からかけ離れた目立った衣装だとしても、この表現の語源が示唆するように、仮面を身につけることに等しいことは明らかだ。いいかえれば、仮面は身体をイメージへと変容させる全体のための部分なのである。
仮装や仮面によって、身体は別のイメージを語りだす。古代のシャーマンが仮面を身につけて神や祖先やほかの生き物を憑依させる理由もそこからわかる。
仮面は身体上につけられ、イメージを呈示しながら、実はこのイメージによって身体そのものを隠蔽する。仮面は身体をイメージと交換するのだ。
仮面がイメージを現前させるとき、それがつけられたメディアとしての身体は見えなくなる。
イメージとメディアの関係はそういう関係にある。
イメージが見えているとき、メディアは隠蔽される。
絵を見るとき、僕らはそれが書かれた板やキャンバスを見ることはない。
逆に、保存状態が悪くて、画面がひび割れていたり、傷ついていたりすれば、絵のなかからかくれていたメディアそのものが現前化してきて、逆に絵のイメージは見えなくなっていく。
仮面のひび割れから元の素顔が覗くようなものだ。

仮面がはがれて
仮面と身体の関係から、ベルティンクは次のような面白い指摘をしている。
仮面は本来、担い手である身体のために作成されたにしても独自の素材から作られているので、その表現を保ったまま、身体から引き離して観賞することも可能であった。したがって、仮面と肖像画には、あきらかにエジプトのミイラ肖像画に認められるような連関が存在するといってよい。ギリシア=ローマ世界で死者への追憶を呼び起こしていた板絵が、エジプトではそれまでの立体的な仮面に代わって、ミイラの顔に取り付けられたのである。そこで敷衍して、肖像画とは、身体から独立し、新しい支持体メディアに移された仮面であると解釈することも可能だろう。
仮面は身体から離れて鑑賞用の芸術品になりうる。
鑑賞のための顔をモティーフにした芸術作品と言えば、当然、肖像画が思い浮かぶ。エジプトのミイラの仮面が立体的なものから平面の板絵に変わったというのは興味深い。
たしかに肖像画はメディアの異なる、仮面と言えそうだ。
しかし、メディアが変わり3Dだったものが、2Dのものに変わると、イメージの意味もまた変化する。
絵は、観者の身体が世界に投げかける標準的なまなざしを模写することになったのだ。それは身体のメディアではなく、まなざしのメディアであったので、近世のイメージ概念の基本となった。絵画は、活版印刷とは別の意味で、単に芸術の分野には限らない西洋文化自体の主導的メディアとなったのである。
3次元的な仮面であることを離れ、2次元の肖像画となったとき、それは身体的な代理として存在するものから、まなざしを受けることで不在の代理をするものに変わった。それは活版印刷技術とともに、人という種をまなざし=視覚偏重の生き物に変えた。
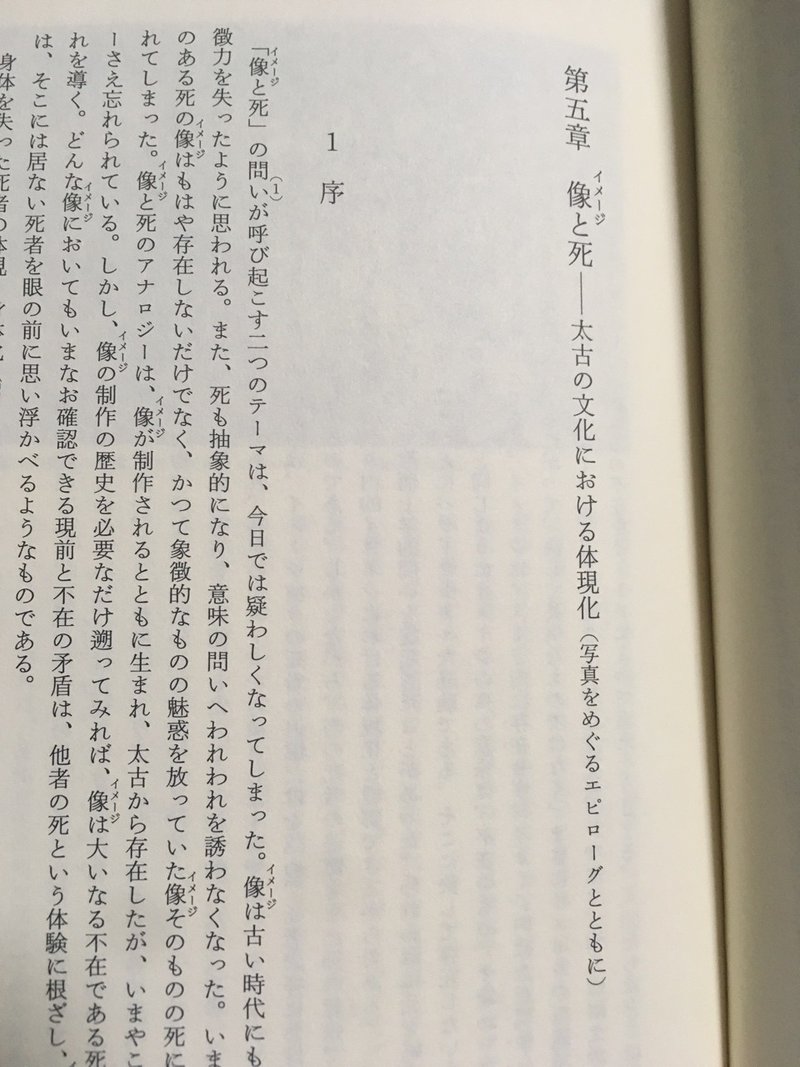
イメージに祈る
肖像画というイメージは、現在、その起源としての代理機能が忘れられてもいる。
しかし、それは現在のスマートフォンの小さなディスプレイに映るさまざまな人々の写真同様に、そこに不在の人へとアクセスするためのユーザーインターフェースであったのだ。
今日のわれわれは肖像のほうを「自律的肖像画」と呼んではばからないだけでなく、直接、身体を表すのは、ただそうした肖像画だけだと考えている。しかしその際、法的要件において肖像板絵に代理と認証の役割を与えるひとりの人物が、背後に控えているということが忘れられている。宗教的領域でも、肖像画は単に描かれた人物の容貌を家族と友人たちに思い起こさせるというよりも、その前で祈りに励むよう奨めるものであり、また神と象徴的対話を行うためのメディアでもあった。したがって、それは不在の人物と接触するための、一種のユーザー・インターフェースと呼べるかもしれない。
そう、代理としての肖像画は、必ずしも有名な画家によって描かれた誰かの絵ではなく、仏壇に飾られた大切な人の遺影のように見る者によって生気を与えられて、死者のイメージが蘇ってくるようなユーザー・インターフェースだったのだ。
僕らが画面の向こうの、ここには不在の人々(のイメージ)に話しかけるのも、それと対して変わらない。
これからメディアがVRなどに変わっていっても、僕らが代理としての肖像に話しかけ続けるのは変わらないだろう。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
