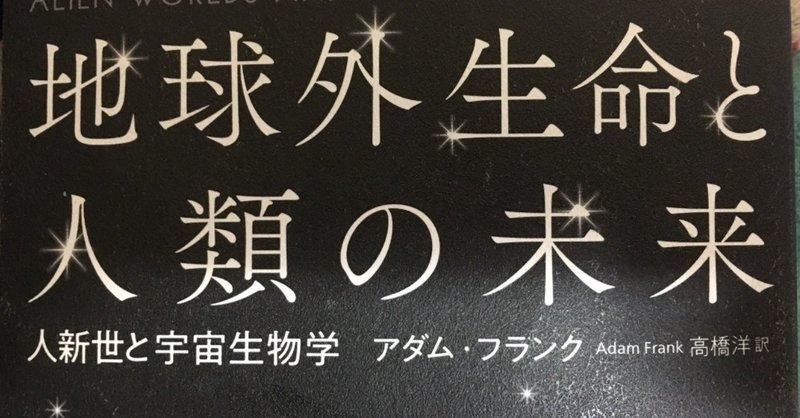
地球外生命と人類の未来/アダム・フランク
「先進技術を発展させた文明は、平均してどの程度長く存続できるのか?」
この問いは、1961年にアメリカの天文学者フランク・ドレイクによって考案された、この銀河系に存在し、地球に生きる僕たち人類とコンタクトできる可能性をもった地球外文明の数を推定するための方程式における、7つあるパラメーターのうち、最後の1つだ。
他の6つは、
1.この銀河系で1年間に誕生する恒星の数
2. ひとつの恒星が惑星系を持つ割合
3. ひとつの恒星系がもつ惑星のうち、生命の存在が可能となる状態の惑星の平均数
4. 生命の存在が可能となる状態の惑星で、実際に生命が発生する割合
5. 発生した生命が知的レベルにまで進化する割合
6. 知的なレベルになった生命体が星間通信を行う割合
となっている。
この6つのパラメーターに、さらに、そうした生物が現在もなお存続している割合として、先の7項目を掛け合わせれば、自然と地球外生物か僕たちにコンタクトをしてくる確率がわかるというわけだ。
では、その確率はどれくらいだろう?
答えは「わからない」だ。
今回紹介する『地球外生命と人類の未来』の著者で、天文学者のアダム・フランクは、こう書いている。
アインシュタインの有名な方程式「E=mc2」は世界の振る舞いに関する基本的な真理を表現している。自然がそれ自体でいかに作用しているのかに関する理解を記述したものなのだ。それに対しドレイクの方程式は、私たちの理解の欠如を表している。つまり、「宇宙にはいくつの地球外文明が存在するのか?」という特定の問いに対する答えを導くために知る必要のあることを教えてくれるのだ。
そう。ドレイクの方程式は、答えを教えてくれるものではなく、答えを導くために人類が何を知るべきかを教えてくれるものなのだ。
解を提出するのではなく、問いを提出する。これこそ、まさに科学的な姿勢だと思う。
こんな風に、著者も言っているように。
すぐれた問いを見つけることは、真っ暗な部屋に明かりを投げかけることにも似ている。つまりそれは、新たな光のもとで世界を見られるようにし、世界に関するストーリーを語る新たな方法を発見するための第一歩となる。
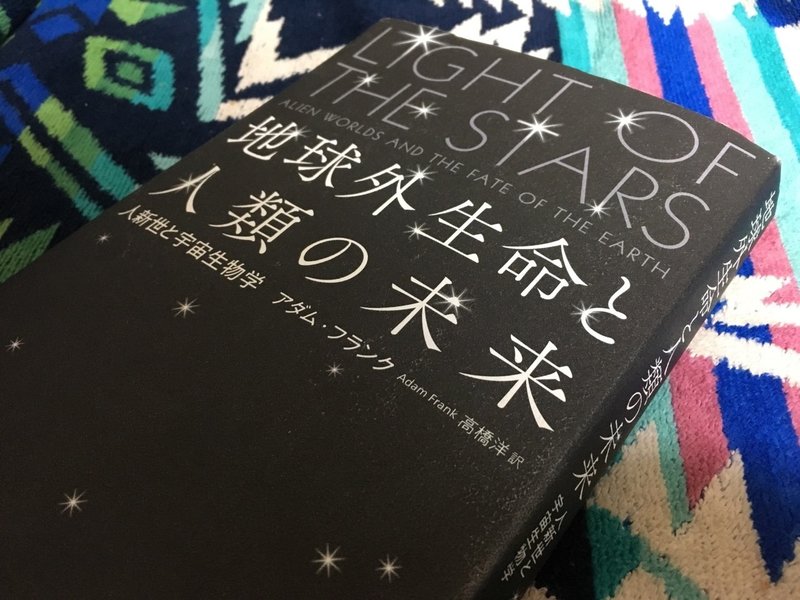
方程式の前半部分
さて、先のドレイクの方程式の7つの項目は、前半3つは天文学的な問題である。
ドレイクの方程式の最初の項(N※)は、恒星が誕生する割合を表している。この項は、1950年代後半以来、ある程度の正確さをもって知られており、それ以後の研究は、その数値(1年におよそ1個)を精緻にしたにすぎない。しかし1961年にドレイクがこの方程式を提起したとき、惑星をともなう恒星の割合を表す第2項(fp)と、ハビタブルゾーンに位置する惑星の数を表す第3項(np)は、誰にもわからなかった。
ドレイクの時代には、最初のひとつ以外は、答えがわからなかった問いもいまや科学的に答えられるようになってきている。
それまでは難しかった惑星の存在を発見することが、ケプラー宇宙望遠鏡の登場によって可能になったからだ。
ケプラーのデータに基づく研究や、他の系外惑星研究が本格化すると、科学者たちは、それらの項に意味のある値、言い換えると統計的に有意な値を与えるに十分なデータを手にするようになる。
このケプラー宇宙望遠鏡の成果は、すごかった。
それまでの惑星発見の方法では、恒星の近くの軌道を回る比較的な大きな(木星大の)惑星をひとつずつ時間をかけて見つけることしかできなかった。
けれど、異なる探索方法によるケプラーの成果は違った。
ケプラーのデータによって最初に系外惑星が検知されたのは2010年の1月のことだったが、それはもっとも重要なニュースではなかった。それとともに、数千の「候補」が見つかったのである。(中略)そして2014年、この福袋は大きく開かれる。その年ケプラーチームは、たった一度の発表で715個の系外惑星の発見を報告したのだ。かくして、一括した惑星探査は現実のものになった。2015年までに、ケプラーと他の方法を合わせて、天文学者が詳しく調査できる1800の新たな世界が発見されていた。
しかも、その後の進展がとんでもない。
このケプラー宇宙望遠鏡による研究の結果が示したのは、この宇宙(この銀河系ではなく宇宙全体だ)には、ドレイクの方程式の3項目め、生命の存在が可能となる状態=ゴルディロックスゾーンにある惑星は、100億×1兆個存在するということだからだ。
途方もない数で、これなら確実に地球外生命体は存在するだろう。
方程式の後半
しかし、前半部の数字が明らかになる一方、後半部の進展はあまりない。
4つめ、5つめは生物学的な問題で、次の6つ目が強いて言うなら社会学的なものだろう。だが、この問いに答えるための科学的なデータはないと著者はいう。
代わりに著者が提示したのは、この4、5、6項目の3つをかけ合わせた際の、悲観主義的な限界はいくつかというものだ。
答えから示すと、それは「100億×1兆分の1」だ。
勘のいい人は気づいたと思うが、この4-6項目めの悲観主義的限界数と、先の1-3項目めにあたる惑星数100億×1兆をかければ、1である。
ようするに、全宇宙で地球に生きる僕たち人類とコンタクトできる可能性をもった文明の数は1。つまり、僕たちだけというのが、4-6項目めの悲観主義的限界数だ。もっとも小さく見積もった場合がそれだとしたら、僕らがこの広い宇宙でひとりぼっちである確率は少なさそうだ。
最後の7つ目の項目
しかし、先の答えが"1"になるのは、まだ僕らが存在しているからだ。
7つ目の「知的生命体による技術文明が通信をする状態にある期間」という項目こそ、人新世に入り、地球という惑星が自分たちと一心同体であることに気づいた人類にとつては、非常に重要なものとなった地球生物学的な問いである。
もしかすると宇宙は、長期にわたって持続可能な技術文明を生まないのかもしれない。宇宙の全歴史を通じて存在してきたあらゆる系外惑星を対象にしても、そのような文明はうまれなかったのかもしれない。
と著者はいう。
いまだ、人類が地球外生命体の存在を見つけられないのは、技術文明が持続可能性がきわめて低いからではないかと。
著者は、かつて発展した文明を持っていたであろう痕跡を残しつつも、衰退してしまった孤島、イースター島の例を持って人口の変化と環境の変化、そして、衰退との関係を示す。
島民が食糧の確保、あるいは技術の行使のために島の資源を使うにつれ、人口は増加する。木のような資源は再生可能で、島民によって伐採されても自然に回復していくことは、方程式によって記述されていた。(中略)資源の再生は、やがて人口の増加に追いつかなくなる。過剰な伐採は資源の枯渇を招き、島の人口も減りはじめる。かくしてイースター島の人口は、紀元1200年頃にピークに達したあと、徐々に減っていき、オランダ人が到来した頃には数千人になっていた。数理モデルはイースター島の歴史の一般的な趨勢を正しくとらえていたのだ。
人間の行動が環境に影響を与えることはこの例を持ちだすこともなく、僕らもみな気づいている。
しかし、大事なのは、どこで取り返しのつかない臨界点を超えてしまうかを知ることだろう。
そのシミュレーションとして、著者らのチームは、惑星とそこに住む技術文明を持った生物の数の関係を数理モデルを用いて分析している。

この4つのパターンが示すのはおそろしい結果だ。上の2つは絶滅こそしないが、少なくとも左の「集団死」は失うものが大きい。
ましてや、下の2パターン「崩壊」は完全に絶滅を免れないし、右下に関しては途中で悔い改めて、資源の使い方を見直してもなお、結果は同じだ。ようは改心が遅すぎたということだろう。
惑星システムの一部として
著者が明らかにするのは、何もこうした脅しのような予測ばかりではない。
むしろ、著者が示すのは、「私たちは、生物圏と文明を相互作用し合う惑星システムの一部としてとらえるよう理解を深めていく必要がある」という改心の方向性だ。
そもそも高度な技術文明だけが、その惑星の環境を変えてしまうわけではない。生物圏という言葉があるとおり、生物の存在は、そもそも惑星システムの一部であって、時に大きく惑星環境を変えてしまう。
著者は、25億年前頃に起こったとされる、ほとんど酸素のなかった地球に大量の酸素を発生させた、大酸化イベント(GOE)を例にあげる。
進化は、水を用いて化学作用を駆動するという新バージョンの光合成をあみ出したのだ。水は地球上に豊富に存在するので、新バージョンの光合成を利用する生物は、古い形態の光合成を用いる生物に勝利した。しかし藍藻(シアノバクテリア)と呼ばれるこの生物は、単に増えるだけでなく、水、二酸化炭素、日光を取り込んで、その活動の一種の廃棄物として酸素分子を吐き出し始めたのである。(中略)やがてシアノバクテリアの活動によって、非常に大量の酸素が海洋や大気に投棄されたために、地球全体がその状態に反応しなれけばならなくなった。地質学的な記録は、大気の酸素濃度がわずかに上昇した「ひと吹き」が起こったことを示している。しかし25億年前にはその状態が定着し、わずか数億年のあいだに大気の酸素濃度は100万倍に上昇した。
そう。酸素のほとんどなかった地球環境を、生物が酸素で満たしたのだ。
しかも、「酸素を生成する(が呼吸しない)細菌は、GOEを引き起こした、それ自身の活動によって地球の表面から追い払われて」しまう結果になるにも関わらず、その後にほかの生物が大空や大海原を支配できる環境に、惑星の環境を一変させたのだ。
GOEは、地球の歴史の初期の時点で、生命が惑星の進化の道筋を完全に変えたことを明らかにする。また、人新世の到来を駆り立てている今日の私たちの営為が、新奇なものでも、先例のないものでもないことを教えてくれる。しかしそれと同時に、地球を変えることが、当の変化を引き起こした生物にとってよい結果につながるとは限らないことをも教えてくれる。
つまり、人間だけでなく、微生物も含めて、地球というシステムの一部だということだ。
熱力学第二法則に従って
人間の影響力はとてつもなく大きくなり、自分たち自身さえ脅かすほど、惑星のシステムを変更させてしまったが、そもそも、影響がない状態などあり得ないのだ。
著者がこう書くように。
持続可能性に関する公開討論では、化石燃料から、地球への影響が小さい資源へとエネルギー源を切り替えることに、議論の焦点が置かれている。この目標自体に問題があるわけではないが、論点は、ときに「地球への影響が小さい」から「影響がまったくない」へ歪曲されることが多い。宇宙生物学の視点をとって惑星のように考えるよう心がけていれば、「地球への影響がまったくない」などということはあり得ないことがわかるはずだ。
惑星ように考える。
そう。僕らは、惑星と一心同体のホロバイオントだ。ホロバイオントという概念を提唱した生物学者のリン・マーギュリスも、ガイア理論を打ち立てた人のひとりとしてこの本にはたびたび登場する。
生態系というシステムをはるかに超えた、宇宙生物という規模のシステムとしての思考が求められるのだ。
そして、著者は、科学者らしく、このシステムに関わるのはずばり熱力学第二法則であることを指摘する。
エネルギーをまるまる有用な仕事に変換することは不可能であると、熱力学第二法則は教えてくれる。つねに廃棄物が生じるのだ。そのためいかなる惑星のどんな生命であろうと、エネルギーを費消すれば、その形態を問わず必ず廃棄物が生じ、蓄積した廃棄物は、惑星システムへとフィードバックされる。この観点からすれば、化石燃料を燃やすことで生じた二酸化炭素は、人類の文明構築に由来する一種の廃棄物として見ることができる。いかなる形態であれ、廃棄物は惑星に影響を及ぼす。大気、海洋、氷床、陸地の状態はすべて、廃棄物が蓄積するにつれ変わっていく。これこそが、気候変動や人新世に関する真の科学的なストーリーなのだ。
だとすれば、「ドレイクの最終項によって示される問い、すなわち「先進技術を発展させた文明は、平均してどの程度長く存続できるのか?」」という問いについて考えるためには、このような意味で惑星システムを今後どのような形で惑星そのものとともに運用していくかが問われる。
エネルギー変換の限界は、人新世の基本的な教訓である。惑星を自分の思いどおりに利用することなどできない。つまり、文明構築のためにエネルギーを利用すれば、必ずや惑星からのフィードバックが戻ってくる。その代わり私たちは、生物圏と文明を相互作用し合う惑星システムの一部としてとらえるよう理解を深めていく必要がある。
著者は、惑星の状態を、熱力学第二法則の観点から、5つのクラスに分け、人新世に入った地球の状態を、クラス4を抜け、クラス5に入るか、それとも、そこに至らず絶滅の道を辿るのかと問いかける。
その際、クラス5に入るためな必要となるのが、惑星システムの行為主体として、システム全体のとるべき道を示せるかどうかだろうという。
もっとも深い意味において、クラス5惑星はガイアの完成を表している。その世界では、惑星全体が進化の方向、つまり目的を持っている。これこそが、行為主体の支配する生物圏という言葉の意味するところだ。この文明は自らの存続を目指して、それ自身を生物圏の表現として認識し、とるべき方向を選ぶのである。
これは、1つ前のnote「虚構の「近代」/ブルーノ・ラトゥール」で書いたブルーノ・ラトゥールのモノの民主主義にもつながる話だろう。
そこでも僕は「人間があらゆる意味において、あらゆる人間以外の生物、そして非生物と共生関係にある中で、人間の無自覚な拡張が自分たち自身の生活や生存をリスクに晒すような影響を与え続けている状態から、いかにどちらの方にシフトすれば良いのか?」と書いたが、まさに本書で書かれていることも、それを考える上での大きなヒントになるものだ。
こうした意味でも、僕らはラトゥールのいう近代から非近代へのシフトを今すぐにはじめないといけない。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
