
どうやら中間的なものが好きらしい。
中間、プロセス、メディア、はざまなどに惹かれるし、変容だとか、両義性、横断とかも中間的なものを感じさせて気になる。
はざまで共振する
だから、アビ・ヴァールブルクの歴史上の複数のイメージ同士が共振する様を感じとるような思考やそれを視覚的に表してみせる行動にも惹かれるのだろう。
時間を不連続にする亀裂、言葉とイメージのあいだの隔たり、そしてイメージ内部の両極性といったものすべてがひとつの間隔である以上、ヴァールブルクのあらゆる思考はいわば間隔の問題なのだ、とディディ=ユベルマンは大胆に総括する。
こう書くのは『歴史の地震計』の田中純さん。ヴァールブルクの晩年の仕事である『ムネモシュネ・アトラス』を論じた1冊だ。

『ムネモシュネ・アトラス』でヴァールブルクは、971枚の図版を総数63枚の黒いパネルに配置している。まさに歴史上の複数のイメージ同士が互いの類似性と相違性のあいだで共振しあう様を可視化した「地震計」である。
僕などは、いわば図像によるKJ法だと思ってしまう。KJ法自体、ここ最近、繰り返し言及しているように、異なるもの同士を隠喩的につないでいくもの、詩的な洞察力で隠れた共通項を複数のデータの間に見出していくもの、だからだ。
ヴァールブルク自身は「間隔(=中間地帯)のイコノロジー」を、イメージによる原因の想定と科学的記号による原因説明とのはざまを揺れ動く精神の振動に関する心理学的な分析、と定義していた。
やはり、テーマは、中間、はざまである。イメージと科学のはざまというのは1つ前の「詩と科学の重なるところ」という話にも通じる。
心の中間領域から現れるもの
両義性にも、中間的なものを感じると書いたが、そんな両義性をもった20世紀絵画を論じたのが、ダリオ・ガンボーニの『潜在的イメージ』という1冊。

この本でガンボーニは、両義性あるいは多義性を持った絵が存在しうる理由を考察しながら、精神分析の研究を参照している。その一例にまたしても中間的なものが見つかる。
「移行空間」(乳幼児に自己と非自己の橋渡しをする領域)や「移行対象」(幼児の初めての外的所有物とその経験的範囲の触知可能な記号)という概念を用いてウィニコットが研究したのは、主に幼年期の中間領域についてであった。彼は、こうした統覚と知覚の中間領域は「成人になっても、芸術や宗教においては本質的に具わっている」と主張し、さらに「他者に対して、他者が有していない幻影を共有するよう(……)強く要求するような症例は、明らかな精神異常の兆候である」と述べている。
乳幼児が外部を認識したり、認識した外部を記号に置き換える中間的な領域が大人になっても芸術や宗教の領域で持ちいられるという指摘は、「デザインの誕生」で言及したマニエリストたちのディセーニョ・インテルノ=内的構図にも通じる。
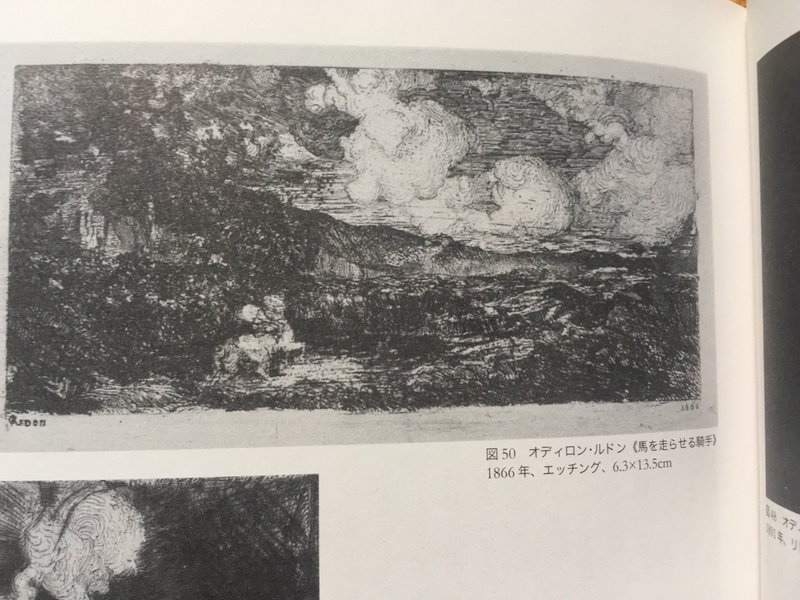
また、もう1つの精神分析からの参照例では、僕が「変容」に中間的なものを感じると書いた意味で、イメージを動的に捉えすぎることで知覚対象をうまく認識できない例が紹介される。
一方、精神科医のレオ・ナヴラティルは、分裂病患者の線画作品の研究を通じて、「前=形態」の経験を重視する創造モデルを提起している。この経験のもとでは、(非具象的な)構造的特徴よりは、(具象的な)外見的特徴が優先され、形態と背景の区別も明確にはなされないし、また、知覚対象はつねに動的にみえるため、イメージが継続的に変容し続けるのだという。この経験は、極度の緊張や恐怖を伴ったり、あるいは極度の環境への固執を伴ったりして、思い通りにイメージを修正できなくさせることがあるとも述べている。
イメージを形態としてのみ捉えてしまい、その構造を把握できなければ、いわゆる分類的思考が働かない。
そのことは、ゲーテが、リンネが植物を静的な構造として捉えて分類しすぎ、その生長を考慮していないといって「植物メタモルフォーゼ」という植物の生長=変容に焦点を充てた学問を創始したことからも想起させる。
茫漠として不確定なイメージ
ゲーテが動的に形態というものを捉えようとしたという話の流れで、もうひとつガンボーニからの引用。
しかし、サルトルもまた、こうした動的な性質をイメージの本質と捉えていたようで、イメージを「一種の茫漠たるもの、根本的に不確定的なもの」と特徴づけている。また彼は、知覚とイメージの対立を相対化しつつ、「外的要素と心的要素を統合する中間領域に属するもの」の存在も認めていた。彼によれば、中間領域に属するのは、たとえば「炎のなか、あるいはタピスリーのアラベスク模様のなかに、人間の顔を読み取ったりするとき、あるいは、眠りに入るときなどに」みられる現象である。
サルトルによっても、イメージは本来動的であり、それゆえ、不確定だとされる。そして、やはり、ここでも中間が登場する。
さらにこの現象が起こる条件を主体と客体の双方から説明し、主体の側からいえば「緊張緩和の状態」・「半睡状態」・「催眠状態」などにこの現象が起こり、一方、客体の側からいえば「表の姿と秘密の姿をもつ脆弱で曖昧な形態」(ガラス玉やコーヒーの垂らした跡を用いる伝統的な占いのような)「絶えず人目を引きつつその眼を欺く性質をもつ形態」がこの現象を誘発すると述べている。
このあたりの話は「しみとデザイン」で取り上げた、レオナルド・ダ・ヴィンチの壁のしみからの創造という話も想起させる。

その延長線上にあるのがガンボーニがこの本で論じる20世紀の両義性をもった絵画だろう。それらは何かあるものとして定まった状態を描いたというより、これからまさに生成してくる何らかのものを描いているのかもしれない。
あるいは、すべてのものは生成してくるものだろうか?
すべての形態、とくに有機物の形態をよく眺めると、どこにも持続するもの、静止するもの、完結したものが生じてこないことに気がつく。むしろ、すべてのものは絶えず揺れ動いているのである。それゆえドイツ語は、形成という言葉を適切にも、すでに生み出されたものについても、また現に生み出されつつあるものについても使うことにしているのである。
と、ゲーテは先の『植物メタモルフォーゼ』で書いている。
当たり前といえば当たり前だが、形成は、静止したもの、完結したものからは生じない。同様に、しみのような不定形なものが想像を働かせるし、複数の像やデータの間に新たな発見は生じる。
定義されたもの、固定化したもの、確固としたもの。そうしたものから何かが生まれてくる気はしない。
何かを創造しようとしたら、あるいは、何かをデザインしようとしたら、謎めいて蠢く中間領域にこそ足を踏み入れてみないといけないのだろう。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
