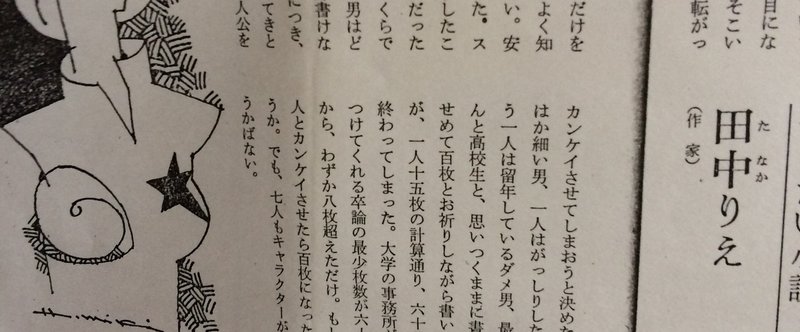
書きたい小説 (素敵な女性)
今年の四月、大学時代に書いた小説が講談社から本になった。この本にのっている五つのはなしもいれて、まだ十コぐらいしか小説を書いたことがない。大学三年から文芸科にはいり、レポートとして小説を書くまでは。小説を書こうなんて気はまったくなかった。書きたいことがあって書いたわけじゃないので、できた小説はどれも短い。本の題になった、『おやすみなさい、と男たちへ』がいちばん長くて、六十八枚。ほかは、二十枚から三、四十枚どまり。どうせ書きはじめたんだから長く書きたいと思って書いているのだが、すぐに終わってしまう。もともと本人の性格がサッパリしているので、小説の主人公をしつこい性格にできないのも、はなしがすぐ終わってしまう原因のひとつだろうが。
『おやすみなさい、と男たちへ』は卒業論文だ。卒論指導の先生に、「このさい、二百枚ぐらい書いてみたら」といわれ、せめて、百枚は書きたいと思い、はなしを長くするにはどうするか、それだけを考えた。長いはなしなら、自分のよく知っている世界でなければ書きづらい。安直に主人公は大学生の女と決まった。ストーリーは、やっぱり、男とどうしたこうしたというのになるなあ、それだったら、まわりを見わたせばネタはいくらでもころがっていそうだし。相手の男はどうしよう、一人だけだったら長く書けない。なにしろわたしは、一人の男につき、十五枚平均しか、書けないのだ。てきとうに違ったタイプの男、四人と主人公をカンケイさせてしまおうと決めた。一人はか細い男、一人はがっしりした男、もう一人は留年しているダメ男、最後はなんと高校生と、思いつくままに書いた。せめて百枚とお祈りしながら書いたのだが、一人十五枚の計算通り、六十八枚で終わってしまった。大学の事務所が受けつけてくれる卒論の最少枚数が六十枚だから、わずか八枚超えただけ。もし、七人とカンケイさせてら百枚になっただろうか。でも、七人もキャラクターが思いうかばない。
だから、いいわけになるのだが、なにも、わたしは、平気で複数の男と寝る女子学生を描きたくて『おやすみなさい、と男たちへ』を書いたわけじゃない。長く書かなきゃ卒業できないから、ただひたすら長く長くストーリーを考えているうちに、ああなってしまった。
それなのに、本を読んでぜんぶわたしの体験だと思うひとがいる。男性週刊誌の取材をうけたとき、男性記者二人から、「あれは事実だろう」とせまられ、「そんな、じっさい、あんなにつごうよくつぎつぎと男が四人もあらわれてくれるもんじゃないでしょ」と笑ってごまかそうとすると、「いいや、男はムリだが、女だったら本人さえその気になれば、いくらでもこなせる」なんて、ムチャクチャなことをいわれた。
知らないひとだったらまだいいけれど、父の友だちに電話で、「いやあ、おもしろかったけど、じっさいにりえちゃんがあんな体験したかと思うと、驚きだねえ」なんていわれると、恥ずかしくて、いやんなっちゃう。
これだけ困って六十八枚。ちょっとは長いのも書いてみたいけど、とうぶんダメみたい。だいたい、ふだんは小説のことほとんど考えてない。大学を卒業して一年間勤めた会社を五月にやめてから、夏のあいだはずっと夏休みだった。今は秋休み。七月には二十日間北海道に行き、八月は十日間、九州の伯父さんの家にいて、大阪のナンバと梅田の花月に寄って帰ってきた。
伯父さんの家から歩いて五分で海。毎日、ビーチパラソルの陰で空気枕を頭に、ラジオをきいていた。唐津の近くなので、韓国の放送がきれいにはいる。一日中、寝っころがっていれば、たまには長篇の構想でもねろうかしらと、小説のことを思いだすのだが、人気のない砂浜で韓国演歌をきいてると、日本にいる気もしなくなり、頭のなかがボワーっとまっしろになって、なにも考えられない。たったひとつだけ思いうかんだのが、次のはなし。
ある日の夕方、男が海辺を歩いていると蝶ネクタイをしめたカメが寄ってきて、「お兄さん、いいコがいるんだけど、飲んでかない」と誘われる。カメの背にゆられて海の底に行けば、そこは、キャバレー・龍宮だった。乙姫ギャルたちの大サービスにうかれて時がたつのも忘れて遊び、もらったばかりのボーナスをぜんぶとられてしまう。しょんぼりした男を岸まで送ったカメは、おみやげに玉手箱をくれた。ふたをあけると、モクモクと白い煙が立ちのぼった。箱のなかをよく見ると、ドライアイスと、白髪のかつらと、やはり白髪の長い付けひげがはいっていた。男はかつらとひげをつけて、奥さんに朝帰りのいいわけをどういおうか考えながら、家にむかってトボトボと歩いていった。
これじゃあ、やっぱり、長篇にならないね。
(よろしかったら投げ銭お願いいたします)
続きをみるには
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
