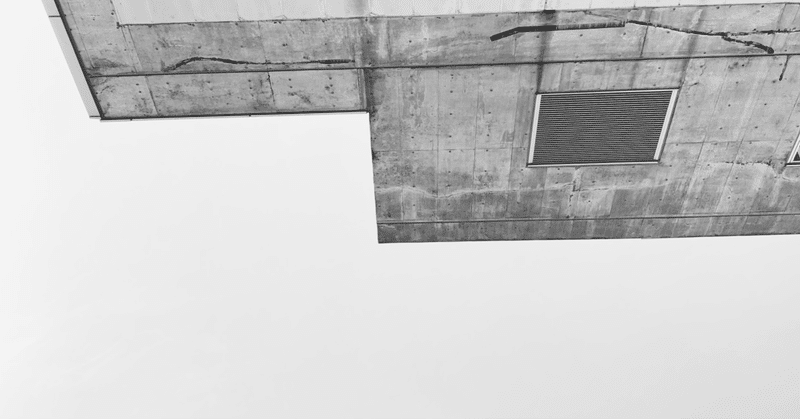
わたしはいつも一人だった。
わたしはいつも一人きりで立っていた。立ち尽くしていた。悠々と生い茂る緑に、美しい水をたたえる泉に目を奪われながら、わたしの周りには顔のない亡霊しかいなかった。目に映るものすべてが美しかった。すべてを愛していた。そこに嘘はないと断言できた。
真上からそそぐ太陽は暖かくわたしを包んでくれたし、その光を反射した水面のきらめきは不規則に揺れる葉に翳って、わたしを魅了した。
わたしは只管歩いた。この感動を誰かと分かち合いたかった。わたしの言葉が、遠い昔に誰かがばら撒いた宝石たちの合間をすり抜けて消えていった。最後には足音だけが残り、それも終わった。
突然、大きな虚無がわたしを襲った。輝きたちが一瞬にして色褪せ、廃墟へと変わった。誰にも伝えられないのなら、存在しないのと変わらないじゃないか。絶望のなかでわたしは叫んだが、顔のない亡霊たちは体を揺らして笑うだけだった。わたしは地面にへたり込んだ。
そしてまた時は経った。人はいつしか絶望にすら倦むもので、わたしは再び歩きだした。まったく人間というのは良くできている。生きることを志向してしまう。森の途中で見つけた切り株に腰掛けてわたしはりんごを齧った。この世界は、あまりにも豊かだ。
そうしてわたしは理解した。鳥の鳴き声が、木の葉のざわめきが、すべてがわたしを祝福していた。もう完成されていたんだ。誰かに伝えることで初めてそこに世界があらわれるだなんて、愚かで傲慢な勘違いだった。
芯だけになったりんごを放り出し、わたしは走った。世界に溶け込んだわたしは、幸福感に満ちていた。息づかいや、躍動する肉体が、わたしのすべてだった。わたしが世界そのものだった。
今日も森では顔のない亡霊たちが踊っている。
寿司が食べてえぜ
