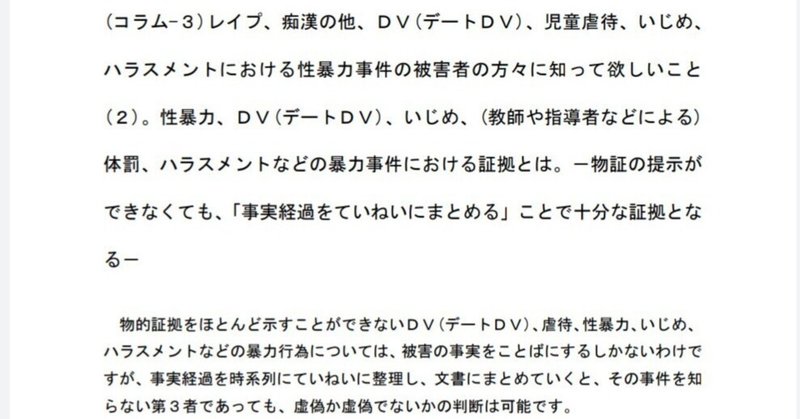
(コラム-3)レイプ、痴漢の他、DV(デートDV)、児童虐待、いじめ、ハラスメントにおける性暴力事件の被害者の方々に知って欲しいこと(2)。性暴力、DV(デートDV)、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力事件における証拠とは。-物証の提示ができなくても、「事実経過をていねいにまとめる」ことで十分な証拠となる-
物的証拠をほとんど示すことができないDV(デートDV)、虐待、性暴力、いじめ、ハラスメントなどの暴力行為については、被害の事実をことばにするしかないわけですが、事実経過を時系列にていねいに整理し、文書にまとめていくと、その事件を知らない第3者であっても、虚偽か虚偽でないかの判断は可能です。
なぜなら、虚偽のときは、必ずどこかでつじつまが合わない、論理破綻をおこすからです。
つまり、文面の「証拠があったからできた」ことではなく、被害の事実をていねいに文書にまとめることで、「事実を説明」することで、十分な証拠とすることができます。
あとは、加害者とやり取りをしたメール文、やり取りを録音した(留守電に記録された)音源データ、写真、診断書などがあれば、それらを文書としてまとめた「事実」の裏づけ(根拠)としていきます。
では、証拠として、「事実経過を時系列にていねいに整理し、文書にまとめていく」重要性を理解していただくために、「コラム-3」でとりあげた「近親者(おじ)による性的虐待被害を受けた被害女性(提訴時30歳代)が、PTSD、離人症性障害、うつ病などを発症し、最後の性的虐待被害を受けた小学校4年生の夏休みから20年以上を経過した平成23年(2011年)4月、30歳代(提訴当時)の女性が、おじに対して約4,170万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審」に少し踏み込んでみたいと思います。
以下の文中に、文中に『準備書面』という文言がでてきます。
「準備書面」とは、民事訴訟において、訴訟の当事者が、次の口頭弁論で陳述する事項をあらかじめ記載して裁判所に提出し、同時に、相手方に送達しておく書面のことで(民事訴訟規則79条)、口頭弁論は、書面で準備しなければならない(民事訴訟規則79条)との規定にもとづいています。
以下、この性的虐待事件の事実経過の要約に、私が解説を加えたものです。
『 昭和53年1月上旬、祖父母宅において、叔父は、3歳10ヶ月の被害女性の体をなで回すなどの行為に及び、以降、叔父は同宅において、毎年1月上旬と8月の2回、被害女性へのわいせつ行為を繰り返し、行為をだんだんとエスカレートさせていきました。
昭和57年8月中旬、叔父は同宅において、8歳5ヶ月の被害女性を布団の中にひき込み、着衣の上着を脱がせたうえ、わいせつ行為に及び、昭和58年1月上旬には、叔父は同宅において、8歳10ヶ月の被害女性に対し、布団の中にひき込み、着衣を脱がせて裸にし、わいせつな行為をおこなったうえで、姦淫するに至りました。
続く、同年8月、再び姦淫被害を受けることになりました。
つまり、被害女性が正月や盆に親の実家に帰省するたびに、性暴力被害にあっていたことになります。
これに対し、被告の叔父は、原告の被害女性の身体を触るなどの行為が平成56年1月から平成58年1月までの4回程度あったことは認めたものの、姦淫行為があったことは否認しました。
「準備書面(21頁)」には、『虐待行為のたび、加害者は被害者に対して「他の人にはいってはダメだよ」等といい、口止めをしてきました。
その結果、被害者は「親や祖父母などに知られたら何か大変なことになるんじゃないかとか、家族や親戚中がもめたり、ぐじゃぐじゃになったりして、すべてが崩壊してしまうんじゃないか、自分さえいわれるままに黙っていれば何事もなかったように進むんだろうか、自分さえがまんすればいいということなんだろうかというふうに思いました。」と、当時の被害女性の苦しい心内が述べられています。
現に、大人になった被害女性は、父親に哀しい体験を打ち明けようとしたとき、父親は耳を傾けることなく、「聞きたくない」と拒絶しています。
被害女性の弁護団は、子どもに対する性的虐待については、「損害賠償請求権の除斥期間の起算点を成人時と解すべき」と主張し、その理由を「準備書面(1)(38頁)」で、『性的虐待が親族間でなされた場合、その性質上、未成年者の法定代理人が、未成年者を代理して損害賠償請求権を行使しうることは困難である。権利行使によって、犯罪行為という身内の恥をさらす結果となり、親族関係を破壊する結果を招くからである。』と述べています。
つまり、子どもが親族から受けた性的虐待については、子ども本人が訴えることも、親が代わりに訴えることも難しいことから、被害者が成長し大人になってから権利を行使できるようにすることが必要です。
この高等裁判所判決では、この点については認められませんでしたが、今後、被害者救済の政策や法改正を考えるうえで重要なポイントになってきます。
さらに、「準備書面(2)(5頁)」では、『そして成長するにつれ「小学生のころから早く死にたい、消えたいと考え、にやにやして近づいてくる加害者であるおじの顔が急に近づいてくるような気がして、フラッシュバックを週に何度も起こし、悪夢にうなされながら生きてきた。』と、昭和58年1月、小学校3年生の冬休みに姦淫被害にあって以降、被害女性はフラッシュバックに苦しくことになった状況が述べられています。
さらに、被害女性は睡眠障害、回避症状、離人体験に悩まされ、高校生になると摂食障害、自傷行為に苦しむことになります。
被害女性は、小学生から死を願い、悪夢にうなされながら生きてきたのです。
そして、平成18年9月ころから、被害女性(31歳)は、著しい不眠、意欲低下、イライラなどの症状に悩まされ、うつ病の疑いと診断され、平成20年ころになると、仕事がまったくできない状態が続くことになります。
そして、平成23年3月11日の東日本大震災の報道をきっかけに、自らが苦しんできた諸症状がPTSDによるもので、その原因が性的虐待にあることを自覚するに至り、同年4月、医師から「心的外傷後ストレス障害・抑うつ状態」と診断されています。
1審で、被告の叔父側は「自らが行為をおこなってから25年以上が過ぎ、原告の女性がうつ病やPTSDと診断されたのもごく最近である。」として、「原告の症状は、いまの結婚生活など、これまでの生活状況がストレスになっている可能性が高い。」と主張していますが、札幌高等裁判所の判決では、精神科医の尋問を踏まえ、原告(被害女性)は被告(おじ)から性的虐待行為を受けたことにより、昭和58年ころ、PTSD及び離人症性障害、高校在学中に摂食障害を発症し、平成18年9月ころ、うつ病を発症した」ことを認定しています。
一方で、PTSD及び離人症性障害、摂食障害を発症したことを理由にした損害賠償請求権は、被害女性(原告)が訴訟をおこした平成23年4月には除斥期間が経過していましたが、「平成18年9月ころに発症したうつ病は、PTSD及び離人症性障害、摂食障害にもとづく損害とは質的にまったく異なるものである。また、うつ病の損害は、性的虐待行為が終了してから相当期間が経過した後に発生したものと認められるとして、除斥期間の起算点は、損害の発生したとき、つまり、うつ病が発症した平成18年9月ころというべきだ」としました。
「PTSDは昭和58年ころに発症しており、20年が経過しているが、うつ病は平成18年に発症したもので、20年は経過していない。そして、そのうつ病の発症の原因は性的虐待にあったことを本人が知ったのは平成23年2月であり、訴訟を起こした平成23年4月の時点で3年も経過していない。したがって、時効・除斥期間は成立しない。」との考えを示し、被害女性の損害賠償請求を認めました。
そして、「控訴人(被害女性)が、被控訴人(加害者の叔父)から本件性的虐待行為を受けたことで、極めて重大、深刻な精神的苦痛を受けたことは、当該行為を受けてから、子供時代、就職、進学、結婚といったライフステージを通じて、…生活上の支障、心身の不調に悩まされたほか、妊娠、出産、育児に対する不安感、恐怖感を感じていたことから容易に想定できる。また,控訴人(被害女性)は、本件性的虐待行為を受けた後、…生活上の支障、心身の不調に悩まされながらも、…やりがいを持って働いていたが、うつ病を発症したことにより、…勤務だけでなく、身の回りのこともできなくなったものである。…現時点では症状が軽快したものの、辛うじて日常生活が営める状態になった程度にとどまるものであり、発症から約8年が経過しても、いまだ相当期間の治療を余儀なくされる状況で、寛解の見通しも立っていない。このような事情のほか、本件性的虐待行為の内容、期間及び頻度、平成23年3月17日における話合い以降現在に至るまで何ら謝罪の姿勢を示していない被控訴人(加害者の叔父)の対応など、本件訴訟で現れた事情を総合考慮すると、控訴人(被害女性)の精神的苦痛を慰謝するための慰謝料は、2000万円とするのが相当である。」と損害賠償額の根拠を示しています。
さらに、この釧路地方裁判所と札幌高等裁判所の判決で重要なことは、被害女性の供述は、「性的虐待行為の具体的な時期、及び内容について、その記憶のとおりに述べたものとみるのが相当である。」とし、一方の加害男性(叔父)の主張は、「その正確性に疑いを入れざるを得ない。」とし、「概ね被害女性が主張するとおりのものであった。」と、3歳10ヶ月-8歳10ヶ月のときの記憶を間違いのないものと認定していることです。 』
このように、「準備書面」で示したことをもとに、口頭弁論が実施され、それにもとづいて、事実認定をするか、しないかが判断されます。
その判断が、判決につながります。
少し私ごとで説明します。
私の主活動は、「婚姻破綻の原因は、配偶者からのDV行為である」として、被害者が夫婦関係調整(離婚)調停や監護権者指定の審判を申立てた家庭裁判所で、DV行為としての暴力の事実と、その暴力被害による後遺症としてPTSD、その併発症としてのうつ病を発症したことを、被害者のアドボケーターとして『レポート((被害の事実と後遺症、その経過))』にまとめ、DV行為としての暴力の事実を立証することです。
DV事件では、被害者が被虐待体験をしているとき、長期化、複雑化します。
そして、「DV行為としての暴力」の物的証拠は、刑事事件化するような苛烈な身体的暴力を受けない限りほぼ存在せず、基本的に、ことば(文字)で、いつ、どういう状況で、こういう暴力を加えたと主張します。
その主張の数々に、わずかな物的証拠がないかさまざまなアプローチをしていきます。
地道に、時間をかけて(かなりの労力を費やして)、こうしたことを積み重ねて、ひとつのことばでまとめた「状況証拠書(レポート)」なるものをつくりあげます。
ことば(文字)で被害の事実を立証するポイントは、他の解釈はできないように、行動科学、(発達)心理学、医学的に裏づけできる説明をていねいにすることです。
つまり、加害者に反論の余地を与えない記述ができれば、十分な証拠能力を得ることができます。
確かに、被害を受けたという物的証拠はほとんどありませんが、一方の加害者も暴力を加えていないことを立証する物的証拠を示すことはできません。
被害者の多くの人たちは、「自分が被害を受けた証拠を示せない」ことばかりに囚われ、加害者も同じということに気づいていないので、戦う相手が巨大な壁のように怖れてしまっています。
しかし、加害者にはなく、被害者だけが示すことができる物的証拠があります。
それは、被害者自身の心身が示す体調不良(PTSD、その併発症としてのうつ病の症状や傾向を含む)です。
そのため、「診断書」が大きな役割を担います。
しかし、単なる病名や処方薬だけが記載された「診断書」はあまり意味を持ちません。
そこで、必要となるのは、「暴力行為がその後遺症として・・を発症した」との“因果関係”を詳細に説明している「意見書としての診断書」です(*別途、「コラム-4 DV離婚事件、性暴力事件など、証拠としての「診断書」をどう捉えるか」で詳述します)。
重要なことは、「示されているこの症状や傾向は、こういうトラウマとなり得る体験をしていない限り、あり得ない」と逆説的に主張することです。
例えば、DV(デートDV)、虐待、いじめ、(教師や指導者などの)体罰、ハラスメントなどを暴力行為繰り返し受けるようになり、家に夫が帰ってくる、学校から家に帰宅しなければならない時間が近づいてきたり、登校したり、出社したりする時間になったときに「頭痛」、「腹痛」、「動悸」、「震え」の身体的な症状を示すことはよくあります。
これらは、PTSDの初期の症状、つまり、ASD(急性ストレス障害)の症状です。
前の2つは「PTSDの身体化」の症状で、後の2つは「PTSDの過覚醒によるパニックアタック」の症状です。
疾患の症状や傾向の正しい知識により、示している症状や傾向と結びつけることができます。
例えば、その症状や傾向がいつごろからあったかがわかれば、その症状や傾向を示す原因となったできごとがいつごろにあったのかと事実に近い類推ができます。
そこで、重要になるのが、『別紙2 性暴力、DVと面前DVの影響、後遺症としてのPTSD』にまとめている基礎知識です。
例えば、ストレス(脅威/恐怖)を覚えたときに、なぜ腹痛を起こすのか、ASDを発症するメカニズム(脳内物質が分泌され、どの器官(部位)がどういう反応をするのかなど)は存在するのかなど、その見えない(わからず、理解を得られ難い)ことを医学的な根拠を持って説明する(ことばにします)ことができます。
性暴力事件で、被害者をひどく傷つける2次加害となる「なぜ、被害を受けているとき声にならないのか、逃げられないのか?」は次のように説明できます。
『 では、危機に遭遇したとき、人のからだでなにが起きているのか、ホメオスタシスの維持が危うくなるそのメカニズムを説明する。
トラウマ(心的外傷)体験となる危機に遭遇すると、脳のⅰ)「視床」は、危険の情報をキャッチし、ⅱ)「扁桃体」が危険信号をだす。
そして、ⅲ)「視床下部」で、「CRFホルモン」が「脳下垂体」を刺激し、ⅳ)「脳下垂体」は、「副腎」を刺激し、緊張ホルモン「コルチゾール」「アドレナリン」を分泌させる。
その結果、ⅴ)「脳幹」が血圧を上げ、心拍を早くし、血糖値を上げる。
「CRF(cortictropin releasing factor:副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン)」は、視床下部から分泌されるペプチドホルモンのひとつで、「ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)」の放出を刺激する。
CRFが分泌され、前頭連合分野に伝達されると「不安」が生じる。
その不安を抑えるために、抑制性の神経伝達物質「セロトニン」の分泌を亢進させ、抑制性の神経伝達を亢進させることで、「前頭連合野」の興奮を抑制することができると不安が解消される。
慢性的なストレス刺激は、「扁桃体」を異常に興奮させるので、CRFの分泌が異常に促進し、不安が強まる。
「セロトニン」がその不安を抑制することができないと、理由のわからない不安感に苛まれることになる。
「コルチゾール」や「アドレナリン」などの緊張ホルモンが、脳や体内に回って、危険と立ち向かう超人的な力をださせたり、物凄い勢いで逃げたり、気絶したりするなどの反応をおこさせる。
このことを「HPA機能」という。
その結果、ⅵ)「前頭葉」とことばをだす「ブローカー野」は機能を停止する。
この「HPA機能」の結果、「ⅵ)「前頭葉」とことばをだす「ブローカー野」は機能を停止する。」ことが、フリーズと呼ばれ、レイプされたり、殴られたことのない人がはじめて殴られたりしたときに、「助けて!」が声にならなかったり、茫然と佇んだり、逃げられなかったりする状態である。
予期できないできごとは、恐怖が拡大し、「扁桃体」の興奮が続くと「ストレス障害」になる。
大脳辺縁系の「扁桃体」は、恐怖感、不安、悲しみ、喜び、直観力、痛み、記憶、価値判断、情動の処理、交感神経に関与している。
「扁桃体」は神経細胞の集まりで、情動反応の処理と短期的記憶において主要な役割を持ち、情動・感情の処理(好悪、快不快を起こす)、直観力、恐怖、記憶形成、痛み、ストレス反応、特に不安や緊張、恐怖反応において重要な役割を担っている。
味覚、嗅覚、内臓感覚、聴覚、視覚、体性感覚など外的な刺激を「嗅球」や「脳幹」から直接的に受け、「視床核(視覚、聴覚など)」を介して間接的に受け、「大脳皮質」で処理された情報、および、「海馬」からも受けとる。
また、扁桃体は、「記憶固定」の調節にかかわる。
学習したできごとのあとに、そのできごとの長期記憶が即座に形成されるわけではなく、そのできごとに関する情報は、記憶固定と呼ばれる処理によって長期的な貯蔵庫にゆっくりと同化され、半永久的な状態へと変化し、生涯にわたり保たれる。
衝撃的なできごとが起こる(トラウマとなり得る体験をする)と、そのできごとは、「海馬」を通して大脳に記憶として生涯的に残る。
この衝撃的な記憶を反復して思いだす(トラウマを追体験する)ことにより、「扁桃体」が過剰に働く。
つまり、強い不安や恐怖、緊張が長く続くと「扁桃体」が過剰に働きストレスホルモンが分泌され長く続くことから、神経細胞が萎縮して他の脳神経細胞との情報伝達に影響し、「うつ病」の症状が発現する。
これが、PTSDの併発症としてのうつ病を発症するメカニズムである。 』
こうした説明ができると、「「助けて!」と大声をあげたり、逃げたりしなかったのは、被害がなかったからではないか?!」といった非難の声を封じ込めることができます。
「多くの被害者がそうだから」といった印象論ではなく、科学的に根拠を説明することで、2次加害を防ぐ(封じ込める)ことができます。
個人的には、司法の場で、こうした根拠を示すときには、心理学用語ではなく、医学用語、つまり、医学的に説明することが説得力があると考えています。
なぜなら、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力などの暴力事件で、加療を要する傷害について証言は、精神科医、その証言する専門分野の医師に求められることが圧倒的に多いからです。
また、発達期に受ける虐待事案では、ネグレクト、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待で受けるダメージがなにに及ぶのか、加えて、MRI画像診断で、それぞれの虐待行為によりどの部位が萎縮したり、肥大化したりするなど視覚化することも明らかにすることができます。
加えて、乳幼児期、学童期、思春期(前期10-12歳/後期12-13歳)、青年期(前期10-12歳/後期12-13歳)のどの時期に虐待を受けたが、人が身につけていく概念や価値観(考え、判断し、行動する根底となるもの)のなにを身につけられ、なにを身につけられていないのかを示すことができます。
こうしたバックボーンが、「この症状や傾向を示すには、こういうトラウマとなり得る体験をしていない限り、あり得ない」と逆説的に主張する根拠となります。
つまり、根拠(裏づけ)のある説明ができれば、反論の余地はなく、反論してきても、逆に、それは根拠のないもの(ただのいいがかり)になります。
最後に、警察官は権威に弱い(気がひける)傾向があるので、民事事件で「暴力行為により精神的苦痛を被ったことに対する損害賠償金の支払い」を求め、その判決を持って、刑事事件に持っていく方法もあると考えます。
つまり、民事事件の判決が“権威”に相当するということです。
例えば、民事事件で、「婚姻破綻の原因は、配偶者の夫のDV行為であり、そのDV行為により精神的苦痛を被ったことに対する損害賠償金(慰謝料)の支払い」を求めて、その判決(調停では合意)にもとづいて、「加害者は暴力行為を認めた」、あるいは、「・・家庭裁判所は暴力行為を認め、損害賠償金の支払いを命じた」という状況で、警察に苛烈な身体的暴力などの被害届(あるいは、捜査の強制力のある「告訴状」)を提出する方法です。
稀な」「例がない」は「できない」につながりやすい思考なので、「できる方法はないか」にフォーカスすると、解決策につながるいろいろな切り口があることに気づきます。
あと最大の問題は、被害の事実やその後遺症の症状や傾向を詳細にまとめることがトラウマの追体験となり、「気が狂うほど苦しかった」と述べるほど過酷な作業になる可能性があることです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
