
Symmetry / Peter O’Mara
今回はAustralia出身のギタリストPeter O’Maraの1994年作品「Symmetry」を取り上げたいと思います。全曲メロディアスで良く練られた構成からなるオリジナル、作曲者の意図を確実に踏まえ巧みにサポートするリズムセクション、そしてフロントに名手Bob Mintzerを迎え存分に演奏させた充実の作品です。
All Compositions by Peter O’Mara Recorded and Mixed 24-26 May 1994 at “Systems-Two” Recording Studios, Brooklyn, NYC by Joe & Mike Marciano GLM Label, Germany
g)Peter O’Mara ts, ss)Bob Mintzer b)Marc Johnson ds)Falk Willis
1)Fifth Dimension 2)The Gift 3)Catalyst 4)Seven-Up 5)Chances 6)Symmetry 7)Steppin’ Out 8)Expressions 9)Blues Dues
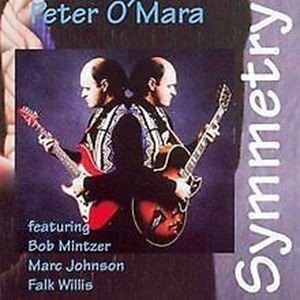
1957年12月Australia, Sydney生まれのPeter O’Maraは地元の音楽学校やJamey Aebersold, Dave Liebman, Randy Brecker, John Scofield, Hal Galperら米国ミュージシャンのクリニックで多く学びました。80年にAustraliaのJazz作曲部門コンテストで一位に輝き同年初リーダー作「Peter O’Mara」をリリースし、海外留学の資格も得て81年NYCで様々なミュージシャンに師事しました。同年暮れからGermany, Munichに移住し90年には欧州のWeather Reportと呼ばれたサックス奏者Klaus Doldinger率いるバンドPassportに参加(個人的にはWRには聴こえず、いわゆる”フュージョン”グループです)、欧州、 南アフリカ、Brazilでのツアーを経験しました。現在までに共同名義を含め10作以上のリーダー作を発表、音楽教育でも精力的に活動しており教則本を4冊出版(日本でも翻訳されています)、YouTubeでギター講座を展開しています。
初リーダー作Peter O’Mara
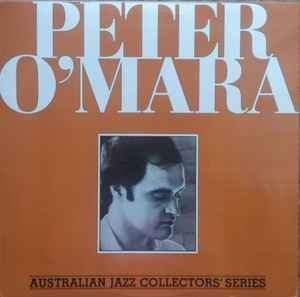
O’Mara参加Klaus Doldinger & Passportの作品Down to Earth

早速演奏曲について触れて行きましょう。1曲目Marc Johnsonの力強いベースパターンから始まるFifth Dimension、米国に同名の5人編成R&Bコーラス・グループがありますが、こちらは文字通り5拍子のナンバーです。A-A-B-A構成のこの曲、テーマをBob Mintzerがテナーで演奏しますが、初めのAでユニゾンで演奏するO’Maraのギターが次のAからハーモニーに転じサウンドを厚くしています。サビのBセクションの展開もイケてます!オープニングに相応しいインパクトのあるキャッチーなテイストを持つ、大好きなナンバーです。それにしてもMintzerの音色の素晴らしさと言ったら!太くてダークでコクがあり、ハスキーな成分が含まれるバランス感は絶妙です!何度か彼のライブを聴きましたが、この人の生音はさほど大きくはなく、特に派手な楽器の鳴りという認識はありませんでした。いわゆるマイク乗りの良い音、倍音成分が豊かで録音しても音痩せする事がなく、音の旨味成分がしっかりとレコーディング媒体に残される傾向にあります。効率の良い鳴らし方のテナー奏者のひとりと言えるでしょう。随所に的確でソリッドなフィルインを入れるMunich出身のドラマーFalk Willisは録音時24歳になったばかり!タイム感、グルーヴ、センス、そしてJohnsonのベースのコンビネーションともに申し分ないと思いますが、ドラムの音色がややラウドな傾向にあるので、もう少しコンパクトにまとまっていればバンドサウンドにより溶け込めたように思います。セットチューニングや録音の関係とも考えられますが、ジャケ写を見るとかなり身長のある人なので腕が長く、スティックを振り下ろすストロークがあるのでしょう、特にスネアや皮ものが鳴ってしまうのかも知れません。テーマ後のテナーソロ、5拍子をものともせずタイトなリズムで巧みに、緻密に、スペースを保ちながらストーリーを展開して行きます。曲の持つ雰囲気や構成に全く合致していて、曲の裏メロディでは、と見誤る程のクオリティを感じさせる、更には予め書かれたかのような次元のアドリブですが、同時にスポンテニアスでもあります。High F#音やフラジオB音の音の割れ具合にはグッと来てしまいます!サックスの高音域を割れた音色で確実にヒットさせるにはむしろアンブシュアがルーズでなければ出来ず、こちらでも理想的な奏法のプレイヤーと言えます。ギターのバッキングも付かず離れず、Mintzerに好きに演奏させるべく浮遊感を感じさせるアプローチに徹しているようです。その後のギターソロはこれまた素晴らしい音色でのプレイです!タイムとしてはかなり前ノリで、ジャズよりもロックのテイストが強いグルーヴ、ソロのアプローチのように感じますがコーラス、ディストーション、ハーモニクスを交えたソロはテナーと良い対比をもたらしているように聴こえます。Johnsonのベースがしっかりとリズムの芯となりバンドの要を担当しており、アクティブな他のメンバー3人の後見人のような役割を果たしています。ラストテーマはサビには行かずにA-Aでカットアウト、Fineです。
2曲目は一転してスイングのリズム、柔らかいムードの佳曲The Gift、美しくナチュラルな雰囲気を湛えています。メロディラインの間に入るMintzerのフィルインも出過ぎず丁度良い語り口です。先発ソロは先ほどの演奏で出番がなかったJohnsonのベースから。正確なピッチ、美しい音色、よく歌うピチカートのラインからはテクニシャン、そして都会的なセンスを感じます。ソロのバックでのWillisのブラシワークも巧み、さり気なくスティックに持ち替えてMintzerのテナーソロへ。穏やかさを基本にしながらも、いきなり鋭利な刃物のような切れ味鋭い、テンションを多く含んだフレージングを、端正なグルーヴで繰り出す様はさすがユダヤ系プレーヤー、知的で大胆です!4’00″からのフレーズはMichael Breckerも70年代使用したJoe Hendersonのもの、おふたりJoe Henも研究したのですね。続くO’Maraのソロは先ほどとは打って変わりタイトな8分音符を主体としたアプローチ、ジャズギタリストとしての真骨頂を披露してくれており、音使いの選び方もとっても好みです!
3曲目Catalystはアップテンポのスイング、ここでのWillisのシンバルを主体としたドラミングは皮ものの鳴りが少なくなるので、ラウドな傾向は影を潜めます。イヤー、カッコいい曲ですね!メロディの組み合わせ方の妙と言いますか、何処かで聴いた事のあるフラグメントの配置の仕方、再構築に作曲者のセンスを感じます。テーマ部分はテナー、ギター、ベースがユニゾンでメロディ奏、先発ギターソロからベースがバッキングを担当します。John Aebercrombieを彷彿とさせるギターソロは、ギターキッズならば頷かざるを得ないクオリティの内容です!ドラムのアイデア豊富なバッキング、ベースの変幻自在なサポートがトリオのインタープレイの次元を高めています。79年録音Abercrombieの作品「Abercrombie Quartet」でのバンドの一体感をイメージしました。
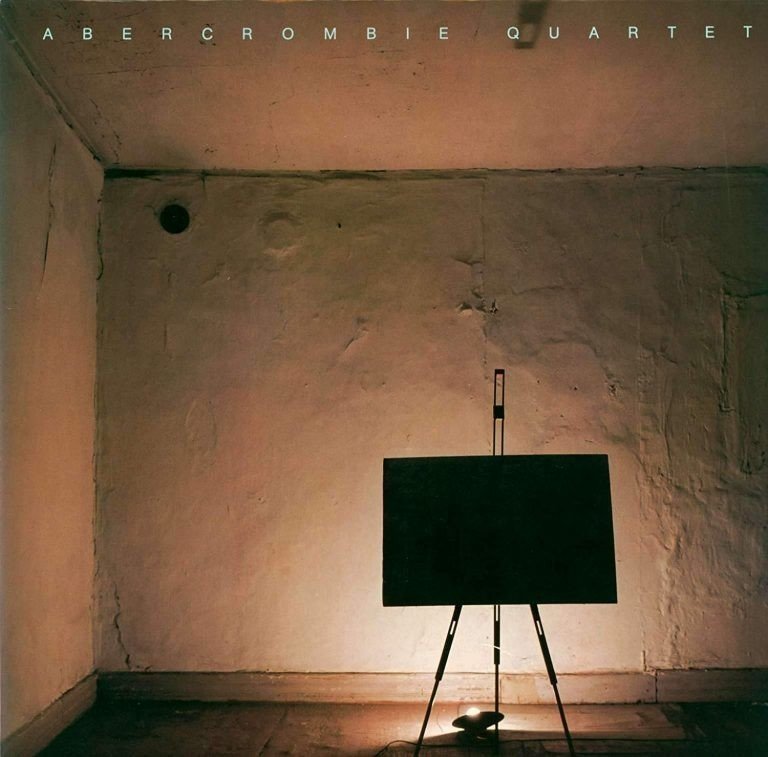
テーマの一部分をインタールードに用いて次のソロイストやテーマに移行していますが、Catalystとは「きっかけ」の意味、このインタールドの事を指すのかもしれません。続くテナーソロでは1人増えた4人でのインタープレイの応酬がスリリング、Mintzerとことん盛り上がらず含みを持たせた大人の対応を見せてCatalyst後ベースソロへ、ドラムだけがサポートし両者組んず解れつの演奏後、短くCatalystを経てバンプ的ドラムソロ、ラストテーマも無事終了です。
4曲目Seven-Upはその名の通り7拍子のファンク・ナンバー、米国でお馴染みの清涼飲料水と同名、O’Maraさん1曲目といいタイトル付けがちょっと安直な気もしますが、ひょっとしたら単に僕と同じダジャレ好きなだけなのかも知れません(笑)、ギターのカッティングから始まる実にゴキゲンなナンバー、こちらは変拍子を感じさせないナチュラルなメロディラインとグルーヴが印象的です。テーマは2回演奏され1回目ギターはそのままカッティングのみでのバッキング、繰り返し回はコードとメロディを巧みに組み合わせてのオーバーダビングを含めたバッキング、芸が細かいです!先発Mintzerはここでも4拍子+3拍子からなる7拍子を、リズムセクションの大健闘と共に難なくグイグイと盛り上げています!ソロは決してtoo muchにならず、バランス感を常に念頭に置いた演奏に徹しています。ギターソロも音色を変えつつ変幻自在なアプローチ、途中から再びオーバーダビングでギターのカッティングが聴こえ始めますが、レコーディングでは良く行われる手法のひとつです。カッティングが加わる事でグルーヴ感を強調させるのが目的なのでしょう。ソロが終わってもそのままカッティングがうっすらと残りラストテーマへ、レコーディング・テクノロジーによる最小限の演奏上の音加工が功を奏したテイクになったと思います。
5曲目Chancesはアコースティックギターを用いたイントロに始まるバラード、アコギの響きが堪りません!メロディを奏でるMintzerはバラードの名手でもある事を再認識させてくれました。深いビブラート、強弱付けによる抑揚、もっと聴きたいところで先発はギターソロ、テナーは暫しお預けです。しかしギターソロの最中に倍テンポになってしまいました(涙)。そのままでのバラード演奏を楽しみにしていたので肩透かしを喰らいましたが、曲の本題は後半部分なのかも知れません。でもエンディング部分で再びサブトーンでのメロディを堪能することが出来ました。
6曲目タイトル曲Symmetryはヘヴィーなリズムのワルツ・ナンバー、ドラムのテイストもどこかElvin Jonesを感じさせますが、このようなグルーヴのジャズワルツではありがちな事なのでしょう。でもElvinとの最大の違いはレイドバック感です。ここではWillis君のドラミングにスネア&皮ものが再登場し、ちょっと鳴り過ぎの感が…しかしテーマのメロディ奏に脱力系の色気を感じるので、帳尻が合っているのかも知れません。先発テナーソロは曲の持つムードをキープしながらをワンコード・オープンの上で次第に熱くフラジオ音も使ってブロウ、おそらくキューを提示してテーマのコード進行に移行します。ギターソロも同様にワンコードでのオープンソロ、クリアーなトーンでジャズギタリスト然とソロを展開、Willis君も果敢にフレージングに対応しています。テーマのコード進行に移ってからはメロディも伴われ、ラストテーマへ。ここでもMintzerの吹き方にテナーマンとしての色気を認める事が出来ました。
7曲目Steppin’ Outはドラムのソロから始まる速いテンポのスイング・ナンバー、シンバルを主体としてビートを刻むドラミングからTony Williamsのテイストが聴こえます。シンプルさの中にもO’Mara流のスパイスが効いた、こちらも外連味のない佳曲、先発のギターもリズムセクションとの一体感が見事なソロを聴かせています。on topで巧みにビートを繰り出すJohnsonのベースがこの演奏の要、Willisのビート感も実に素晴らしい!テナーソロ後にギター、テナーとドラムの8バースが繰り広げられますが、年齢を鑑みた音楽的表現の未熟さを微塵も感じる事はありません!この貫禄と風格は何処から来るのでしょう?O’Mara自身のライナーノートによればWillisとは”Old” Friendsという事で、以前取り上げた「Fuchsia Swing Song」のSam RiversとTony Williamsの関係と同じです。ちなみにJohnson, Mintzerとはレコーディングのリハーサル前には会った事がなく、電話でやり取りをするだけだったそうです。(現在ではメールという事になりますが)彼らはそんな付き合い方から演奏に至るまでを称しTelephone Bandと呼ぶのだそうです。
8曲目Expressionsは巧みなベースソロをフィーチャーした叙情的なイントロから始まるEven 8thのナンバー。Mintzerのソプラノサックスがこの上なく美しいです!テナー同様に倍音成分が実に豊富で複雑な鳴りをしていますが、バランス感が絶妙、この曲の持つムードにまさしくピッタリです!ソプラノばかりに耳が行ってしまいがちですが、曲のメロディ、構成も実に素晴らしい出来です!Mintzerが参加するグループYellowjacketsの98年作品「Club Nocturne」の1曲目、以降のYellowjacketsの重要なライブレパートリーでもある名曲Spirit of the West、ここでのソプラノの音色、演奏も実に堪りません!そういえば同じくユダヤ系Coltrane派テナー奏者、70年代からのMintzerの盟友であるDave Liebman, Steve Grossman, Michael Breckerたちもソプラノの名手でした。
ギターソロはさすがコンポーザーとしてのイメージをふんだんに散りばめた、深淵な世界を作り上げています。ラストテーマではソプラノの鳴りが更に極まったように聴こえ、一時この曲ばかりヘヴィロテで聴いた覚えがあるのを思い出しました。
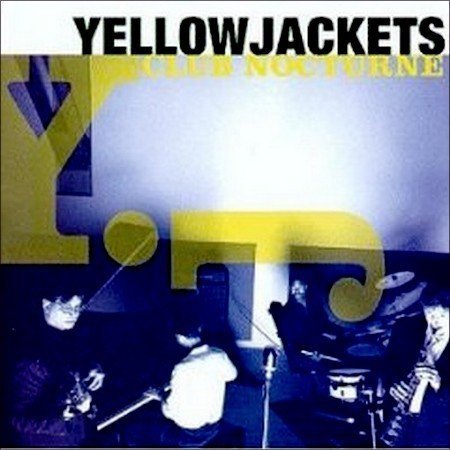
9曲目最後を飾るBlues Duesはリラックスした雰囲気のナンバーですが、O’Mara流の捻りが効いた作風に仕上がっています。先発ギター、様々なテイストを織り交ぜながらテクニカルに、カラフルに歌い上げています。ドラム、ベースのふたりもチャレンジしつつO’Maraの演奏に対処しています。テナーソロもギターの雰囲気を受け継ぎつつよりファンキーに、ブルージーにホットにソロを展開しています。ベースも淀みないラインを実に余裕で演奏していますが、実はとんでもない高度な内容のソロです!
本作のようにAustralia出身のギタリストがGermanyに移り住み演奏活動を展開、移住先で知り合った若いドラマーを連れて渡米、ジャズシーン最先端のテナー奏者、ベーシストとNYで共演し全曲自身のオリジナルを録音、これ以上の出来はないほどのクオリティ作品を作り上げる。世界は狭いと捉えるべきか、ジャズという音楽の柔軟性が成せる技か、その両方なのかも知れません。いずれにせよ本作を紹介出来たことを嬉しく思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
