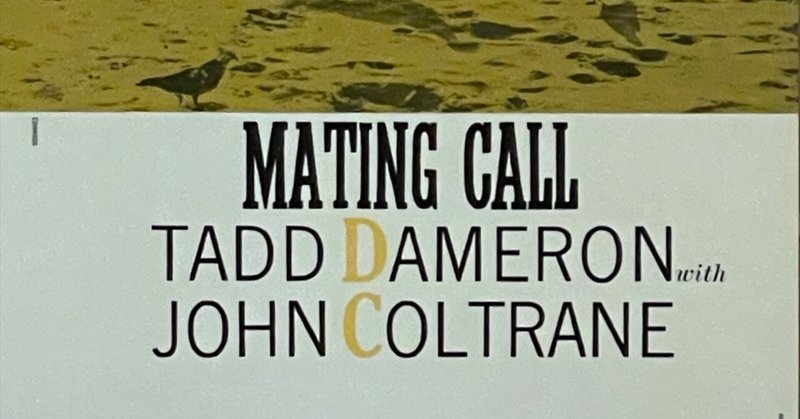
メイティング・コール/タッド・ダメロン
ピアニスト、作曲家タッド・ダメロンの1956年録音リーダー作『メイティング・コール』を取り上げましょう。
録音:1956年11月30日
スタジオ:ヴァン・ゲルダー・スタジオ、ニュージャージー、ハッケンサック
エンジニア:ルディ・ヴァン・ゲルダー
プロデューサー:ボブ・ワインストック
レーベル:プレスティッジ
(ts)ジョン・コルトレーン (p)タッド・ダメロン (b)ジョン・シモンズ (ds)フィリー・ジョー・ジョーンズ
(1)メイティング・コール (2)ニッド (3)ソウルトレーン (4)オン・ア・ミスティ・ナイト (5)ロマス (6)スーパー・ジェット

モダンジャズ華やかなりし1950年代バップ〜ハードバップ期、多くの個性的なピアニストが現れシーンを賑やかにしました。彼らの中には作曲の才を持つ者が多く、佳曲を切望するジャズファン、ミュージシャン、時代から求められたゆえにその才能を遺憾無く発揮出来ました。
主だったところではバド・パウエル、セロニアス・モンク、ホレス・シルヴァー、マル・ウォルドロン、そして本稿の主人公であるタッド・ダメロン。
パウエルは驚異的なピアノ演奏能力を有し、個性的でメランコリックなナンバーを多く作曲した事でその存在を印象づけました。
モンクはパウエルの親友でもあり、互いの才能を認め合った関係を維持しました。超個性でありながらモダンジャズの名曲足りうるナンバーを同様に数多く産み出したモンク、そのピアノプレイは自作曲と不可分な関係にあり、打鍵に由来するユニークなピアノの音色とタイム感にはワン・アンド・オンリーなテイストを見いだせます。
シルヴァーは多岐に渡る音楽性から、モダンジャズの変遷に則した個性的なオリジナルを多数産み出します。自作曲を演奏するために率いた自己のクインテット活動は、メンバーを頻繁に変えながら新たな風を取り入れ、自身の個性的ではあるものの、今一つアピールに欠ける打鍵のマンネリを回避していたように感じます。
ウォルドロンの演奏は訥々とした表現の中に哀愁や、時として呪術的なメッセージを感じさせる個性を持ち、押しつけや過度なメッセージを伴わないプレイから多くのファンを獲得しました。自身のオリジナルのジャズ度にはハッとさせられる瞬間があり、同様にスタンダードナンバーのアレンジにも知的さを感じさせます。
ダメロンの知名度の低さは短い活動期間とアルバム数の少なさに起因しますが、ジャズのルーツに確実に根差したオリジナル楽曲の独創性、品位は魅力に溢れ、聴き飽きることの無い、食べ飽きることを知らない穀類や新鮮な果実の素朴さを覚えます。
ジャズマンがダメロンのオリジナルを今もなお頻繁に取り上げる事からも伺えますが、アワー・ディライト、タッズ・ディライト、ホット・ハウス、レディ・バード、グッド・ベイト、ザ・シーン・イズ・クリーン、ザ・チェイス、イフ・ユー・クッド・シー・ミー・ナウ等、彼がプレイヤーとしてあまり知られていないのにも関わらず、オリジナル楽曲の方は独り歩きしています。
ダメロンのナンバーはいずれも決して大作ではなく、小唄や鼻唄の次元での名曲揃いで、ジャズという音楽があり続ける限り決して無くなることのない、文化遺産であると信じています。

ダメロンは晩年まで自分は作曲家なのだと言い続けていたそうです。確かに彼のピアノ奏にはテクニカルな側面、そこから発する華麗さ、グルーヴ感、スインギーさは感じられません。寧ろ辿々しさを覚えます。ピアノを用いた自身のインプロヴィゼーション表現には興味がなかったのでしょうし、発言の根拠にはプレイヤーとしての自信の無さがあったかも知れません。
前述のパウエルを除いたピアニストたちにも言える事ですが、例えばモンクのピアノプレイに感じる危なげなテイストは彼の場合、確信犯的に演じていたフシが伺えます。
モンクのごく初期の演奏を収録した、40年代初頭のニューヨークにあったジャズクラブ、ミントンズ・プレイハウスに於けるプライヴェート録音では、50年代以降よりもずっと流暢な打鍵を聴かせています。それもその筈、モンクはバッハ、ベートーヴェン、リスト、モーツァルトらの作品を学び、とりわけショパン、ラフマニノフの音楽に惹かれていたそうです。ひと通りクラシックの作曲家たちの楽曲をアカデミックに通過しているので、ピアニストとしての素養は備わっていた訳です。
ただピアノ奏者として、当時の個性という点で語れば独自色の表出よりもファッツ・ウォーラー、アート・テイタムらのプレイに影響を受けた演奏でした。
モンクも同様にジャズ史に残る名曲を数々残していますが、オリジナルを演奏する際に個性の発露を求めた結果、次第にテクニカルな演奏よりも自分にしか表現出来ない打鍵、ニュアンスを突き詰め、徐々に個性的なプレイを習得したのでしょう。

ダメロンが存命中に発表したリーダー作は僅か4作ほど、本作メイティング・コールが第3作目で、62年録音『ザ・マジック・タッチ/タッド・ダメロン・アンド・ヒズ・オーケストラ』がラスト作になります。
全曲ダメロンのオリジナルとアレンジをビッグバンド編成で演奏しますが、ブラス・セクションにフレンチホルンを含んでいるため、サウンドに一風変わったテイストがプラスされています。加えて9人編成のラージアンサンブルでも4曲演奏、そこに女性ヴォーカルが2曲フィーチャーされました。
いずれの楽曲もコンパクトな演奏でありながら、ダメロンの音楽性を濃密に表現しており、結果彼の最終作にして代表作になりました。
収録曲イフ・ユー・グッド・シー・ミー・ナウは46年にダメロンがサラ・ヴォーンのために書いた名バラード、歌詞をカール・シグマンが担当し、ここではバーバラ・ウィンフィールドが歌唱します。コンポーザー自身のビッグバンドアレンジは楽曲の細部に至るまで、綿密に美的感覚溢れるカラーリングを施しています。
アルバム中ダメロンはピアノを一切弾かず作曲、アレンジ、コンダクトに徹し、ピアニストには当時新進気鋭のビル・エヴァンスを迎えています。
この作品のために書き下ろした新曲、またアワー・ディライトをはじめとする自身のオリジナルの再演には新たなコンセプトを加味したアレンジを行い、ホーンのアンサンブルにはダイナミクスが徹底したジャジーな抑揚を効かせ、ジョニー・グリフィン、ジミー・クリーヴランド、ジョー・ワイルダー、クラーク・テリー、エヴァンスらに短いながらも主張のあるソロをとらせています。
ドラムの椅子には本作メイティング・コールにも参加の名手フィリー・ジョー・ジョーンズが座ります。
普段はピアノトリオやカルテット、クインテット等の小編成でのプレイが中心で、あまりビッグバンド経験が無い筈の彼ですが、総勢20人近いメンバーに包括的な対応が役割であるビッグバンド・ドラマーとしての、セクションの呼び込みフレーズやチュッティのダイナミクス付け、アンサンブルへの寄り添いを見事に遂げています。
同時に本来のコンボ的なビートの的確さやアイデア、グルーヴ、ドライヴ感、ドラムソロのフレージングに流石と思わせるところが多々あり、ドラマーとして大は小を兼ねるならぬ、小編成は大編成を兼ねるを地で行っています。
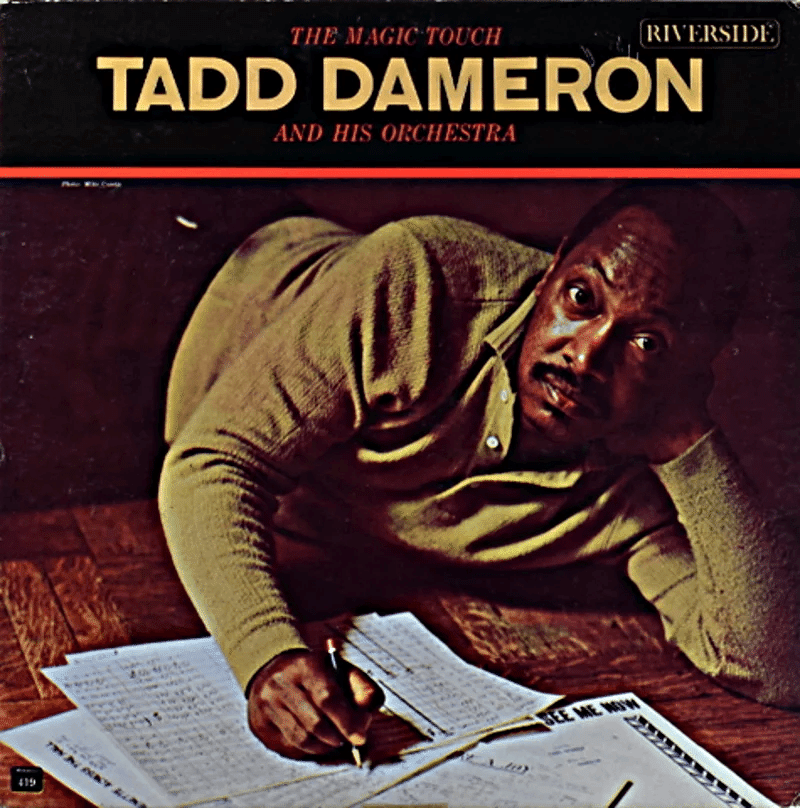
タッド・ダメロン・アンド・ヒズ・オーケストラ
本作『メイティング・コール』でもう一点触れなければならないのがジョン・コルトレーンの参加です。彼のプレイ無しにはこの作品は有り得ませんでした。
ダメロンは他のリーダー作が全て大きな編成による、管楽器アンサンブルを聴かせるのが主体でした。本作では言わば管楽器複数人分の役割を、コルトレーンが担っている形になります。
コルトレーンは本作録音の前年にマイルス・デイヴィス・クインテットに迎えられ、事実上デビューを飾ります。
55年11月『ザ・ニュー・マイルス・デイヴィス・クインテット』のレコーディングを皮切りに56年『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』、マイルスが所属したプレスティッジ・レーベルとの契約解消のための、所謂マラソン・セッション4部作『クッキン』『リラクシン』『ワーキン』『スティーミン』と立て続けにレコーディングします。
55年参加当初のコルトレーンのプレイにスリリングな展開を認める事は出来ませんが、既にスタイルの独自さ、アプローチ、表現の指向性の萌芽を確認する事が出来、オリジナリティを手にしていると言えます。
翌56年を通じたのマイルスとの共演、57年モンクのカルテットへの参加で芽生えは明らかな発芽となりました。
短期間のコルトレーンの成長ぶりは、決して新たなスタイルを手にした結果ではなく、以降も一貫するのですがあくまで55年のプレイが原点となり、演奏経験と猛練習、そしてマイルスとモンクたちのサジェスチョンにより表現のディレクションを明確にします。
奏法とアイデア、後のシーツ・オブ・サウンドに代表される、激しくとも過剰さはなく必然性を帯びたテクニックの習得、これらは増加曲線を描くグラフの如くコルトレーンに備わり続け、方向性はより精度を増します。
取り分け感じるのは自分のプレイの発展途上、未熟さに対する焦燥感を一切感じさせず、一貫してマイペースに自己のウタを歌いながらコルトレーンが進化し続けた点です。

マイルスはコルトレーンという原石の可能性を見抜いていました。ギャラリーや評論家の彼に対する不評価を馬耳東風に雇い続け、無骨さ、飾り気のなさ、どちらかといえば不器用さを感じさせるプレイヤーを、短期間でジャズシーンの先端で通用するテナーマンに磨き上げ、以降ジャズ史を大きく変える、ダイヤモンドの輝きにも匹敵する偉業を成し遂げたミュージシャン、コルトレーンを育てたのです。
とは言えコルトレーンがドラッグや過度の飲酒行為を行い、当時のマイルスのホームグラウンドであるニューヨーク、カフェ・ボヘミアで度々の失態を犯し、56年10月マラソンセッション直後に解雇されます。
その後繰り返された再雇用、再解雇を鑑みれば、マイルスはコルトレーンの演奏はもちろん、人柄を愛していたのでしょう。

以下収録曲について触れて行きます。全曲ダメロンのペンによるナンバーです。
1曲目メイティング・コール、実にユニークな曲想のナンバーです。どこかホレス・シルヴァーの作風に近いものを感じるのは、曲中に用いられるエキゾチックな雰囲気を醸し出すルンバのリズムに由来します。
シルヴァーは自身のオリジナルに世界各国のリズムを用いており、そのパイオニアとしても知られていますが、それは60年代以降の話です。ここでのダメロンのエキゾチックさの表出は、時代の魁と言えましょう。
タイトルの意味するところは動物の求愛に際する聴覚信号、曲中のリズムの変化からさまざまな音を発して相手を求めているようです。
冒頭の急速調のハイハットとバスドラムの連打、サンバのリズムのようにも聴こえます。ピアノの左手によるパターン、コルトレーンのメロディ奏が始まり、メロディラインは変わらずにピアノとドラムがルンバにチェンジします。
サビの展開部ではミディアム・スイングに変わりピアノがメロディ奏を行いますが、その後ろでコルトレーンがうっすらとピアニシモで、コードの構成音をなぞるかのように、全音符を用いてバッキングしています。
再びルンバによる主題部分がプレイされソロに入り、スイングにチェンジします。先発はコルトレーン、マイルスのマラソンセッション時よりも明確なサウンドイメージを感じます。音色がクリアーになり、メッセージ性、リズムの発露を感じます。タンギングは相変わらず絡れ気味ですがスピード感が表現されています。
淀みなくフレーズを繰り出し、リズムのレイドバックを伴いながら巧みにタイムを表現し、変則的なフォームによる1コーラス40小節のソロパートを、コルトレーンは2コーラスプレイします。
続いてのダメロンのソロは良く言えばモンク的なアプローチを聴かせますが、曲自体のイメージの豊かさに比べて、内容は凡庸です。
フィリー・ジョーのドラミングと共に的確なグルーヴを提供するベーシスト、ジョン・シモンズはダメロンの前作56年3月録音『フォンテーヌブロー』からの付き合い、骨太な音色で堅実なビートを刻みます。

私見ですがダメロンの音楽にはポール・チェンバースのベースがフィットするようにイメージしています。彼はコルトレーン、そしてフィリー・ジョーとのコンビネーションも抜群ですし、ダメロンのメロディアスなオリジナルを力強くサポート出来るに違いないと信じています。
勝手な妄想のレヴェルですが、多忙を極めたチェンバースのスケジュールを押さえられなかったためでしょうか、次作ザ・マジック・タッチではロン・カーターとジョージ・デュヴィヴィエが曲毎にベースを担当し、Mr. P. C.はダメロンのリーダー作での共演は実現されませんでした。
1コーラスのピアノソロを終えてラストテーマに入りますが、確実にテーマを演奏しているのはコルトレーンだけ、リズムセクションは「おっと、いけねえ!」とばかりに、変化を察知してからやっと3小節目でルンバに変わります。
若しくはダメロンも2コーラス演奏する予定だったのでしょうか、リズム隊が「あれ?もう1コーラスある約束なのに、ジョンがひとり先にラストテーマに行っちゃたよ。(顔を見合わせながら)ヤツに従わざるを得ないか」と暫く様子を窺った末なのかも知れません。
サビでは珍しくピアノとドラムの2小節交換が行われます。その後主題部に入り、エンディングはテーマのメロディが繰り返されフェードアウトしますが、ドラムのリズムはルンバではなくイントロで行われた急速調のハイハットを用いています。
ルンバをテーマだけではなく、ソロ時にも用いていたのならばよりエキゾチックなムードを表現出来たと推測しています。56年当時では中南米のリズムをアドリブ時大胆に採用するには、躊躇があったのかも知れません。
2曲目ニッドはジャジーで暖かさを持つミディアムスイング・ナンバー、個人的に大好きな楽曲です。諸説ありますが、タイトルの意味するところはスラングで”お馬鹿さん”が通説のようです。
テナーとピアノのユニゾンによる変則的な7小節のイントロでは何ヶ所かオルタード・テンションを用いた音を使い、緊張感を伴いつつオシャレな響きを表現、そしてプレイヤー全員による2拍3連のメロディのユニゾンが心地よくプレイされています。
テーマに入り、コルトレーンのメロディ奏バックでリズム隊によるシンコペーションのキックが演奏され、サビではスイングでプレイされます。再び主題に入りますがその後のインタールードが印象的です。4小節構成の1度目はオクターヴ下でメロディが演奏され、2度目はオクターヴ上げて変化を付けています。
1小節のブレークの後ソロはピアノから、この位のテンポではシモンズのベースのオントップさが際立ちます。
朴訥とした1コーラスのダメロンの打鍵に続き、コルトレーンのソロへ。曲想に合致したスインギーなアドリブを展開、1コーラスプレイの後にドラムが先発してピアノと2小節交換を16小節行います。
サビからコルトレーンが半コーラスソロを行い、ラストはテーマのAA部分をショートカットしてサビからテーマ奏に入ります。ヘッドのテーマ同様インタールードを経て、エンディングは終始感を得るべく別なセクションを用いてFineです。

3曲目ソウルトレーンはタイトル通りダメロンがコルトレーンに捧げた、独創的にして美しいバラードナンバー。ストイックさを感じさせるのはコルトレーン自身のプレイによる所が大です。
後年コルトレーン・カルテットに在団した名ドラマー、エルヴィン・ジョーンズが自己のバンドで取り上げています。日本が誇る素晴らしいドラマーで、私もお世話になった日野元彦氏もレパートリーに加えていました。
コルトレーンにもぜひ自己のカルテットのナンバーとして演奏して貰いたかったところです。
ピアノがベースのアルコを伴ってイントロを奏でます。その後テナーの高音域を生かしたソリッドでタイトなトーンでのメロディ奏、そこでは美しさの中にダメロンらしい捻りの効いたコード進行が反映されています。
テーマの後半からフィリー・ジョーが倍テンポのニュアンスを出し始めます。50~60年代の多くのバラード奏では、テーマはバラードでプレイされていてもソロに入った途端に倍テンポになる場合が多く、特に60年代のコルトレーン・カルテットではそれが顕著でした。
案の定ドラム、ベースとダブルタイム・フィールでプレイし始めます。その最中に繰り出されるダメロンのバッキングにはウタを感じ、コンポーザーならではのセンスを活かしています。
コルトレーンは1コーラスソロを取ります。テーマ奏から引き続く見事なプレイは、曲想に決して埋没する事なく自己の主張を遂げていて、明らかな成長ぶりを示しています。
ダメロンのソロに続きます。何事も無かったかのフレージングから始まりますが、コルトレーンの演奏を刷新する意味合いがあったのかも知れません。
コーラスの前半16小節をプレイし、サビからコルトレーンがテーマを演奏します。
バラードでテンポキープしていたフィリー・ジョーがバックビートを強調し始め、再び倍テンポの雰囲気が提示されますが、サビの終わりと同時にバラードテンポに戻ります。エンディングではカデンツァがプレイされ、翌年の飛翔をイメージさせる速いパッセージには、シーツ・オブ・サウンド的なテイストを感じます。
ラストのダメロンの打鍵で聴かれるグリッサンドはユーモラスに響きました。
4曲目オン・ア・ミスティ・ナイトの印象的なイントロ、エンディングに用いられるアウトロは、メジャー7thコードを巧みに用いた独創的なもの、テーマのメロディ、コード進行と不可分の存在です。
56年と言うハードバップ真っ只中には新しさが際立つサウンドです。
とは言え都会的なセンスと言うよりも、ダメロンの生まれ故郷米国クリーヴランドの素朴な風土、日本と同じく四季があり、豊かな自然と充実した文化施設が点在している土地出身ならではのテイストではないでしょうか。
曲調全体にほのぼのとしたムードが漂い、佳曲揃いの本作中この曲がお目当ての方も多いように思います。
コルトレーンの高音域のハスキーさと曲の持つムードが合致した名演奏です。
スタンリー・タレタイン2002年リリースのコンピレーション・アルバム、その名も『オン・ア・ミスティ・ナイト』に同曲が収録されています。
タレンタインのオクターヴ下の低音域でのメロディ奏と、サブトーンを活かしたテキサステナー〜ホンカー系の豪快なプレイから、ある意味コルトレーンとは真逆、ゴージャスなアレンジも相俟って、もはや全く別な楽曲に仕上がっています。
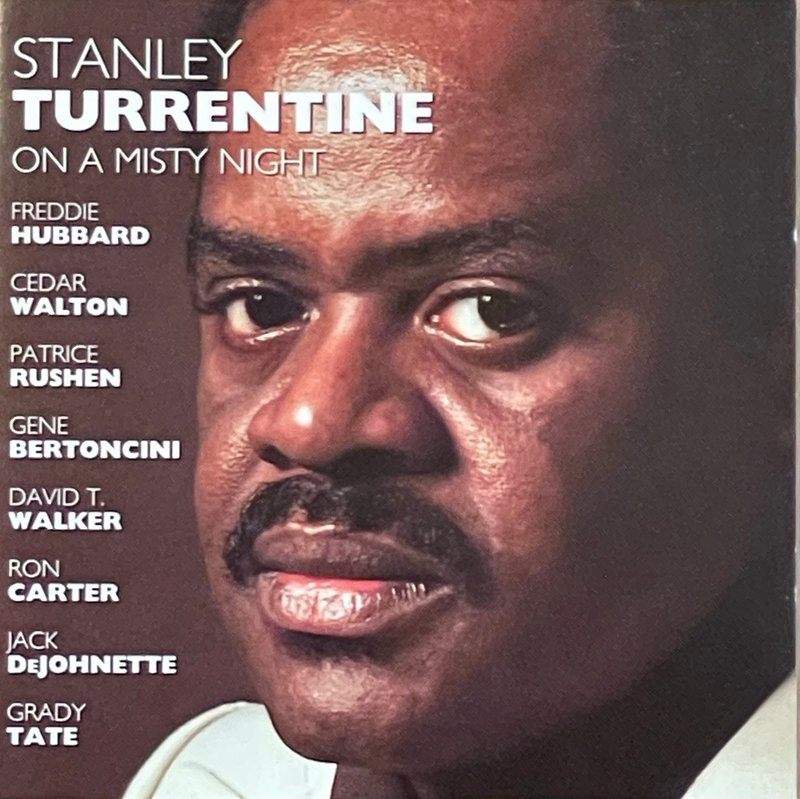
テーマのサビはピアノがメロディを弾きますが、明確にメロディは提示されておらず、コードのアルペジオを中心に辿っているようで、不明瞭さをサポートするべくでしょう、フィリー・ジョーが3, 4小節目と7, 8小節目に倍テンポを繰り出しています。
因みに『ザ・マジック・タッチ』再演時ではサビに明確なメロディラインが設けられ、ジョニー・グリフィンが吹奏しています。
ソロはコルトレーンから。朗々とコード進行に身を委ねるが如く気持ち良さそうにブロウする様は実に好感が持てます。2コーラスプレイした後ドラムがブラシに持ち替えダメロンのソロが開始されます。フィリー・ジョーはサビを丸々倍テンポでプレイ、2コーラス目からスティックに持ち替え、ここでのサビは通常のスイングでプレイします。
その後はラストテーマへ。サビではベースがソロをプレイし、アウトロに向かいますがその入り口に不自然さが漂うのは、作曲者ダメロンがアウトロに入り忘れて一瞬コードを弾かなかった事に起因します。

5曲目ロマスはスローブルース、ピアノとベースの演奏から始まります。2コーラス直前にドラムのスネアロールが入り、それまで揺れていたテンポが確定しますが、テーマらしいテーマは演奏されません。
合計4コーラスをトリオが演奏しコルトレーンが登場します。間を活かしつつプレイしますが、翌57年8月録音コルトレーンのリーダー作『ラッシュ・ライフ』収録トレーンズ・スロー・ブルースのコンセプトを感じます。キーも同じBフラットなので然もありなんです。
テナーソロ後再びダメロンがレイジーに打鍵し、穏やかにエンディングを迎えると見せかけて、意外性のある裏コードのE7でFineとなります。

6曲目スーパー・ジェット、アルバムのラストを飾るアップテンポのスイング・ナンバー、8小節のドラムソロから始まります。冒頭全音ずつ下降するコード進行に4度進行を織り交ぜたチェンジから成ります。
これだけの速いテンポに大きくリズムを取り、難易度が比較的高い全音下降のコードチェンジを物ともせずブロウするコルトレーン、翌年迎えるブレークスルーの準備は整いました。
テナーソロ後のダメロンは速いテンポについて行くのがやっとだったのでしょう、自分のソロ後に行われる2コーラスに及ぶドラムとの4小節交換はコルトレーンに一任します。
その後はドラムソロを迎えこちらも2コーラスプレイします。ラストテーマの入り口をコルトレーンが一瞬躊躇しますが、リズム隊の的確なリカヴァーを伴い平然とクリアー、その後のエンディング・セクションまで難なく演奏しFineとなります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
