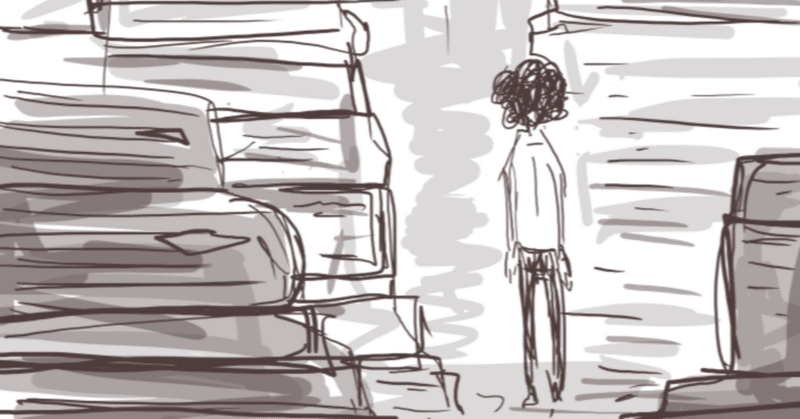
おじいちゃんの日記
何年か前、実家の屋根裏で祖父の日記を見つけた。
私は祖父を知らない。
祖父はある朝、昏睡状態に陥っていて、意識が戻ることなく一年後に亡くなったと聞いている。
当時私は2歳。
遺影は白黒でピンボケ。
祖父についての記憶の断片はわずかにあるが、それが思い出なのか夢なのかもわからない。
祖父の日記――
歴史家が古文書を発見したときは、こんなふうに高揚するのだろうか。『農業日記』と冠された分厚い日記帳。それが角を揃えて十冊ほど積まれていた。
人となりもまったく知らない私が、祖父を知る手がかりとなる古文書を発見したのだ。
早速ページを繰る。
しかし残念ながらそれは、表題通りの農業日記でしかない。事実のみをほんの数行書き連ねる様はもはや業務日報であり、祖父の内面を綴ったものではなかった。
すぐに手持ち無沙汰になり、しょうがなく今度は筆跡を眺めてみる。
昔人らしい、少し崩した文字。
以上。
投げやりにページをパラパラめくっていると、「……なのか」と珍しく心情を表すような言葉が通りすぎた。
慌てて戻ると、相変わらず短い文章で
「○○子、今朝入院。大丈夫なのか」
と書き付けてあった。
――母のことだ。
表紙には「昭和50年」とある。
日付は、姉が生まれる3日前。
姉は安定してお腹にいたが、いざ出産となるとなかなか出てこず、母も衰弱したと聞いている。
大丈夫なのか――
たった一言だけど、「業務日報」の祖父から出た言葉だと思うと、表には出さない優しさを持った人なのかと、輪郭がぼんやり見えた気がした。
「そうだ!」
閃いて私は積み上げられた日記帳から「昭和54」年を探し始めた。私が生まれた年である。
私がお腹にいた頃、母は流産の気があり、9ヶ月間も入院したと言っていた。そんなに大変だったなら、祖父が日記で何か語っているに違いない。私が生まれるとき、祖父は何を思い、どんな言葉を書き残したのか。
――知りたい。
その一心で私は「昭和54年」の日記を探した。しかし何度探してもそれは見つからない。書いていないのか。書いてはいたが、ここに置いていないだけなのか。
どちらにしても、この日私は、祖父との繋がりを見つけることはできなかった。
屋根裏で一人うなだれながら、日は傾いていった。
*
それから何年か経った2014年。
祖父の三十三回忌法要が執り行われた。
父の弟妹で、私にとっては叔父叔母にあたる4人と、その伴侶が集結。
一人ずつ思い出を語ろうということになり、思いがけず祖父を知る機会に恵まれた。
3番目叔母からは、祖父が畑で歌う民謡がとても良かったと教えられた。
「父ちゃんの歌が忘れられなくて……」
叔母も民謡を習い始めたという。
2番目叔母の夫は、
「農業や畜産の面で尊敬していた。もっと教えてほしかった」
と声を震わせた。この義叔父は、地元ではわりと有名な大農家である。
長男である父は、若い頃祖父とケンカしたとかで不仲だったと以前母が話していた。父にだけ厳しかったらしいとのことだったが、末の叔父が、
「親父は娘には甘かった! 俺にはいーっつも厳しかったもん!」
と語るのを聞いて、父だけじゃなかったんだなと、私も母も安堵した。
私の番。
夢か思い出か、判別不能の記憶の断片を話す。
黒か紺のどんぶぐ(綿入れ半纏というのかな)を着て、コタツに座っている祖父の姿。
「ああ! 着てたねえ、そういう色の!」
誰かが言った。
じゃああの人はやっぱり、私のおじいちゃんなんだ。――顔は覚えていないが、それでもちょっと、嬉しくなった。
あと覚えているのは、病室で眠り続けている祖父。祖母と時々会いに行った。
あとは、実家の座敷での記憶。
黒い服の大人たちが、大きな箱を囲んでいた。
その箱の中に祖父がいることは、子供ながらにわかっていた。
大人たちの輪の外から見ていたら、割烹着を着た近所のおばちゃんに「あっちさ行ってようね」と手を引かれた。
なんで? 私ここにいたいのに。
疑問に思ったが、大人だけの厳粛な雰囲気で、私は子供扱いされたんだと感じた。悲しいとか寂しいという感情は特になく、みんなで何やってんのかな、と思っただけなのに。
「――あ、それと。おじいちゃんの日記を見つけました」
私が言うと、途端に叔父叔母たちの目が輝いた。
「日記なんてあったんだ」
「読みたいなそれ」
叔父叔母たちが口々に祖父の日課などを語り始めた。そこから祖父がかなり几帳面な性格だったことを知る。
お金は祖父が管理。牛や蚕をやっていたので、年に一度、帳簿の整理を手伝わされたと、叔父叔母が懐かしげに語る。
「でも私が生まれた年の日記はなかったのよ。書くのやめちゃったのかな」
私の言葉に、末の叔父が首を大きく横に振る。
「それはない。あの親父だ、倒れる前日まで絶対書いてるから。もう一回探してみて」
祖父の絶対的な几帳面さのおかげで、期待が膨らむ。
姉からは嬉しいことを言われた。
「おじいちゃんの几帳面、あんださ遺伝してんでない?」
私はわりと、メモ魔である。
指摘されるまで無自覚だったが。
「この子は精神的に何か問題があるのでは」と母が心配するほどのメモ魔である。
メモ魔として覚醒したのは、病を得て通院するようになってからなのだが。
いつも必ず書くものを持ち歩く。日記は毎日ではなく書きたいときだけ書くスタイルだが、手帳には行動や体調を毎日欠かさず記録している。書くことだけに特化しているが、たしかに几帳面と言えるかも知れない。
今まで私は、祖父との関係になんの繋がりも見出せなかった。でもようやく「私のおじいちゃんなんだなあ」と実感できた気がした。
ちなみに4つ上の姉に、祖父のことで覚えていることを聞いてみたことがある。
「なーんにも覚えちゃいないねぇ」
「ああ、そう……」
姉はそういう人である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
