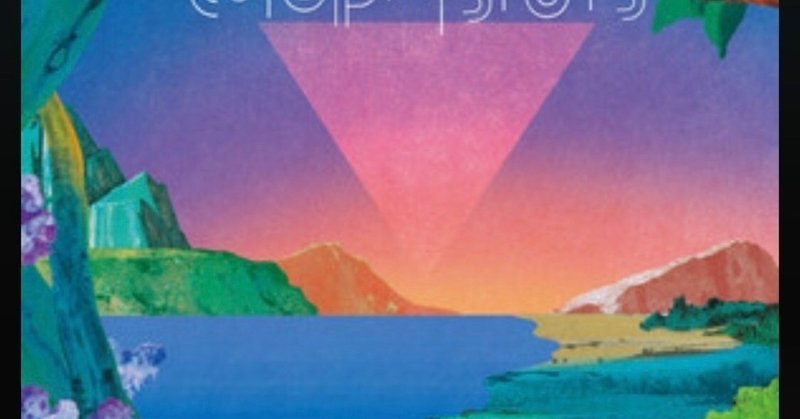
2018.9.6 STUTS / Eutopia
今日も朝から晩まで船橋のお店。昨日よりも忙しかったものの、程々順調に終えたので、心地良い疲労感と共に、昨日より30分くらい早い電車で帰宅中。
聴くぞ聴くぞ、と気合いを入れて、昼休みにSTUTSのセカンドアルバム「Eutopia」を聴く…が、なんとなく僕の気持ち的にはピンと来ないまま、最後の曲まで聴き終えてしまった。特に、ラップやボーカルが入る曲(人選もバッチリだし、それぞれの声のキャラクターとトラックとの相性も素晴らしいと思う)では感じなかったけれども、インストの曲ではなんとなく音と音の隙間や、質感みたいな部分で、うまく言えないけど「違和感」みたいなものがずっとひっかかってしまった。
mikikiのインタビューを読みながら、何故こういう「違和感」みたいな感覚が残ったのだろうと色々考えてみたけど、このあたりにヒントがある気がした。
「以前から自分はただMPCを叩いて、トラックを作る人にはなりたくないと思ってましたし、今後の活動の広がりを考えると、サンプリングの手法にも限界を感じていて。一方で、ファースト・アルバムでも自分で入れたシンセのフレーズを〈耳に残る〉と言ってくれる人が結構いたので、今回は自分の個性と言えそうな部分を色濃くしたくて、自分で考えたコード進行やメロディーをもとに作ったデモをミュージシャンに聴いてもらい、セッションして、その素材を編集して曲を仕上げていくやり方――言い換えれば、サンプリングの手法とバンドの手法が混在した〈作曲〉に近い作り方にも挑戦しました。生演奏の編集に関しては、〈ざっくりと機械的に編集しました〉というグルーヴではなく、自分が理想とするナチュラルなグルーヴに近付けるために、一音一音の緻密な編集や調整、ミックスの作業にはいちばん時間をかけましたね」。
一度、ミュージシャンが生演奏した音やフレーズを再度編集していく手法、って決してこの手のサンプリングベースで曲を作るブレイクビーツ系のアーティストでは珍しいやり方では無いと思う。だけど、元々のレコードの中に封じ込められたグルーヴを、フレーズサンプリングで切り取って、そのグルーヴをベースに他の音を組み合わせていくのと、ゼロから新しい素材で作っていくのでは全然意味合いが違うと思う。
「Eutopia」のM9「Above the Clouds」にも参加しているラッパーKID FRESINOの7インチで発売された「Coincidence」やミニアルバムのJJJと共演した「Salve」は、気鋭の若手ミュージシャンによる生演奏トラックをバックにラップしているけれども、これらの曲を聴いていても前述したようなグルーヴの「違和感」を全く感じなかった。
https://www.youtube.com/watch?v=JvOBHAfXX1Y
https://www.youtube.com/watch?v=nlCQZ4jdEc8
「Coincidence」は特に、現在日本の若手ドラマーで最も注目されてて、個人的にも参加している音源は全部チェックしたくなる天才ドラマー石若駿が叩くかっこいいドラムと、FRESINOの軽やかなフロウが完全にスイングしてて、それだけでも首を振りたくなるグルーヴに満ちあふれてる。
STUTSに関して言えば、2017年のAlfred Beach Sandalとの共作アルバム「ABS+STUTS」は本当に素晴らしい名盤で、とても愛聴していたし、個人的にも90年代に玉石混合で沢山いた、サンプリングベースでMPC1台を叩いて作られた様なインストのブレイクビーツアルバムはたっぷり聴いてきたので、彼みたいな新世代のトラックメーカーにはどんどん後進のアーティストの為に道を切り開いて欲しいと、めちゃくちゃ期待しているので、どんどん作品を作って、問答無用で筋肉痛になるくらい首を振れるヤバいサードアルバムを作って欲しいと願います。
毎日聴いた音楽についての感想を1日1枚ずつ書いています。日々の瑣末な雑事についてのメモもちょっと書いてます。
