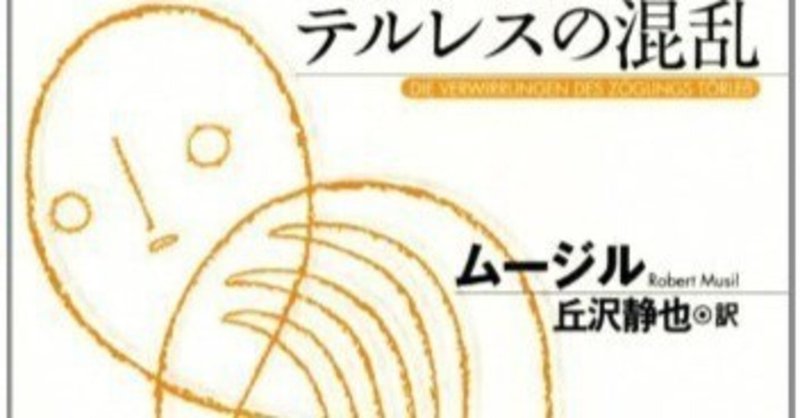
『寄宿生テルレスの混乱』―ロベルト・ムージルの初期作品を読む
この本を読んだきっかけ
ロベルト・ムージルの作品は、下記の小説を読んだことがある。
『愛の完成』『静かなヴェロニカの誘惑』
『三人の女・黒つぐみ』
そもそもは、古井由吉がムージルを研究していたことで興味を持った。
特に、古井由吉が翻訳している『愛の完成』『静かなヴェロニカの誘惑』は難解にも関わらず、強く惹きつけられた。古井由吉の丹念で研ぎ澄まされた和訳のせいもあるかもしれない。
だが私が惹きつけられたのは、この小説の表現や言葉遣いが感覚的な魅力を感じたからで、内容を理解できなかった。
その点、ムージルの初期作品である『寄宿生テルレスの混乱』は『愛の完成』『静かなヴェロニカの誘惑』よりは読みやすい気がした。
この初期作品に、『愛の完成』『静かなヴェロニカの誘惑』を読み解くヒントがあるといいな、と思って読み始めた。
果たしてヒントはあっただろうか?
1. 確かに「思春期もの」ではあるが
小説の舞台は、全寮制のエリート校の寄宿舎。少年テルレスが親に連れられ寄宿舎にやってくるところから始まる。
出版社の紹介文は下記の通り。
お金を盗んだ美少年バジーニが、同級生に罰としていじめられている。傍観していたテルレスは、ある日突然、性的衝動に襲われる......。寄宿学校を舞台に、言葉ではうまく表わしきれない思春期の少年たちの、心理と意識の揺れを描いた、『特性のない男』ムージルの処女作。
思春期の少年が主人公で、男子生徒しかいない寄宿舎生活で過ごす中、同性に性的魅力を感じる。美しい少年、寄宿舎、また美少年に魅力を感じるのは主人公テルレスだけでなく、テルレスの友人、ライティングとバイネベルグも美少年との性的関係を匂わせており、三角関係、四角関係の駆け引きのようなものもある。ボーイズラブの条件は揃っており、ボーイズラブの古典的作品といえばその通りかもしれない。
ただ、小説の題名にもなっている、テルレスの「混乱」は、思春期の恋愛や嫉妬だけではなさそうで、テルレスの内面に深くかかわっているようだ。
ではテルレスが一体何に対して混乱しているのか、後ほど書いてみたいと思うが、まず感じたのはテルレスの悩みが思春期ならではの一時的な戸惑いというよりは、彼の根本的な考え方に由来しており、一生を通じて起こるような混乱ではないか、という気がした。
テルレスは寄宿舎に入った当初から、こんな悩みを抱えていた。
―出来事とテルレスの感情の間に境界線がある。感情を理解しようとすると(境界線に近づこうとすると)、ますますわからなくなる。これが最大の悩みである。―
2. テルレスと二人の友人(ライティングとバイネベルグ)について
この小説の登場人物は、主人公テルレス、テルレスが性的魅力を感じる美少年バジーニ、そしてライティングとバイネベルグという二人の少年がメインだ。
ライティングとバイネベルグはテルレスの友人で、二人はテルレスより年長で、素行の良くない不良。テルレスは内面が弱く自分を見つけられないため悪い先輩に憧れた、とある。
二人の少年がどんな人物かというと、ライティングはナポレオンを尊敬する肉体派の不良。バイネベルグは哲学者を尊敬し、インド哲学に感化されている。二人はよくつるんでいるが、かなりタイプの違う少年だ。
ところでバイネベルグは父親の影響でインド哲学に造詣が深いが、ドイ
ツ語圏なら西洋哲学の本場なのに、なぜインド哲学?という疑問が残る。
当時のオリエンタリズムのようなものだろうか。ちなみにバイネベルグがインド哲学にのめり込むきっかけとなった父親は知的な人物ではなく、むしろ粗野な軍人として描かれている。
話が少し逸れたが、不思議なのは、テルレスのような内面的な人物なら肉体派のライティングより哲学好きのバイネベルグと気が合いそうだ。実際、バイネベルグとは何度か議論を交わしている。バイネベルグの方はひょっとしたら、テルレスに親近感を持ち、哲学の議論ができると期待していたかもしれない。
だが、テルレスはバイネベルグに反感を持っている。バイネベルグとの会話は嚙み合わないし、インド哲学にも興味が持てない。
一見テルレスは思春期も相まって自分は何者なのか、人間の存在意義を問う哲学のように見えるが、ちょっと違うようだ。
3. 理系少年テルレスは哲学に興味なし
小説の中盤くらいにカントの本が出てくる。この小説が刊行されたのは1906年、カントの『純粋理性批判』は1781年ということなので、100年以上も経ってはいるが、カントについて下記のように書かれている。
―カントの名前は人から聞いてよく知っていたし、テルレスには市場価値があった。
人文科学に縁のない人たちの間でも、カントの名前は―哲学をあらわす最後のキーワードとして―一般に通用していたのだ。
それに、テルレスが思ったのは、カントが哲学の問題を最終的に解決したので、それ以来哲学は無意味な仕事であり続けている。―
100年以上も前の古臭い本、ということのようだが、そもそもテルレスは哲学に興味がない。
テルレスとバイネベルグの違いを見ていくとよくわかる。
テルレスはある時数学の授業で虚数を学び興味を持った。バイネベルグにそのことを話す(テルレスはこの話ができるのはバイネベルグだけだと思った)が、バイネベルグは一向に興味を示さず、肩透かしを喰らう。
バイネベルグはテルレスとは違い、言葉(哲学)を信じている。
一方テルレスは、言葉で言い表せないものがあること、言葉の不完全性を知り、苦しんでいるので、不完全や矛盾も言語化するのが哲学だとするならば、言語化し得ないことに悩んでいるテルレスにとっては哲学は信じられない。
4. バジーニの件が決定的になった
バジーニに性的魅力を感じること、それを言葉に言い表せないことでテルレスは戸惑う。
もっとも以前からその戸惑いはあったが、バジーニに対する感情が決定的となった。
以前から、言葉では言い表せない感情があること、言葉は仮に表現される口実のようなものだと気が付いていたが、言葉が不完全なら、自分の精神(言葉で表現できないもの)と、自分との間に架けられる橋、つながりを見つけたかった。
バイネベルグとライティングが金を盗んだバジーニを屋根裏に呼び出し、バジーニは服を脱がされ鞭で打たれた。テルレスはバジーニに暴力を振るわなかったが性的に興奮した。
性的に未熟な思春期の少年にとって、性や官能は言葉で説明できない代表的なものだ。
テルレスは自分の中に性的衝動がなぜ起こるのか理解できず、言葉は不完全なものだと知っており、その代わりに自分と外部とのつながりを見つけたかったのに、つながりどころか、境界線が深まるばかり。
5. テルレスの「境界線」「二つの異なる世界」そして「距離」
作者のロベルト・ムージルは、数学や自然科学に造詣が深かったという。
ロベルト・ムージルが小説を書いた20世紀の初頭、自然科学がどんな意味を持っていたのか、また理系の人ムージルがなぜ小説を書いたのか、興味は尽きないが、いかんせん私の勉強不足である。
この小説が面白いのは、思春期ならではの心理を描きつつ、テルレスの独特な距離の取り方があるところだ。
テルレスの混乱は、異なる二つの世界、相反する矛盾に葛藤し悩む、といったものではない。言葉の不完全性を知っているテルレスは矛盾を追求しようとはせず、その現象を観察する。
まるで科学者のようだ。
テルレスはすでに、言葉の不完全性を知っていた。だからバジーニに性的魅力を感じること(なぜそのような感情を抱くのかわからない)に戸惑いながらも、受け入れていたように思える。
また、バジーニに魅力を感じながらも、ライティングとバイネベルグのバジーニに対するいじめやサディズムを容認し、積極的ではないにせよ、自分も快楽を味わった。刺激が強すぎて衝撃を受けたとはいえ、愛情とは似ても似つかないいじめに興奮する、そのような相反する感情を抱くのはすでに経験済みだ。
だからバジーニの件では、テルレスはその先を突き詰めたかったのだろう。実験結果から化学反応を導き出す科学者のように。
小説の後半、短い休暇の間寄宿舎に残されたテルレスはバジーニと二人きりで過ごした時、バジーニに問いかける。
「なぜ盗みを働いたのか?(盗んだ理由ではなく、その時バジーニに何が起こったのか)」
「ライティングに性的なことを要求されたとき、亀裂が走らなかったか?」
だが一瞬の出来事だったからわからない、とバジーニは答えるだけで、テルレスの望むような答えは得られない。
それどころか、テルレスはバジーニに肉体的に迫られ、興味を失った。
―以前は何かを期待したことはあったけど、そのうち君にみだらなことを迫られてからは、忘れちゃった。
僕は、ある地点を見つけようと思った。君から離れて、君を観察できるような地点をね。
それが君に対する興味だった。だけど君はそれをめちゃめちゃにしちゃった。―
6. まるで科学者のようなテルレス
テルレスはバジーニと距離を置き、観察することによって答えを導き出したかったが、バジーニに肉体的に迫られた距離が縮まった結果、それは叶わなくなった。
それはライティングとバイネベルグに対しても同じことで、興味を失い、バジーニに密告を勧め二人の友人とも決別することになる。
まるで科学者のようなテルレス。
バジーニが校長に密告し、テルレスは寄宿舎を脱走、その後見つかって連れ戻された時、なぜバジーニをいじめたのか?という教師たちの質問に、
「脳の中のプロセスに興味があった」
と答え、教師たちを混乱させる。
脳の中のプロセス、とは化学反応のようなものだろうか。それとも物理学?
いずれにせよ、内面と向き合い心理を追求するというよりは、人との関わりによって(ことによっては人でなくても良いのかも?)起こった現象をつぶさに観察する。
ムージルがこの小説の後に、少年ではなく成熟した大人を主人公に小説を書くとしたら、恋愛を現象として観察した小説になるのかもしれない。
この点に注目して、ムージルの他の小説も読んでみたいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
