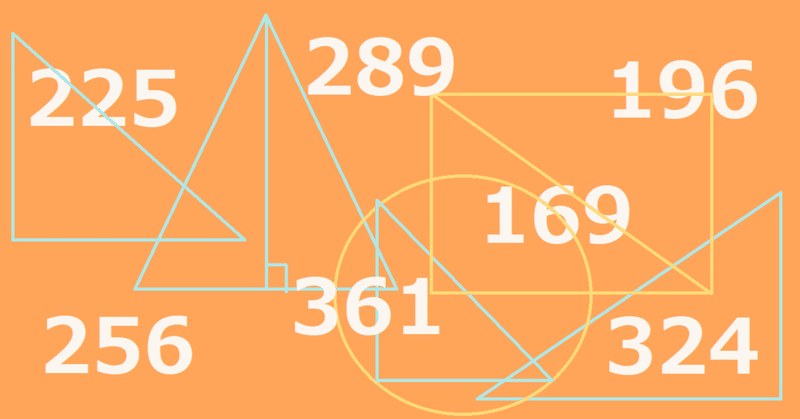
#1685 数学的な授業を創るポイントまとめ【算数科】
今回は、齊藤一弥氏の著書『数学的な授業を創る』から得た学びを整理していく。
・これからの算数科の授業づくりで大切なこと
➀与えられた事象の中から事象を数理的に見る目を育てる
②算数の問題を子ども自らがつくれるようにする
③子どもが今日の授業で取り組んできたことの価値を自覚する
←数学的な見方・考え方を働かせながら
・授業改善に必要なポイント
➀授業のゴールイメージを問い直す
→「何ができるようになったか」を重視する。
→学びを振り返りつつ、次なる学びを見通す。
→見方・考え方の成長と自覚
②数学的活動を資質・能力で分析する
→見方・考え方の明示的指導
③数学的な見方・考え方を鍛える
※見方・考え方の顕在化→明示的指導→自覚化
・見方・考え方の定義
➀見方:身に付ける知識や技能を統合・包括する概念
②考え方:教科ならではの認識や思考、表現の方法
・数学的活動は「目標」「内容」「方法」である。
・算数・数学の学習過程(A~D)に相当する流れ
➀事象確認
②学習問題把握
③問いの設定(焦点化)
④自力解決
⑤共同思考
⑥まとめ(解決結果)
⑦活用、統合・発展
・見方・考え方を働かせる流れ
➀学びの対象(数学化)、問題設定 ※見方
②自力解決、共同思考、活用・統合 ※考え方
③学びの成果 ※見方・考え方の成長実感
・見方・考え方と数学的活動の互恵的関係
➀見方・考え方で数学的活動を推進
②数学的活動による見方・考え方の成長
→資質・能力の育成、見方・考え方の成長実感
・言語活動を充実させ、見方・考え方を成長させていく学びの連続を重視する。
・子どもの経験をベースにすると、授業の文脈を子どもと共に生起しやすくなる。
・「答えを出すこと」がゴールではない。答えが出てから算数の授業が始まる。
・「身に付けたこと」は出し惜しみせず、どんどん使わせる方がよい。
・能力は「意味的な理解」により発揮される。形式の暗記ではなく、意味的な理解を重視する。
・「先人の文化を創る知恵」を実感させる。
・「割合として見る」という概念を踏まえ、単元をリデザインしていく。
※「同種の2量」と「異種の2量」
※4年生→5年生→6年生という系統
・「先を見越した展開」「前時までの学びを生かした展開」を意識し、単元をリデザインする。
・「Less is More.」を意識する。全てを覚えるのではなく、「必要最小限の概念を覚えれば後はOK」になるようにする。
・これまでの学習を概念的に統合できるような「問い」を投げかける。
以上が書籍からの学びである。
大切なことは、
➀授業冒頭で「見方・考え方」が創出・顕在化するような問題に出会わせること
②子どもが発揮した「見方・考え方」を受容させるために、教師が明示的指導をすること
③共有した「見方・考え方」を転移・活用させ、問題場面を発展させること
④授業終末に振り返りをし、成長した「見方・考え方」を自覚・実感させること、さらに次なる学びの見通しをもたせること
である。
やはり、数学的な授業を創るためには、「見方・考え方」が欠かせないのである。
ぜひとも上記のことを意識して、算数科の授業を創っていきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
