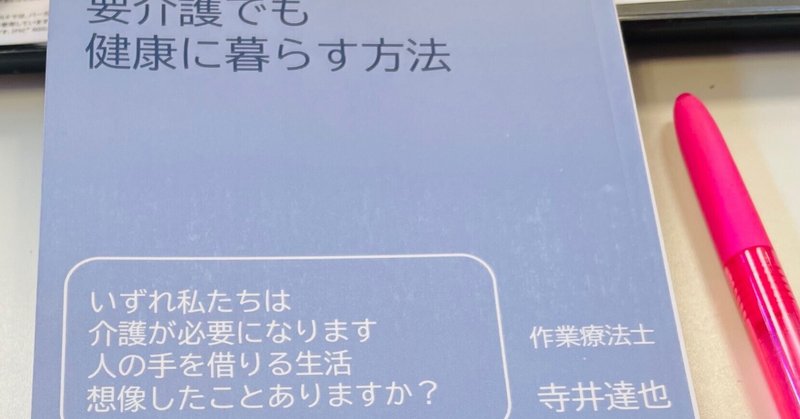
「明るく楽しく健康であり続けるために」
この記事は2054文字です。
少し話を遡りますが、私は子供の頃は本を読むことが大好きで、図書館に行っては生き物の生態の本やグリム童話、日本の昔話、推理小説、ファンタジーのお話など片っ端から読みまくっていました。
でも大人になり、趣味もネットやデジタルでのお絵描きに変わっていき・・・そして脳腫瘍になって以降は、ジャンルを問わず「読書」が大の苦手になってしまいました。
本を読んでも、全意識を集中しないと内容を忘れたり読み飛ばしたりしてしまうのです。挙句30分~1時間もしないうちに疲れ果ててしまいます。
恐らく失語症や、物忘れなど短期記憶が弱い影響もあるのでしょうね。
漫画であればセリフは少ないし全体の流れは絵ですから、ストーリーを把握しやすく記憶に残りやすくなるのですが、分厚い長編小説だったりすると内容を理解する前に脳がオーバーヒート。
特に元々苦手だった登場人物の名前や内容もすぐ忘れてしまいます。
いえ、文字数の多さに無意識に脳が拒否してしまうというべきなのでしょうか。
個人差はあるのでしょうが私の場合、よほど集中しないと印象に残った断片の内容以外は忘れやすいため、ざっくりとしか記憶に残らないのです。
そして今回の本題である、作業療法士寺井達也さんの本「要介護でも健康に暮らす方法」を、物忘れの激しい私がどうやって読んでいったのかという、「本のレビュー」と「どうやって本を読み内容を理解していくか?」というお話です。
内容は本のタイトルの通り、私のような大病を患った方や、体が弱ってきた高齢者になっても、いかに元気に楽しく生きていくかという、医療、特にリハビリに特化した構成。
何せ多数の高次脳機能障害を抱える脳腫瘍持ち&更年期障害が始まるアラフィフ世代ですからね。興味アリアリ、今の私にはピッタリな内容です!
でも悲しいかな、前述した通り、何度読破してもすぐ忘れてしまう。。内容すべてを記憶にとどめておくことが難しい。ならどうするか。。。?
そこで私の取った方法は、読破後2週目では目次の章ごとに、更には小さな見出しごとに興味があるところには○をつけ、重要な箇所は赤線を引いたり付箋紙を貼りながらメモを取り、「自分好みな内容を厳選し集約する」という方法でした。
おかけで貴重な本は線だらけでボロボロになりましたけど、カスタマイズされた事で愛着のある本になりとっても気に入っております(笑
さらに、私、夫に娘、母や義母さんなど、家族ごとに興味のある無しで分類することで、ピンポイントで内容が把握しやすくなっていったのです。
早速仕分けしてみると・・・
○ 私向け ○
●健康寿命が終わっても手、足、頭は使い続けること(29ページ)
●トライアンドエラー(31ページ)
●高齢になって新たな生活習慣を定着させるには(97ページ)脳のこと必読
●脳は快いことを求め、不快なことから逃げる性質がある(104ページ)脳科学のこと必読
●きっかけを設定して生活を再構築する方法(116ページ)
●生活習慣テクニック「wow」(134ページ)
第5章 ●睡眠(144ページ)一番大事!
○娘向け○
●否定は毒 (62ページ)自戒を込めて 必読
○夫向け○
●寝たきり注意報(33ページ)生活不活発病対策にも重要。10年後の夫向け
○ 母&義母さん向け ○
●元気な高齢者の特徴(39ページ)
●高齢者の引越しは意外と危険(64ページ)
●老人ホームへ入所する一人暮らしの女性(69ページ)
○ 家族全員重要 ○
●第3章 高齢化リハビリの現場(73ページ〜94ぺージ)これから介護世代になる方へ 読みやすいしリハビリの解説もいっぱい。読み物としてもオススメ
っと、仕分け内容は以上でしょうか。
この方法ならば、物忘れが激しくても、ストーリー性の有無に左右されず、どんな本を読んでも理解できると、そう思ったのです。少し恥ずかしいですが、これが私なりの本を読み理解する方法です。
纏めると、私のように物忘れなど高次脳機能障害を持つ方が本を読むコツは、
●①● 本を読んで重要な部分は、こまめに線を引いたりメモを取る。
小説など登場人物が多い場合は、名前や人間関係もふりがなを書きゲームブック感覚で記録していく。勢力作りなどをマップ作成するのも楽しいかも♫
●② ● 医療本など、情報系の本の場合は、章や見出しごとに選別し重要なことだけを厳選する。ぺージのメモも読み返しやすくなるので大事。本の全体像も掴みやすくなる。
っと、以上な感じでしょうか。
話は前後してしまいましたが、「要介護でも健康に暮らす方法」は私のような持病持ちや、老いた両親の介護が必要になったときでも、できるだけ明るく楽しく暮らせるためのノウハウが詰まった素敵な本です。
10年後は私の両親が、20年後は私たち夫婦がお世話になるときでも必須な本だと思います。興味のある方は一家に一冊、是非読んでみて下さいね。
以上、「明るく楽しく健康であり続けるために」というお話と本のレビューでした。
つたない文章でお恥ずかしいのですが、参考になりましたら幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
